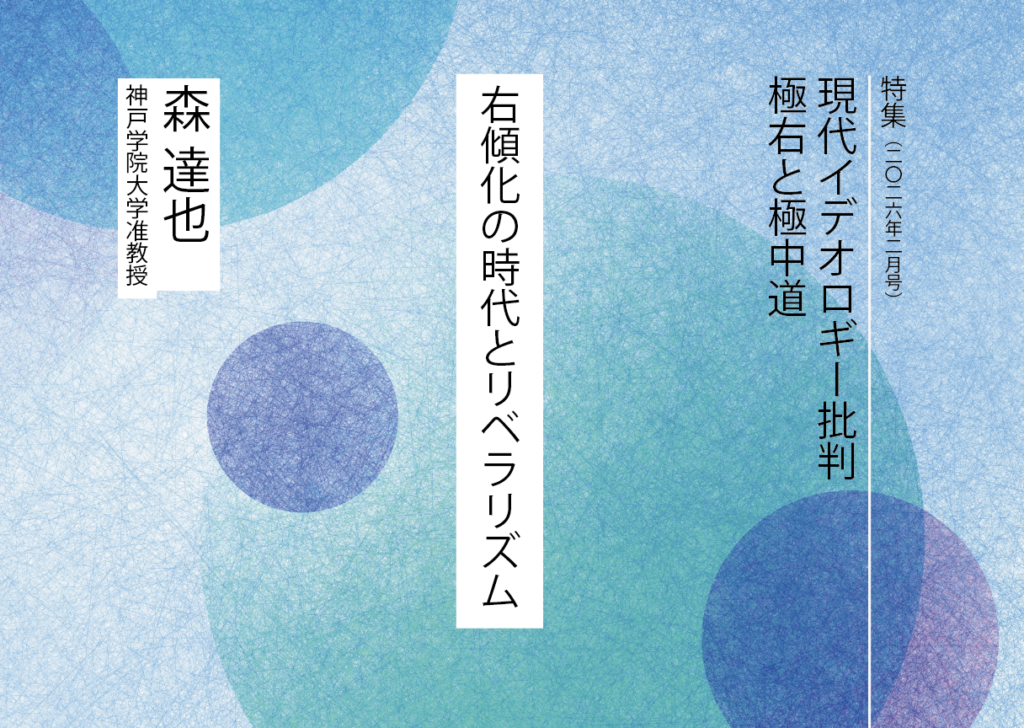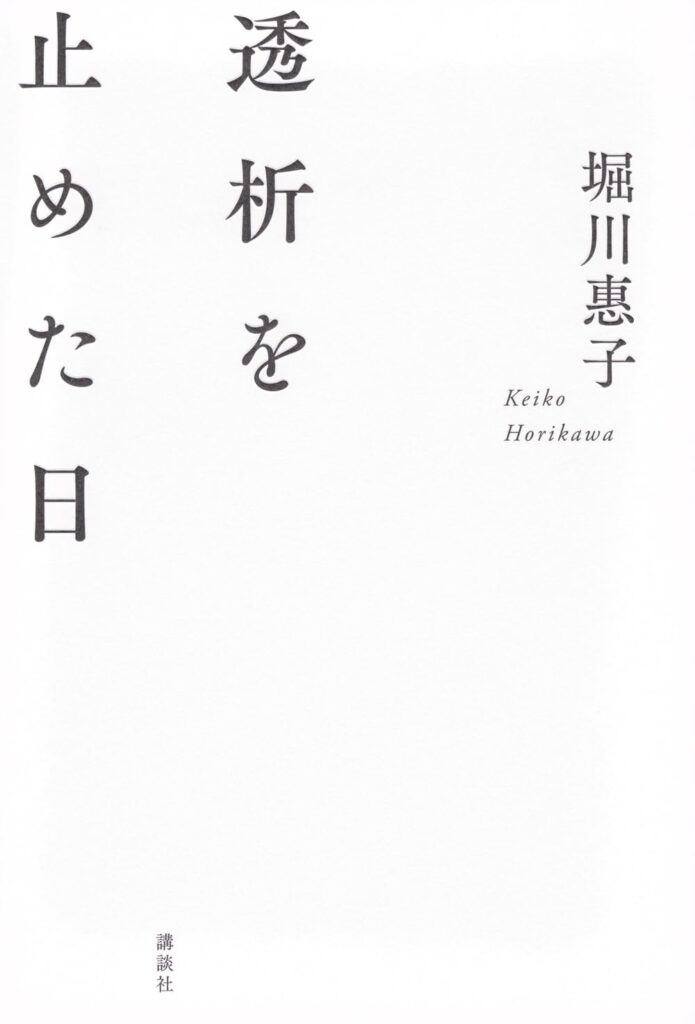阪神・淡路大震災から30年。当時の記録は、いまなおそこにあるリアルな記憶として響く。
東日本大震災でも、能登半島地震でも、布団一枚のスペースでプライバシーもなく寝るしかない被災者の姿は消えていない。調査報告や手記などからなる本書が縷々指摘する、生活につながった部分をつぶさに見直せば、「震災があろうとなかろうと、変わっていないこと」の存在を思い知る。災害は、その一端を噴き上がらせたにすぎない。
阪神・淡路大震災のあとに解雇された女たち。男に依存せざるを得ない状況へと追われ、しかし彼らは女たちのことを気にかけもせず、後回しにする。災害時の性被害・ DVを告発する声は、「加害者も被災者や。大目に見てやれ」などといった言葉に圧殺された。これらに対する苛立ちと嘆き。孤立と孤独に泣き、つながりを見つけて涙する。
これは女性だけの話でもない。外国人、障害者、高齢者……マイノリティ、社会的弱者たちほど、被災で受けた傷は大きく、そして深くなる。「災害は弱い者により厳しい。弱者を守らずして国は何を守れるというのか」とは至言だ。
日本に山積している解決していない問題の多くは、当事者という主体の存在が消されていることが端緒となっている。何十年もほとんど変化していないことと、いつまでたたかいつづけなければならないのか。それでも、たたかわなければ、けっして変わることはない。本書は、その意思の大切さを強く思い出させてくれる。(翼)
〈今回紹介した本はこちら〉
『女たちが語る阪神・淡路大震災 1995-2024——いいたいことがいっぱいあった』
編著:女性と子ども支援センター、ウィメンズネット・こうべ
2024年12月、ペンコム