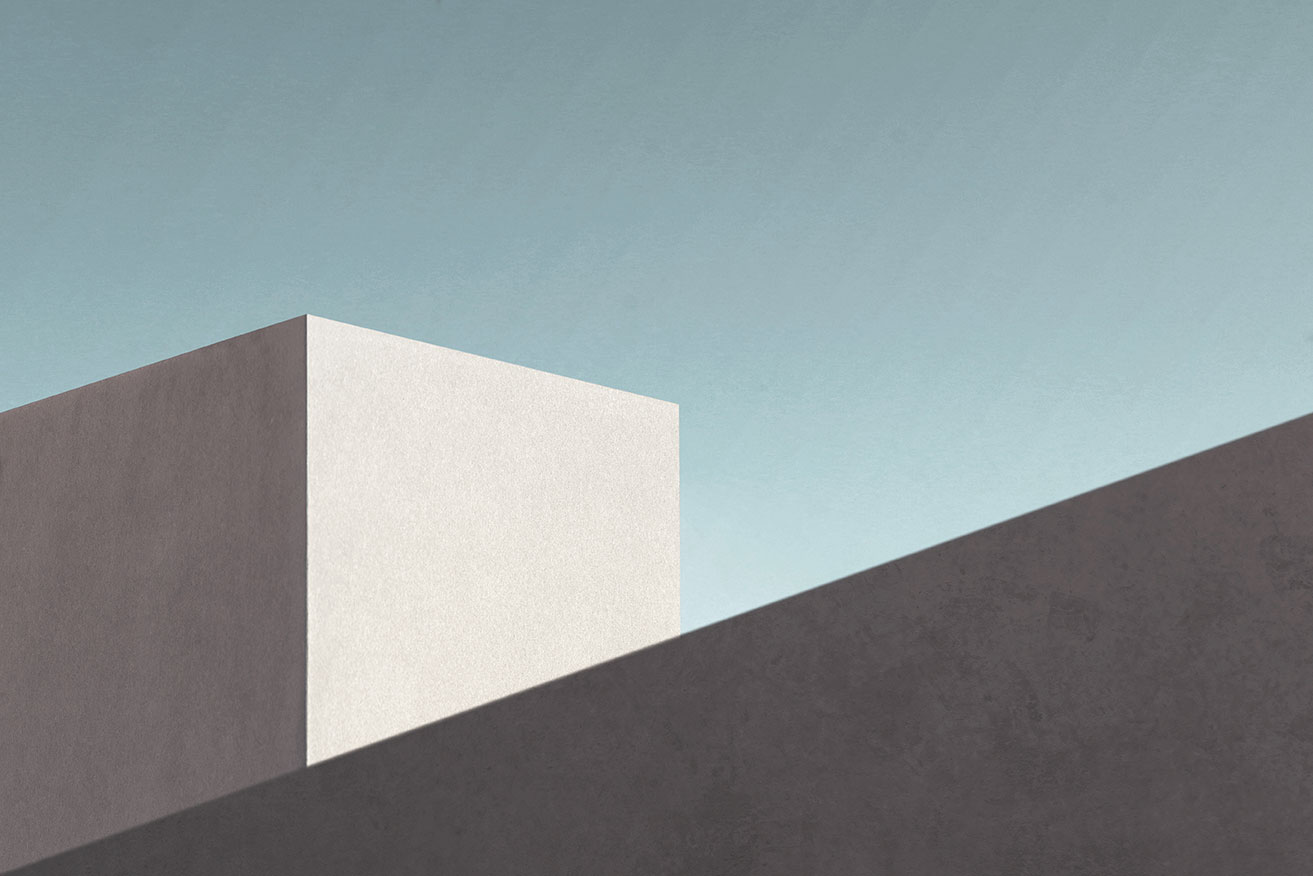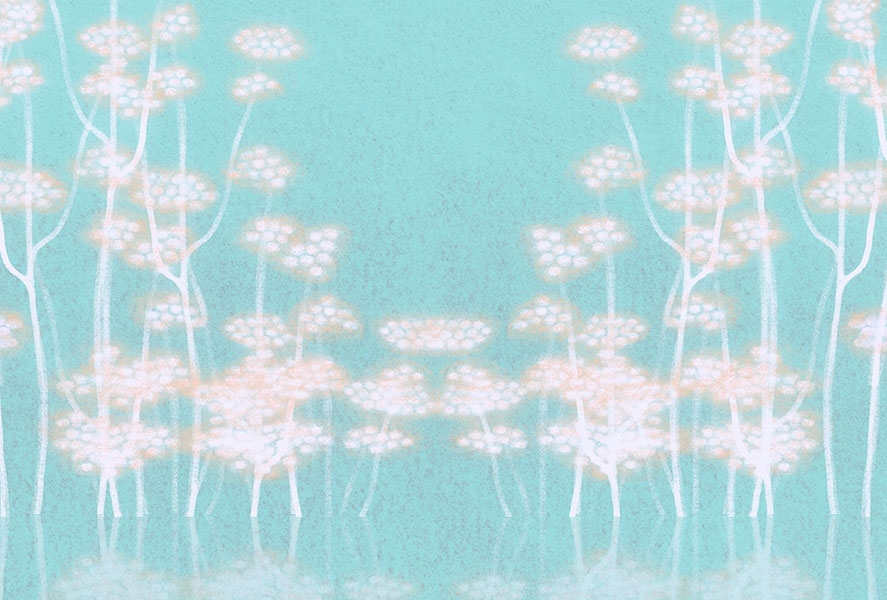【関連】「特集:加害と和解ーー東アジアの不再戦のために2」(2025年12月号)
高橋哲哉(たかはし・てつや)
東京大学名誉教授。哲学者。1956年生まれ。著書に、『記憶のエチカ――戦争・哲学・アウシュビッツ』『歴史/修正主義』(以上、岩波書店)、『戦後責任論』(講談社)、『靖国問題』(ちくま新書)、『犠牲のシステム 福島・沖縄』『沖縄の米軍基地――「県外移設」を考える』(以上、集英社)、『日米安保と沖縄基地論争――〈犠牲のシステム〉を問う』(朝日新聞出版)ほか。
石破所感をめぐって
(聞き手 本誌編集長・熊谷伸一郎)――10月10日、退陣間近の石破茂首相により「石破所感」が公表されました。歴史認識については歴代内閣の立場を引き継ぐとして踏み込まず、主に問題にしたのは、なぜ無謀な戦争に突き進んだのか、という点でした。
高橋 そうですね。戦後50年から10年ごとに首相談話が発表されてきたので、戦後80年にあたって石破首相が何を語るかが注目されたのですが、まず談話を出すこと自体に自民党内の右派から反発がありました。高市早苗氏も反対を公言していましたね。右派からすれば、安倍首相が70年談話で決着をつけたとして終わりにしたい、比較的リベラルと目されている石破氏に新たな「お詫び」や「反省」を語られてはたまらない、ということだったのでしょう。敗戦記念日の8月15日に閣議決定して出したかったのでしょうが、降伏条約調印日(9月2日)にもできず、ようやく新総裁が決まった後に個人的な所感として出すのが精一杯だった。この経過自体、今の自民党を中心とした右派勢力の勢いを表していると思います。
内容を見ると、「無謀な戦争」を始めるに至った日本国内の事情について、なるほど反省的な歴史観を披歴していると言えるでしょう。大日本帝国憲法、政府、議会、メディアと、分野ごとに問題点を語り、文民統制の欠如に焦点を当て、歴史から学ぶ重要性について語っています。「戦争の記憶を持っている人々の数が年々少なくなり、記憶の風化が危ぶまれている今だからこそ、若い世代も含め、国民一人一人が先の大戦や平和のありようについて能動的に考え、将来に生かしていくことで、平和国家としての礎が一層強化されていく」。こうした言葉を首相が国民に向かってきちんと語ることにはもちろん意義があります。日本ではそういう機会がむしろ少なすぎるのです。
ただ、問題設定そのものが物足りない。「敗戦は必然」とされていたにもかかわらず、なぜ突入したのかという問題意識ですが、ここで「無謀な戦争」と言われているのは事実上対米戦争、「開戦」といってもそれは当時の言葉で言えば「大東亜戦争」の開戦なのです。それ以前の満州事変、日中戦争を通して、なぜ隣国中国に、最大時には100万を超える日本の軍人が出兵することになったのか、そこを問う部分がない。植民地支配もまったくテーマになっていないのです。右派勢力は胸をなでおろしたことでしょう。
戦後50年の村山談話には、「植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました」という文言があり、歴代政権はこれを引き継ぐとしてきました。石破首相も「歴代内閣の立場を引き継ぐ」としています。しかし私は、戦後70年の安倍談話以後、あらためて何を引き継ぐのかが問われなければならないと考えます。安倍氏には村山談話を上書きする企図があったはずですが、さすがにそれを完全に否定することはできず、その代わりに「私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」というひと言を入れた。これで終わりにしたいという本音が透けました。村山談話と安倍談話の主旨にはズレがあります。「歴代内閣の立場を引き継ぐ」というだけでは、石破首相の認識が見えてきません。
文民統制の重要性
――石破所感はとりわけ文民統制や言論統制の強化によって批判が封じられたことの問題を指摘しています。
高橋 ウクライナ戦争以降、メディアに元幹部など自衛隊関係者が出てきて戦況を解説する場面が多くなったことに象徴的ですが、自衛隊の存在感が増していますね。
陸上自衛隊でも海上自衛隊でも、靖国神社に集団参拝したことが報じられました。幹部が部下を集団で引き連れて本殿に昇殿参拝までしています。元海将が靖国神社の宮司に就任したり、元幕僚長クラスの幹部が「自衛隊に戦死者が出た時のために靖国神社を国営化すべきだ」と盛んに訴えたりしています。
現役の自衛官を答弁に立たせるか否かについて国会でも問題になりました(2025年2月、衆院予算委員会)。こうした状況を考えると、首相が文民統制を強調することには意味があります。文民統制を実効的なものにするには、政治の側が自衛隊をコントロールできるだけの力を持っていなければなりません。たとえば仮に日米安保体制をやめようという政治的な流れができた時に、「日米同盟軍」はどう動くのか。はたして文民統制は効くのか。
歴史を知らなければ始まらない
――その上で今日への教訓として、「偏狭なナショナリズム、差別や排外主義を許してはなりません」とし、歴史に学ぶ重要性を主張して締めくくっています。
高橋 歴史に学ぶことはきわめて重要ですが、そのためにはまず歴史を学ぶ必要があるでしょう。現代史の基本的な知識を身につけること、それがなければ、歴史に正面から向き合い、そこから学ぶということもできないからです。公教育で近現代史を教え、学ぶことが決定的に重要なゆえんです。日本は第2次世界大戦でナチス・ドイツなどと同盟を結び、連合国相手に戦って敗戦をした。それは遡れば、明治維新以来のアジアへの侵出に始まっている。こうした帝国の歴史を丁寧に教え、学んでいく必要があります。
付け加えると、だからといって、すべてが恥ずべき歴史だということではありません。侵略や植民地支配をした歴史の一方で、それに抵抗した歴史もあります。文化や学術の歴史もあります。「普通の人びと」が生きた歴史にも、当然ながら、さまざまな光と影があったわけです。そういうことも含めて、帝国の時代に周辺諸国との間で何が起きたのかを丁寧に学び、その意味と教訓をそれぞれが考えなければなりません。
石破首相が「偏狭なナショナリズム、差別や排外主義」を戒めたことは、日本の現状に鑑みてきわめて重要です。ただ、それらはいずれも他者との関係、他国や他民族との関係で起きたこと、起きることです。そうであればなおのこと、石破所感では、アジアに対する日本の侵略と植民地支配の歴史にも及んでほしかったと思うのです。
「反省なんかしておりません」
――高市氏は1年生議員時代、国会質問で、戦争体験を持つ河野洋平外務大臣に向かって、「少なくとも私自身は、当事者とは言えない世代ですから、反省なんかしておりませんし、反省を求められるいわれもないと思っております」(1995年3月16日、衆院外務委員会)と述べました。
高橋 この発言はよく覚えています。若い世代の女性議員からこれまでにない率直な発言が出てきたといって、ポジティブに受け止める向きもあったように記憶しています。
たしかに、「当事者」が戦争体験者を意味し、「反省」が自分個人に罪があることを認めて反省するという意味ならば、戦争当時に生まれていなかった人は戦争当事者ではありませんし、その戦争について「反省」するいわれもありませんね。しかし、事はそれでは済みませんし、「1年生」とはいえ国会議員であれば、単なる一個人として済ませるわけにはいかないはずです。こうしたことから、私は応答責任としての戦後責任という議論をしたのです。
私自身も戦後生まれですから、体験者を当事者とするなら当事者ではありません。しかし、もし自分が属する国が過去に罪を犯し、それに対し十分な反省をしていない、被害者に謝罪も補償もしていない、被害者だと名乗り出て謝罪や補償を求める人が今まさに自分たちの目の前にいる、そんな状況があるなら、まずはそれに応答しなければならないのではないか。応答イコール応諾ではありません。どのように応答すればよいのか、それを判断するには、過去に自分の国が何をしたのかを知る必要がある。そしてもし国が罪を犯していて、にもかかわらずその責任をとっていないと知ったなら、その国の一主権者として、国の態度に変更を求める必要があるのではないか。これまでそれをしてこなかったことに、戦後世代の「反省」もあるべきではないか。つまり、被害者の訴えに、イエスと応答すべきではないか。まして、高市氏はすでに国会議員でした。国会議員は全有権者の代表として、謝罪も補償もしてこなかった国のあり方に直接の責任を負うのではないか。
高市氏の論法でもう1つ思い出すのは、第2次安倍政権の官房長官であった菅義偉氏が翁長雄志沖縄県知事に対して、「私は戦後生まれなものですから、歴史を持ち出されたら困ります」と突き放したことです。2015年、辺野古移設をめぐる非公開協議の場で、翁長知事が政府に対して強く抗議した時の発言です。
これには唖然としました。沖縄の歴史を受けとめずに日本の官房長官や首相(菅政権)が務まるのでしょうか。そもそも、翁長知事が語った沖縄の歴史とは、戦前のことというよりも沖縄戦から戦後のこと、米軍基地集中に苦しめられてきた戦後のことであったはずです。
こうした高市発言や菅発言には、歴史の重みを受け止められない日本の政治家の問題点が如実に表れていると思います。
タカ派の嘘?
――高市氏は靖国神社に繰り返し参拝してきました。最近はトーンを弱めていますが、2024年の自民党総裁選では、「首相になっても参拝を続ける」と述べていました。高市氏のこのような執着をどう理解すべきでしょうか。
高橋 安倍氏の政治的後継者たらんとしている高市氏ですが、ときに安倍氏以上に強硬右派的な面が垣間見えます。2022年、靖国神社崇敬奉賛会主催のシンポジウムで、「途中で参拝をやめるなど、中途半端なことをするから相手がつけあがるんだ」と発言したのには驚きました。中曽根首相は公式参拝後に中国からの批判を受けて翌年から参拝をやめた。安倍首相も一度参拝しましたが、アメリカから「失望した」と言われてやめました。途中でやめるから相手が「つけあがる」と言うのなら、安倍氏をも批判することになります。安倍氏はもちろん右派的価値観の政治家でしたが、首相としてプラグマチックに状況に対応する面もありました。中国や韓国を「つけあがらせるな」という態度では、外交はできません。
ロシアのウクライナ侵攻を受けて、高市氏は櫻井よし子氏との共著『ハト派の嘘』を刊行しました(産経セレクト)。そこでこう語っています。「戦争はない方がいいに決まっているのですが、その戦争が『自衛戦争』なのか、いわゆる『侵略戦争』なのかは、開戦時の『国家意思』の問題です。日本国民は開戦時の天皇陛下の詔勅によって国家意思を理解したものと思われます」(90頁)。そして「開戦の詔勅」から、「帝国は今や、自存自衛のため決然起って、一切の障害を破砕するのほかなきなり」が引用されます。
しかし、開戦時の「国家意思」が自衛か侵略かを決めるのであれば、ロシアのウクライナ侵攻もナチス・ドイツの戦争も侵略ではないことになるでしょう。同書でロシアのウクライナ侵攻を「侵略」だと強調していることと矛盾しています。また、日本の「先の大戦」を「自存自衛」の戦争だったと主張するこの議論には、石破所感同様に、中国との戦争が抜け落ちています。
「戦争責任」についてはこう言っています。「日本人は謝罪をし続けるべきだという戦後の風潮を私は『民族責任論』と呼んでいます。例えば、他国は日本のような謝罪をしていないと思うのです」(同頁)。「日本人は謝罪をし続けるべきだという戦後の風潮」がどの程度あったのかは検証を要します。他方、「他国は日本のような謝罪をしていない」というのは、ドイツの例を見れば事実に反します。
植民地支配についてはどうか。
「『植民地支配』はいまの価値観で考えると悪いことで、そこに住んでいらっしゃる方々の民族の誇りを傷つけるものですが、当時の正当な、国際的に認められた条約に基づいて植民地となった国々はたくさんあります。例えば、日本の支那ママにおける諸権益は日清戦争以降の『日支間条約』によって定められていたものです。日韓併合は、1910年に調印した『日韓併合に関する条約』によって実現し、当時、ロシアとイギリスはこれを了承し、アメリカも異議を唱えていませんでした。
でも、日本はそれを『日本だけが悪い』としてきました。植民地支配が全部悪いのだとすれば、 アメリカもイギリスもフランスもオランダも、謝罪を続けなければいけなくなります。でも、他国はそうしていません」(92頁)。
この発言に櫻井氏が応えて、「他国は日本のような『謝罪外交』などしていませんね」と述べています。
しかし、「他国は謝罪などしていない」というのはやはり事実ではありません。かつて植民地支配を行なったヨーロッパのすべての国ではありませんが、すでにいくつかの国々はその非を認め、植民地主義は不正であったという認識に立ち、謝罪などの行動に表しています。
21世紀に入り、国連「ダーバン宣言」が採択され(2001年9月)、奴隷制と奴隷取引は「人道に対する罪」であり、「植民地主義が起きたところはどこであれ、いつであれ、非難され、その再発は防止されねばならないことを確認する」と宣言されました。欧州議会では「アフリカ系市民の基本的権利」に関する決議(2019年3月)で、「いくつかのメンバー国」が行なった「公式謝罪」等の措置に倣うことが呼びかけられ、アメリカでは BLM(ブラック・ライブズ・マター)運動が、コロンブスまで遡ってアメリカの植民地主義の歴史を告発し、それがヨーロッパに波及していきました。
オランダは2022年から翌年にかけ、首相と国王が相次いで、100年以上前に廃止されている奴隷制について「赦しを乞う」と謝罪しています。ベルギーのフィリップ国王は2022年6月、かつて植民地支配したコンゴ民主共和国(旧ザイール)を訪れ、「父権主義と差別と人種主義」に基づく「植民地支配」により与えた「苦痛と屈辱」に深い遺憾の意を表明しました。フランスのオランド大統領は2012年、アルジェリアの独立50周年記念日にアルジェリア議会で演説し、「132年」にわたる「植民地支配」は「根本的に不正かつ野蛮なシステム」であったと述べています。
東西統一以降のドイツの大統領や首相は、ホロコーストだけでなくワルシャワ蜂起弾圧、ポーランド侵攻、独ソ戦などについて、たびたび「赦しを乞う」と表明してきました。シュタインマイヤー現大統領は、昨年(2024年)9月にイタリアのマルツァボットを訪れ、ナチスによる虐殺について「頭を垂れる」「赦しを乞う」と述べ、10月にはギリシャ・クレタ島のカンダノス村を訪ねて、ドイツ軍が現地で犯した罪について「赦し」を乞いました。そして今年1月にはドイツの議会で「記憶の義務には終わりがない」と演説しています。植民地支配について言えば、現大統領は一昨年11月、アフリカのタンザニアを訪れ、ドイツ植民地軍が先住民の蜂起を弾圧した蛮行について「赦しを乞う」と述べているのです。ドイツ大統領府のウェブサイトには歴代大統領の主なスピーチが掲載されていて、英訳も含めて文言を閲覧できます。日本の首相であれば、当然こうしたことを知っておいてほしいのです。
石破首相は今年3月に硫黄島、4月にはフィリピン・カリラヤを訪問し、6月の沖縄全戦没者追悼式出席、ひめゆり平和祈念資料館訪問、8月の広島・長崎における原爆死没者・犠牲者慰霊式出席、終戦記念日の全国戦没者追悼式出席と、戦争関係の行事が続きました。それらの場で「先の大戦の反省と教訓を改めて深く胸に刻む」とは言っていますが、いま一部を挙げた欧州の例と比べて物足りなさは否めません。北京や南京や重慶、旧満州各地、ソウルや三一独立運動の現場を訪問し、アジアの人たちにその言葉を伝えることはできないのか。「記憶の場所」に赴いて、相手国の人々に直接謝罪するということを、日本の政治家はほとんどしてこなかったのです。
参政党躍進をめぐって
――先の参院選では右翼の参政党が支持をのばしました。
高橋 まず歴史認識について言えば、参政党の神谷宗幣氏は高市氏と同じ危うさをもっていますね。たとえば今年の6月23日、神谷氏は那覇での街頭演説で、「日本軍が中国大陸に侵略していったというのは嘘です。違います。中国側がテロ工作をしてくるから、自衛戦争としてどんどんどんどん行くわけですよ」と発言しています。
現代史とくに20世紀前半の歴史を学んでいれば、こんな発言はできないはずです。日本軍はまず中国東北地方を占拠してから華北に侵出し、上海、南京、重慶爆撃など中国の奥深くにまで進んでいったわけです。これが侵略でないとしたら、何を侵略と言うのでしょうか。満州事変が自衛措置だという日本の主張は国際連盟からも否定され、事実上侵略だと認定されたのですし、それが契機となって日本は国際連盟を脱退したのです。
中国の「テロ工作」といいますが、中国軍が日本のどこかを侵略したのでしょうか。日本軍が中国に侵略していくのに抵抗していただけであり、それを「テロ工作」というのは抵抗を弾圧するための当時の常套句です。神谷氏は、「大東亜戦争は日本が仕掛けた戦争ではありません」とも言います。日本は騙されて戦争に引きずり込まれ、やむを得ず「自存自衛」のために戦ったというのは一種の陰謀論でしょう。「対米英蘭戦争」は帝国主義国同士の戦争で、「自存自衛」と言うなら、植民地帝国を「自存自衛」するためだったわけです。
神谷氏は日本外国特派員協会で会見した際に、「親近感を覚える海外の政党はあるか」との質問に対し、ドイツのための選択肢(AfD)、フランスの国民連合、イギリスのリフォームUK、この3つの極右政党を挙げました(2025年7月3日)。また、アメリカのMAGA運動活動家で講演中に銃撃されて亡くなったチャーリー・カーク氏とも、事件の直前に対談しています。これらは、神谷氏の政治信条が「極右」的であることを示唆する事実です。
参政党の憲法案には、その歴史認識、政治観、人間観がはっきり現れています。
まず天皇について、「天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である」(前文2段落目)。「しらす」は「統治する」を意味する古語ですね。日本は悠久の昔から天皇が統治する国、その天皇を敬慕する家族のような国民の国だという、戦前の「國體」観そっくりのイメージをもっていることがわかります。
国民の要件については、「父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める」(第2章、第5条)。「日本を大切にする心を有する」とはあまりに曖昧で、これを基準に判断されたら、国家権力のやりたい放題に「非国民」が作り出されそうです。
他にも問題は多数あります。「国民主権」も「人権」も出てこないのです。
そして「日本人ファースト」なるスローガンです。「日本ファースト」であれば、日本国籍を有するマイノリティの人びとも含めての「日本国民ファースト」になるでしょうが、「日本人ファースト」にはレイシャルなニュアンスがあります。アイヌや沖縄の人びと、在日コリアンの人びとなどに対する差別やヘイトの問題を神谷氏はどう考えているのか。いずれにせよ、「日本人ファースト」が排外主義的ニュアンスをもつことは否定できません。
参政党のこうした国家観、日本観には、いわばナショナリズム以前の「日本人」ナルシシズムの匂いがします。日本人に生まれてよかった、日本人は世界の人から仰ぎ見られる特別の民族だ、「ニッポンすごい」、その伝統の中心には皇室があり、誰もがそこに日本人ファミリーの理想を見る……そんなイメージです。
参政党の抬頭の背景にあるのは、やはりグローバル化による社会構造の激変でしょう。1990年代から急速に進んだグローバル化によって、新自由主義的な市場経済万能の価値観が日本にも浸透しました。中間層が崩壊し、一部の富裕層とそれ以外の層、とくに貧困層との格差が拡大しました。その矛盾に対する不満はもとより、日本の場合、国全体の国力が落ちて国際的地位が下がっているため、エリート層や非貧困層にも不安や不満が鬱積していると思われます。その不安や不満が、グローバル化の結果として増加した外国人に向かっているということでしょう。
一般に人間は、脅威は外から来ると考えがちです。自分たちとは違う「よそ者」によって日本人の利益が損なわれている、そういう意識が強まっているのだろうと思います。神谷氏が「反グローバリズム」を唱えていることは象徴的です。欧米の極右と同じく、日本でもグローバリズムに対する反動が起きているのです。
言論を萎縮させるスパイ防止法
――高市氏は、「スパイ防止法」の導入を主張しています。
高橋 高市氏は総裁選でスパイ防止法制定への着手を公約に掲げ、維新の会との連立合意にもスパイ防止法の制定が入りました。特定秘密保護法や経済安保推進法など関連する法律がすでにあるので、それらを踏まえて出てくるのでしょうが、「スパイ防止」の名のもとに報道機関や一般市民の言動にまで対象が拡大されないか、最大限の警戒をもって注視していく必要があります。
治安維持法についても、神谷氏は「共産主義者にとっては悪法」だったが、国家にとっては必要だったと正当化しています。思想・表現の自由ということが理解されていないのではないか。治安維持法のもとで拷問を受けたのは共産主義者だけでなく、自由主義者や宗教者、さらには少し厭戦的なことを口にしただけの市民まで被害を受けています。
日本ではすでに、政府に異議を申し立てる市民を排除しようとする発想は珍しくなくなっています。「反日左翼」から始まって、「北朝鮮の工作員」、「中国のスパイ」などという攻撃がネットやSNSには溢れています。政府批判の言論が監視され、排除されるようになり、それを市民が問題だと認識できなくなるとしたら、民主主義にとって致命的です。日本学術会議の任命拒否問題は、安保法制に反対した研究者を標的にしたものでした。
「スパイ防止法」の内容や運用の仕方によっては、言論はいま以上に萎縮してしまうでしょう。言論・表現の自由、思想・良心の自由という憲法原則の価値を再確認しなければなりません。
歴史的な分岐点
――お話をうかがい、右傾化に対抗するには、戦争を学び、反省することからエネルギーを得る必要があると感じました。戦後80年という節目に意味があるとすれば、その契機になることでしょうか。では最後に、当事者の記憶が失われていく現在、過去と向き合う意味についてお聞かせください。
高橋 「当事者」とは言えない世代が歴史に向き合う論理については、すでに簡単に触れました。その上で、体験者がいなくなった出来事の記憶について言えば、それを「記憶」として語るのは一種の比喩でしかなく、いわば「記憶の記憶」、間接的な記憶、実際のところはさまざまな社会的媒介を経て形成される「社会的記憶」になるわけです。歴史書、歴史映画、歴史文学、ジャーナリズムその他の多様なメディアを通して後の世代が知り、各自の背景の中で受け止めていくほかはない「社会的記憶」、それだけ多様な「物語」としての歴史の「記憶」です。そこでますます重要になってくるのは、客観的なものとフェイクとを見分けるリテラシーです。これが疎かになるところでは、歴史修正主義や否定論がはびこることになるでしょう。その意味で、アカデミアと民間とを問わず歴史研究と、公教育における歴史教育の重要性は、日本のようにそれが軽視されてきた国では、いっそう強調されねばなりません。
私は「戦後80年」という今年に特別な意味を感じています。「戦後50年」に、その直前に起きた冷戦終結とソ連崩壊という大転換の記憶が結びついているように、「戦後80年」にも同様の、あるいはそれ以上の歴史的転換が結びついているように思うからです。
「人類が地獄を見た」と言われる第2次世界大戦。それを生き延びた人びとが何に再生の希望を託したかは、国連憲章前文に書かれています。簡単に言えば「人権」と「平和」、それらを保障するための「法の支配」です。これらが国連憲章と日本国憲法に共通の基本理念なのです。ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるガザ・ジェノサイド、そしてトランプ政権の復活によって、これらの普遍的理念が崩壊の危機にあります。歴史認識をめぐる対立も、この状況と深く結びついていると私は考えています。容易ならざる状況です。
――本日はまことにありがとうございました。