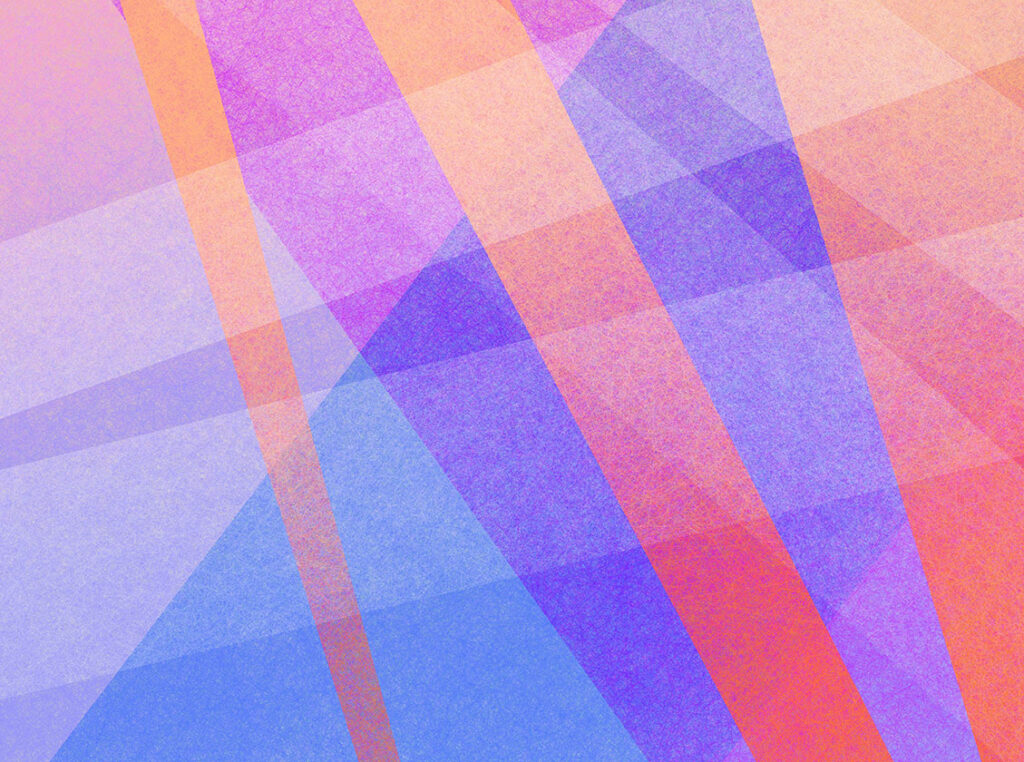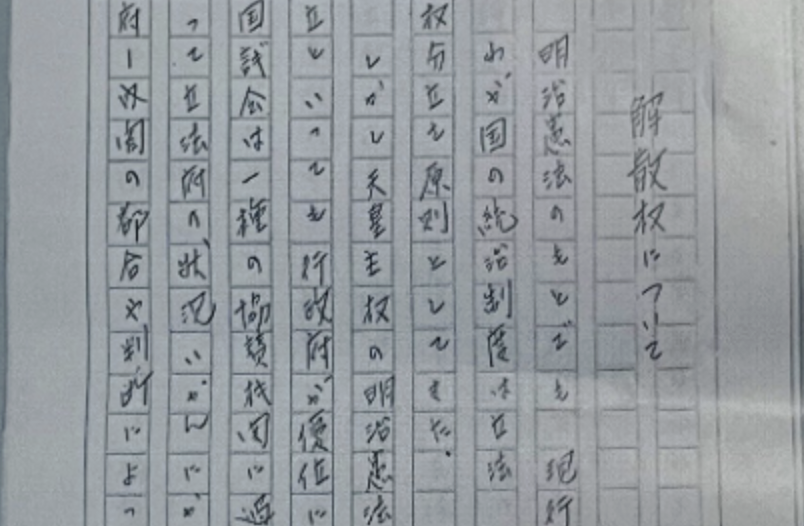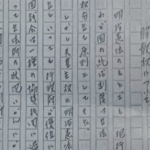未明の奇襲攻撃とマドゥロ大統領夫妻の連行
ベネズエラの首都カラカスは、山あいに浮かぶ街だ。カリブ海に面する国際空港からは車で三〇分ほどだが、一〇〇〇メートル近い標高によって暑さがやわらぎ、一年中、実に過ごしやすい気候である。小高い丘に登れば美しい夜景をのぞむこともできる。その夜空に立ちのぼる炎光、薄煙をスクリーン越しに見た。現地時間で一月三日朝二時頃、時差は一三時間なので、日本時間の昼下がりのことだった。
SNS上には最新情報がとめどなく流れ込む。ボリバル革命のシンボル、チャベス前大統領の亡骸が眠る「山の兵舎」が爆撃されたとの報も出た(後日これは誤報であったと判明する)。攻撃対象のひとつであるラ・カルロタ空軍基地はまさにカラカスの中心市街地にあり、有名ショッピングモールの目と鼻の先である。獰猛に撒き餌へと群がる米軍機と漆黒の空をただただ眺め立ちすくむ人影のひとつに、友人の大きな背中を思い出した。スコールの後の月夜をしっとりと濡らす、小鳥のようなカエルのさえずりが突如よみがえる。
マドゥロ大統領夫妻の米国連行を前に、当日中にはベネズエラの最高裁がデルシー・ロドリゲス副大統領を大統領代理に命ずる声明を出し(国会議長である兄のホルヘ・ロドリゲス氏と区別するため以降デルシーとする)、米国側も交渉相手として承認する形でひとまず事態は落ち着きを見せた。五日には例年通り国会が開幕し、デルシーが宣誓にのぞむ。当初危惧された地上戦への本格的展開、泥沼の内戦化はいったん遠のき、表面だけをなぞれば、単なるマドゥロ大統領夫妻からロドリゲス兄妹への権力移譲劇のようでもある。
本稿執筆時の一月中旬、予断を許さぬ状況が未だつづく。以下、本件に至るまでの経緯を素描するとともに、カラカス空爆、その長い一日の出来事から浮かび上がる国内外のバランスを報告する。二〇二六年初頭のベネズエラ内政・外交の力学を思い返す一材料となれば幸いである。
ポスト・コロナの風景
筆者がベネズエラに到着したのは二〇二二年末だった。入国には新型コロナウイルスをめぐるPCR検査の陰性証明書がいまだ要請されていた頃である。数年前には年一三万%ものハイパーインフレが発生し、物資不足が深刻化していたと聞くが、スーパーに赴けば陳列棚には米ドル価格が表示された商品が並んでいた。米国銀行の口座など、ドルへのアクセスさえ獲保できれば、日常生活には何ら困らない状態である。
第一次トランプ政権は金融制裁(二〇一七年)、石油制裁(二〇一九年)とマドゥロ政権への圧力を強めてきた。内政も混迷を極める。二〇一八年の大統領選挙をボイコットした反体制派はフアン・グアイド国会議長を担ぎ出し、二〇一九年一月からは二人の大統領、二つの国会が居並ぶ異常事態となった。全国民の四分の一が国外へ避難したとも言われる。しかしそれでも体制は揺らがない。二〇二一年初頭にはトランプ政権が退場し、二〇二三年一月には反体制派が維持してきた大統領府も廃止された。政敵を着実に国外へと追いやり、どん底を乗り越えたマドゥロ大統領はむしろ自信を深めているようにも見えた。
外交面に目を移してみても、ロシア、中国、イラン等との連携の中、制裁回避のノウハウは着実に蓄積されてきた(その意味において、二〇二二年二月、ロシアによるウクライナ侵攻にともなう対ロシア制裁の発動は思わぬ痛手となった)。南米大陸では二〇二二年八月、隣国コロンビアにおいて、当国史上初の左派ペトロ政権が発足し、同年一〇月にはチャベス前大統領の盟友でもあったブラジルのルラ大統領が返り咲く。二〇一九年以来、ベネズエラとコロンビアとは断交状態がつづいていたが、両国を仲立ちとした国際的孤立からの脱却の道も見えてきた。
翌年に大統領選挙を控える二〇二三年一一月には、カリブ海のバルバドスで本格的な与野党対話が実施された。マドゥロ政権(代表はホルヘ・ロドリゲス国会議長)と反体制派の調整機構(統一プラットフォーム、二〇二一年発足)の交渉ではあるが、鍵を握るのは米国バイデン民主党政権の出方である。二〇二四年後半における自由選挙の実施、米国人収監者およびベネズエラ政治犯の釈放と引き換えに、マドゥロ政権は部分的な制裁解除を勝ち取った。無論、そこにはベネズエラの命運を握る石油も含まれていた。
暗転
しかし、二〇二四年に入ると雲行きは怪しくなる。