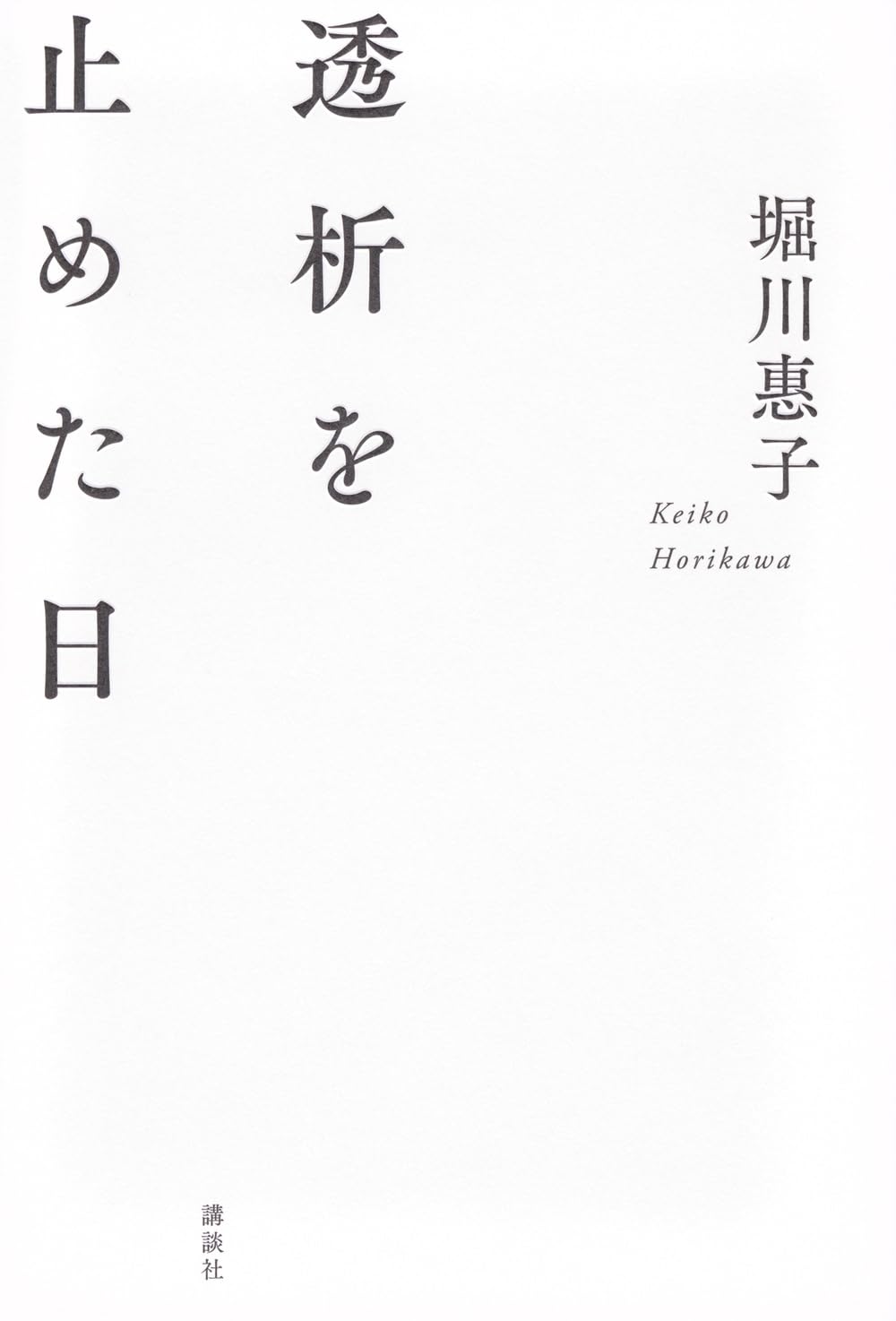紹介する本:『『透析を止めた日』堀川惠子著、講談社、2024年11月
2024年11月、『透析を止めた日』という本を、ジャーナリストの堀川惠子さんが上梓された。この本は、お連れ合いの元NHKプロデューサー林新さんの闘病を支え、その最期を看取った経験から、透析業界の問題に迫った医療ノンフィクションだ。
透析患者はどうして「安らかな死」を迎えることができないのか? どうして、がん患者以外は「緩和ケア」を受けることさえできないのか? 10年以上におよぶ血液透析、腎移植、再透析の末、透析を止める決断をした夫。その壮絶な最期を看取った著者が、徹底した取材で記していた。
「夫の全身状態が悪化し、命綱であった透析を維持することができなくなり始めたとき、どう対処すればいいのか途方に暮れた。医師に問うても、答えは返ってこない。私たちには、どんな苦痛を伴おうとも、たとえ本人の意識がなくなろうとも、とことん透析を回しつづける道しか示されなかった。そして60歳と3カ月、人生最後の数日に人生最大の苦しみを味わうことになった。それは、本当に避けられぬ苦痛だったのか、今も少なからぬ疑問を抱いている。……なぜ、矛盾だらけの医療制度を誰も変えようとしないのか。医療とは、いったい誰のためのものなのか」。
赤裸々に綴られていた。透析患者の終末期の医療現場での医師の対応の酷さに衝撃を受けた。怯え、怒りさえ覚えた。他人事ではないと思った。本屋としてこの現状を伝え、改善を訴えなければならないという使命のようなものが湧き上がってきた。すぐにイベントを企画すべく動いた。医療の問題なので、対談相手には専門的な知見が必要だ。親しくさせていただいている大阪大学名誉教授の仲野徹先生にお願いした。
12月初旬にイベントの告知をするなり、北は北海道の徳洲会病院の医師、南は沖縄で緩和ケアに従事されている方まで申し込みがあった。そして東京や千葉、全国から緩和ケアの施設を経営されている方や、緩和医療指導医、他の科の医師など、医療従事者のお申し込みが殺到した。お住まいは堺なのに、大阪の中央区にある隆祥館書店に、毎月一度は本を購入しに来て下さる松浦基夫先生にも本をお薦めした。するとなんと松浦先生は腎臓内科医だった。
1月18日、イベントの日を迎えた。会場は定員の50人を超えた。オンラインも70名を越えた。
堀川さんは、林新さんの終末期に体験されたことで本に書ききれなかったことについて話された。
「林さんは、透析があったから生きがいである仕事が続けられた。そのことに感謝している。だからこそ全身状態が悪化し、命綱であった透析を維持することができなくなり始めた時にも、心のケアを受けることができたら、『魂の痛み』ともいえる苦しみも少しは、軽減されたのではないか」と話された。
腎臓内科医の松浦先生は、「痛みがある患者さんの痛みを取るということは、緩和医であれ、先進医であれ、透析医であれ、全力で取り組まなければならないことだ! なぜその姿勢で取り組まなかったのか! 非常に残念や」と話され、思わず拍手した。
本書の後半に、末期腎不全の患者への「腹膜透析緩和PD」などを実践する医師が登場する。当事者を間近で見ていた堀川さんだからこそ、取材できたことがある。終末期に「腹膜透析緩和PD」を選んだ透析患者たちの、いくつもの看取りの現場だ。穏やかだったのは、亡き人たちだけではない。彼らを囲む家族や医療者もどこか納得して死を見送っていた気がするという。
この本をきっかけに政治も動いた。2月には、この本を読んだ元法務大臣の上川陽子氏を呼びかけ人とした腎疾患患者に対する自民党の勉強会が立ち上がり、日本腎臓学会、日本透析学会、日本緩和医療学会、患者団体、そして厚生労働省健康局の関係者を交えた勉強会に発展してゆく、そして5月に提言を発表し、それを受けた厚生労働省や関連学会が動き始めた。6月には、来年度予算編成の指針となる「骨太の方針」に腎不全患者の緩和ケアの推進が明記された。
そして、9月末には、すでに自民党議連の提言を受けていた3学会が合同で「腎不全・緩和ケアガイダンス」を公表した。現在はさらに、診療報酬改定に向けた、詰めの議論が行なわれている段階だ。
1冊の本をきっかけに、声なき声が上がり、医療における緩和ケアの大きな岩が動いた。
堀川さんは、メールのやり取りの中で、本書は「制度の改革を実現してこそ成就する」と書かれていた。自らの体験を訴えることで、今この瞬間も苦しんでおられる大勢の方々のために、少しでも早く社会に影響を与えて制度を変えたい、と願いながら刊行されたのだ。その姿勢は、自らを律して、制度と闘っておられるようにさえ感じた。
『透析を止めた日』という本を書いて下さったおかげで、本を薦め、現状を伝えることができた、そして本を読んだ方々が、何とかしなければと動いて下さったのだ。この連鎖の力で、医療制度が動いたと思うと、本を扱っている人間として、身体が高揚してくるような嬉しさを覚えた。