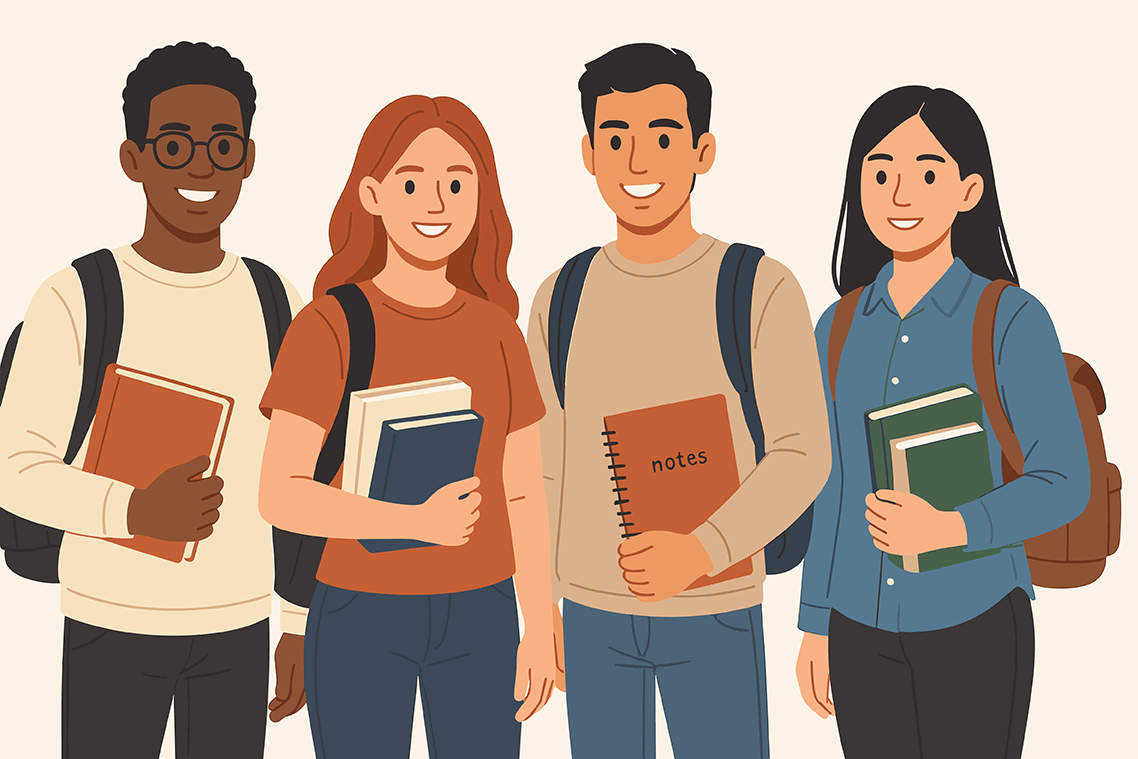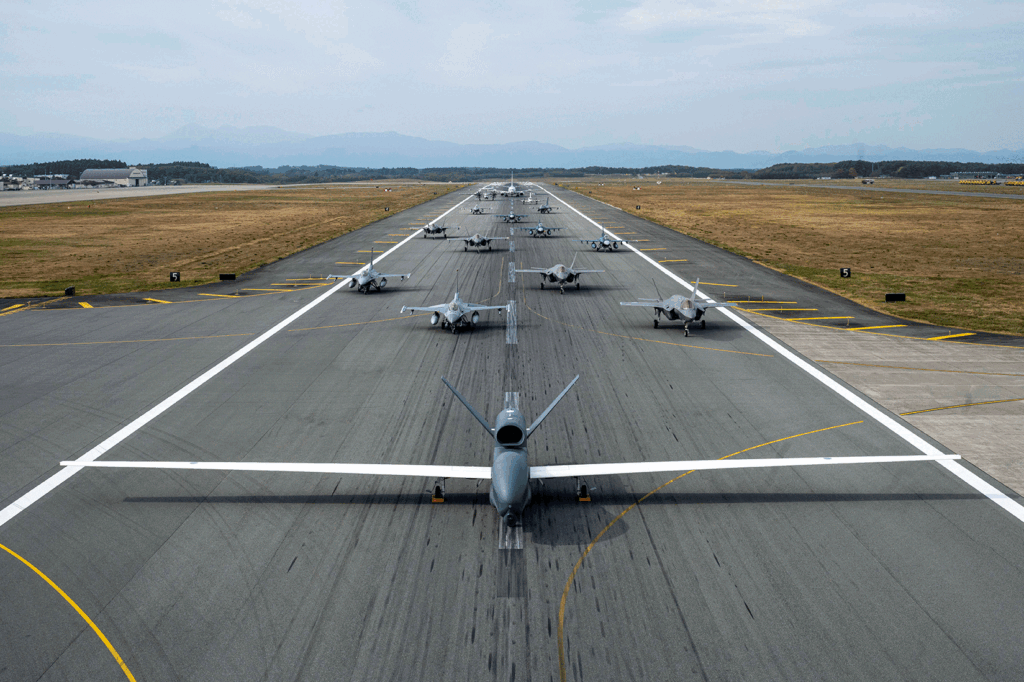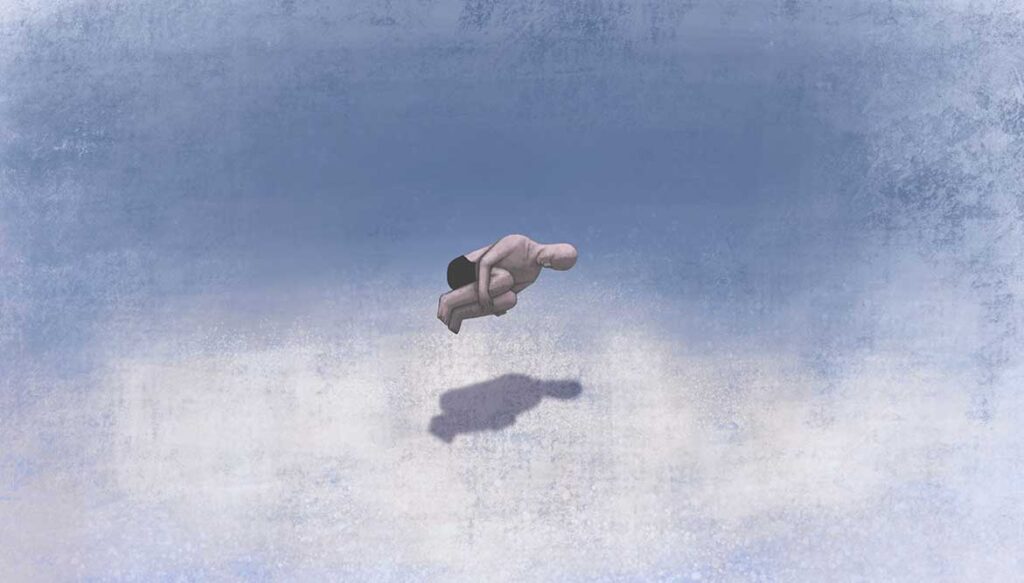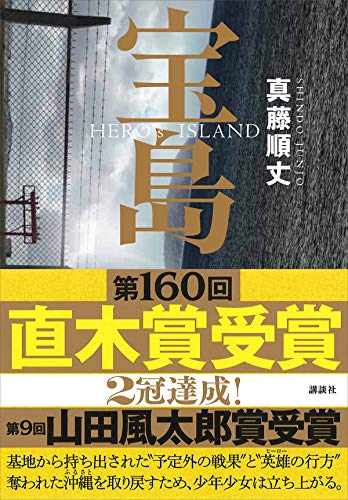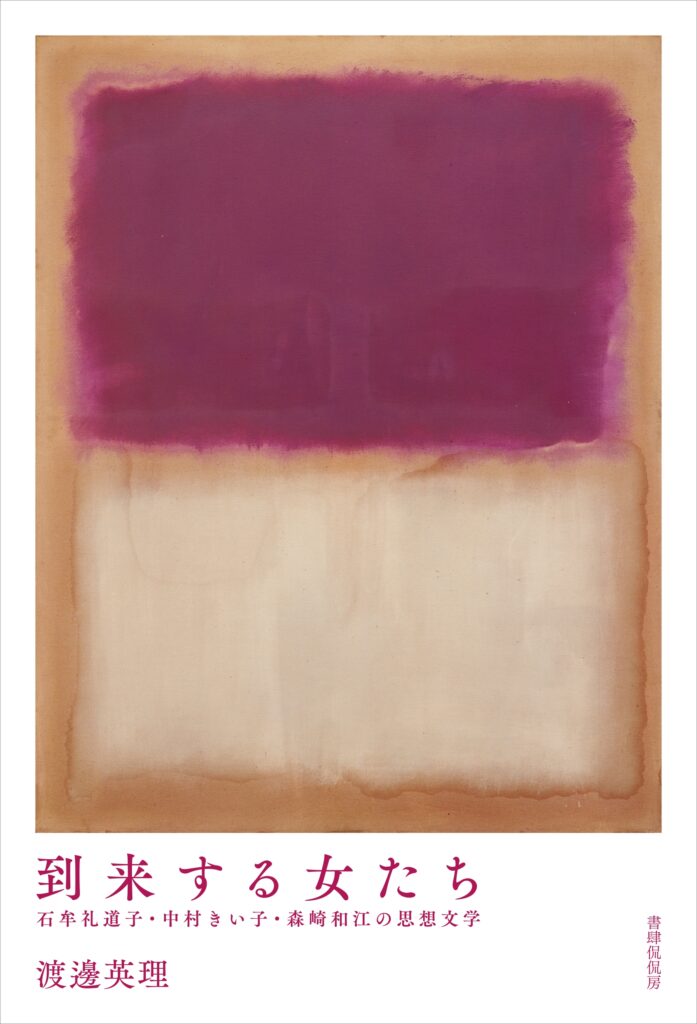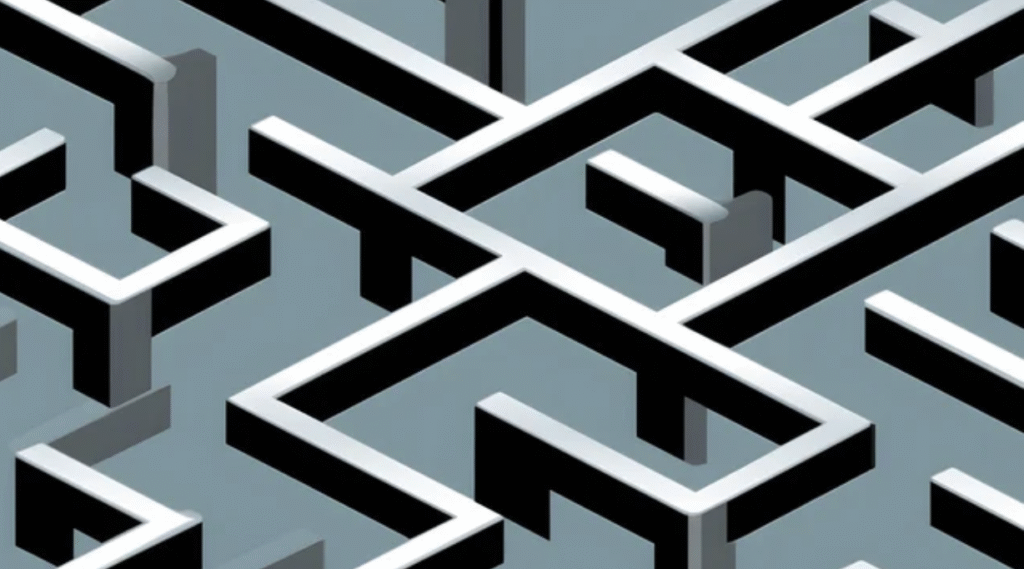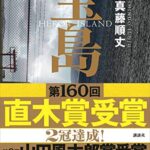文部科学省は、博士課程の大学院生への支援制度・JST SPRING(以下、SPRING)について、今年3月の国会における自民党・有村治子議員からの「問題提起」を受け、支援対象を「日本人」限定にするという方針を6月26日に示し、7月30日に本決定した。これに対して大学院生中心の抗議行動が、9月現在でも続けられている。
筆者は、この抗議行動に発起人・主催者としても関わってきた。その立場から、この文科省の決定を理解するための前提を確認し、その問題点、そして抗議行動の成果と展望について、これまでメディアが言及してこなかった切り口から、『地平』読者のみなさまにお伝えしたい。
博士課程の大学院生の現状
まず前提として、この問題を的確に把握するためには博士課程の大学院生の現状を押さえておく必要がある。
2000年代以降、「イノベーションを創出するためには競争力が必要」という発想から、いわゆる研究の「選択と集中」政策が、特に各種交付金の減額という形で実施されており、大学教員たちが厳しい状況に陥っていることはよく知られている。しかし、このあおりが博士課程の大学院生にまで及んでいることはあまり意識されていない。博士課程は学部・修士課程とは根本的に異なり、研究のアウトプットを行なうことが中心となるため、必要な費用を確保できなければ研究ができず、課程を修了することが難しくなる。教員に分配される研究費が減ると、大学院生に降りてくる額も少なくなるか、まったくなくなる。指導教員が外部研究費を獲得したとしても、特に文系の場合は「一人一分野」と言われるほど教員とテーマが重ならないことが多いため、その研究費を分けてもらいながら自分の研究を進めるという選択肢は消える。すると、博士課程の大学院生も自力で大学内外の研究費を「競争」によって勝ち取るしかなくなるのである。SPRINGは生活費支給と研究費がセットになっているものだが、このような文脈の中で「競争」に勝って初めて受けることができる、国(文科省)の制度である。
こういったプレッシャーに日々さらされる中で、多くの博士課程の大学院生にとって物心両面で「砦」となっているのが、同期や先輩・後輩といった仲間の存在である。ただでさえ博士課程は孤立しやすく、メンタルヘルスが課題とされて久しいが、研究室やゼミに支え合う存在がいてこそ、なんとか前に進めるのである。そして、その仲間の中には、少なくない割合で留学生も存在する。
文科省の「学校基本調査」によれば2024年末時点で博士課程在籍者は約8万人、うち留学生は2万3000人程度である。博士課程の大学院生の平均29%程度、約3人に1人が留学生となる計算だ。筆者の所属専攻では自分を含めた同期4人中、2人が中国人留学生であり、文字通り苦楽を共にしてきた。また「留学生」と聞くと一時的な滞在でいずれ帰国するというイメージが強いが、彼女らはそうではない。中国のアカデミアの就職は厳しさを増しており、応募の際に点数で計算される業績も、日本語のものは点にならないことが多い。彼女らは日本社会に人生をかけているし、日本社会を信頼するしかない。身近な事例ではあるが、お互い支え合う生涯の友となる仲間を、国籍を理由に支援制度から排除することがどれほど理不尽なことか、博士課程の大学院生の目線からどのように見えるのか、という問題である。
「日本人」限定方針の問題点
文科省のこの方針は問題ばかりだが、特に共有しておきたい点が2つある。1つ目は「外国人」という理由で、特に中国人留学生の排除が目指されたこと自体に重大な問題がある。