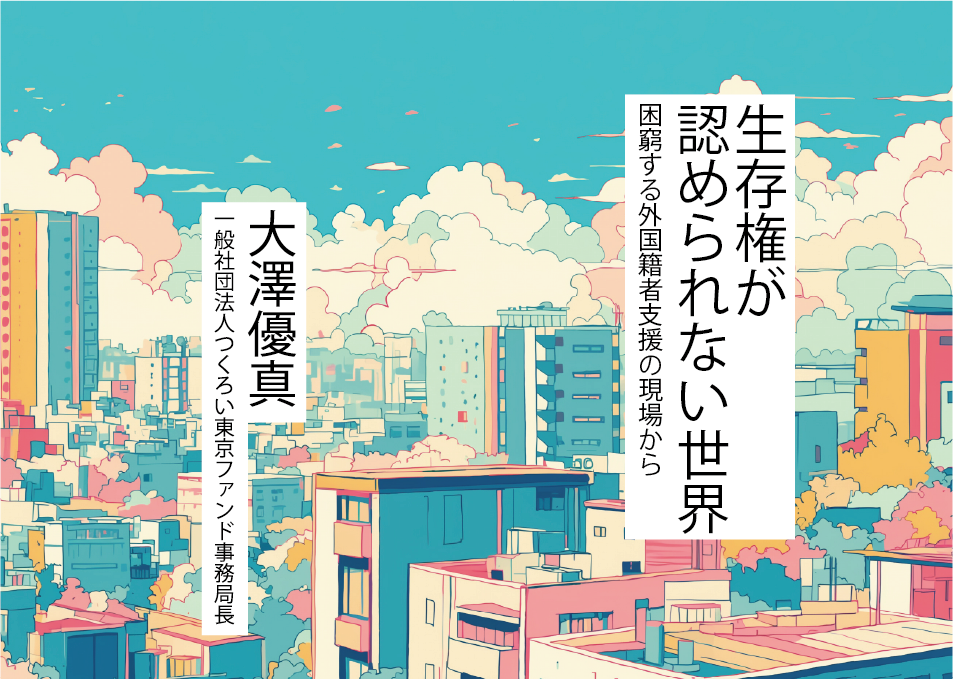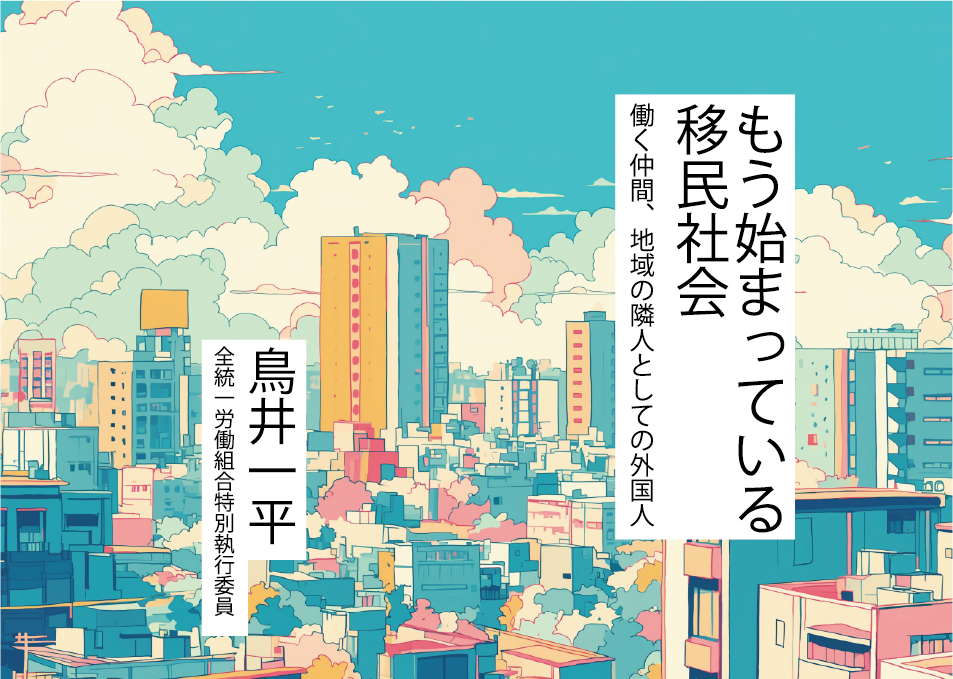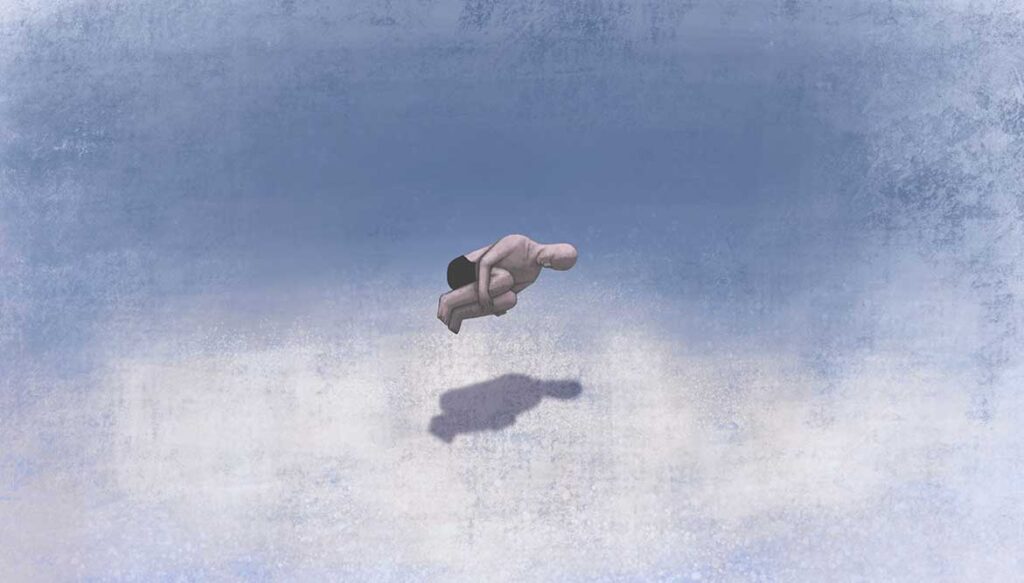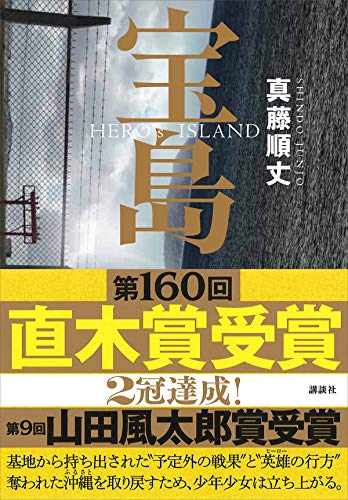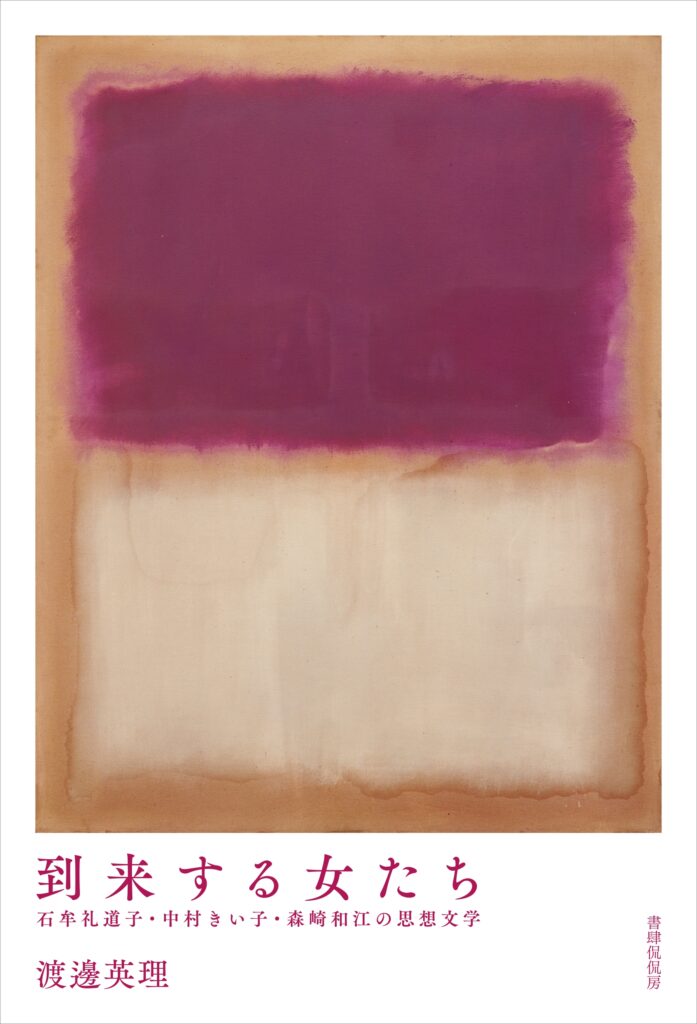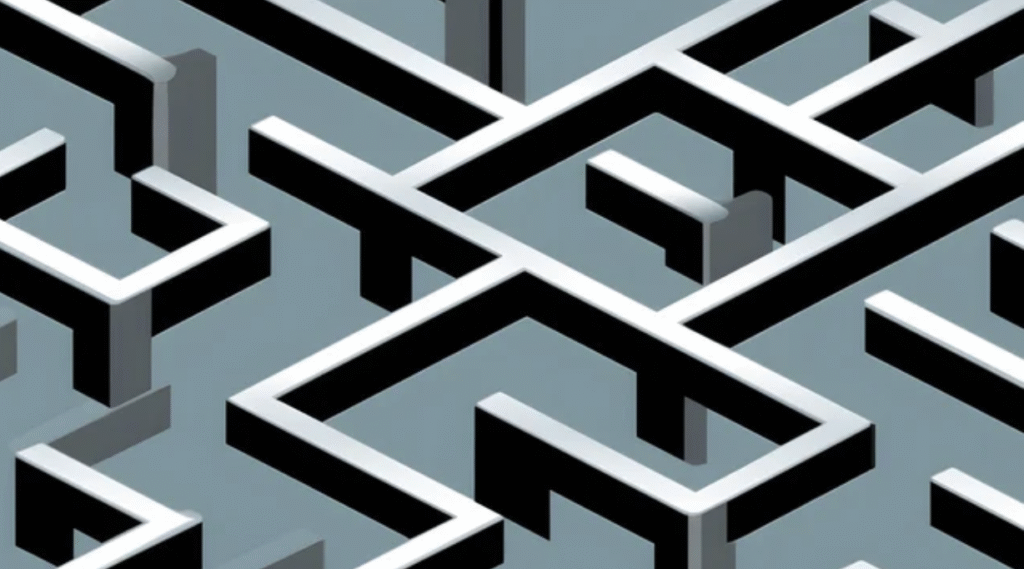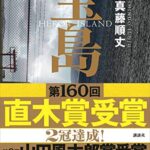【関連】特集:隣人である移民(2025年11月号)
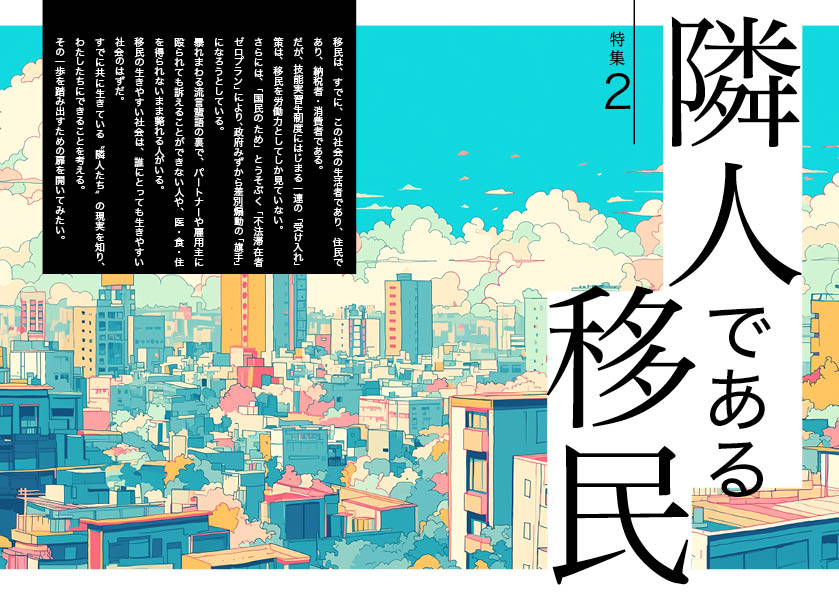
生活保護を廃止にするということ
私は関東圏を中心に、生活困窮者への支援活動を行なっている。国籍による区別は設けていないが、私のもとに寄せられる相談のほとんどは公的制度を利用できない外国籍者からだ。「食べるものがありません」「病気でつらいです。でもお金がなくて病院に行けません」「家賃が払えません」「外で寝ています」といったSOSをほぼ毎日受け取る。
先の参議院選挙では排外主義的言説が多く出回った。その中のひとつに「外国人と生活保護」があった。SNSなどでは「生活保護受給世帯の3分の1は外国人」「生活保護目当てに外国人が殺到している」といったデマ情報が拡散された。当選したある議員は「われわれの税金で外国人が生活保護もらったりして年間1200億円ぐらい……日本人はなかなか受給できないのに、外国人はね、すぐさまもらえてしまう(注1)」と発言していたが、明確なデマである。また、議席を大幅に増やした国政政党は「外国人への生活保護支給を停止」を公約に掲げていた。外国人生活保護廃止を主張する候補者は以前からいたが、多くは「泡沫候補」で、さほど目立っていなかった。しかし、今回は違った。
1 NHK 2025年7月16日「参院選・神奈川 初鹿野裕樹氏(参政・新)ノーカット動画・演説全文」。
2007年、北九州市で生活保護を無理やり辞退させられた男性が、「腹減った。オニギリ食いたい」と日記に書き残し、餓死した事件があった。外国籍者の生活保護を廃止するということは、このような事件が起きるということであり、それを問題なしとするということである。そして後述するように、現にいま日本に暮らす外国籍者の半数以上は、困窮しても生活保護を利用できない。どうにかする人もいるが、どうにもならずに支援団体へと冒頭のようなSOSを出す人が多くいる。なかには亡くなった人もいた。外国人生活保護廃止を主張する人は、この現実を理解した上で発言しているのだろうか。私にはそうは思えないし、もしそうであるなら人の命と健康を軽視しすぎている。
しかしながら、外国人生活保護廃止を唱える人が増えていることも感じている。その背景のひとつに、現実が知られていないことがあるだろう。排外主義が吹きすさぶいま、現実にもとづき組み立てる議論が必要だ。そこで本稿では、支援者の立場から、公的支援を利用できない外国籍者の「生きていけない」現実を読者のみなさんと共有したい(注2)。
2 「外国人と生活保護」に関するデマに関しては複数のマスメディアがファクトチェックを行なっている。筆者個人ウェブサイト「外国人関係ファクトチェック記事まとめ」等を参照されたい。
生活保護「準用措置」
日本には、生活に困窮したときに利用できる制度として、生活保護がある。生活保護は生活に困窮している人に、日本国憲法第25条に規定されている「健康で文化的な最低限度の生活」、生存権を保障する仕組みであり、具体的には生活費や医療費、住宅費などが国・自治体から支給される。生活保護を利用することができれば、不十分かもしれないが、ある程度の医食住が保障されるようになる。
一方で、外国籍者にはこの生活保護を利用する権利がない。その代わり、ややこしいのだが、権利性のない「準用措置」という形で保護を利用できる場合がある。ただし、「準用措置」はすべての外国籍者に開かれているわけではなく、限定された在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特定活動の一部)を有していることが条件となっている。2024年末時点で、日本に暮らす在留外国人のうち57.0%(162万70人)は「準用措置」の適用対象外だ(注3)。この162万人の外国籍者すべてが生活に困窮するわけではないが、かれらがひとたび困窮すると公的支援はほとんどなく、そこから脱することが困難になる。
3 在留外国人統計より筆者計算。
それに、「準用措置」を利用できたら問題なしかというとそういうわけでもない。「準用措置」は権利ではないので、不利益なことがあっても審査請求ができない。この原稿を書いているいま、夫のDVから逃れている外国籍の女性が警察に相談したのち、市役所で「準用措置」の申請を行なったものの、婚姻関係が続いていることを理由に却下されてしまったという相談を受けている。この場合、日本国籍者であれば都道府県知事に審査請求を行ない、その対応が正当であったか判断されるのだが、外国籍者の場合は法的に文句を言うことができず、泣き寝入りになる可能性がある。「準用措置」利用をきっかけにした在留期間の短縮や更新不許可を恐れ、申請をためらう人も少なくない。