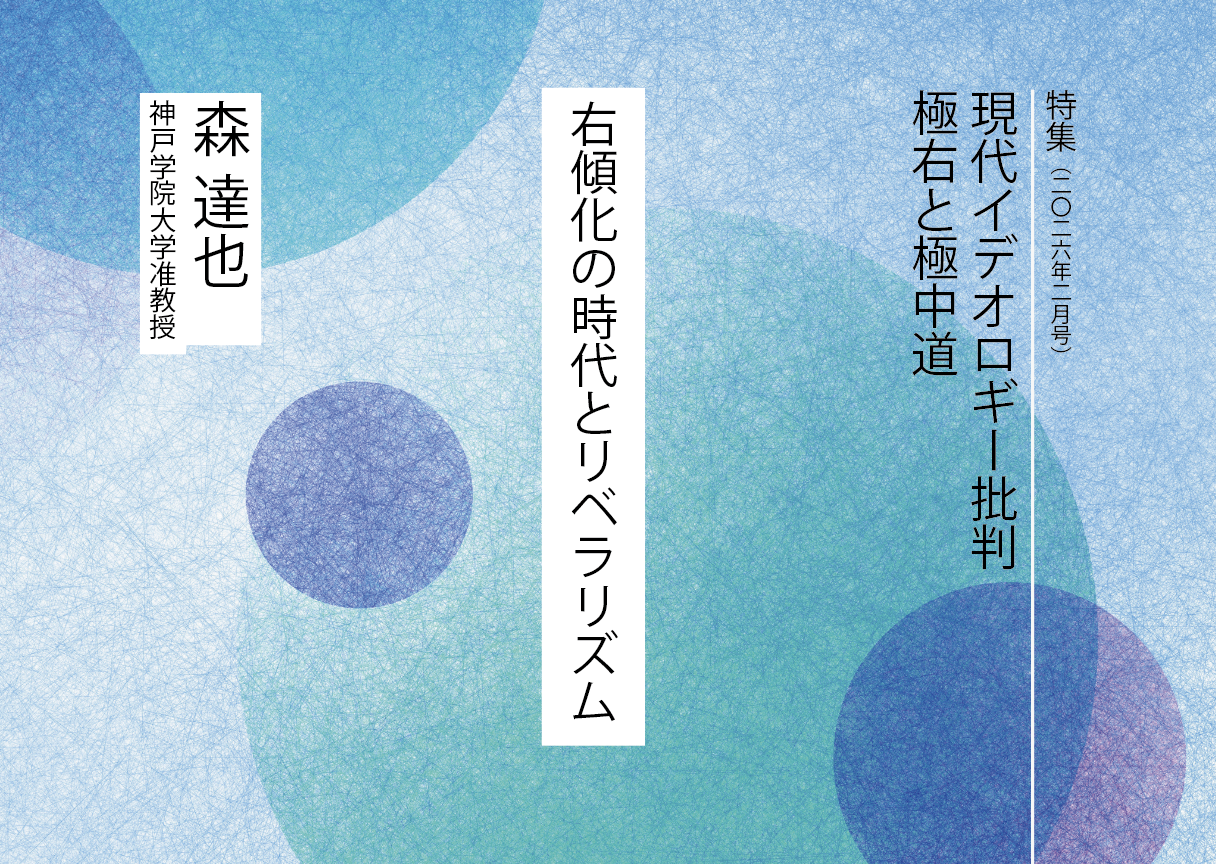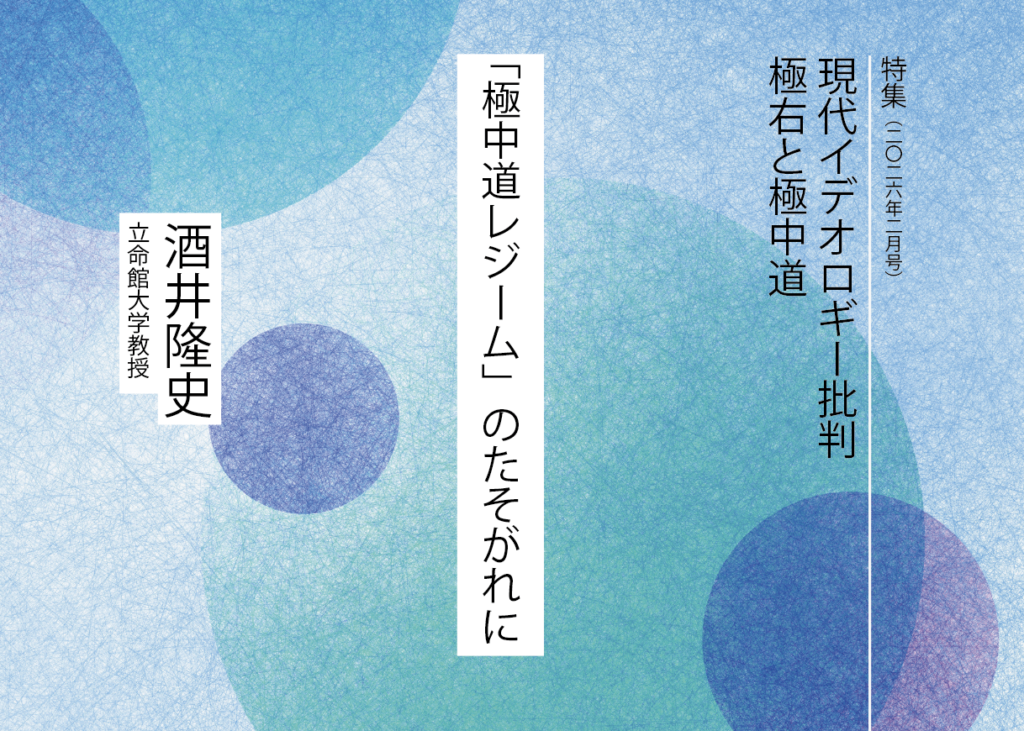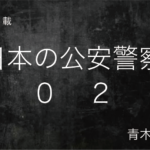【関連】特集:「現代イデオロギー批判:極右と極中道」(2026年2月号)
世界を席巻しつつある極右思想、これを果たして思想と呼ぶべきか否かという問いは、ナショナリズムは思想であるか否かという問いと似ている。
真剣な思想家は誤謬や矛盾を極力排除することを試みるが、極右思想はむしろ積極的に虚偽を取り込みながらその勢いを増す。それは人びとの情念を喚起する簡易な思想的発火装置として機能する。この政治的武器は非常にシンプルで扱いやすいがゆえに、各地の極右たちの間で取引され、カスタマイズされ、実戦投入される。しかも実際の武器とは異なり、インターネットを通じて容易に運び出すことができる。「ペンは剣よりも強し」という言葉があるが、極右思想はもう一つの剣なのである。
以下ではまず、今日の世界的な右傾化の諸要因とその思想的特徴を把握するために、近年相次いで刊行された二著作の議論を紹介する。その上で、それらとやや趣を異にする服飾の歴史に関する著作を通じて、私たちがこの流れに対抗するために何に目を向ければよいのか、その糸口となりうる一つの考えを提示したい。
グローバル化する極右とリベラリズムの後退
まず取り上げるのは、佐原徹哉の『極右インターナショナリズムの時代』である。今日のグローバルな極右台頭の背景とその伝播のメカニズムを解き明かす本書は、私たちが日々あちこちで目にする多様な右傾化の断片のその隙間にパズルピースが次々嵌め込まれていくような、稀有な読書体験を与えてくれる。もちろん、人間にはもともと現象間のつながりを推論する傾向があるため、ネットワークの存在を安易に想定することは陰謀論の入り口でもあることを私たちは知っているが、本書は膨大な資料と著者の見識に裏づけられた議論によって極右の国際的ネットワーキングの実態を鮮明に描き出している。
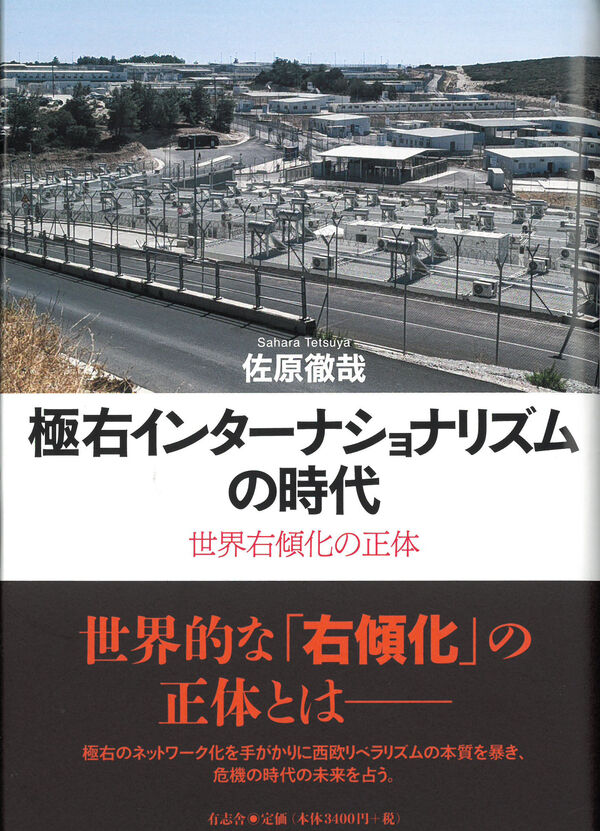
「カウンター・ジハード主義」とは文字通りには「ジハード主義」への対抗を指す言葉だが、この運動はイスラム過激派の撲滅を目指すものではなく、むしろジハード主義の台頭を招いたとされるリベラルな多文化主義政策を敵視し、その恩恵にあずかるマイノリティを攻撃対象とする過激思想であるという。実行犯はしばしば「キリスト教原理主義者」だと説明されるが、実際は信仰者ではなく、インターネット上の陰謀論などに触発されて単独犯行型の無差別攻撃事件を引き起こしている。他方で「ジハード主義」が伝統的なイスラム教とはかけ離れた現代的カルトであることは比較的知られているが、著者は一九七〇年代末に信仰復興運動の一種である近代サラフ主義の軍事主義的な変種が生まれたのち、地域紛争に参じる義勇兵の教育を通じてそのネットワークが拡大していく様子を詳らかにしている。両者は一見すると正反対の運動であるが、グローバル化と新自由主義に対抗する「反システム運動」という性格を共有している点で鏡像関係にあるという。
本書の最大の特徴は、この両者が共にバルカン半島と深い関わりをもつという洞察である。バルカンは「冷戦後の地域紛争や新自由主義政策の失敗によって『グローバル化』の負の側面を集中的に経験してきた地域であり、更に、ヨーロッパで唯一の歴史的なムスリム地域であるという理由から、イスラム主義者と『白人』人種主義者の双方が深い関心を向けている場所でもある」(六頁)。たとえば二〇一一年のノルウェー連続テロ事件の犯人であるブレイヴィクの反移民思想の背後には、「人口動態戦争」によってムスリムがヨーロッパを乗っ取るという「歴史的ジェノサイド論」と、その「最前線」で戦うセルビア民族主義者の英雄視があったという。これらの言説は欧米の極右とセルビア民族主義者との交流から生まれた。かれらは自分たちの「学術共同体」を構築して仲間内で「論文」の相互引用を繰り返すという、いわばアカデミア版エコーチェンバーによって知的権威を擬態しており、もはや門外漢には本物と見分けがつかない。そしてかれらの記事に感化された「ネット戦士」たちがそれを拡散・実行するというパターンが確立する。他方でジハード主義者たちはボスニア内戦に際して「セルビア人の民族浄化から同胞を救う」という名目で戦闘員を送り込んだが、紛争終結後に定住した一部が形成した閉鎖的なコミュニティが、欧州諸国を標的とするテロリズムの拠点として機能したという。こうした過激思想の台頭は穏健なイスラム主義にも影響を及ぼし、トルコのイスラム国家化を進める一因となった。
極右の活動がマジョリティの右傾化を促進するという現象は欧州でも生じている。第三章では前述の陰謀論にも垣間見えた「入れ替え論」が検討されている。フランスの極右思想家ルノー・カミュは古典的な文化保守の立場から出発しながらも、ムスリムを異質な「ヨーロッパの他者」と規定することにより、みずからの文化防衛論を人種主義(レイシズム)へと変質させることになる。それが新大陸の人種主義者たちに受容され、白人ナショナリズムと融合する。アーネスト・ゲルナーの言う社会的耐エントロピー特性を実証するかたちで、イスラムと有色人種という目立つ特徴に向けて差別が収斂していくのである。加えて、イスラエルのパレスチナ人迫害を欧米の極右が「人種主義の復権」のために支持するという構図と、欧米諸国による親イスラエル政策が重なり合った結果、イスラエル批判を「反ユダヤ主義」として政府が取り締まるという異常な事態が生じている。
第四章では世界的右傾化の典型例として、ポスト冷戦期におけるブルガリアの極右勢力台頭の経緯が説明される。同国における極右の台頭は移民の増加によるものではなく、むしろ「オスマンの軛(くびき)」という被害者意識に基づく強烈な反イスラム主義と、ポスト社会主義体制下における同国の新自由主義政策の破綻がその主要な原動力であるというのが著者の見解である。この被害者意識ナショナリズムは歴史の客観視を拒む。二〇〇七年の「バタク論争」では、残忍なオスマン・トルコが無辜のブルガリア人を虐殺したという「神話」は必ずしも真実ではないという歴史家の議論が、民族主義者によって激しく拒絶されたという。
深刻なのは、こうした極右のムスリム像がリベラルの間にも浸透しつつあるという事実である。第五章では欧州難民危機がもたらしたEUの倫理的破綻が暴露される。シリア難民の大量流入に直面したEUと加盟諸国は表向きには人道主義を掲げながらも、「難民に紛れたテロリスト」のイメージを利用して国境管理を厳格化し、強制収容、域外送還、そして難民条約に違反する「押し戻し」を実施した。著者によれば、こうしたダブルスタンダードは「極右がリベラル派の本音を代弁し、それを口実に、それまで躊躇してきた極端な政策を遂行」(三六九頁)した結果である。ゴムボートに乗った地中海の難民は、かれらが他の安全なルートを通ってEU加盟国に入国する道を法的に閉ざしたがゆえに(さらには国家当局と犯罪組織との結託により)生じたという事実は、シリア難民に関する私たちの表層的な認識を改めるよう迫る。
このように著者の現状認識は厳しいものであり、その展望にも楽観的なところはない。新自由主義システムが育むグローバル・エリートたちは強固なネットワークを構築し、資本の利害に基づいてより一層選別的な移民政策を実施する。このエリート層を頂点として、その下に従属する流動性の低い人びと、さらに人間としての権利を奪われた実質的な奴隷身分という「三層構造の世界」が展望される。この構造が存続するかぎり、反システム運動である過激派の活動が止むことはない。この暗い未来像を変えるためにはどうすればよいのか。著者によれば、必要なのは第二層と第三層の人びとが「連帯」し、目下の分配メカニズムの変更を求めることであるが、そこには常に両者を「分断」させることでエリート層に奉仕する極右の存在があるという。つまり反システム運動はシステムと表裏一体の関係にある。グローバル資本主義の下で「リベラルは左派とは相容れないが、極右とは仲良くやれる」(三七二頁)という皮肉な状況を直視することなくして、私たちが出口を見つけることはできないのかもしれない。