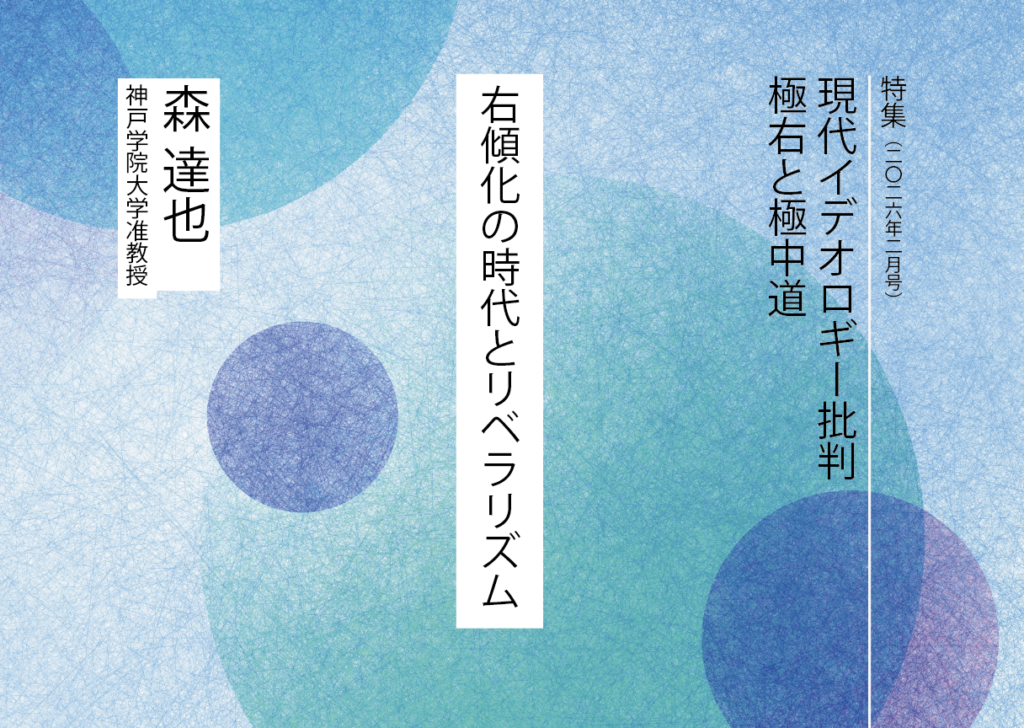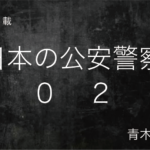大島堅一
龍谷大学政策学部教授。専門は環境経済学。著書に『炭素排出ゼロ時代の地域分散型エネルギー』(日本評論社)、『原発のコスト——エネルギー転換への視点』(岩波新書)、『原発はやっぱり割に合わない——国民から見た本当のコスト』(東洋経済新報社)など。
(聞き手 本誌編集長・熊谷伸一郎)
再稼働をめぐる経営問題と政治問題
――新潟県知事の同意により、柏崎刈羽原発の再稼働が現実味を帯びてきました。福島第一原発事故の賠償も終わっておらず、事故の収束すら見通せていない中の再稼働について、その意味をどのようにお考えになりますか。
大島堅一(以下、大島) 福島第一原発事故を起こした当事者である東京電力(以下、東電)が、再び原発を動かそうとしているという時点で、きわめて重大な問題です。福島原発事故の教訓を踏まえれば、本来は動かしてはいけないはずのもので、それでも再稼働しようとしていること自体、根本的な議論が必要ではないでしょうか。
まず指摘しておきたいことは、この再稼働という方向性は、通常の企業の経営判断としてはありえないものだということです。そもそも東京電力という会社は、もはや自律的に経営の観点から判断できるような通常の民間企業ではなくなっています。政府が設立した原子力損害賠償・廃炉等支援機構は東電の過半数の株式を持っており、実質的に政府が資本を握る「国有民営」の状態となっています。今回の動きは、政治的な意図によって再稼働が進められている面が大きいと思います。合理的に考えれば、福島原発事故の収束もしておらず、柏崎刈羽の安全対策にも莫大な投資が必要で、再稼働したとしても経済的に採算が取れることはありえません。普通の経営判断なら原発の運用自体をやめたほうがいいという結論になるはずです。
――「再稼働によりコストが浮く」とも言われています。
大島 それは単純化された言い方だと思います。これまでの莫大な投資を度外視して燃料費の差額だけで見れば、単年度ではプラスになるかもしれません。しかし、本来の投資という観点から見れば、それは意味を持ちません。
柏崎刈羽にかかる追加安全対策費は、二〇一九年の時点で一兆一六九〇億円とされていました。実際にはそれ以上に膨らんでいるでしょう。さらに、毎年一〇〇〇億円ほどの維持費がかかってきています。この巨額の投資額に対して、再稼働により得られる見返りはわずかです。
投資家は資本に対する利回りを考えるものです。ところが東電は単年度の損益しか考えておらず、その損益についても根拠があやふやです。東電やマスメディアは再稼働により「年間で一〇〇〇億円程度のコストが浮く」と、まことしやかに言うのですが、根拠は不明です。
たとえば、電力を市場調達で買う場合と比較して三〇〇億円程度はコストが安くなるという計算なら、現在の市場価格と東京電力の需要から割り出して、理解はできます。たとえば、柏崎刈羽の原発を二基動かし、トラブルもなく順調に稼働できたとして、年間の発電量は約一五八億キロワット時です。これを市場調達した場合には、今年の調達価格で掛け算すれば一九一三億円程度になります。再稼働すれば、維持費が約一〇〇〇億円、核燃料費が約四〇〇億円で、合わせて一四〇〇億円強となり、その差額は三〇〇億円ほどになるわけです。どこをどう見ても一〇〇〇億円という話にはなりません。
しかし、仮に東電が言うように一〇〇〇億円程度のコストが浮くとしても、安全対策だけで一兆二〇〇〇億円、事故後の維持費だけでも一兆円を超える額を投資していて、それはさらに増える見込みなのですから、年間の利回りは微々たるものです。原発の稼働率を60%で見積もれば赤字です。そして、いつ地震やトラブルで完全に停止してしまうかもわからない。事故を再び起こすようであれば、東京電力という企業は今度こそ消えることになるでしょう。
つまり、すでに柏崎刈羽原発は、通常の企業であれば「損切りして撤退すべき案件」であることは明らかです。経済的な合理性で考えれば、これまでの巨額の投資をもっと別のものに振り向けておくべきだった。しかし、判断の主体が実質的には政府なので、政治的な理由で再稼働をしようとしているのです。これは経営ではなく、政策です。