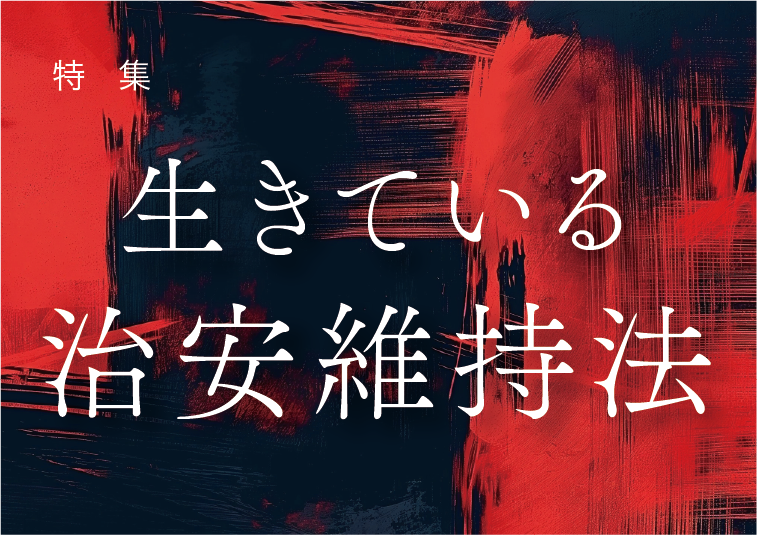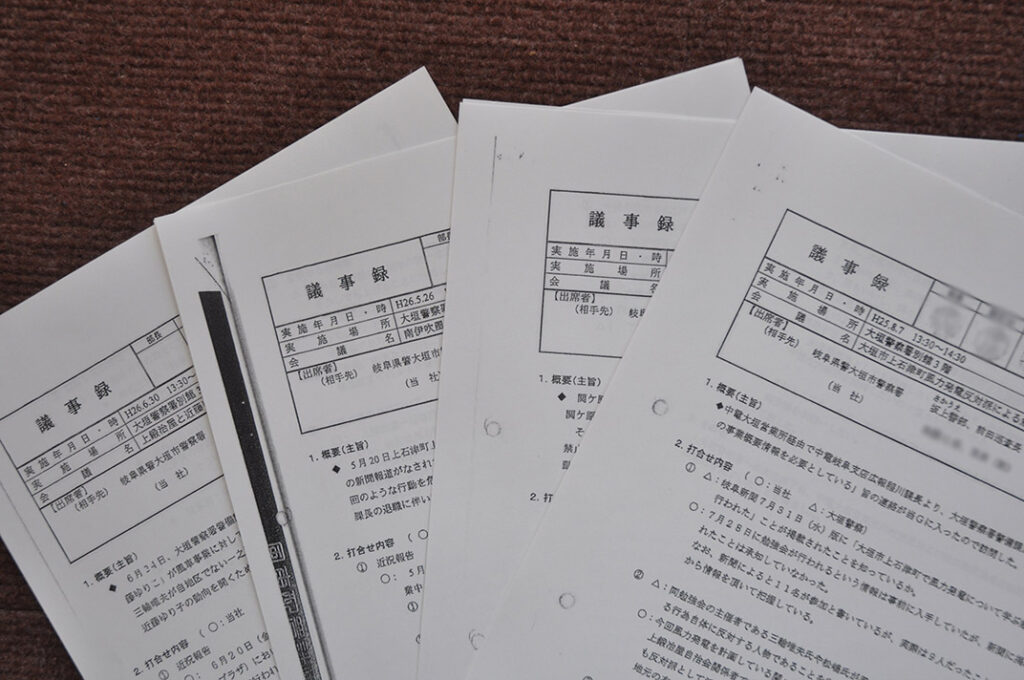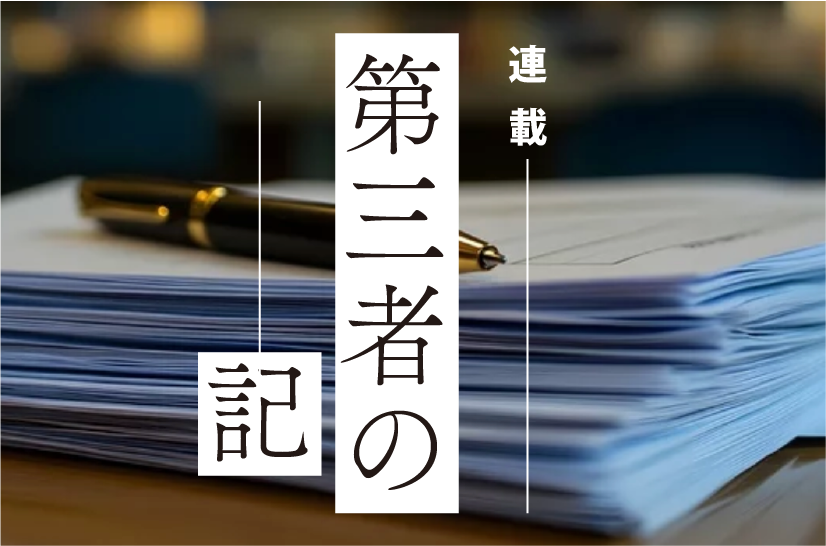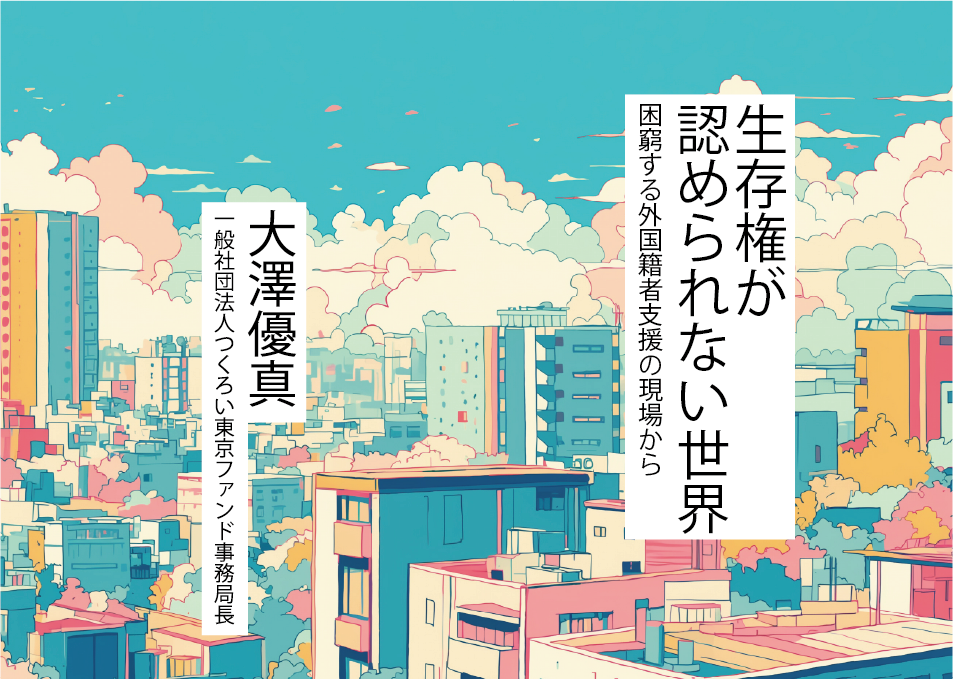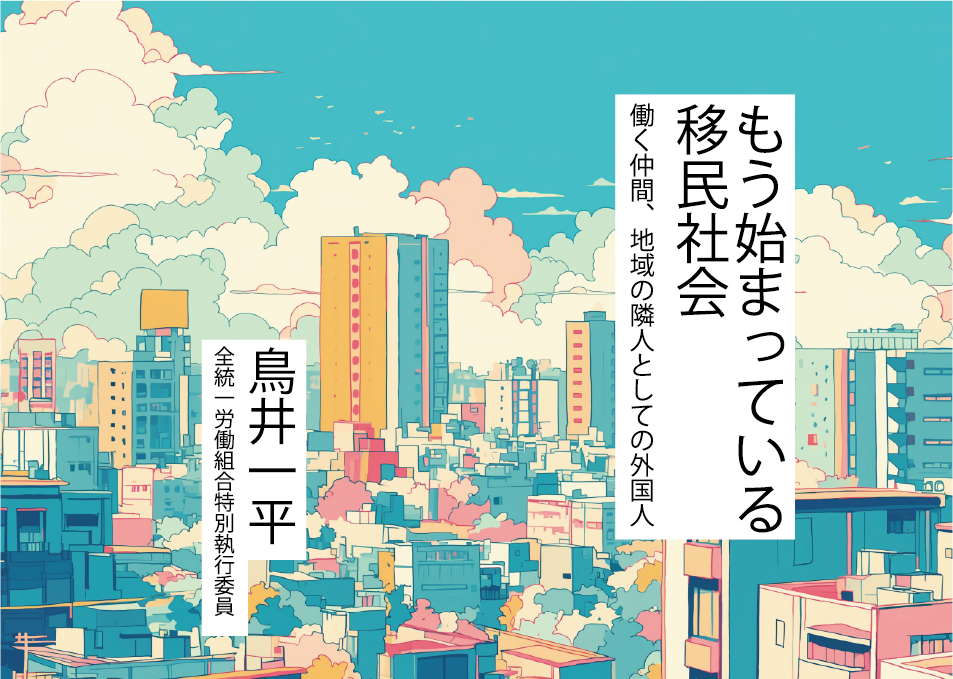特集「生きている治安維持法」のほかの記事はこちら
治安維持法擁護・肯定論
小野寺拓也・田野大輔『ナチスは「良いこと」もしたのか?』(岩波ブックレット)にならって、「治安維持法にも『良いこと』があったのか?」という設定をしてみよう。その問いは「歴史学や法学などからみて、治安維持法に評価できる点はあったのか」と言い換えることができる。すなわち、治安維持法の「悪法」性を否定し、擁護・肯定する論の検証をおこなうことになる。
この擁護・肯定論は大きく二つに分けられる。
一つは「悪法も法なり」の観点に立って、実際にどれほどの苛烈さで運用されたかについては捨象し、問答無用に合法であったとする見解である。その論理は、治安維持法の運用の主導者であった池田克が「公職追放」解除後の1955年、最高裁裁判官に就任する際に語った「あの時代の国家の事情としては、国会を通ったのだし、望ましいことではないにしても、やむをえなかったのではないか」(『週刊朝日』1955年2月27日)という他人事のような弁明に早くもあらわれている。
三木内閣期の自民党幹事長であった中曽根康弘は1975年12月のNHK「国会討論会」で、スト権回復闘争に関連して「治安維持法の話が出たが、不満な法律であっても法律としてあるからには守らなければならない」と発言している(山本英典・内中偉雄中曽根康弘研究』、1976年)。この発言と通底するのが、2017年6月の衆議院法務委員会の共謀罪法案審議における金田勝年法相の「治安維持法は、当時適法に制定されたものでありますので、同法違反の罪に係ります勾留、拘禁は適法でありまして、また、同法違反の罪に係る刑の執行も、適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいて適法に行われたものであって、違法があったとは認められません」という発言である。
もう一つは、共産主義思想・運動を防遏(ぼうあつ)し、革命を阻止し、社会秩序を維持するためには必要であったとする論である。1976年には春日一幸民社党委員長の共産党スパイ査問事件に対する国会質問を端緒に、稲葉修法相らの治安維持法・特高警察を肯定する発言があいついだ。春日は「治安維持法は悪いが、暴力革命はなお悪い」と題する文章で、「凄惨な暴力集団に対して、自由と民主主義を守る側が治安維持法の有無にかかわりなく、何らかの反撃に出たであろうことは当然の仕儀であろう」とする(『天鼓』第6集、1976年)。
非難の嵐となったこの暴論が受容されることはなかったが、これを機に、もっともらしい理屈でよそおった積極的な擁護・肯定論が顕在化する。その代表格は清水幾太郎の1978年の「戦後を疑う」(『中央公論』78年6月号)で展開された、社会の変革を求めるような結社の自由は制限されて然るべきとする論である(その批判は拙著『検証 治安維持法』参照〔平凡社新書、2024年〕)。
それを渡部昇一は「共産主義思想を防御するという治安維持法本来の目的、そして、共産革命は残虐行為を伴うものだという2点を考えれば、一概に悪法と決めつけることはできない」とよりあけすけに展開した(『年表で読む日本近現代史』増補改訂版、2009年)。また、中澤俊輔の『治安維持法』(中公新書、2012年)も終章で「治安維持法は、暴力や革命の発生源となる結社を取り締まろうとした。……現代社会においてまず尊重されるべきは、個人の言論であり、そのためには思想、出版、結社の自由はみな大切である。そして個人の言論を不当に抑圧することは方法を問わず許されない。そのような結社はやはり規制されるべきである」と述べるように、制定は妥当であり、そもそもは「悪法」でなかったという立場に立つと思われる。
なお、これらの論も、共産党を壊滅させたのちの社会民主主義や宗教、民主主義・自由主義、そして戦争遂行に障害とみなされた思想・意識までに襲いかかった1930年代後半以降の治安維持法については「悪法」に変容したとみなしている。だがその一方、拡張解釈しない段階での治安維持法の適用は許容されるとする見解である。
治安維持法についての現在の「悪法」という一般的な認識の大部分を占めるのは、拷問をともなった取調などとともに、運用後半10年間の際限なき拡張解釈の下でフレーム・アップが頻発したというところだろう。とすれば、運用前半10年間の日本共産党とその周辺の運動に対する治安維持法をもってする抑圧取締については、積極的に擁護・肯定はしなくても、当時としてはやむを得なかったという意識が含意されている可能性がある。清水や渡部らの肯定論の意味は、国家防衛や社会秩序維持のためには治安維持法の制定と運用は当時の国際状況の下では必然であり必要だったという立場を前面に押し出している点にある。
「悪法も法なり」を打破するために
反対運動や世論の反発をかわして、ともかくも法として成立させてしまえば、あとは運用する側の意のままであり、必要であればその運用実態に見合った「改正」を繰返し、当初の想定をはるかに超えた法律に成り上がっていくことは、治安維持法を典型例とするとはいえ、日本に限らず現代の治安法令にもあてはまる特徴といってよい。「悪法」であるという非難の存在を認識しつつも、開き直って形式的な合法性に依拠して自らに都合のよい価値観に固執し、社会秩序の維持に汲々となる。
この論理を打破するためには、その法律が成立した時点での政府当局者の説明と実際の発動・処罰の状況との大きな乖離にあらためて目を向ける必要がある。「不満な法律であっても法律としてあるからには守らなければならない」という中曽根発言がはらむ重大な誤りは、発動・処罰する権限をもつ側が率先して法律を破りつづけたことを頬かむりしていることにある。