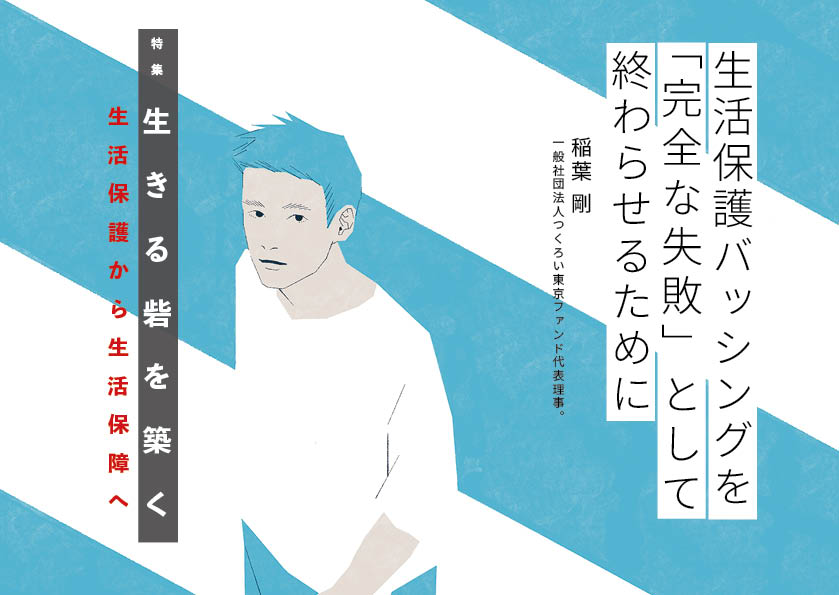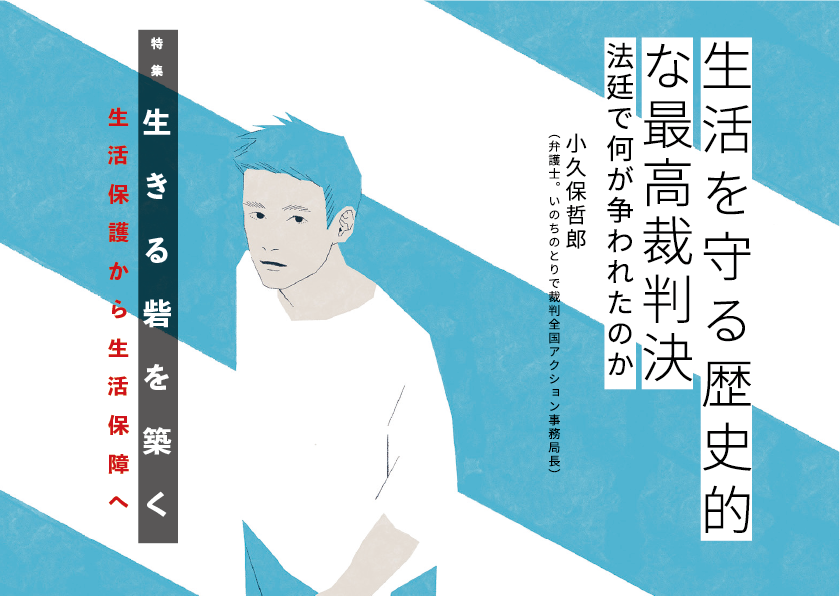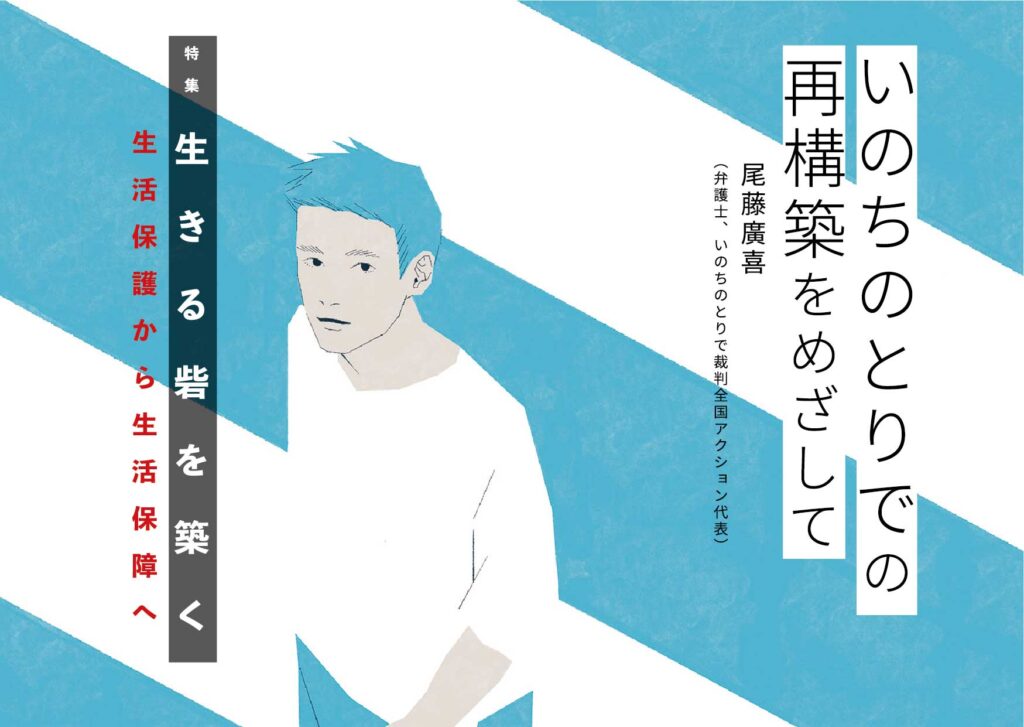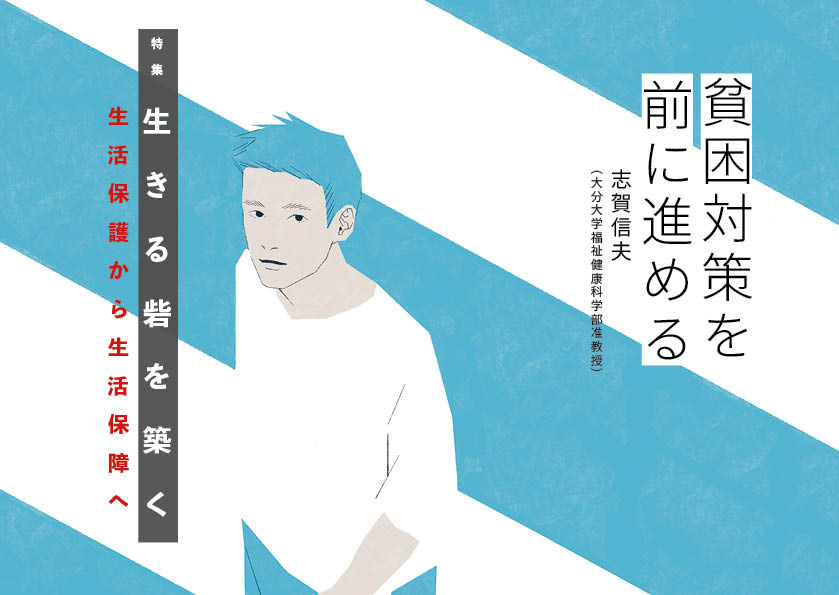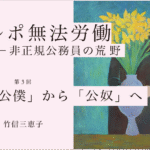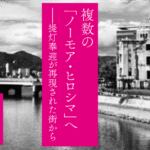2013年1月に厚生労働大臣が決定した生活保護基準の引き下げが、2025年6月27日の最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)の判決によって生活保護法違反だと認定され、減額処分が取り消された。
なぜ今から12年前に法律に違反する決定が行なわれたのか。なぜ違法状態が12年以上も放置・継続されてきたのか。
その理由を探るためには、2012年に引き起こされた「生活保護バッシング」からの流れを振り返る必要がある。
政治が仕掛けた生活保護バッシング
2012年4月、当時、野党であった自民党の「生活保護に関するプロジェクトチーム(PT)」は、生活保護の「見直し」に関する提言を発表。その内容は、民主党政権下で生活保護費が増加し、「制度に対する国民の不公平感・不信感が高まって」いるとして、生活保護基準の10%引き下げや医療費の抑制等、予算の削減と管理強化を前面に打ち出すものだった。
この提言発表と同じ4月、PTのメンバーである片山さつき参議院議員が、ある芸能人の親族が生活保護を利用しているのは不正の疑いがあると批判するキャンペーンを開始。片山議員は連日、テレビや週刊誌のインタビューで「生活保護を受けることを恥だと思わなくなったのが問題」、「正直者が馬鹿を見る社会になっている」と、制度利用者全体に問題があるかのような主張を繰り返した。
PTの座長を務めた世耕弘成議員も自身のブログや週刊誌のインタビューで自説を展開。「(生活保護利用者は)税金で全額生活を見てもらっている以上、憲法上の権利は保障したうえで、一定の権利の制限があって仕方がないと考える」と主張した。
この時期、マスメディアでは連日、生活保護制度の「悪用」を問題視する報道が行なわれた。その中には、金額ベースで約0.4%しか存在しない不正受給の割合を過大に印象づける内容も含まれていたため、生活保護利用者に対するネガティブなイメージが急速に社会に広がった。いわゆる「生活保護バッシング」である。
テレビのワイドショーの中には「生活保護受給者をどう思うか」という街頭インタビューを実施して、個々の利用者の素行を告発した番組もあった。当時、私は知り合いの生活保護利用者から「生活保護の支給日に区役所で保護費を受け取って、外に出たら、待ちかまえていたテレビ局のクルーが近づいてきて、『役所からパチンコ屋に向かうところを撮らせてくれたら、謝金をあげる』と声をかけられた」という話を聞いたことがある。
特定のグループの人々を「社会のモラルや秩序に脅威を与える存在」と見なし、多数の人々が激しい怒りや侮蔑などの負の感情をぶつける現象は、社会学の用語で「モラル・パニック」と言われる。
2012年の「生活保護バッシング」を主導した片山さつき氏は同年、『正直者にやる気をなくさせる!? 福祉依存のインモラル』というタイトルの書籍を出しているが、片山氏らの言説はまさに生活保護利用者をモラルに反する存在として描き出すことに成功した。自民党の政治家が生活保護費を縮減するという自党の政策を実現するために、モラル・パニックを引き起こしたのである。