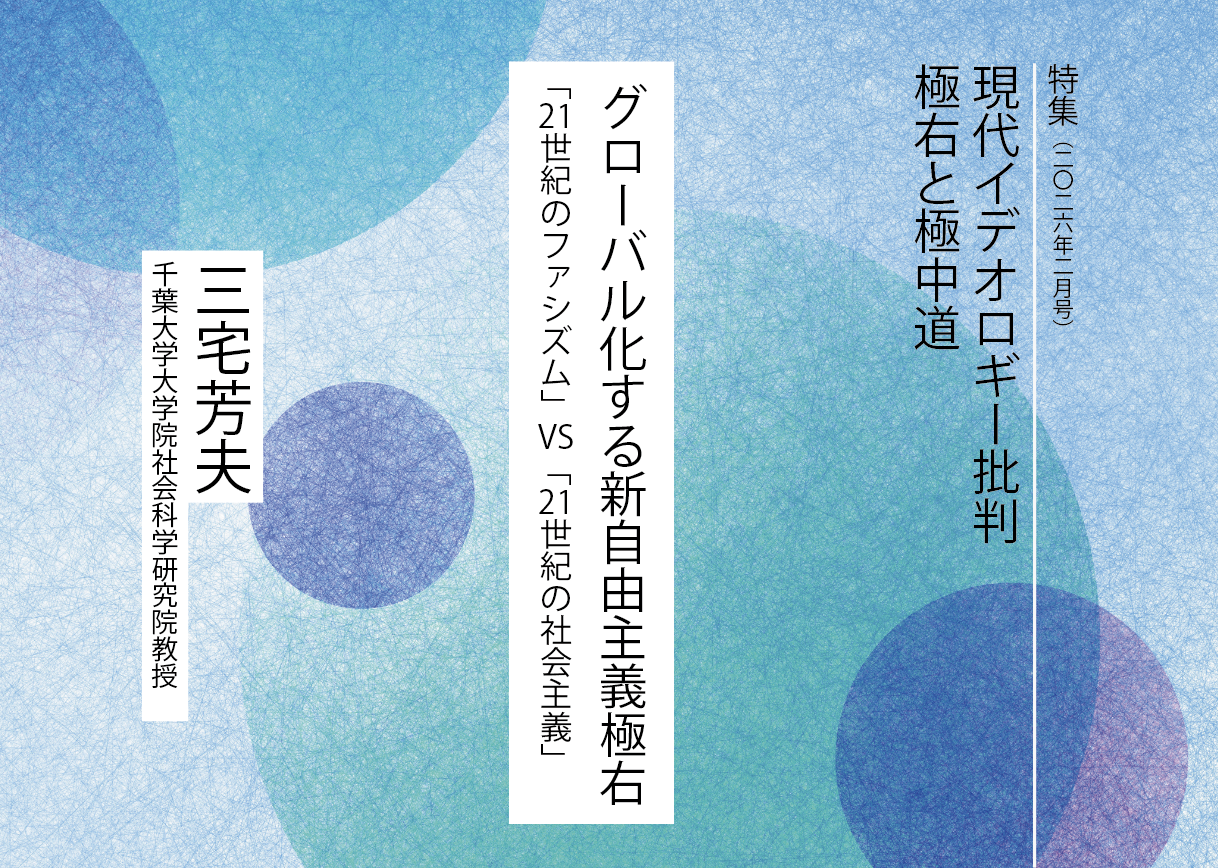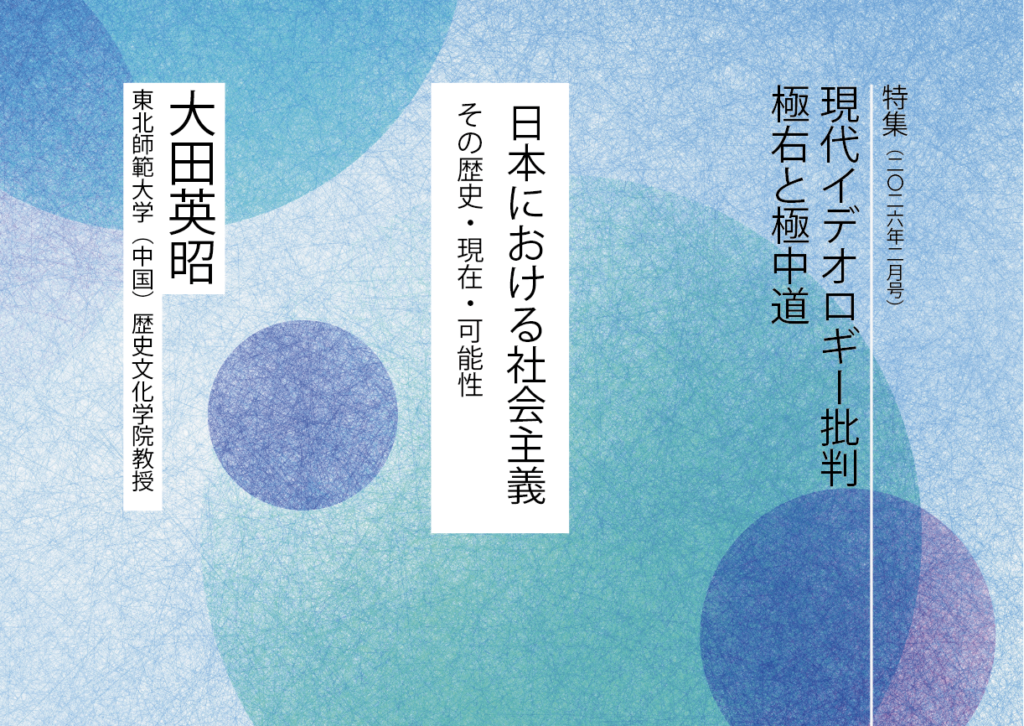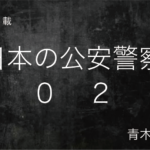【関連】特集:「現代イデオロギー批判:極右と極中道」(2026年2月号)
一九二九年のウォール・ストリートの「株価大暴落 Crash」の衝撃を受けて、一九三〇年から世界は本格的にファシズムの時代に突入する。一九三三年にはナチスが政権に就いたドイツだけではなく、米、英、仏などのいわゆる「自由主義」体制の地域でも極右ファシズムが燎原の火のように勢力を拡大した。
一九三六年にはスペインの人民戦線政府にフランコが軍事クーデターを試み、イベリア半島は血塗られた内戦(civil war)へと突入していく。一九三九年まで続くこの内戦の過程で、ムッソリーニのイタリア、ヒトラーのドイツは、公然とフランコに軍事援助を続け、あまつさえ、一九三七年にはドイツ空軍部隊「コンドル」とイタリア空軍がスペイン北部の都市ゲルニカを無差別爆撃、市街は壊滅し、多数の死傷者を出した。カタルーニャ出身のP・ピカソは直ちに有名な「ゲルニカ」を制作、これを批判するも、人民戦線政府への援助をあくまで拒む英国、それに引きずられるフランスの「未必の故意」が主因となり、ついに一九三九年にフランコが勝利、一九三八年にチェコスロヴァキアを見捨てたミュンヘン会談とともに、大陸ヨーロッパでの極右ファシズムの覇権は決定的になる。
東アジアでは一九三一年に満州事変が勃発、軍部を中心とした「上からのファシズム」が次第に進行していく。一九三二年の五・一五事件(犬養首相暗殺)、血盟団事件(前蔵相井上準之助及び団琢磨・三井合名会社理事長暗殺)、一九三六年の二・二六事件(首相官邸及び警視庁襲撃、内大臣斎藤実及び蔵相高橋是清暗殺)といったテロを利用しながら、パワー・エリート内部でのヘゲモニーを確立した軍部は、一九三七年七月七日の日中戦争開始を機に総力戦体制を完成させ、以後国内における正面からの、ないしは組織的な批判は、運動であれ、言論であれ一切不可能になる。
同時に、一九三三年の滝川事件、一九三五年の天皇機関説事件によって、左派的言論のみならず、大学のいわゆる「自由主義」的言説も瞬く間に弾圧されていく。この過程で、一九三四年には「左翼」として、すでに法政大学から放逐されていた哲学者の戸坂潤は一九三五年に『日本イデオロギー論』を上梓し、「日本主義」と「自由主義」の双方を「社会主義」の立場から批判した。戸坂は日中戦争勃発後の一九三八年に逮捕・拘禁され、一九四五年八月九日、長崎原爆投下の日に獄死した。従って、『日本イデオロギー論』に綴られた文章は、「ファシズム」への戸坂の「言葉による抵抗」として、「白鳥の歌」とも言えるものでもある。
1
現在、トランプの米国とネタニヤフのイスラエル枢軸を中心にした「新自由主義+極右」原理主義のうねりが世界を席巻している。自称「中道」政権である、英国、フランス、ドイツさらにオランダ、フィンランド、ノルウェー、デンマークをはじめとした、元来「リベラル」の旗を掲げているはずだったEUの西欧・北欧地域でも極右の勢力伸長は著しい。
二一世紀に入った頃のハンガリー、ポーランド、チェコスロヴァキアなどにおける極右の抬頭は、旧社会主義圏=東欧の西欧民主主義体制への「遅れ」として語られもしたが、事ここに至っては「西側民主主義の優位」という解読格子は、完全に失効したと言えるだろう。実際、ギリシア、イタリア、スペインなど「西側」に所属していたはずの地域での極右拡大はすでに目覚ましいものがあった。さらには現在イタリアなどのように、極右が政権入りしている国家もある。また「革命の祖国」であるはずのフランスでは、二〇二三年の大統領選で、極右のマリーヌ・ルペンが第一回投票で相対一位を獲得している有り様である。
それに何と言っても、二〇二五年には自由主義体制の盟主である米国で、比喩的にではあれ「ファシズム」と形容されても不思議ではないトランプ政権が登場し、暴走を続けているのだ。少なくとも、『日本イデオロギー論』の戸坂の表現を使えば、トランプ政権を「云わば議会制度を採用した処の一種のファシズム」と見做すことはあながち暴論とも言い切れない。この一節を戸坂は次のように続けている。
ファシズムを独裁制という政治形式だけから考えることは許されないので、政治形式としての独裁制を取らない処のファシズムは、イギリスにもアメリカにもフランスにもあるのだ(1)。
1 『戸坂潤全集 第二巻』勁草書房、一九六六、四三三頁
表向き議会制度を残しながら進行するファシズムのことを戸坂は「立憲的ファシズム」と呼ぶが、これはグローバルに形成されつつある「二一世紀のファシズム」を考察する上でも一つの参照枠を提示していると言えるだろう。
2
無論、二〇世紀のファシズムと現在前景化しつつある「二一世紀のファシズム」はまったく「同じ」というわけではない。まず、この両者の違いを国際関係の側面から確認しておこう。
二〇世紀のファシズムの国際的特徴はまず第一に、WWI末期の一九一七年のロシア革命とそれに続く、ドイツ、ハンガリー、オーストリアの社会主義革命(の可能性)に対する「反革命」として成立したことにある。ロシアの革命政府に対して、一九二〇年まで続く内戦を仕掛け、さらに直接軍を派遣した欧米列強+日本は、当初より「社会主義政権よりは軍事独裁、場合によってはファシズムのほうがまし」という態度で一貫していた(2)。
2 なお、「社会主義政権より軍事独裁のほうがまし」というドクトリンはグローバル冷戦期のアメリカに正式に採用され、この方針に基づいて、米国政府はラテンアメリカ、アジア、アフリカなどの第三世界にグローバルに介入した。
一九二二年のイタリアのムッソリーニの政権奪取(ローマ進軍)を英国が積極的に支援したのは、そうした態度を象徴したものである。ちなみに日本は、ロシア革命に際して、一九一八‐一九二二年の間、総数七万二〇〇〇人を超える、いわゆる「シベリア出兵」を行ない、「ザバイカル共和国」の名の下、ロシアからシベリアを分離・独立させる工作に従事した。つまり、傀儡国家を樹立して東北アジアに勢力圏を拡大する日本帝国主義の方針は、シベリア出兵から満州事変にまで連続している、とも言える。
ナチスの基本方針も国内・国際双方の側面で「反共産主義」に貫かれていた。であるからこそ、英国とフランスの支配層及びファシスト達は、ドイツがソ連へ侵攻することを期待して「宥和政策」を推進したのである。従ってドイツ、イタリア、日本の枢軸同盟=三国同盟が一九三七年当初は「防共協定」として発足したのも決して偶然ではない。
ところで、国際ファシズムが「反共産主義」として成立した条件は二一世紀には失われている。というのも、一九八九‐一九九一年の冷戦終結と社会主義圏の崩壊によって、現在地球上のすべての国家が、世界資本主義システムに包摂されているからだ。なるほど、いわゆる「西側」ではロシア、中国、場合によってはインドを念頭に権威主義体制と自由民主主義体制の対立という構図が煽られもする。
しかし、これらの諸国は、明らかに「体制」としては資本主義体制であり、いくらかサプライ・チェーンの再編が語られるにしても、中国、インドないしはブラジル、南アフリカなどのいわゆる「グローバル・サウス」を完全に排除した世界資本主義システムは当面考えられない。言説の上では──とりわけ日本では──米中対立のハイパー・インフレーションが観察できるけれども、実際のところ、それはせいぜい近代世界システムの延長戦上での中長期的な「覇権の交代」の次元でしかない。
しかも、巷間語られることとは異なり、現在の所はアメリカの優位は動かしがたい。なるほど、GDPの数字だけ見れば、中国はあたかも近々アメリカに追いつき、追いこすかもしれない(3)。しかし、中国のGDPの数字の内には欧米日多国籍企業の生産高が多く含まれている上、金融、さらに軍事上でのアメリカの優位は圧倒的である。何と言っても、アメリカの軍事費は一国だけで世界の総軍事費の37%を占めているのだ。これにNATO及び日本を加えた「西側諸国」の軍事的優位はまさに圧倒的である。何もこの上、軍事費をGDP比2~5%に増額する必要など、客観的にはないに等しい。
3 日本では中国の軍事費総額の伸びが頻りに語られる。しかし、中国のGDP比ないし政府予算比における軍事費の割合は長期にわたり一定している。急激に割合を伸ばしているのは、社会保障費及び教育費である。これは中国の一四億という総人口と少子高齢化を考えれば、避けられない政策でもあろう。たとえ、一党独裁制を採用しているとしても、それは「人民の合意の調達」を完全に無視できる、ということではないのだ。さらに言えば、総力戦が可能になるのは、人口構成において青年層が分厚い時期に限られる。日本はもちろん、中国においてもすでにその条件は失われている。一〇〇万人以上の戦死者を出した朝鮮戦争の再現を想定するのは、もはや非現実的である。付け加えて言えば、敵前上陸能力を全く欠いた「台湾侵攻」に関しては中国政府には「その意図も能力もない」としておくのが常識的だろう。
要するに、現在の世界は、いまだに一九八九‐一九九一年の冷戦終結・社会主義圏の崩壊以降継続する、米国を盟主とする「西側」の一極支配の下にあるのだ(4)。WWⅡ以後、敗戦国であるドイツ、イタリア、日本はもちろん、英国、フランスなどの旧帝国主義列強も軍事的な意味での独立を喪失し、アメリカの保護=管理の下に入った。現在は、ロシア・中国だけが、軍事的にはアメリカの「支配の外」にあるとはいえ、これはすでに述べたように、力関係の圧倒的非対称性を覆すものではない。
4 このアメリカを中心とした「西側」の一極支配を悲劇的な形で可視化したのが、二〇二三年一〇月から続くイスラエルによるガザのパレスティナ人に対する、まさに「法―外」なジェノサイドであろう。旧東側諸国を含め、国連加盟国の圧倒的多数が――ジェノサイド開始以前に――すでにパレスティナを国家として承認しており、またジェノサイド開始以降は、留保なくこれを批判していたにもかかわらず、米国の支持を受けたイスラエル政府の暴走を――国連も含め――全く止めることができなかったという事実は、いまだに世界がアメリカを盟主とする旧帝国主義列強の支配下にあることを白日の下に曝け出した。この観点から言うと、英国スターマー政権や仏マクロン政権のパレスティナに対する――遅ればせながらの――「国家承認」のパフォーマンスなどはまさに「茶番」と言うほかない。
これに関連する、今一つの重要な差異としては、二〇世紀のファシズムと世界戦争において遂行された、青年男性人口の大部分を前線の兵士として動員する、「総力戦 Total war」体制の本格的な構築は当面考えられない、ということが挙げられる。
この変化には、いわゆる「軍事革命」によって、戦争の致命的な場面は、宇宙空間を管理する電子技術と核弾道ミサイルによって決定されるようになったことも関係している。実際、海によって隔てられたアメリカとロシア、中国の間の軍事的最終審級が、WWⅡ時のように、機甲師団と航空支援の組み合わせによる「電撃戦 Blitzkrieg」ではあり得ないことは明白である。
また、トランプが現在頻りにラテンアメリカに対する威嚇として動員している空母打撃群は――制海権の確保と地上爆撃を目的とする――軍事的に圧倒的に「格下」の相手に対しては有効かもしれないが、結局は決定打にはなり得ない。最終的には原子力潜水艦に装備されたSLBMが全てを決するのだ。したがって、日本の一部支配層が夢見る航空母艦の保有などは、八〇年以上前のアジア・太平洋戦争のトラウマに引きずられた「時代錯誤」でしかない。実際、もはや航空母艦などは「時代錯誤」でしかないからこそ、米国も「やれるものならどうぞ」ということで形式的には保有の可能性を認めたのでなかったのか?
なるほど、言説の水準では、中国脅威論や排外主義的言説の異常な高まりは留まる処を知らない。しかし、情報操作によるものであるとはいえ、この排外主義的言説に熱狂する最も過激な人々でさえ、自分自身や自分の家族がWWⅡ時のように、「兵士として」地獄の前線に赴くことなど夢にも思っていない。せいぜい、米国に頼るか、ないしは抽象的な「他人」によって構成される自衛隊が念頭にあるくらいだろう。排外主義的言説を煽る国民民主党党首は頻りに「血を流す覚悟」を国民に求めているけれども、その意味では、本格的な制度化=徴兵制を導入することはそれほど簡単なことではない。実際、防大卒業生の進路を見ても、アフガニスタン・イラク戦争やウクライナ戦争など海外での大きな戦争が勃発する度に、自衛隊任官への辞退者が跳ね上がっているのである。
さて、ここで「排外主義」という言葉が浮上した。自民族中心主義と結合した排外主義は反共産主義と並んで、二〇世紀のファシズムのイデオロギーの主要要素であった。他方、「二一世紀のファシズム」を体現しているトランプ主義においても、排外主義・外国人排撃は――レトリックとしての反共産主義と並んで――最も特徴的な言説並びに実践であることは言うまでもない。
では、この両者の関係は如何なるものだろうか?