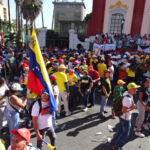「特集・軍事化される西日本」のほかの記事はこちら
石油の時代に向かいはじめた頃に佐賀の炭鉱町で生まれた私には、国策に翻弄される与那国の姿は、故郷と重なる。
30年ほど前の与那国は、斜面に棚田が広がり、水面に浮かぶ月と海風の強さが不思議に調和していた。いま、その光景はない。
押し寄せる一つひとつに、「今なにができるか」も大切だ。しかし「本当はどうしたいのか」に向きあうこと、それは現実逃避ではなく、選択肢を狭める現実を根本から問い直すことである――日本で研究する台湾の方の言葉に励まされる。
昨年、東北を訪れる機会があった。暮らしの破壊、農水産業の衰退、住みつづけた地から意に反する移動(避難)を余儀なくされた各地の現実は、与那国の行く末と重なった。
黒一点の島にも
やや長い引用を許してほしい。50年近く前の文章は、いまの与那国を見ているかのようだ。
宮古島生まれ、詩人、思想家として、意識の外に見落としかねない視点を提起してきた川満信一(1932~2024)の一節である。
〈地図帳には、たくさんの国が識別できるようになっているが、その中で海洋に漂う小島は……大方、針の先ほどの黒点か、あるいは地図のうえから消えてしまっているかのどちらかである。……その場合、地図のうえから消えている小島の種族や文化なども視野のそとへ消されてしまう。そういう漫然とした地図のイメージを変えて、針先一点の小島にも、人々が想定している以上の、はるかな古代から、人間の営みが続けられてきたのだ、ということをあらためて見返すとき、海洋空間の黒点は、突然、鮮やかなイメージを描き出してくるはずである。〉
(「未来の縄文――島尾敏雄『ヤポネシア論』の示唆するもの」『カイエ』1978年12月臨時増刊)
島の南岸に接する「樽たる舞まい湿原」をご存じだろうか。
地図帳で島全体が点にしか見えないのだから、この湿原を確認することはできない。視界と意識から消える。
島に住むフリーライターの西村仁美は、自らも泥沼に浸かりつつ、湿原の調査研究をしている方々を取材。「与那国島は日本本土や、琉球弧の中でも、非常にユニークな形で、植物や生き物が存在する」「樽舞湿原は……島で一番大きな雨水の溜まる『水瓶』」という屋富祖昌子氏の言葉をレポートしている(『週刊金曜日』2025年2月7日号)。
樽舞湿原は、島各地の水量を調節する心臓の役割をもつと言われる。だが、いま町と国はこの心臓をえぐり出し、巨大な内陸港を造ろうとしている。
同時代の台湾は意外に遠い
「台湾は見えますか」と旅の人によく聞かれる。意外にも、あまり天気の良くないときに見える。西の水平線を埋めるように広がり、4000メートル近い山頂だけが連なることもある。昨年、長い時間見えた時があった。やはり、翌日から天候が荒れた。
その距離、約100キロ。眼下に広がる台湾海峡を「今もっとも厳しい安全保障環境にある」と日本政府が繰り返すようになって久しい。黒潮が北上する厳しい海域だが、風を使って小舟を操りながら、台湾と与那国の人びとは、隣り村のように往来してきた。
16世紀前半、与那国は琉球に制圧された。その琉球が薩摩や日本、米国に「処分」されると、与那国もまた人びとの意思とは無関係に「処分」されてきた。1880年、明治政府は対中国政策の外交カードとして“先島”を中国(清)に差し出す条約まで結ぼうとした。