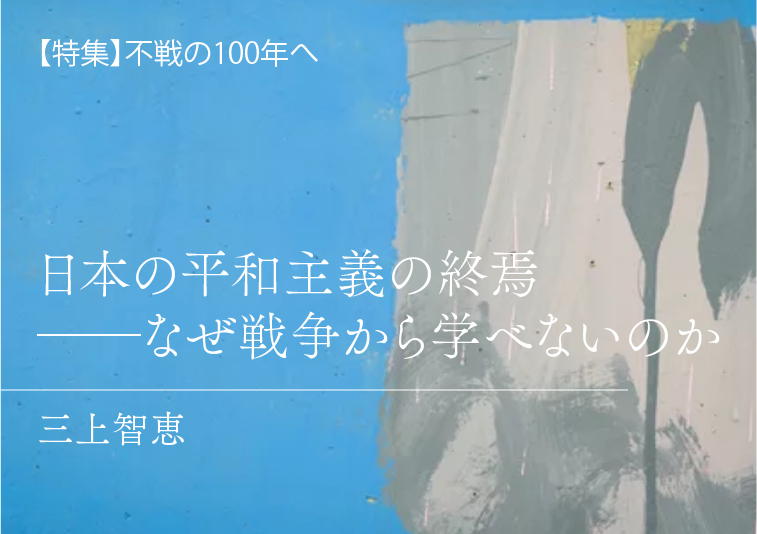「特集・軍事化される西日本」のほかの記事はこちら
沖縄周辺での自衛隊の強化は「南西シフト」と表現され、このワードは報道でも多用されている。
南西諸島で自衛隊配備の動きが表面化するのは2016年。与那国島への陸上自衛隊駐屯地の設置で始まり、2019年に宮古島と奄美大島、23年に石垣島と、駐屯地の新設が相次いだ。一般に沖縄県の宮古島以西を「先島」と表現するが、宮古島の空自レーダー基地を除いては自衛隊施設がなかったこの地域を、政府は「防衛上の空白」と呼び、部隊配備を進めてきた。目的として、与那国島は「監視態勢の整備」、石垣・宮古・奄美は「災害を含む各種事態発生時に迅速に対処」が掲げられた*1。
近年では自衛隊と米軍による演習・訓練も激化する。与那国島や石垣島では民間の港や港湾も使い、日米の部隊が展開している。演習は、建前として「特定の国を想定していない」と強調しつつも、台湾有事をにらみ、中国軍への対抗を意図しているのは明白だ。
源流
ここ数年の流れを端的に示した、一つの記事がある。石井暁共同通信記者による、台湾有事を想定した日米共同作戦計画の原案策定の報道だ。2021年12月に各紙に掲載された*2。
台湾有事の初期段階で、米海兵隊が南西諸島の島々に攻撃用の軍事拠点を置く計画で、2022年1月に開かれる外務・防衛閣僚の日米2+2で正式合意される見通しとなっていた。報道では米海兵隊が有事に部隊を離島に分散展開する遠征前方基地作戦(EABO)に基づき、米側が日本側に提案。米軍は中台の紛争への介入を視野に、中国艦艇を排除するため対艦攻撃できるロケット砲「ハイマース」を展開し、自衛隊には輸送や弾薬・燃料の補給など後方支援を担わせるとした。
2022年1月、2+2で日本の外務省が公表した共同発表では「同盟の役割・任務・能力の進化及び緊急事態に関する共同計画作業についての確固とした進展を歓迎」との一文が躍る。この年、日本政府は12月に「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」のいわゆる安全保障関連三文書を閣議決定する。敵基地攻撃能力(反撃能力)の明記が注目されたが、沖縄関連では陸自15旅団(那覇駐屯地)の師団への格上げや弾薬などを保管する「補給処支処」の設置などが盛り込まれた。陸自の強化について国家防衛戦略では「沖縄における国民保護をも目的として、部隊強化を含む体制強化を図る」としており、一見、住民避難に重きを置いているようにも読み取れるが、「をも」と記していることから、目的は別にあるとみるべきであろう。これらの方針は、2+2で日米が決定した方針を日本側の防衛構想として確認したといえるものであった。
2023年に入ると、県内では3月に陸自石垣駐屯地が設置され、与那国・宮古・奄美・石垣と続いてきた南西諸島における陸自駐屯地新設の区切りとなった。石垣駐屯地などに配備された地対艦ミサイル(12式地対艦誘導弾)をめぐっては、敵基地攻撃に対応する「能力向上型」の開発が安保関連3文書に盛り込まれている。南西諸島への配備について石垣市民はじめ住民から懸念も上がり、沖縄県も反対の立場を示している。一方、政府は「具体的な配備先は決定していない」との説明を繰り返す。
この年、米側での動きとしては、11月に沖縄本島の米海兵隊キャンプ・ハンセン(金武町など)の海兵隊部隊がEABOに対応した海兵沿岸連隊(MLR)へ改編された。この年になると、EABOの作戦構想をなぞるかのように、米軍が先島地域に展開しての共同訓練が本格化し、自衛隊輸送機が与那国島や石垣島の民間空港に飛来。10月の日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」では、自衛隊機が日米の部隊や物資を運び込む様子がみられた。
2024年、自衛隊の配備では、3月に沖縄本島・うるま市の勝連分屯地に「第7地対艦ミサイル連隊」が発足した。南西諸島の奄美大島・宮古島・石垣島に配備される地対艦ミサイル部隊を束ねるもので、中国艦艇を念頭にした、自衛隊の対艦ミサイル網が構築される形となった。同市では、石川地区に自衛隊訓練場を整備する計画が浮上していたが、住民や各政党、市や県の反発により、昨年四月に防衛省が取りやめる出来事もあった。10~11月の日米共同統合演習「キーン・ソード」では前出の「ハイマース」が石垣島に空輸され、駐屯地に展開された。これはEABOを念頭に日米のミサイル部隊が連動して運用されたとみられる。
日本側での有事を見据えた制度も登場する。自衛隊などの利用を念頭に、国が民間空港や港湾を整備・促進する「特定利用空港・港湾」だ。昨年四月に第一段が発表され、沖縄県内では那覇空港と石垣港が指定された。沖縄県は施設の指定に慎重な姿勢を見せてきたが、2025年2月、新石垣空港、宮古空港、中城湾港について、指定に応じる姿勢を県議会与党会派に説明している。
同様に動きが本格化してきたのが、有事の避難計画だ。先島地域(与那国町、竹富町、石垣市、多良間村、宮古島市)の約12万人を空路で九州各県に分散避難させる案で、政府が6月に九州地方知事会に示した。9月には石垣市で有事に住民避難をする、国民保護法に基づく「実地確認」も行なわれた。新石垣空港では、避難者役と職員役に分かれ、避難者の手続きや航空機搭乗前の手荷物検査、座席の登録などをした。行政が「実地確認」としたこの取り組みは、事実上の「住民避難訓練」といえる。
2024年11月、共同通信は台湾有事の際に南西諸島に米海兵隊と自衛隊、フィリピンに米陸軍が展開する方針であることを報道し、各紙に掲載された*3。前出の石井氏の取材である。中国が軍事ラインとする「第一列島線」に沿ってミサイルを構え、中国艦艇の展開を二方向から抑止する構想と報じており、南西諸島での動きが具体化した一方で、作戦の区域がフィリピンにも拡大している。