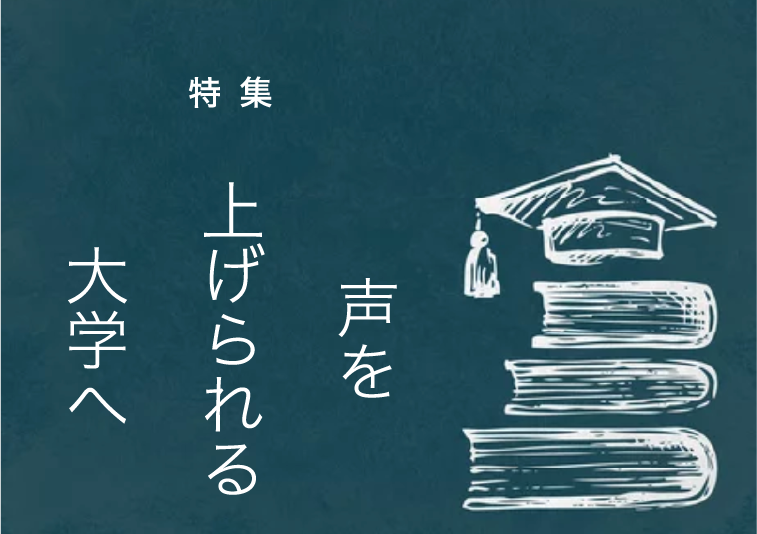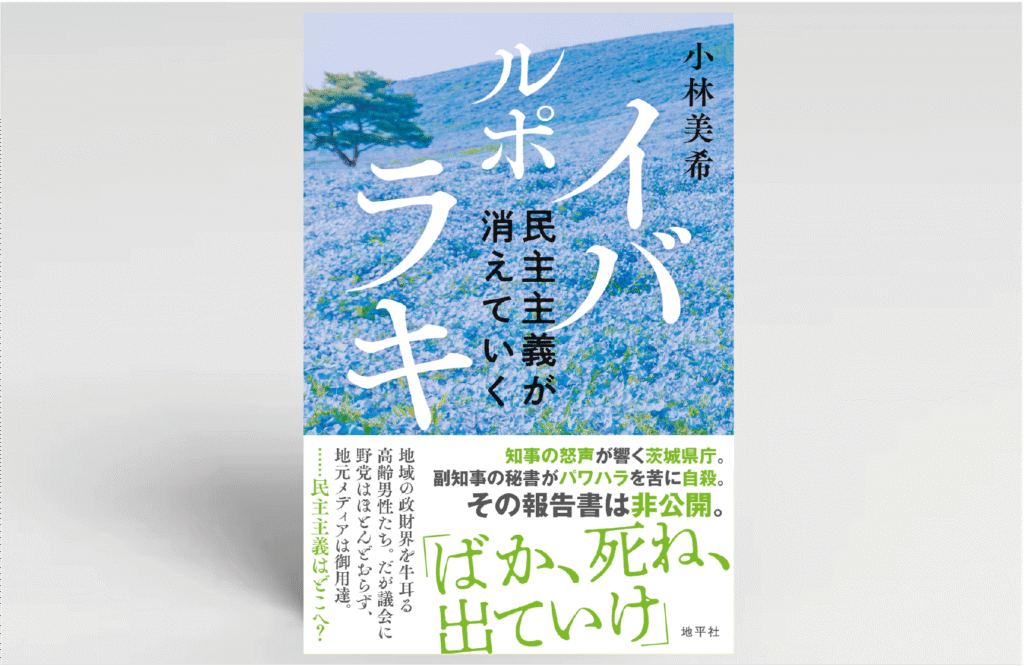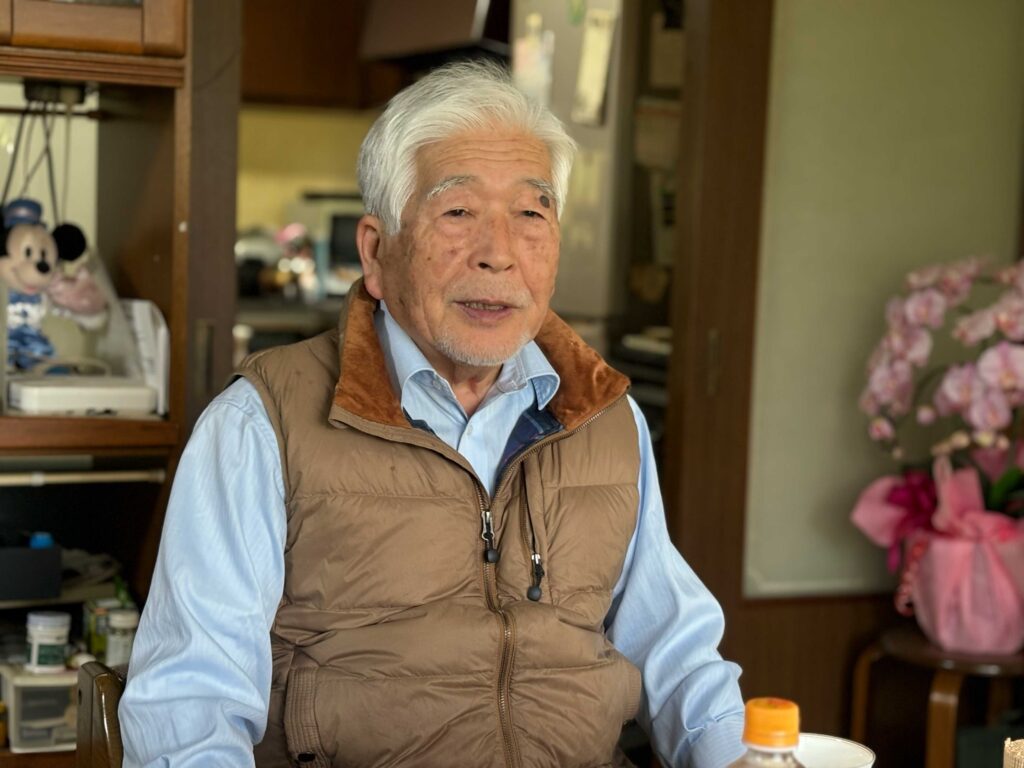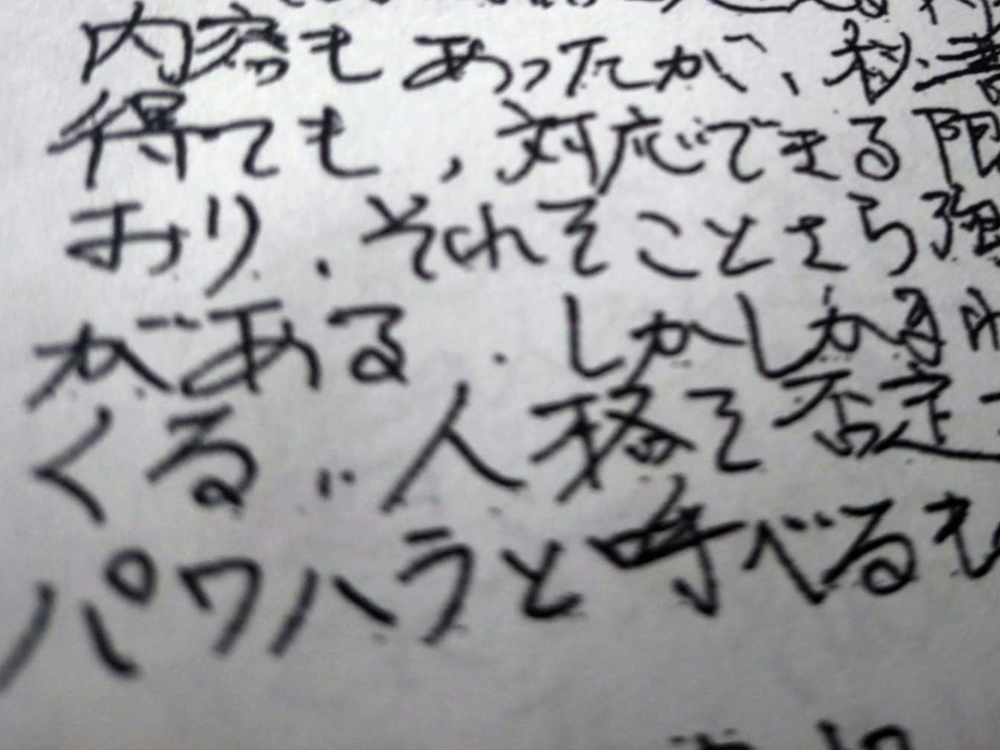これまでの記事はこちら
難関大至上主義――進学校の異変
現役の東大合格が3人――。
茨城県内きっての進学高校の県立水戸第一高校。この春、現役で東京大学に合格した人数がわずか3人だったことで、関係者の間に衝撃が走った。
2025年度の東大合格者数は土浦一高が14人(うち現役が12人)、並木12人(9人)、竹園7人(6人)、水戸一高7人(3人)だった。京都大学は、水戸一高が6人(2人)、土浦一高が4人(4人)で、現役合格は土浦一高が最多だった(『サンデー毎日』2025年3月23日号)。
各進学高校が難関国立大と医学部合格を競うなか、水戸一高の東大合格者は2022年で14人(11人)、23年で15人(同)、24年度で11人(6人)と年々減っている。この状況について、教員や同窓生などの関係者が口を揃える。
「学校がいくら躍起になっても、東大合格者が大幅に増えるわけではない。偏差値・難関大至上主義の教育に偏重した結果が合格者減だったのではないか。そもそも水戸一高に入る学力があれば、自分の力で勉強できる。受験対策に走るから、かえって考える力が育たなかったのでは」
筆者の母校でもある水戸一高といえば「バンカラ」で有名だった。制服はなく、校則もないに等しい。生徒、教員、校長が対等に議論するのは当たり前。自由と多様性が重んじられる校風が受け継がれてきた。生徒に対して教員が「勉強しろ」「授業をサボるな」と指導することなど滅多になく、勉強するも部活に打ち込むも、学校をサボるも、すべて自己責任。その自由な環境の中から各界に人材が輩出されてきた。ところが今や、学校には「東大研究会」が発足し、進路支援部が東大合格者に対して学校生活や日々の学習計画、学習法など「先輩からのメッセージ」の執筆を求めているというのだ。ある保護者が呆れる。
「入学早々、進路アンケートの提出を求められました。東大、京大、医学部などに丸をつけるよう指示があり、私立大には早稲田や慶応もあるのに『その他』扱いでした」
2月の国公立大の入試前日と当日は、都内に会議室を借りて教員を派遣し「受験サポートセンター」まで開設(同校ホームページより)。こうした難関国公立大と医学部への偏重ぶりが、部活動にも影響していると見られる。大井川和彦知事の肝いりで2021年度に水戸一高に附属中ができたが、本格的な部活を行なうことができない。日本中学校体育連盟に加盟しておらず、大会に出場できないからだ。
2023年度に県大会でベスト4に入った伝統ある高校野球部について見てみる。茨城県では、いくつかの高校に限って、体育や芸術分野などですぐれた実績のある中学生を対象に「特色選抜」を行なうことが県から認められている。水戸一高で2022年度から実施された野球選抜が2025年度は行なわれないことになった。県は同校の入試志願倍率が高く公平性に欠けることを理由にした。
野球部員の保護者は、「中学受験のために小学生のうちにスポーツを諦めた子が少なくない。特色選抜で一定の生徒が野球部に入部することがなくなれば部員が揃わず、野球部存続の危機が訪れるかもしれない。これは勉強だけすればいいという意味だと受け止めています」と憤る。そうしたなかでの現役東大合格3人という結果。関係者は「今度は学校行事もなくなるのではないか」と危惧する。
一方で、ある進学高校の卒業生(20代)は、「合格しやすい国公立大学の受験を担任が強要していました」と打ち明ける。
高校1年生の頃から「どこでもいいから国公立を第一志望にすること」と指導された。担任はハラスメント体質。授業のたびにチョークをボキボキと折り、生徒が答えを間違うと「疲れんなー」「帰りたいなー」と嫌味を言った。同級生はその抑圧に負け、志望していない国立大を受けた。卒業後に附属中学が設置されたことで「よりいっそう国公立大に偏重するのでは」と心配し、茨城県教委に、その教員が「受験の強要やハラスメント行為を続けていないか生徒側に調べてほしい」と相談したが、調査には至らなかったという。教育委員会に確認すると「(筆者が)第三者のため、相談があったかどうかを含め答えられない」とした。
中高一貫校の増設――県政肝いりの教育政策
県内の各進学高校が国公立大の合格に躍起になる背景に、大井川知事が得意とする「数値目標」が存在するのではないか。県教育委員会に尋ねると、「県教育委員会から各校に合格目標や実績を求めることはしていません。合格実績が教職員の人事評価につながることもありません」と答えた。しかし、多くの教育関係者が「自分の評価を気にして『上』を見て忖度するのは、当たり前のこと」と言う。