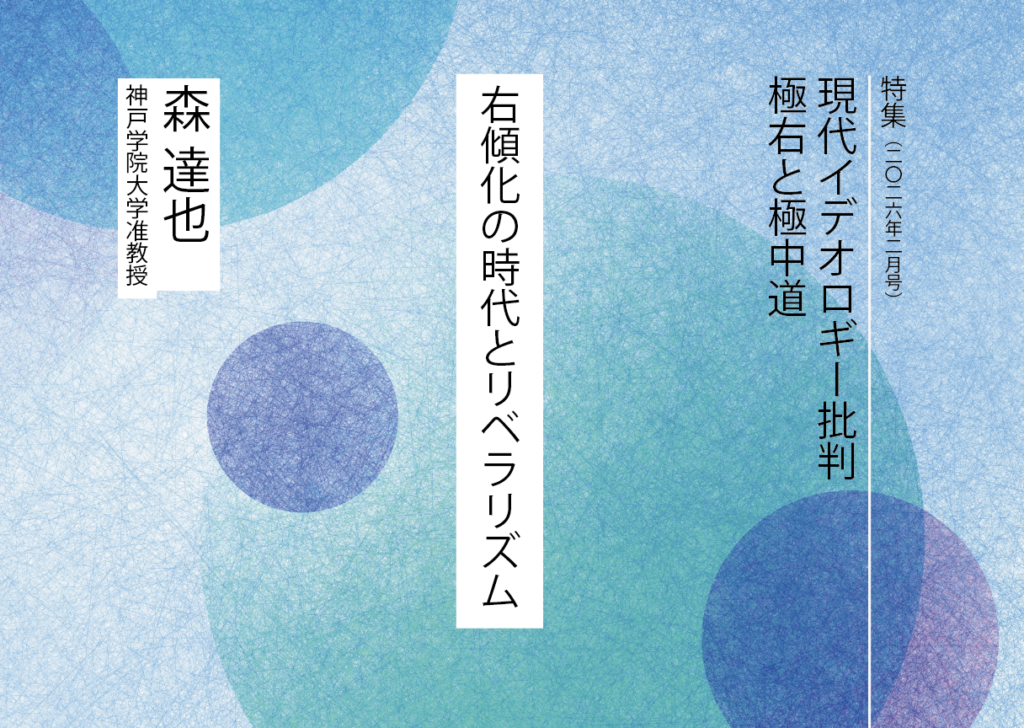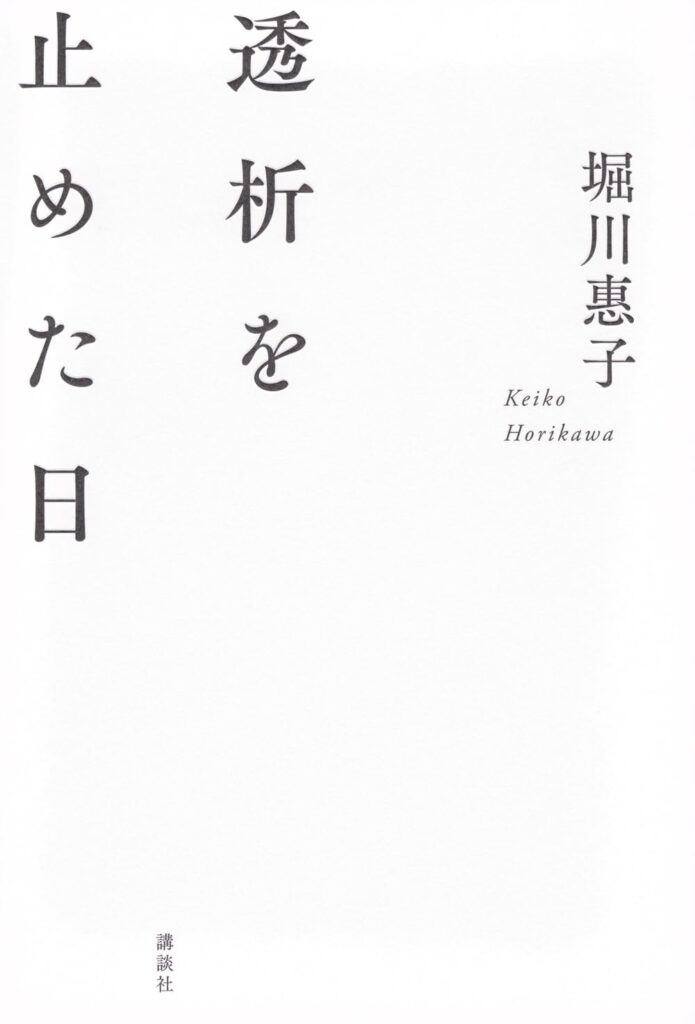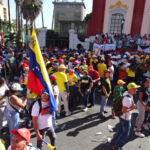店にお気に入りの一輪挿しを置いている。花屋で、そこに生けるための一輪を選ぶ時間が好きだ。店に持ち帰って、さっそく生ける。面倒くさがりだから、付属する栄養剤も入れずに水を入れた一輪挿しにそのまま挿すのだが、あるとき栄養剤を入れない方が花は長持ちするのではないかということに気がついた。
ではなぜ栄養剤が付属しているのだろうか。実際に栄養剤を入れることで成長が促進され、入れない場合よりも元気に咲くのだろう。しかし、その分生命のサイクルも早くなり、萎れるのも早くなるのではないか。生命のサイクルが早くなればなるほど、買い替えの頻度も高くなり、花屋は儲かる──。実際の思惑がどうかはさておき、一輪の花を生けること一つとっても、その行動は資本主義という大きなシステムに無意識的に規定されていることに気づく。
大きなシステムの下では、「何のために」と問うことは非効率で、省略されてしまいがちだ。それは消費の面だけでなく、生産においても同様だ。自分の仕事が「何のために」あるのか見失いそうになる。人が作ったシステムに、人が従属してしまう。求められる社会人像をイメージし、そこに自らを合わせていく。合わせられないと生き延びていけないという切迫感に胃をキリキリさせながら生きていくしかないのだろうか。
いや、できることはまだまだたくさんある、と教えてくれるのが本書だ。大きなシステムの利点を活用しつつも、一人一人が自分の時間を生きられる社会を模索し、実践してきたことが綴られている。本書には△と▽の二つの三角形が登場する。「△」は、最初に成果を設定して、そこに最短距離で到ろうとする社会のあり方であり、そこでは人間は手段化されてしまっている。それに対して「▽」は、成果を事前に設定せず、一人一人の意思を根本に、偶発性や縁によって形成された関係性を重んじる社会のあり方である。そして、本書が提案するのは、△に対して、▽の社会づくりである。
このように書けば、何を理想論を、と思いたくなるかもしれないが、読めば実際に▽の社会づくりが一つの会社にとどまらず西国分寺というより広範囲の地域共同体のレベルにおいても根付いているのを目の当たりにするだろう。それらは地域通貨や地域食堂といった形で結実していて、資本市場の構想も描かれているのだから驚く。なにより西国分寺を羨ましく思うはずだ。
△を▽にするためにはどうすればよいか。本書からポイントを二つ紹介する。まずは、「主語を小さくする」ということ。国、社会などの大きな主語ではなく、私、私たちなど、身近なところから実践していくということだ。二つ目は、「他動詞ではなく自動詞」で考えるということ。「変える」のではなく自ずから「変わる」のだ。自発性を尊重する姿勢の軸にあるのは「一人一人のいのちが大切にされる社会をつくるには?」という問いだ。
「問い」は光のようなものだと著者は書く。問うことを忘却させようとする社会にあって、まず取り戻すべきは「問い」なのだろう。自分は今を生きていると言えるのだろうか。そうでないとしたら何が原因なのだろうか。自分にできることはないだろうか。問うているうちに、なんだか変われそうな気がしてくるから不思議だ。
花が咲くには、水のほかに光も必要なのだった。世阿弥は「住する所なきを、まず花と知るべし。」という言葉を遺した。一つのところに安住しないことが、花であるということだが、前段を「システムに従属しないこと」と言い換えることもできる。一人が笑顔を咲かせ、目の前の人の笑顔も咲き、それが連鎖して、みんなが花開いていく。そんな未来を想像させてくれる書であり、著者はそれをファンタジーと呼ぶ。
〈今回紹介した本〉
『大きなシステムと小さなファンタジー』
影山知明著、クルミド出版、2024年12月、2500円+税