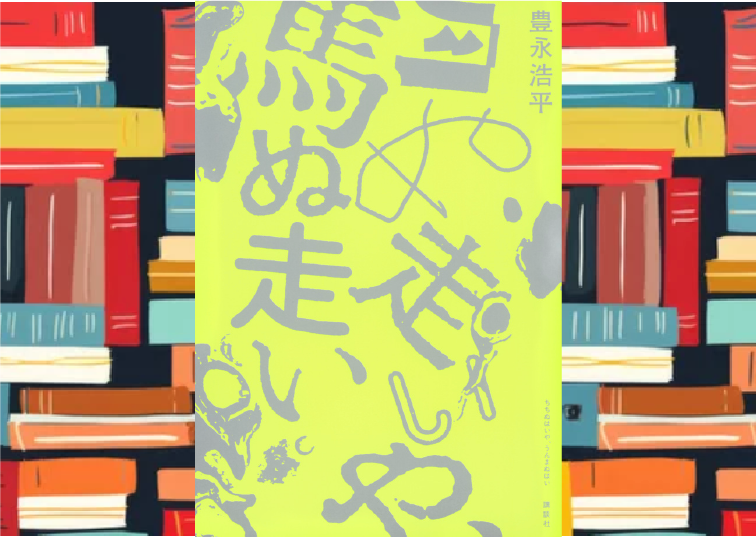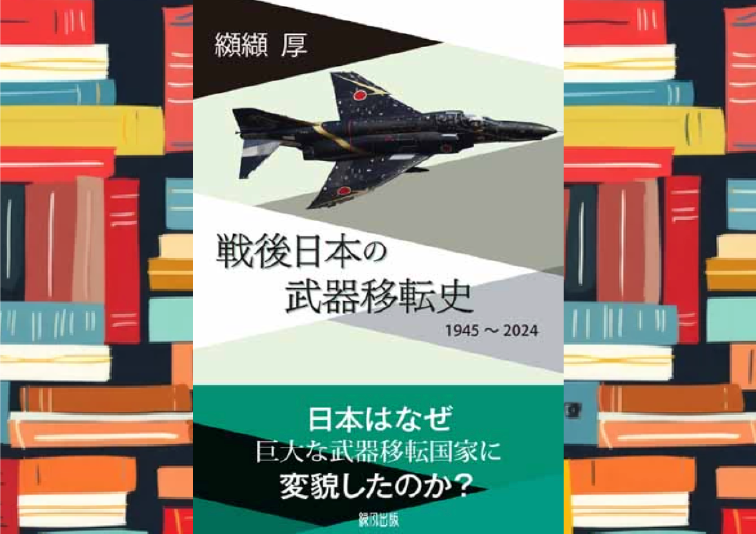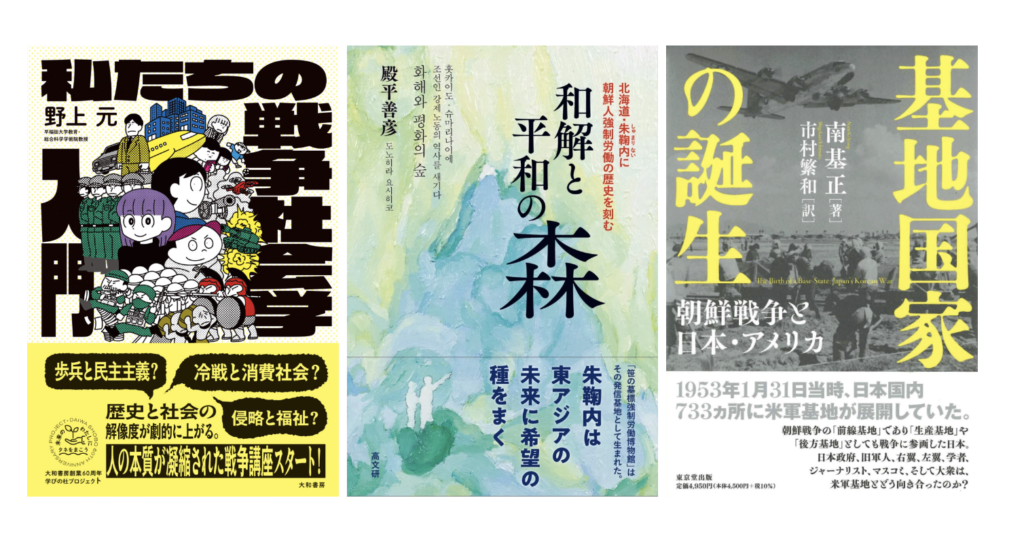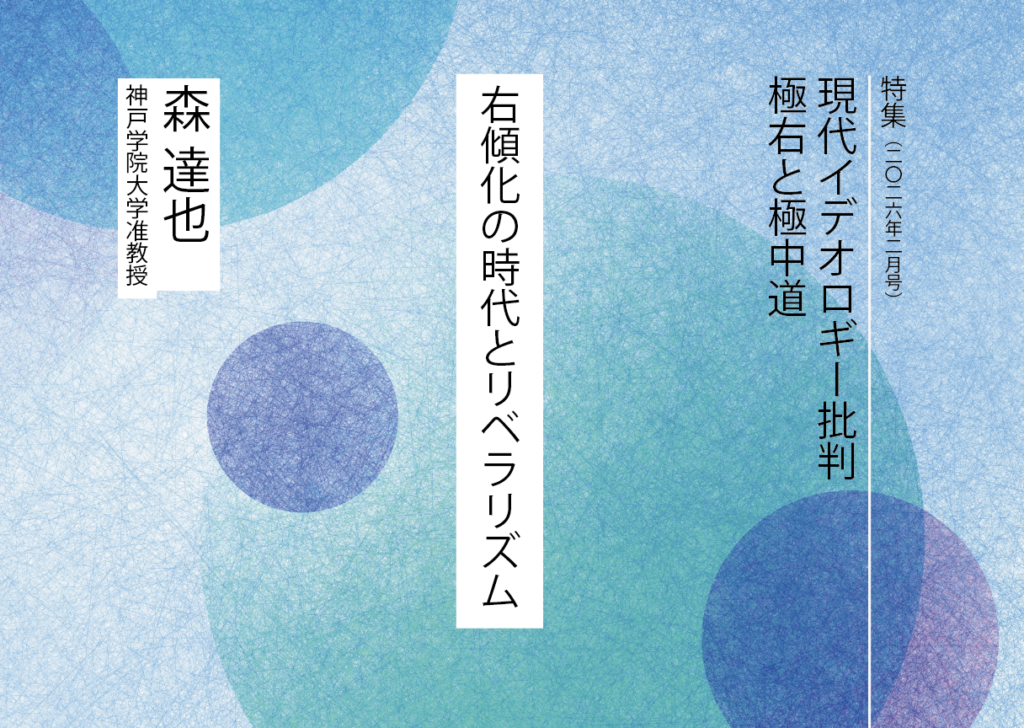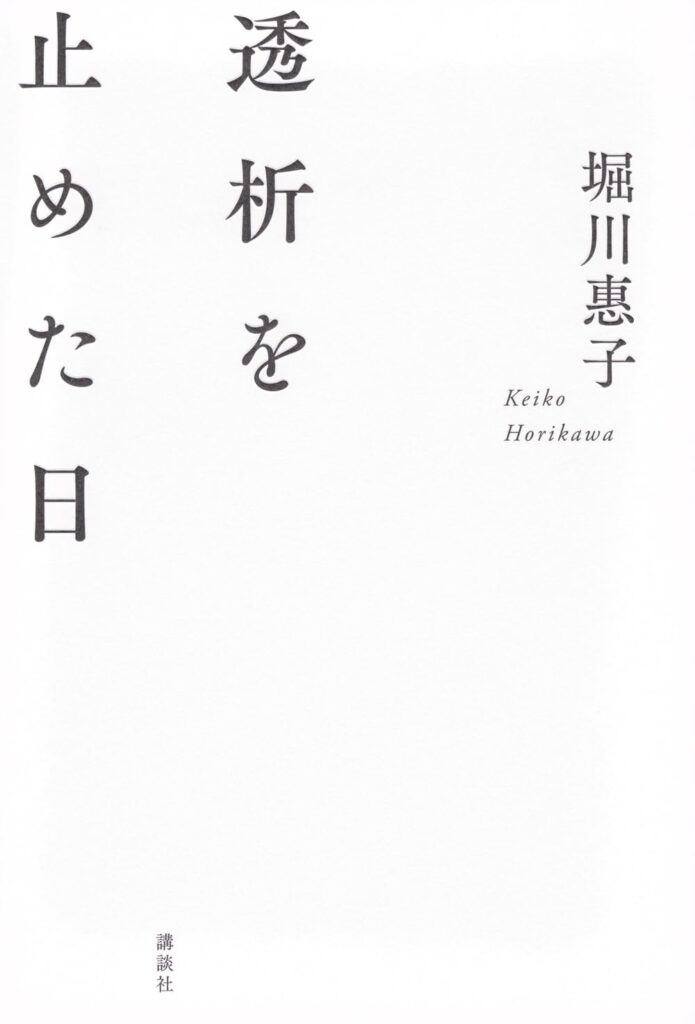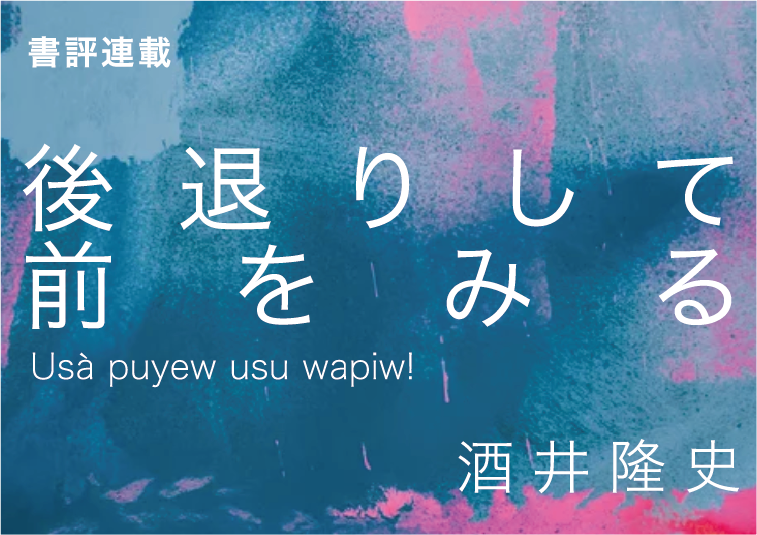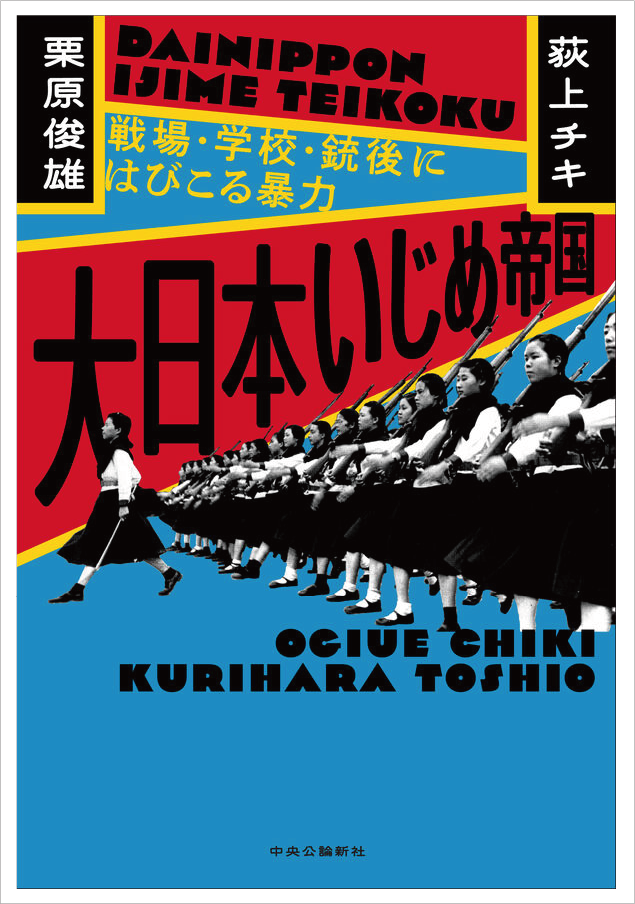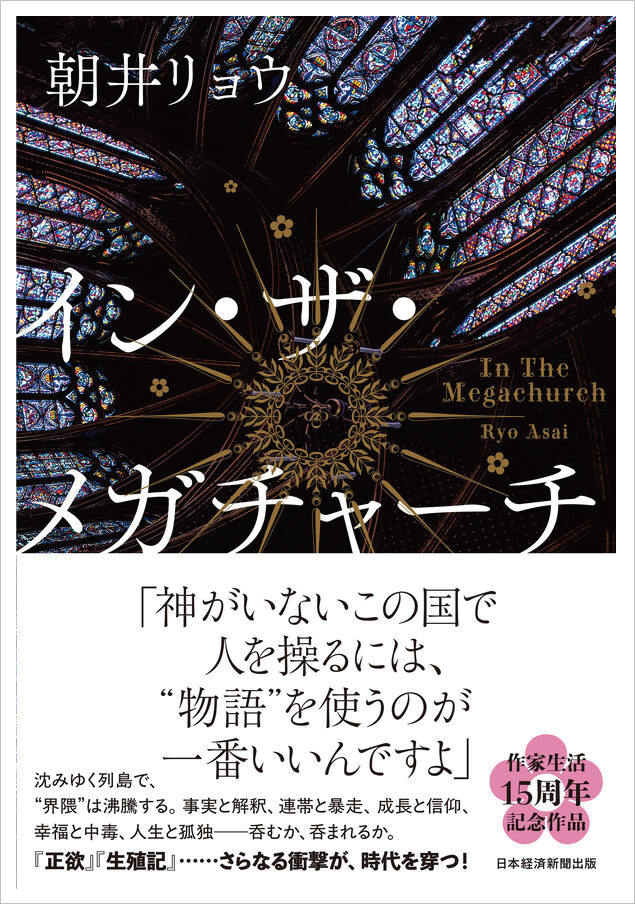沖縄では観光客が求める〝南国の楽園〟とは裏腹に、いまだ終わらない〝戦後〟がある。20年前、初めて訪れた沖縄でそれを目の当たりにした、国道をいで物々しく存在する米軍事施設の数々。走らせたレンタカーの横には米軍の軍事車両が並走する。学校で学ぶことしかなかった戦争は、どこか非現実的なものであったが、沖縄で、〝戦争〟の一端を肌で体感した感覚であった。
それから数年後に沖縄に移住すると、県外からは分からなかった、沖縄の別の表情が見えてくる。日常的に上空を飛び交う戦闘機、米軍兵による事件事故。
多くの観光客、多くの県外者は、沖縄をリゾートとしての〝癒しの島〟とするが、沖縄はずっと80年もの間、戦争と隣り合わせにある。沖縄の現状は米軍の存在によってその影を落とし、ほんの少し前にも、米兵による性的暴行事件のニュースが駆け巡った。それは何十年も変わらないままだ。
1967年に米兵によるレイプ事件を描いた『カクテル・パーティー』で沖縄出身者として初の芥川賞を受賞した大城立裕氏、その後に同じく芥川賞を受賞した又吉栄喜氏、目取真俊氏をはじめとする沖縄出身の作家が、そんな沖縄における不条理を小説作品にしてきた。
そして昨年、同じ志を持った、途轍もない沖縄の小説家が誕生した。豊永浩平。それもまだ大学生の21歳だ。沖縄の名作家たちの思いが豊永に繋げられた瞬間だ。戦後27年続いた米軍統治下に置かれた時代を知らない沖縄の青年が、戦争の惨たらしさ、〝沖縄問題〟と括られる、米軍基地の問題、貧困、性と暴力などの沖縄の現実を描き出した。
物語は14の断章から構成される。小学生の男の子・島尻ケンドリック浩輔が、恋心を抱くかなちゃんと、夏のお盆の日に海に行くと日本兵の幽霊と遭遇する。浩輔の一人称の語りで進んでいく。そして語りがそのまま繋がるように、二章へと接続される。場面が変わり時代は沖縄戦のただ中、最大級の戦闘として知られるほどの激戦であった嘉数高地の戦い、日本兵による一人称の語りとなる。ひらがなの多い日記調から漢字の多い文体へとガラッと切り替わる。米兵との惨たらしい殺し合い、沖縄方言で助けを求める母子をもめる日本兵。物語のキーワードとなる天皇からの恩賜の軍刀。三章、女子高生の愛依子、四章、沖縄をルーツに持つ「大和の兵隊」の島尻大尉と、そのあとも異なる一人称で、現代と過去を章ごとに行き来するように連なっていく。それぞれの章での時代や性別の違う一人称の語りに合わせた文体ではあるのだが、数種の小説を読んでいるかのようでもあり、21歳のその才能に圧倒されることだろう。
タイトルの『月ぬ走いや、馬ぬ走い』は沖縄の黄金言葉の一つだ。古くから伝わる沖縄方言のことわざで、黄金のように価値のある、沖縄で引き継がれている教えである。月日は駿馬のように駆け行くように足早に過ぎる。あとで後悔しないためにも、時間を大切にせよと。この黄金言葉が作中で時代を紡ぐように数回、語りの中で登場する。片足を失った米兵に嫁いだ沖縄女、島尻オバァ、高校生ラッパーの歌詞の中にも散りばめられる。
沖縄戦から現代まで、あっという間に時が過ぎた。基地反対、賛成、そんな議論があちこちで繰り広げられてきたが、基地がなければ理不尽な事件は起こらない。戦争がなければ、基地がなければ、沖縄の現在はどんな景色だったのか。
過去と現在を行き来し、現状の沖縄の基地や貧困、沖縄の影は沖縄戦から続くことだと再認識する。今年は戦後80年。いまだ戦争は終わっていない。
〈今回紹介した本はこちら〉
『月ぬ走いや、馬ぬ走い』
豊永浩平(著) 講談社 1500円+税