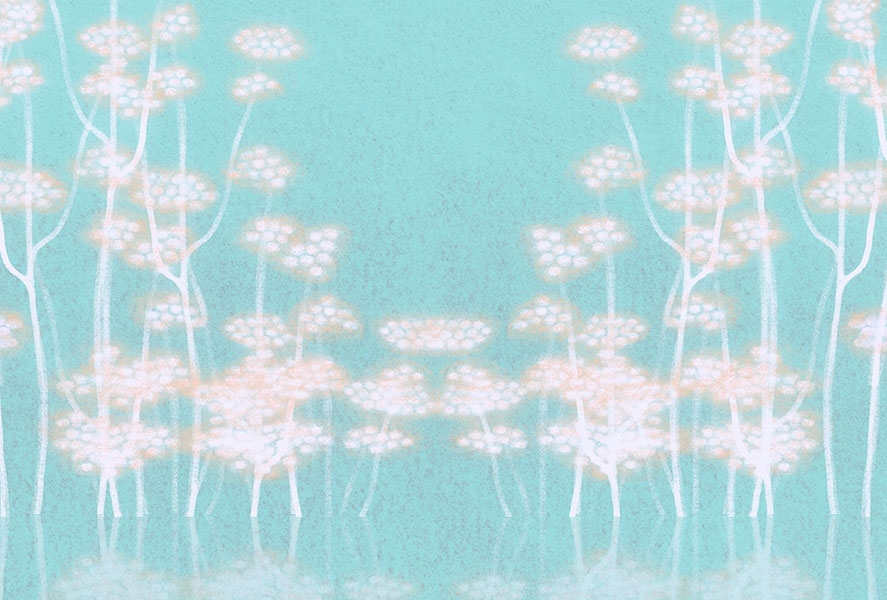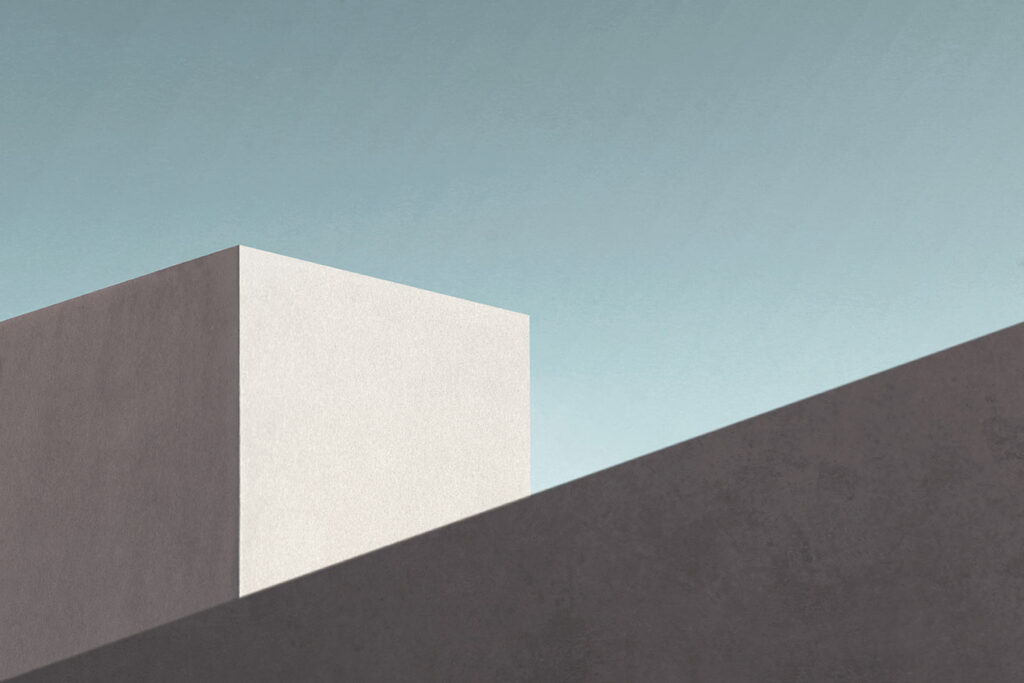【関連】「虚飾の防衛イノベーション(下)――軍事研究大国化の企てとその内実」千葉紀和(毎日新聞記者)
【関連】「日本版DARPA発足――新たな軍事研究所は何を狙うか」井原 聰(東北大学名誉教授)
【関連】「危機に瀕するアカデミア——軍拡バブルのもとで」天笠啓祐(ジャーナリスト)
招かれたノーベル賞候補
人々でにぎわう東京都心の複合施設・恵比寿ガーデンプレイス。レンガ調の瀟洒な建物が並ぶ中心に、地上40階建てのオフィスビルがそびえる。この23階に防衛装備庁が新設した「防衛イノベーション科学技術研究所」がある。
エレベーターを降りてすぐの扉をカードキーで解錠すると、右手に広い部屋が見える。室内は色とりどりのソファや椅子が並び、大型モニターやカフェスペースもある。演出されたカジュアルな雰囲気は、厳重な警備で殺伐とした市ケ谷の本庁と対照的だ。唯一、入口に飾られた大きなドローンが違和感を醸し出す。「人の交流を促して防衛イノベーションを創出する」という、この研究所を象徴する空間である。
3月28日の昼下がり、著名な物理学者がここに招かれて講演した。岩手県立大学学長の鈴木厚人氏。国内有数の研究機関である高エネルギー加速器研究機構の機構長を9年間務め、素粒子ニュートリノの研究でノーベル賞候補と目されていた人物である。
ニュートリノは極めて軽く、あらゆる物をすり抜けて飛ぶ。恒星が一生の終わりに起こす超新星爆発や太陽内部の核融合反応などで生じるとされるが、検出は困難だった。日本はこの分野の研究をリードしてきた。岐阜県の神岡鉱山地下に建設された装置「カミオカンデ」は、1987年に超新星爆発のニュートリノを世界で初観測したことで知られる。この功績でノーベル物理学賞に輝いた小柴昌俊博士の右腕だったのが鈴木氏だ。その後は、低エネルギーでも識別できる装置「カムランド」の建造を主導。原子力発電所の原子炉と、地球内部のウランやトリウムの崩壊によって生じるニュートリノの検出にも成功した。
この道の泰斗である鈴木氏は講演で、スライドを映しながら研究の歴史や意義を語った。さらに、次世代加速器「国際リニアコライダー」計画の東北誘致の必要性も強調した。耳を傾けたのは、研究所の片山泰介所長と装備庁の猪森聡彦・装備技術官(海上担当)、海上自衛隊の幹部、防衛技官ら40人近く。話が終わると、盛大な拍手で謝意が示された。
軍事と物理学――。この両者は歴史上、たびたび交わってきた。原子爆弾、レーダー、補償光学など、その産物を挙げれば例に事欠かない。しかし、宇宙の起源に迫るニュートリノとなると、途端に縁遠く感じる。この講演、開催の目的は何なのか。
内情を知る装備庁関係者は思わせぶりに口にした。「難解な話を出席者たちが理解できたかどうかは怪しいが、そんなことはどうでもいい。鈴木さんにここで話してもらったことに意味がある」。
日本版DARPAの現状
この研究所はいかなる存在なのか。防衛省の外局である防衛装備庁が、5つ目の研究機関として昨年10月に開設した。従来の研究所は各地の駐屯地内にあり、民間施設に設けたのは珍しい。最大の特徴は、米国防総省の国防高等研究計画局(DARPA(ダーパ))をモデルにしている点だ。米国の安全保障のために産官学連携で技術革新を追求する軍事機関である。ゆえに「日本版DARPA」と呼ばれている。
本家を意識してか、英語表記の頭文字を取った「DISTI(ディスティ)」なる愛称も用意されている。だが、私が取材した装備庁の関係者は全員が「イノベ研」と呼んでいた。よって、本稿では原則、イノベ研と略する。
所属するのは、職員60人に非常勤職員を加えた総勢91人。このうち44人が研究職だ。ここには後述するプログラムマネジャー(PM)も含む。研究所といっても、実験施設や装置は一切存在しない。では、何をしているのか。
イノベ研の説明資料を読むと、目的は「社会を大きく変える防衛イノベーションの創出」とある。そのために「従来の常識を覆すブレークスルー研究」を進め、「先進的な民生技術を取り込み、将来の戦闘様相を一変させるゲーム・チェンジャーとなり得る技術を早期に実用化する」らしい。定義の曖昧な横文字の多用で煙に巻かれた気分になるが、できる限り補足説明を加えながら先に進めよう。
イノベ研が担う事業の柱は3本ある。①ブレークスルー研究、②安全保障技術研究推進制度の運用、③先端技術の調査や分析を担うシンクタンク活動――だ。本丸の①は2種類に分かれ、「革新型ブレークスルー研究」と「実証型ブレークスルー研究」と命名されている。
前者は外部の研究者をPMとして登用し、目的に沿った研究開発を進めてもらうのが特徴だ。初年度に選ばれたのは14人。国立研究機関や民間企業の研究者のほか、横浜国立大学や信州大学、熊本大学などの現職教員が名を連ねている。DARPAのPM経験者もいる。
各PMが手がける研究内容は明らかにされていない。その中で、例外的に政府が早くから公言してきたのが「素粒子を用いた革新的な潜水艦探知機能の研究」である。視界の利かない海中にいる潜水艦の探知には現状、音波が用いられている。ところが、水中の音速は温度などで変化を受けやすく、正確さを欠く。近年は潜水艦の静粛性も向上し、探知が一層難しくなっているという背景がある。それゆえ新たな探知手法が必要というわけだが、具体的な研究内容は不明だった。
今回取材したイノベ研の研究統括官である南亜樹博士は「原子力潜水艦の原子炉から出るニュートリノを検知し、位置を特定する手法」だと明かした。
ニュートリノで原潜探知
ニュートリノでどのように原潜を探知するのだろう。詳細な手法は当然ながら公表されていない。PMに登用されたのは佐々木真人氏。ニュートリノ研究の国内拠点である東京大学宇宙線研究所で昨秋まで准教授だった人物である。
素粒子研究の応用と聞けば、極めて革新的な印象を受けそうだ。しかし、実はニュートリノを監視に用いる発想は斬新なものではない。原子炉ニュートリノによって、他国の原子炉の稼働状況を遠隔で探る米国主導のプロジェクトがある。核拡散防止条約(NPT)に反し、違法な原子炉が動いていないかを監視する試みだ。
とはいえ、通常の原子炉は地上に固定されるのに対し、原潜は海中を移動する。信号源の位置が変わるのだから、特定の難易度が段違いなのは想像に難くない。たとえニュートリノ研究が日本の「お家芸」だとしても、実現可能性は気にかかる。まず信号自体を検出できるのか。仮にできるとして、位置までわかるのか。素人考えでも、装置が1基では不可能だろう。3点測位の要領で最低3基あれば、それぞれから交わる1点の位置が計算できるのだろうか。
ここは専門家に聞くしかない。まず訪ねたのは、ニュートリノの研究で鈴木氏に匹敵する実績と名声を持つ世界的研究者だ。ここでは仮にA氏としておく。