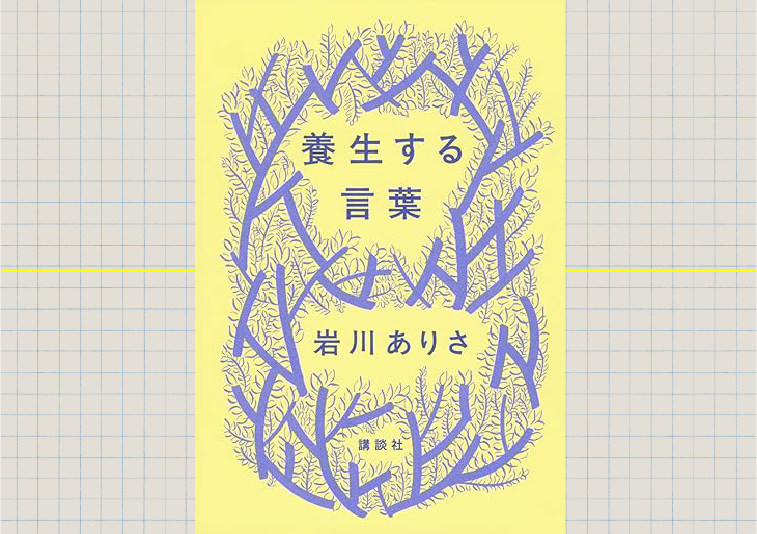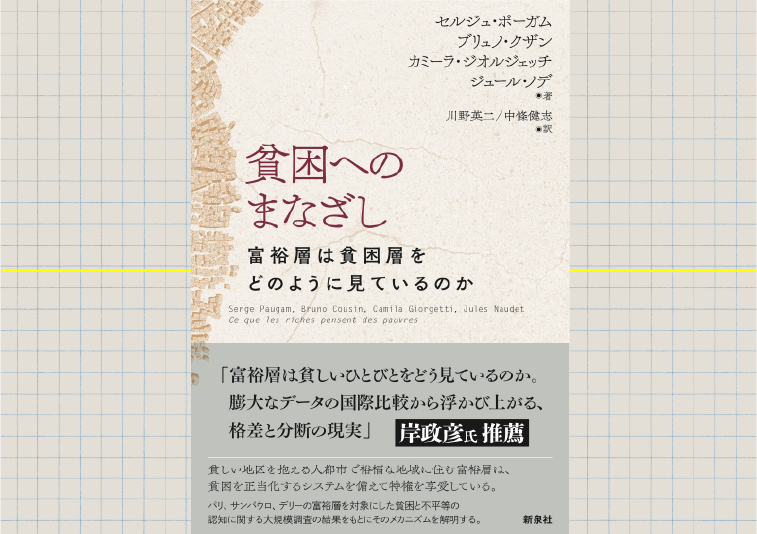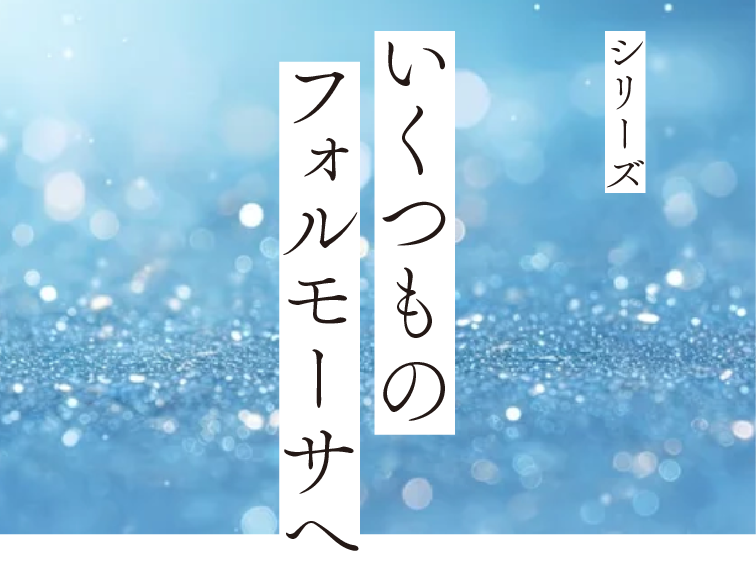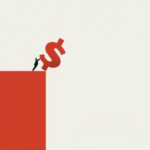ケアの姿勢が貫かれた本
「養生」という言葉はどんなときに耳にするだろう。身近なところでいえば、布やパッドを養生テープで壁や床に貼って保護してから家具などを運搬する際、「養生する」と表現するときではないだろうか。そのテープもはがさなければならないため、粘着力も弱めである。このように「養生する」には、大切なものが傷つかないよう保護するという意味があるが、岩川ありさによる『養生する言葉』は、まさに誰も傷つかない世界をつくろう、傷ついた人がいれば手を差し出そうとするケアの姿勢が貫かれている。
タイトルが「養生論」ではなく、「養生する言葉」となっていることにも、著者の明確な意図があるように思われる。「正・誤」を前提とする「論」は、「正しいものを残し、正しくないものを蹴飛ばす動きを生」んでしまう。反対に、養生は根本的に「生を養うこと」であり、「生が失われないようにすること」である(『養生する言葉』、127頁)。もし「養生論」というように「論」を取り込んでしまっては、それ自体、言葉が矛盾してしまうのだ。岩川は、「他者を一撃で突き崩そうとし、あざけるような『論破』」が「いのち」を「ひやり」(同、21頁)とさせるという精神科医の神田橋條治の言葉を参照しつつ、「論」が含意するものがいかに生の伸びやかさを奪ってしまうかを訴えている。
本書の魅力は、読者が抱えるかもしれない傷にそっと寄り添おうとする語り口である。岩川は多様な作品や著作から選りすぐった言葉を編み込みながら、さまざまなテーマについて幅広く語っていく。大江健三郎、ハン・ガン、津村記久子の小説だけでなく、泥ノ田犬彦の『君と宇宙を歩くために』や金城宗幸・ノ村優介の『ブルーロック』といった漫画、それから中井久夫の『執筆過程の生理学』や上岡陽江・大嶋栄子『その後の不自由』などのケアをめぐる本などから養生する言葉を抽出していく。
岩川自身が負った心の傷を回復へと導くために必要としてきた言葉を、今度は読者のために投げかけてくれるのである。トラウマをめぐる自分との対話、生きるための知恵、「助けて」というハードルをさげる方法、トランスジェンダーと災害、学び直し方、養生の体系のつくり方、スピリチュアルケアなど、さまざまなテーマを扱いながら、言葉による養生を試みる。
脱近代とケアの「光」をめぐって
おそらく本書で重要なのは、言葉によって養生がなされたとき、岩川はそれを「光」として捉えていることであろう。たとえば、泥ノ田犬彦の『君と宇宙を歩くために』には、学校でも、バイト先でもいつも失敗ばかりしてしまう小林大和という主人公の例が挙げられる。誰からも承認されない小林はすっかり自信を失ってしまっているが、突然、転校してきたばかりの宇野啓介に声をかけられる。
小林大和くん!!
(『君と宇宙を歩くために』第1巻、第1話)
こんばんは!!
岩川は、この言葉を「大きな光」だと表現する(同、66頁)。自分以外の人が易々としていることを小林はできない。そんな彼が、ある日、宇野にフルネームで呼ばれ、勇気づけられる。
ここで使われている「光」という表現は、「啓示宗教」としてのキリスト教の光でもなければ、反対に、啓蒙時代の理性の「光」ともまるで印象が違う。「蒙」(物事に暗いこと)を「啓」(ひら)くという意味の啓蒙思想は、科学と合理主義哲学によって政治的、宗教的偏見や迷信を打破し、“公正〟な社会の構築をめざそうとした。啓蒙思想という言葉は、英語(Enlightenment)、フランス語(les Lumières)、ドイツ語(Aufklärung)のいずれの言語でも「光で照らすこと」と書かれる。
たしかに、ジョン・ロックからイマヌエル・カントにかけて近代の思想家たちは、「個人」の権利が守られる“公正〟を基盤とする社会で「光」があまねくすべての人を等しく照らし、その恩恵に与れるようなヴィジョンを見据えていた。けれども、法の下で平等が謳われる社会になっても、強者だけが権利を勝ち取れるという弱肉強食の状況であることは変わらない。
岩川が見いだそうとする「光」は、目に見えるわけではなく、人の心を感じ取ることでその存在を確かめるようなものだ。『君と宇宙を歩くために』の宇野自身も不得意なことばかりで、生活するうえでのさまざまな困難を乗りこえようとしてきたマイノリティである。小林はそんな彼が積み重ねてきた「試行錯誤」の証左を、「悔しくても/泣くのは家に/帰ってからにする」という宇野の言葉のなかに探り当てた。小林は「このとき、宇野の心のなかの宇宙に触れたのだ」(同、67頁)。「光」は目に見える形で表出するのではなく、他者の「心のなかの宇宙」にあった。
近代的な自我の確立は個の尊重と引き換えに、他者を養生するというケア思想を遠ざけてしまった。だからこそ、「養生(=ケア)する」とは、自他境界をあえてあいまいにし、「自己責任」という名のエゴイズムに抗うことで、新たな主体を構想することなのだ。それが失われてしまう世界とは、どのような社会だろうか。
「取るに足りない」と思われている人びとの戦い
近代以降、平等な社会が実現しているようにふるまう強者たちが、弱者の存在を透明にし、彼らの声を奪ってきた。社会的弱者が無力であるばかりに社会から置き去りにされ、ときに命まで奪われてしまうことがある。
「自己責任」という名の無責任の典型例はセウォル号沈没事件に見いだされるのではないだろうか。『〈弱さ〉から読み解く韓国現代文学』(NHK出版、2024年)の著者、小山内園子は、2014年に起きた大型客船セウォル号が沈没したことで乗客乗員476人のうち304人――250人は高校生――が亡くなった沈没事故を、「沈みゆく船を見殺しにしたという自責の念」がまだ多くの人の記憶に新しい事件であると形容した。
十分救える時間的な猶予がありながら、これだけの人のいのちを救えなかった背景には、休暇中の船長に変わって1年契約の船長が乗船していたこと、経験の浅い乗員の判断ミス、メディアが取材せずに誤報を出したことなどがある。それによって、乗船していた多くの子どもたちが犠牲になってしまった。しかも驚くべきことに、当時の朴槿恵大統領が最初に事故の報告を受けてから、中央災難安全対策本部を訪問するまでの間、「空白の7時間」があるとされている。
ファン・ジョンウンという韓国人作家はこの事件に衝撃を受けて、いっさい作品を書けなくなってしまった。「国家とは何か、社会とは何か、そして文学の果たす役割とは何か」、彼女は国や社会への信頼や期待を失ったのだった(同、138頁)。しかし、2年後の2016年の秋、朴大統領が知人に機密文書を漏洩していたことが報道されると、彼女の退陣を求めるデモが行なわれた。人びとは火をともしたろうそくを手に集まった。
ジョンウンの『ディディの傘』という小説には、このキャンドル・デモの様子が描かれている。恋人を喪った主人公はこう語る。
他の場所、他の人生、他の死を経験した人たち。彼らは愛する者を失い、僕も恋人をなくした。彼らが戦っているということをdは考えた。あの人たちは何に抗っているのだ。取るに足りなさに 取るに足りなさに。
(同、137頁)
セウォル号沈没事件は氷山の一角である。社会の強者から、「取るに足りない」と思われる人びとのいのちが世界中で軽んじられている。
『養生する言葉』では、1948年のイスラエル建国に前後して、約75万人のパレスチナ人が故郷や居住地を追われ、難民化した「ナクバ」という出来事や今ガザで起こっているイスラエルによる殺戮を取り上げている。「私は目を逸らしたくない」(『養生する言葉』、129頁)と岩川はいう。遠くの地で苦しむ人びとに単に同情するのではなく――なぜなら「自分は「無罪」だと主張するような効果を上げてしまうから――彼らから自己の「責任」を切り離さしてはならないと強調する。それはそのまま、スーザン・ソンタグが訴える言葉であるという。
戦争や殺人の政治学にとりまかれている人々に同情するかわりに、彼らの苦しみが存在するその同じ地図の上にわれわれの特権が存在し、或る人々の富が他の人々の貧困を意味しているように、われわれの特権が彼らの苦しみに連関しているのかもしれない(中略)という洞察こそが課題であり、心をかき乱す苦痛の映像はそのための導火線にすぎない。
(『他者の苦痛へのまなざし』、102頁)
大学教員である岩川も、そして同じ立場にいる評者も、「特権」を意識している。「自分が認め放棄したと思っている『特権』を実はその後も保持している場合もあるだろう」。だから「その不均衡について意識し続け、変えてゆく実践に加わることこそ『特権』と戦うことなのである」
(『養生する言葉』、139頁)。
小山内もまた、より多くの可能性をもたらしてくれるのは「より強い腕力、より良い視力、より敏感な聴力」ではなく、「自分が今のめり込んでいる活動の意味と必要性を自ら省みることのできる能力」であるという。誰もが不安や欠損を抱えながら生きているにもかかわらず、「大丈夫なふり」をしつづけてしまったり、「強いものの規範に自分を合わせて」しまったりする(234頁)。どうすれば「強い」ふりをすることをやめて、いのちの弱さを認め合うことができるのだろうか。
かろうじてともる〝ろうそく〟の光
公共体から排除されてきた女性やマイノリティたちは、じっさい権利が保障されてこなかっただけでなく、自立から程遠い存在で見放されていることが多い。養生するとは、いかに互いに弱い存在であるかを認め合い、支え合いながら生きられるかに注視することである。そのたとえとして、岩川が選んだのが、ハン・ガンによる『すべての、白いものたちの』(斎藤真理子訳)で語られる「生まれて2時間で死んだ」姉をめぐる物語、そして、同作者による『少年が来る』(井手俊作訳)でつぶさに記録される、民主化を求めて抗争し、戒厳軍に殺された光州の人びとの物語である。
ここで岩川は「ごくふつうの人々の記憶と記録を、ろうそくのようにともし続けること」の大切さを江南亜美子の言葉を援用しながら語っている。『少年が来る』では、「子どもたち、貧しさにあえぐ人びと、女性、被傷性を帯びた男性たちなどに光があたっている」のだ(『養生する言葉』、50頁)。傷つきやすい人たちと共に探し求める「光」はろうそくの火のように微弱である。だから、「かろうじてともる「ろうそく」の光に映し出される他者をどのように記憶できるか?」(同前)という岩川の問いこそがもっとも重要なのだ。
この微弱なろうそくの火は、近代のリベラリストたちが見過ごしてきた子どもたち、貧しさにあえぐ人びと、女性、被傷性を帯びた男性たちの傷を照らし出すことができる。戦争や革命の勝利を掲げるヒロイックな物語や正義を振りかざす強者の物語から排除されてきた弱者たちの取りこぼされてきた人のための「光」が消えないよう、本書は言葉を紡いでいる。
岩川が語り直した『君と宇宙を歩くために』『すべての、白いものたちの』『少年が来る』、そして小山内が取り上げた『ディディの傘』にも、共に苦しみ、支え合うケアの営みがある。「誰かが悔しさや痛みを感じて泣いているとき、それを目撃したり、触れてしまったりしたとき、目をそらせず、立ち去ることができないことがある」という。それが岩川のいう「共感共苦」である(同、67頁)。
すなわち、弱さを認め合い、互いに支え合うことこそが「養生」なのだ。津村記久子による『水車小屋のネネ』を読んだ岩川は、「自分の人生を振り返っている気持ちと重なって、読みはじめるとやめられなくなった」という。これは、母親の恋人からの精神的虐待に苦しんでいた8歳の律の傷に触れてしまった姉の理佐が律を連れて家を出る物語である。理佐は律が学校を卒業して経済的な力を持つまでは、ある蕎麦屋で住み込みとして働く決意をする。二人は蕎麦屋の夫婦や鳥であるヨウムのネネの支えを得ることで、なんとか生き延びることができた。当然小学生だった律ができることはかぎられているが、それでもネネの相手をすることでケアは循環する。
たしかに『水車小屋のネネ』が教えてくれるのは、「自分がそこにいてもいいと思える場所があって、自分たちを傷つける人たちのそばにいる必要がないということ」である(同、99頁)。それは「不当な暴力に抵抗すること、不服従であること、連帯すること」(127頁)でもある。無力な子どもたちを保護するはずの大人が不当な暴力をふるうのなら、依存先を増やして生き延びるべきだという力強いメッセージである。
津村の「レコーダー定置網漁」は、「大変な状況」に直面した人が「思いやりつつ、最小限に設定したハードルをクリアする」ことが主題である(同、95頁)。離婚を経験し、「何もやる気が出ない状態にある」加賀美綾子という料理の先生が、「面倒くさくて、でも、ある程度、体に良さそうなもの」をつくり、「ハードルを下げる」ことを肯定している(同、94頁)。これはいかなるケースにも応用できそうだ。心の傷を抱えているとき、パーフェクトな解を求めすぎないこと、おのおのができることを少しずつ実行することが大事なのかもしれない。
本書を読み終わって、阿部暁子による『カフネ』(講談社、2024年)を思い出した。溺愛していた弟が急死して悲嘆にくれていた主人公の野宮薫子が、掃除をする才能を買われ、プロの料理人である小野寺せつなとともに様々な問題を抱える家庭を訪問し、家事代行のボランティアを行なっていく物語である。薫子がせつなと個々の家庭の事情に配慮しながら、家をきれいにし、最適な料理を提供するが、そこには元の生活を取り戻させるという傲慢さはかけらもない。どちらかといえば、掃除や料理さえする心のゆとりを失っていた人たちに少しだけ息がしやすくする余白をもたらす活動なのだ。薫子もまた弱さを認めることで生きる力を取り戻していく。これこそ、岩川のいう「養生する」ということではないだろうか。
本書は、近くで起こっている他者の困難も、遠くで起きている戦争や暴力的な弾圧も自分とは無関係だとして思考停止してしまわず、その事象について考えつづければ「養生」につながることを教えてくれる。「養生することはいつも社会的なことである」(250頁)と岩川はいう。評者も、無慈悲にも戦争で人びとのいのちが奪われる現状を容認しないこと、性暴力で傷ついた人たちが社会の構造的暴力によってさらに苦しめられていることを許さないことも養生することにつながると信じている。
〈今回紹介した本〉
『養生する言葉』
岩川ありさ 著、講談社、2025年2月