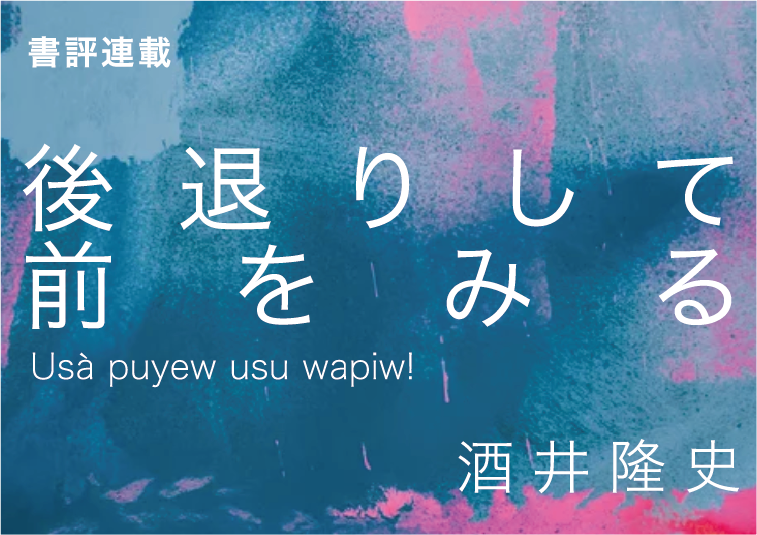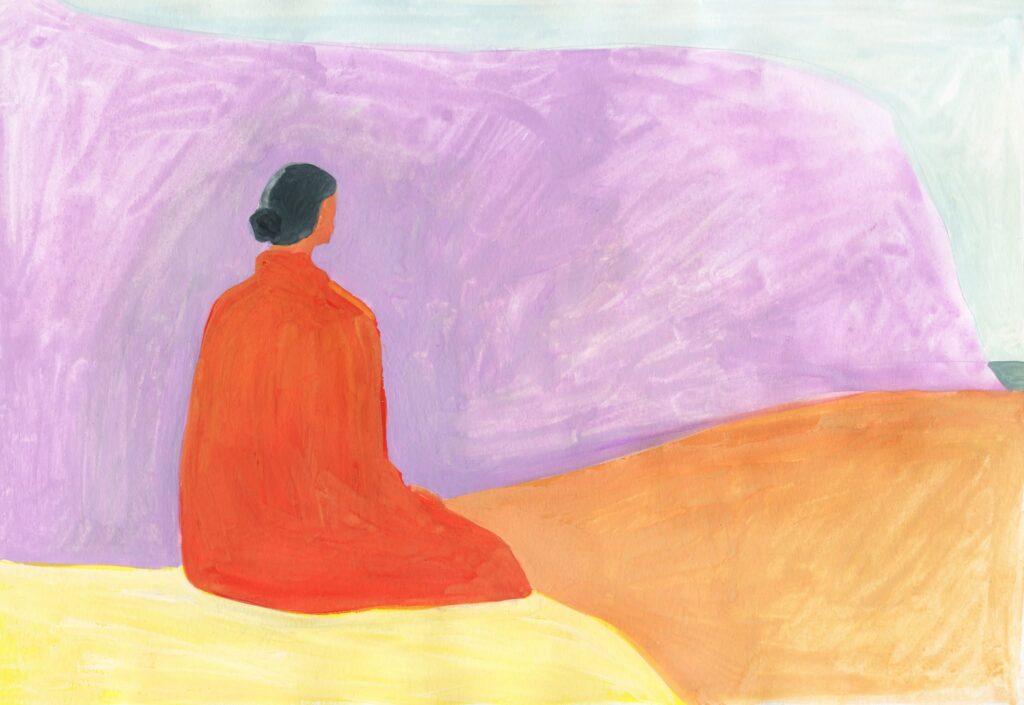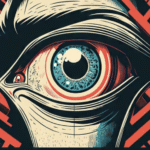これまでの記事はこちら
単純に割り切れば、現在、世界には二つの「ゾーン」のイメージがあって、それはわたしたちの世界のイメージにかたくむすびついている。かたや、『ストーカー』系、かたや『スノウ・クラッシュ』系。
説明しよう。まず、『ストーカー』系。
アンドレイ・タルコフスキーが映画にしたストルガツキー兄弟の『ストーカー』(深見弾訳『ストーカー』ハヤカワ文庫、2018年)のものがある。ゾーンとはそこでは、エイリアンが痕跡を残していった一帯であって、国家による管理区域だが、そこには「ストーカー」と呼ばれる闇の売人がいて、リスクをかえりみずそこに残された遺物をもちかえり、高値で売りさばいている、そんな一帯。未知との遭遇、根源的に異質な世界である。この作品が書かれたのが1972年。ちょうどその20年後、もうひとつの「ゾーン」のイメージによって、そんな崇高なゾーンのイメージは上書きされ、くつがえされる。
いっぽうの、ニール・スティーヴンスンの『スノウ・クラッシュ』(日暮雅通訳『スノウ・クラッシュ(上下)』ハヤカワ文庫、2022年)系。このテキストがえがく世界はまず二層だ。「メタヴァース」(いま知られているメタヴァースはここからとられた)というヴァーチャル空間、そしてすべての諸制度や諸機関がほぼ完全に市場化された、私有化/民営化された国家、いや疑似国家、疑似共同体からなる極度に断片化されたリアルな空間。それぞれに厳重なゲートがあり、身元チェックがあり、不断の監視によって、逸脱があればすぐさまガードマンあるいはロボットがやってきて取り締まる。主人公はフリーのエンジニア兼ウーバーを先取りしたようなフードデリバリーのギグワーカー。テクノリバタリアンや「アナルコ=キャピタリスト」たちは、この世界から強力なインスピレーションをえる。
『ストーカー』のゾーンが、それこそデリダの「ファルマコン」よろしく、ミステリアスなエイリアンによって異世界にひらかれた、人類にとって毒と薬の極端な両義性を帯びたタブー空間であったとすれば、『スノウ・クラッシュ』のゾーンは、パスワードとガードマンによって厳格に隔たれた、私企業が国家にとってかわった両義性もタブーもクソもない世俗的空間だ。主人公も、冒険家、破滅型、アウトロー気質の狩猟人のストーカーは、そうした資質は起業家気質に昇華させ、その想像力はメタヴァースに封じ込めた、シリコンバレー的現代人である。