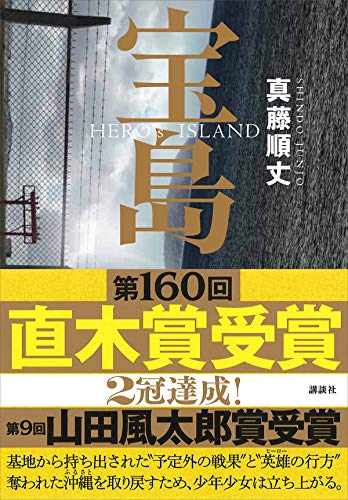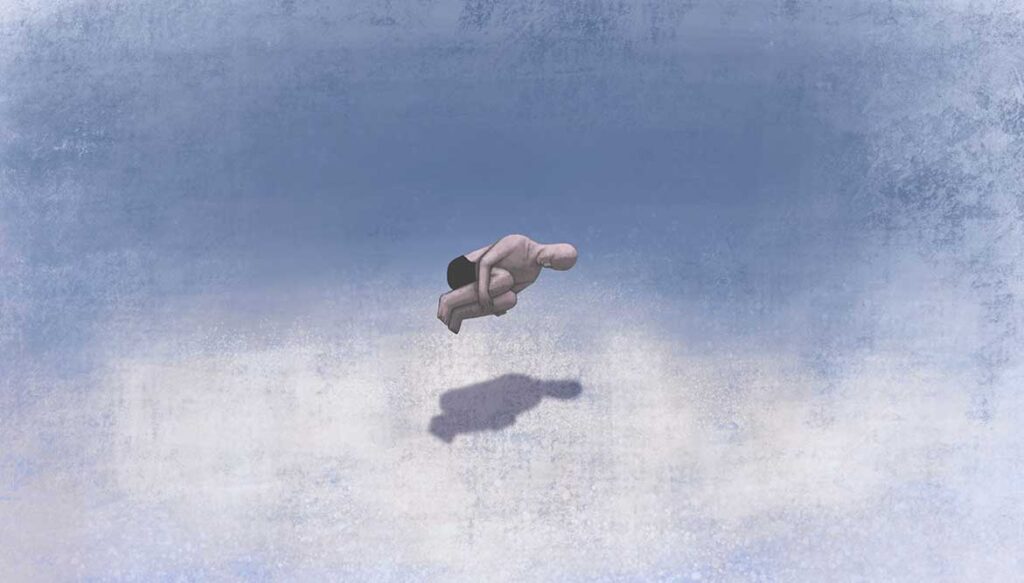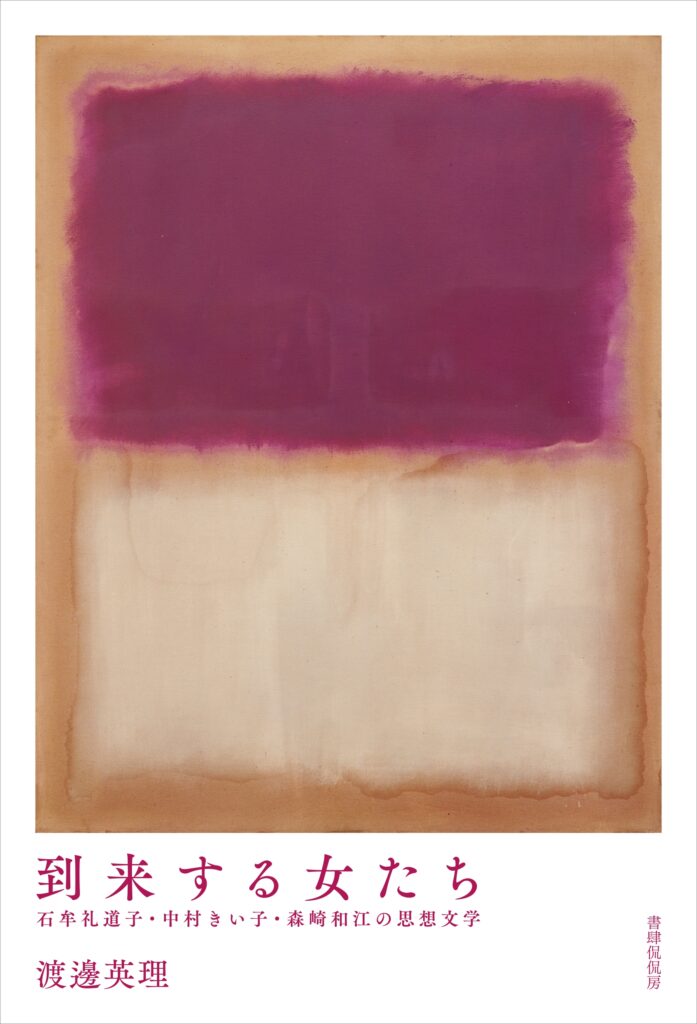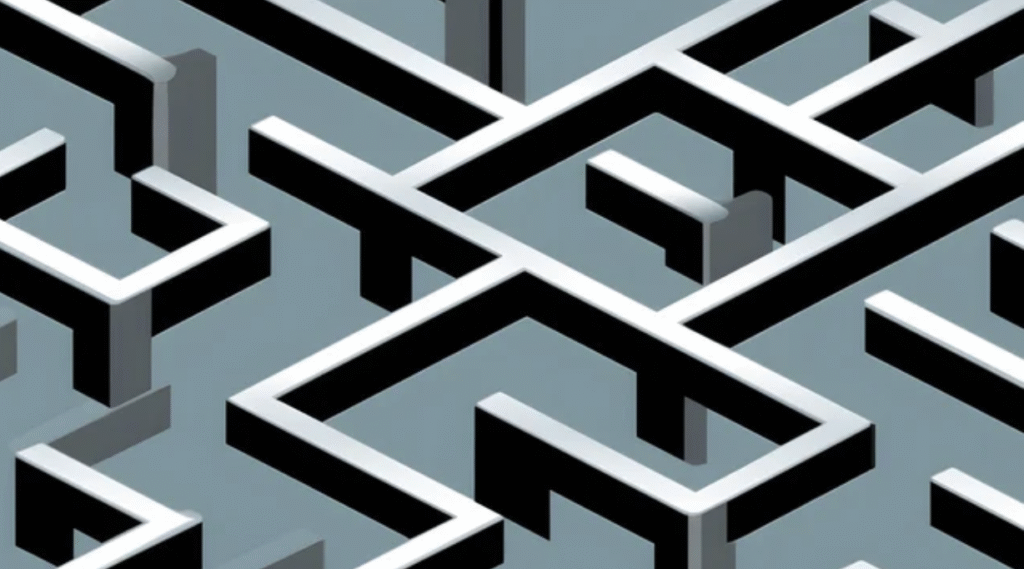紹介する本:『宝島』(真藤順丈著、講談社、2018年6月)、『英雄の輪』(同、2025年9月)
2018年の直木賞受賞作『宝島』が映画化され、いよいよ9月に公開となった。当初は数年前には完成していたはずの映画であるが、コロナ禍によって大幅に遅れ、豪華キャスト陣のスケジュール上、奇しくも戦後80年の今年になったようだ。そんな今年は「かなさんどー」「木の上の軍隊」「風のマジム」など沖縄が舞台の映画が平年より多く公開されている。
『宝島』は沖縄の米軍統治下時代を舞台に、〝戦果アギヤー〟と呼ばれる若者たちを描いた物語。アギヤーとは沖縄方言で〝持ち帰る者〟という意味で、当時の住民の生活は困窮し、米軍基地に忍び込んで物資を奪い、それを貧しい人々や仲間たちに分け与えていたという。沖縄戦を経てアメリカに支配され、理不尽な時代に立ち向かって生き抜こうとする姿に多くの共感を呼び、県内でも大ベストセラーとなった。
だが、刊行当初は違った。後に直木賞を受賞するこれほどの作品のゆえ、ご当地沖縄ではどこの書店でも売場の一角に大きく展開され、ジュンク堂でも店舗入口の一等地にて猛プッシュした。しかしながら、なぜかまったく売れない。1カ月間、大展開したが、その陳列場所では開業以来、もっとも少ない売上冊数となったのだった。分厚い大長編だから? タイトルが沖縄であるとわかりにくいから? いろんな理由を考えたが、私がその売場付近で作業をしていたとき、70代くらいの女性に声を掛けられ、理由が判明する。
「書いた人、ナイチャーね。これ読めないね」
県外者が沖縄を描くことの難しさを痛感する出来事だった。ましてや沖縄戦後の歴史が題材だ。その後も多くの方から同様の意見を頂戴した。発売3カ月後には著者イベントも企画したのだが、集まった方々はたったの5人。県外ではすでに高評価になっていたが、まるで不買運動でも起こったかのような状態だ。
それから2カ月後、直木賞受賞が発表され、状況が一変する。賞が沖縄の読者を後押しし、ようやく売れていく。著者真藤の父親は沖縄と深く関わっていて、家には大田昌秀元知事の書物や、沖縄の歴史本や写真集が溢れ、真藤は子どもの頃からそれらを読んでいたという。そんな著者の沖縄に対する長年の思いと、沖縄を描く相当な覚悟が明らかになっていくことで、真藤自身が沖縄で連日メディアに大きく取り上げられ、時の人となった。受賞後に再度行なったイベントは満席で座席が足りず、なんと会場は200人の人で溢れた。彼の登場時には割れんばかりの拍手と指笛が飛び交い、ずっと続く沖縄の怒りをこの小説に描いた真藤に対し、沖縄の皆さんの気持ちがここに集約された。
映画の公開に合わせ、『宝島』の続編『英雄の輪』が刊行。「宝島」にまつわる6編の短編を書き上げた。沖縄のチャップリンと呼ばれ、戦後復興時に沈んだ沖縄を歌と踊りで励まそうとした演劇人・小那覇舞天「ブーテン」。日本復帰後19678年7月30日に「車は右・人は左」から「車は左・人は右」と交通ルールが切り替わり大きな混乱が生じた出来事を背景に、本編の登場人物のその後を描いた「ナナサンマル」など、まだまだ沖縄の戦いは終わらず続いていく。
これまで多くの県外の方に基地負担をどう思うのか聞いてきたのだが、語られるのは県外目線の国防の話ばかり。そもそも沖縄への無関心からの答えなのだろう。宮森小学校戦闘機墜落、米軍車両死亡事故の無罪判決、県民の怒りが爆発したコザ暴動。この作品を通して、多くの県外の方に沖縄の歴史を知ってほしい。新たな価値観で見えてくるはずだ。沖縄に住む県外者として、映画と共にこの作品を応援したい。