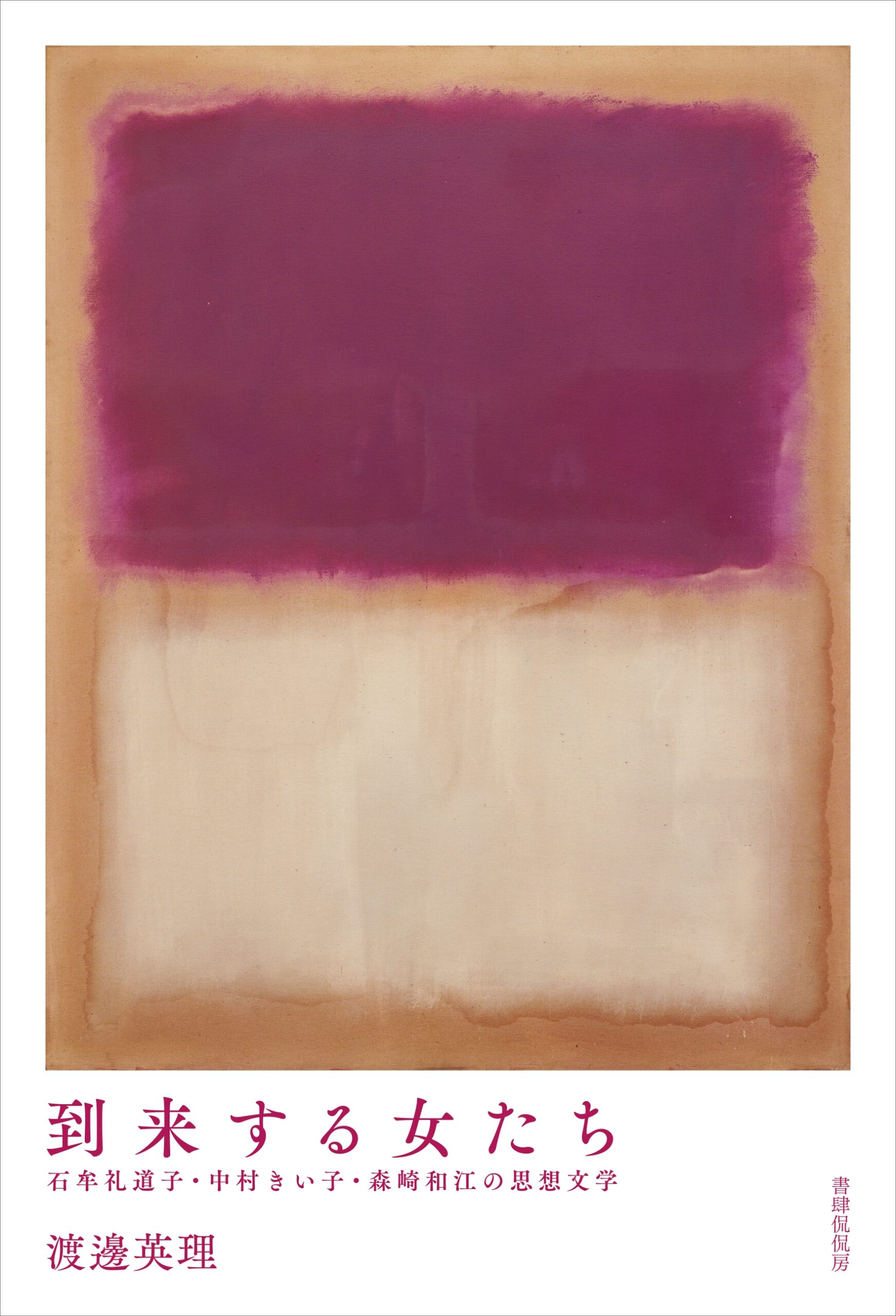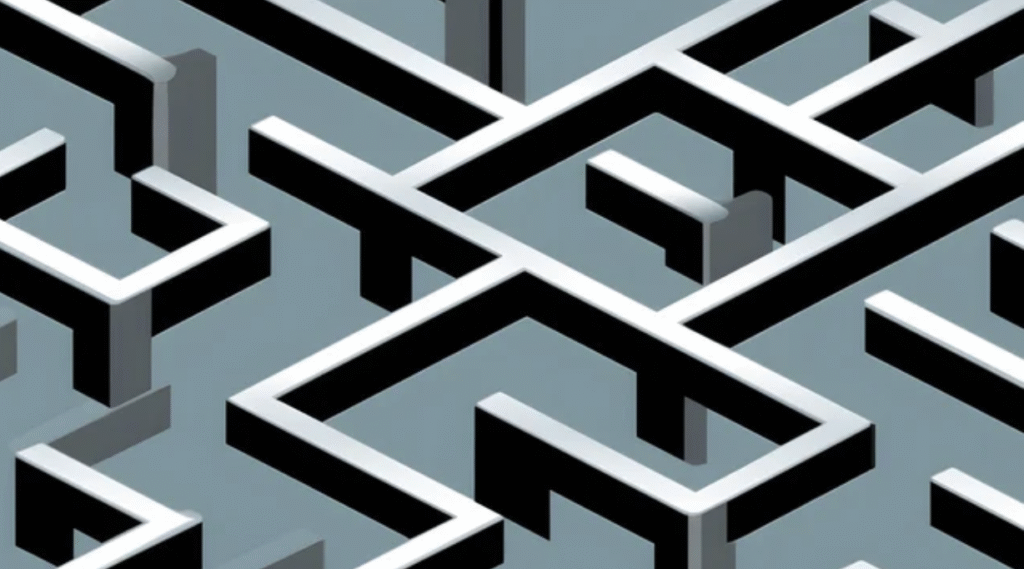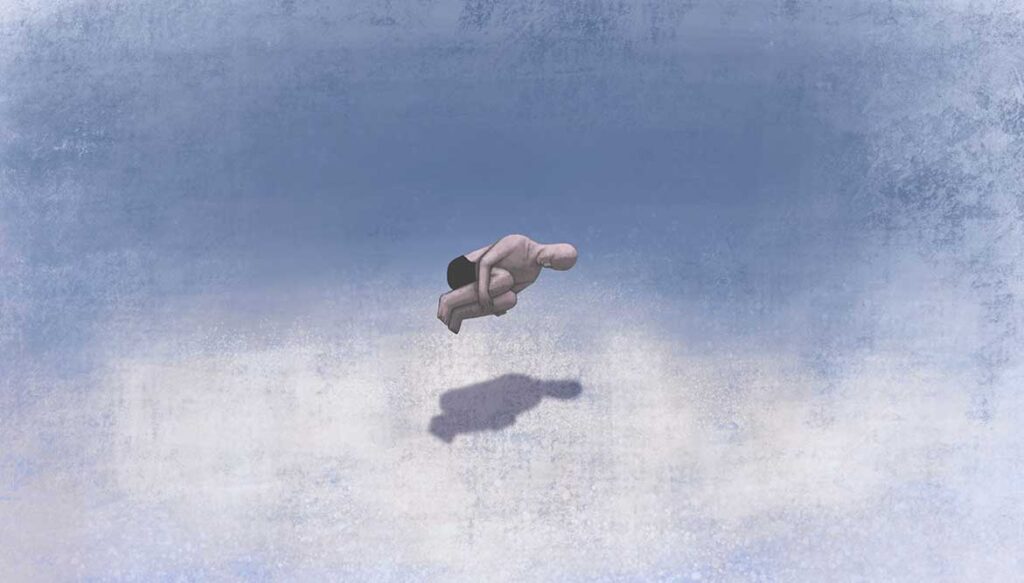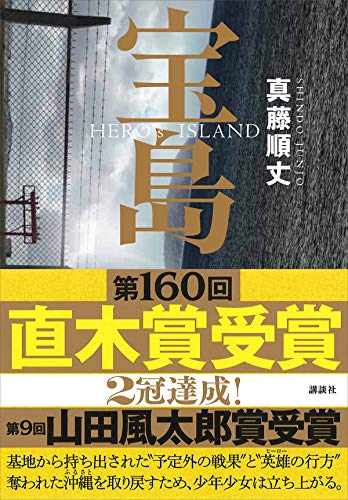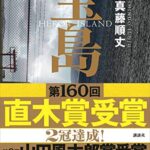紹介する本:『到来する女たち 石牟礼道子・中村きい子・森崎和江の思想文学』渡邊英理著(書肆侃侃房、2025年7月)
九州で書きつづけた女性作家の群像
戦前日本において女性の活躍の場は著しく制限されていたが、文筆を通じて名をなした女性は少なくない。女性運動、労働運動、社会主義運動などにコミットして知識人的な役割を果たした女性も数多く存在する。
ただし、地方生まれの女性の場合、事実上、上京することが作家・知識人として活躍するための前提条件となっていた。九州ゆかりの作家・知識人の場合を例に挙げたい。
福岡県生まれの伊藤野枝(1895―1923)は、高等小学校卒業後に叔父を頼って上京し、上野高等女学校に編入した。女学校卒業後は親の決めた相手との婚約を破棄して東京に留まり、『青鞜』の運動に参加した。『青鞜』終刊後は関東大震災直後に虐殺されるまで、パートナーの大杉栄と共にアナキストとして活動した。
熊本県生まれの高群逸枝(1894―1964)は、熊本女学校を経て、1918年に四国遍路のルポルタージュ「娘巡礼記」を『九州日日新聞』に連載した。1920年に上京して女流詩人として認められた後、アナキストの論客としても活躍した。1930年代以降は世田谷の「森の家」で女性史研究に専念した。
福岡県門司市生まれとされる林芙美子(1903―1951)は、幼い頃は行商人だった両親と共に筑豊や北九州を転々とした。尾道市立高等女学校卒業後、明治大学に入学した婚約者を追って上京し、婚約解消後も東京に留まり作家を志した。やがて『女人芸術』に掲載された「放浪記」が世に認められて、有名作家の道を歩んだ。
これらの女性たちが東京で得たものは、因習的な価値規範や人間関係からの自由に加えて、高い教育と先進的な文化にアクセスする機会、切磋琢磨する仲間、引き立ててくれる年長者、刺激的な活動の場などであった。彼女たちは上京したからこそ才能を開花させることができた。
これらのことを念頭に置くならば、本書で取り上げられる中村きい子(1928―1996)、石牟礼道子(1927―2018)、森崎和江(1927―2022)という優れた三人の女性作家が、いずれも九州で作家活動を始め、活動の拠点を九州の外に移すことなく後世に残る作品を執筆し、九州で生を終えたことは驚くべきことであるように思える。
第1章「はじまりとしての『サークル村』」に詳しく書かれているように、三人の女性作家は、九州・山口のサークル間の交流を目的として創刊された月刊誌『サークル村』(第1期は1958年から60年まで、第2期は1960年から61年まで)の運動を通じて表現活動を本格的に開始した。著者は、彼女らが九州の「南」の視点に立つことで『サークル村』の男性運動家による九州像に批判的に介入したこと、また『サークル村』の男性中心主義を「否定的媒介」としつつ、性役割と性愛、ジェンダーとセクシュアリティの問題を浮上させたことを主張している。評者はこの主張に全面的に賛成するものの、その前提として、サークル運動が、そうした介入を可能にする場であり得た事情について確認しておきたい。