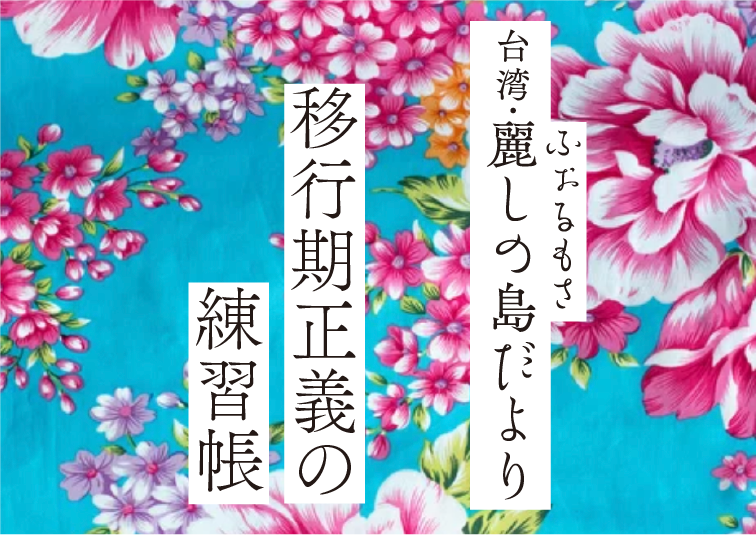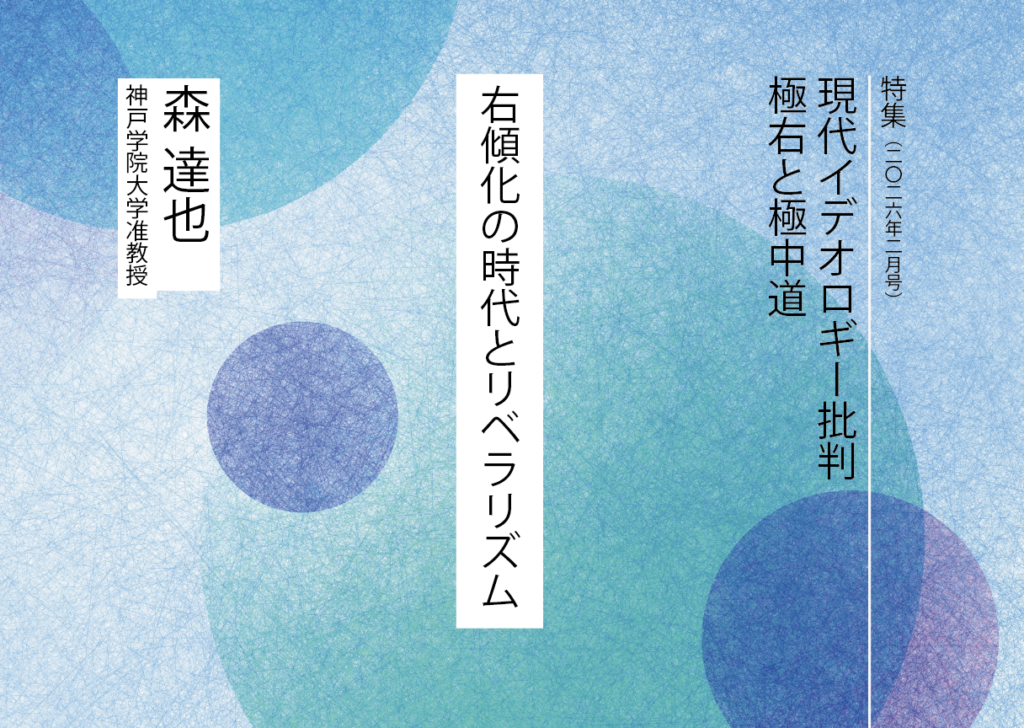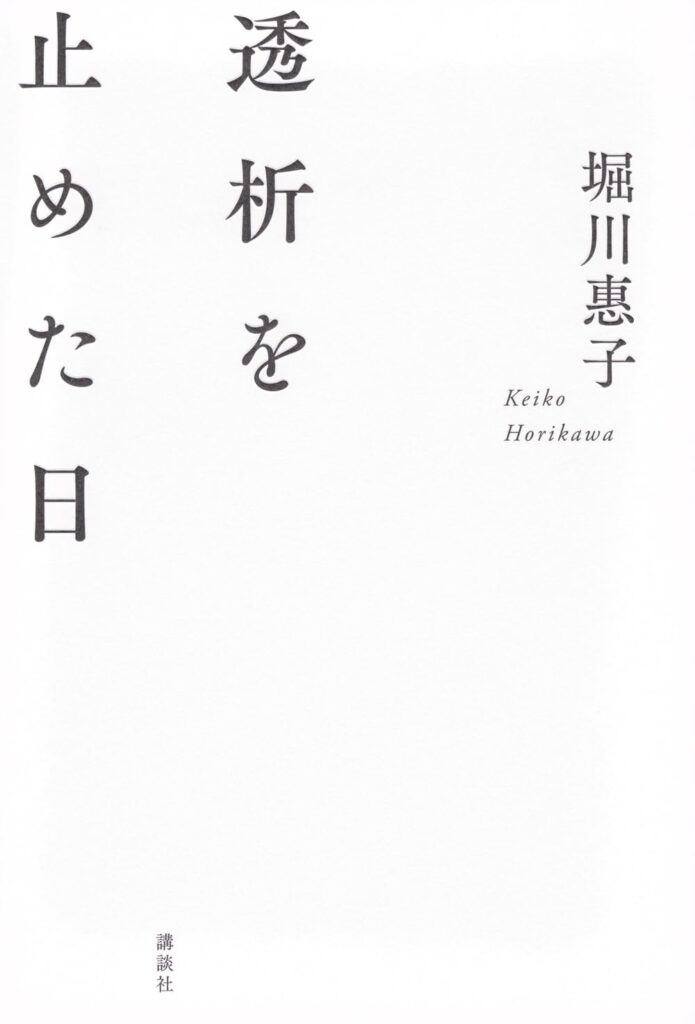この秋、オーサーズツアーでイギリス6都市を回ったのだが、驚いたことがある。10年前に弾丸で旅した時よりも、国全体がヘルシー志向になっていた。どんなパブやレストランにもヴィーガンメニューがあり、ホテルの食事も野菜や果物がたっぷり、サーブされる量も欧米としては、多くなかったように思う。2000年代にアイドル的人気を博していた料理研究家ジェイミー・オリバーは、コッテリわんぱくな料理を作るせいで人気が下火になっていて、代わりにいま熱い視線を浴びているのが、旬の素材がふんだんな繊細なレシピ、ライフスタイルもおしゃれなナイジェル・スレーターやナディヤ・フセインらしい。私が期待していた茶色い肉のパイやゲンコツみたいな焼き菓子、脂っこい揚げ物は、地方都市でやっと少し見かける程度で、それだって「昔懐かしい」の文脈で売られていた。
ちなみに拙著『BUTTER』は、日本人女性に課されたプレッシャーを描いた作品で、私からすると男女平等が達成されたように見えるイギリスでこの本が売れているというのは首をかしげたくなる事態だったのだが、多くの女性の読者さんがルッキズムや会社での昇進に悩んでいたことは、意外だった。街を歩いていても美容に関する広告が少なくていいなと思っていたけど、イギリスでも「痩せなきゃ」の苦悩は年々高まっているのだそうだ。ヘルシー志向の弊害もあるのだ。
ちなみにオーソドックスなイングリッシュ・ブレックファストを食べたい、と現地を案内してくれた関係者の方にお願いしてみたら、「え、あんなに身体に悪いものを食べたいんですか?」と、顔をしかめられた。講演会で知り合った大学生のみなさんも「イングリッシュ・ブレックファストを食べるのは二日酔いの時だけ。二日酔いの後ならあのギトギトも美味しく感じる」と、背脂ラーメンみたいな扱いをしていた。トマトやマッシュルーム、煮た豆なんかが並んだ一皿が、そんなに身体に悪いとは言えないと思うのだが――。
それでもなんとか無理を言ってパブでイングリッシュ・ブレックファストにありついたのだが、直前でスリにあってしまい、そのせいで、じっくり味わって食べることができなかった。
今回の旅はスケジュールがきつく、ほぼ遊びの時間がなかったし、前回の旅行もほんのわずかな滞在だった。だから、私が食べることが叶った伝統料理は、実はさほど多くない。でも、「イギリスって、ごはん美味しくないじゃん?」と言われるたびに、身内の悪口を言われたように反発が募るのは、私が活字からイギリスに入ったせいもある。小説の中で出てくるギトギトしたパイやお米のプディング、バタつきパン……。単なる美味しそうとは、またちょっと違う、独特のときめきを宿している。思い描いてきた憧れと文化をついに咀嚼(そしゃく)する感覚があるので、仮に口に合わなかったとしても、それはそれで別にいいし、シンプルな美味しさとはまた違う味わいがあるはずなのだ。
そんな私にとって、12のレシピに加え文学や映画の引用がふんだんな、食の考察からなる本書は、書き出しからして、うなずきっぱなしである。
「『イギリス料理は不味い』などと平気で口にするような御仁には、自らが惰性的に慣れ親しんでいる味覚の範囲内でしか『美味しさ』を味わえない感性の欠如と、美味しいものの情報を探索することのできない知性の退化をさらけ出してしまっているということにもっと自覚的になってもらいたい。われらコモナーズ・キッチンは、何かが『美味い』とか『不味い』とか、そんなことを自明視しない」(11頁)
われわれの大半にとっては未知の味を興味深く解説しながらも、その多くは階級や搾取の歴史と切っても切れない関係にあるという暗部も、本書は詳(つまび)らかにしていく。とりわけ、「マーマレード」の章で、エリザベス女王の在位70周年の記念動画に「クマのパディントン」が出演して大評判だった時、女王とクマが手にしていたママレードのサンドイッチに着目し、植民地からの搾取の歴史とそれに反省のない王室への批判、さらに現在進行形のパレスチナの苦難まで紐づけていったのは、見事であった。このフェアさが好きだ。さらに、どのレシピも手が込んでいて、いい意味で面倒臭いところも惹かれる。生きたウナギでゼリーを作るために仮死状態にするべく氷水につける工程なんて、初めて読んだ。全くサクサクしていないポークパイのパイ生地もいつかチャレンジしてみたいと思う。
あとがきにも書いてあることだが、レシピとは「理解のため」にある。知らない国の知らない料理を作るうちに、その地で起きた戦争にまで思いが及ぶし、レシピを作り上げた人の人格まで想像がつくようになる。私もいろんなレシピにチャレンジしてきたが、振り返ってみると、確かに「食べたい」よりも「知りたい」の動機が強かったように思う。この本を読むと、イギリスのフィクションで得てきたときめきと、そのときめきでコーティングされた負の歴史の苦味、両方が身体の中に入ってくる感覚がある。
本書を読んでさっそく「イングリッシュ・ブレックファスト」を付け合わせの「ベイクドビーンズ」から、手作りしてみた(写真参照)。
白インゲン豆を一晩かけて水で戻し、野菜のブイヨンをくず野菜でとる。じっくり焼いたベーコンをブイヨンで煮る。思ったよりずっと丁寧な調理法だ。煮汁に砂糖を入れるところでは、日本みたいだ、と嬉しい発見があった。切れ目を入れたソーセージ(イングリッシュソーセージとはいかず、伊藤ハムのフランクフルトだが)とベーコンを焼き、その脂で、トマトとマッシュルームを焼く。目玉焼きに薄切りトーストを添えたら、憧れの一皿の完成だ。「ほら、やっぱり、そんなに不健康じゃないよね」と家族の前で得意満面で平らげたが、食べ終わった今、食材の組み合わせなのか豆のせいなのか、満腹でだるくて、泳いだあとのように眠くて仕方がない。ヘルシー扱いしていたが、トマトとマッシュルームが存分に脂を吸っているせいもあるかもしれない。
味わいは楽しんだが、イングリッシュ・ブレックファストの背脂ラーメン扱いも、ちょっぴり共感できるようになったのである。
〈今回紹介した本はこちら〉
『舌の上の階級闘争――「イギリス」を料理する』
コモナーズ・キッチン著、2024年10月、リトルモア、定価1980円(税込)