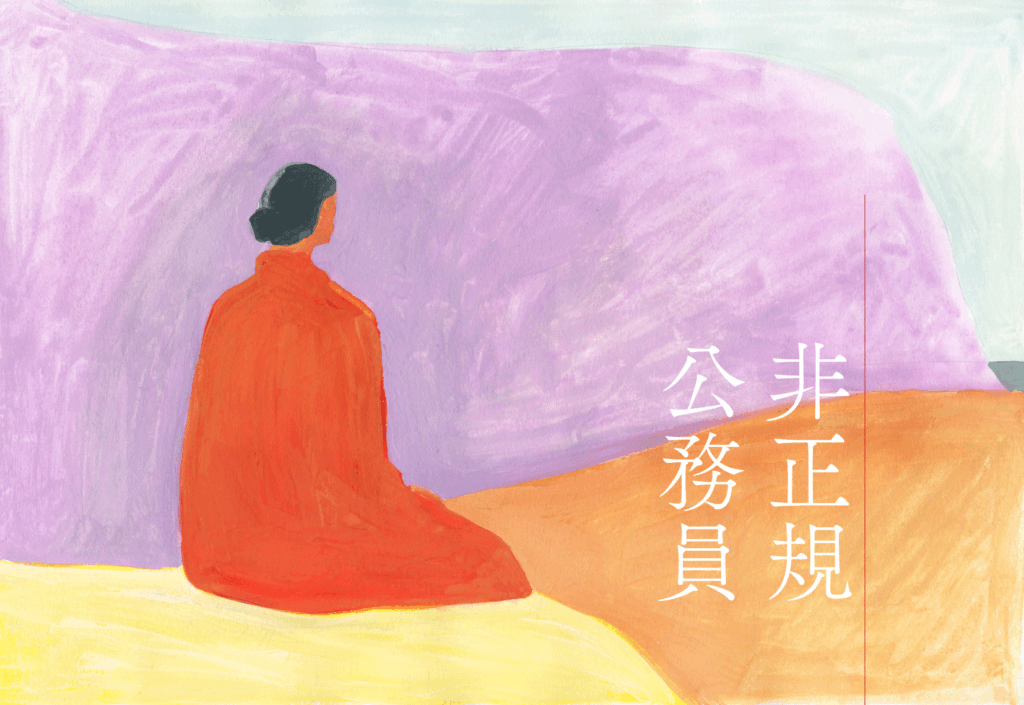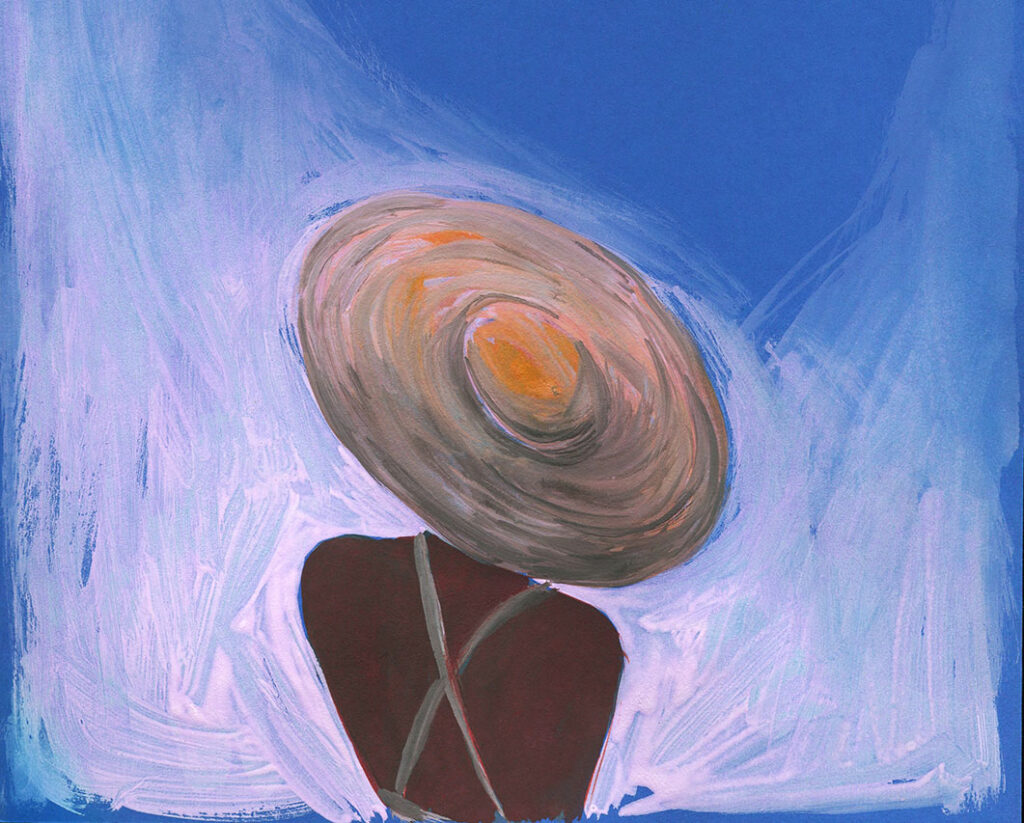異例の税制改正プロセス
自民公明両党と国民民主党の幹事長が2024年12月11日に会談し、いわゆる「年収103万円の壁」を、178万円を目指して来年度から引き上げ、ガソリン税の暫定税率を廃止することで合意した。国民民主党は、2024年度の補正予算案に賛成する意向を示し、予算案は衆議院で賛成多数で可決された。
もっとも本稿の執筆時点では、(1)178万円を目指して来年度はどれだけ引き上げるのか、(2)ガソリン税の暫定税率廃止はいつからなのか、(3)非課税枠引き上げと暫定税率廃止にともなって生じる8~9兆円の減収分をどう穴埋めするのか、については決定が先送りされている。
例年通りならば、税制改正は与党税制調査会で議論され、決定された内容がそのまま「与党税制改正大綱」に反映され、政府の税制改正方針となる。ところが今回は、国民民主党と協議していた宮沢洋一税制調査会会長の頭越しに前記方針が合意され、宮沢氏が「釈然としない」と発言するなど、異例の展開をたどった。
こうした展開になったのは先の衆院選の結果、自公両党が少数与党に転落し、国民民主党の賛成を得なければ予算案が可決.成立しない状況に陥ったためである。与党は、巨額の税収を失うことになる178万円への引き上げは回避したかった。また、暫定税率の廃止は先延ばしして、自動車関係諸税の見直しとセットで2025年末に議論する意向だった。
本件はキャスティングボードを握る野党が、与党と連立を組まずに予算を人質にとって交渉することが、いかに強力な武器になりうるかを白日の下にさらした。今回、あいまいに決着した「178万円を目指して」の部分や、暫定税率の廃止時期についても、国民民主党が本予算を人質にとって2025年度からの完全実施を求めてきた場合、与党が拒否する選択肢はなくなるだろう。
こうした事態を避けたい自民党は当然、選択肢を広げようとする。自民党は同じ12月11日に、能登半島の被災地復興関連予算を1000億円増額する修正案を提出した。これはまさに、立憲民主党が求めていたものだ。立民は補正予算案本体には反対したものの、復興予算の修正案に限って賛成し、同案は衆院を通過した。また自公両党は同日、日本維新の会と三党で教育無償化を議論する協議体の設置で合意した。これを理由に、維新は補正予算に賛成した。
これら一連の動きは萌芽的だが、国民民主党との合意が困難になった場合、立憲民主党、あるいは維新との交渉で本予算を成立させるための環境整備だとみることもできる。
「103万円の壁」問題とは何か
「手取りを増やす」。国民民主党は先の衆院選で、多くの有権者を引き付けるキャッチフレーズを掲げて躍進を遂げた。選挙後、同党がもっとも力を入れてきたのが、「103万円の壁」を178万円に引き上げることだ。
「103万円の壁」とは何か。国税の所得税と地方税の住民税の課税所得を計算するには、給与所得から所得控除を差し引く。所得控除には社会保険料控除や生命保険料控除など、さまざまな種類がある。そのなかでも、基礎控除48万円と給与所得控除(最低額)55万円の合計額103万円は、給与所得者全員に適用される。つまり、年間所得が103万円未満の給与所得者の場合、課税所得がゼロになるので所得税負担は発生しない。103万円を超えると(103万円を超過した所得部分に限ってだが)所得税がかかることになるので、それを回避したいという納税者心理が働く。そのため、給与所得が103万円を超えないよう働き控えを行なう人々が出てくる。これが、「103万円の壁」問題である。
実際、そのような人々がかなりの数にのぼることが、東京大学の近藤絢子教授の調査結果で明らかにされている。有配偶者女性(25~60歳)の給与収入分布をみると、96万円の突出を除くと103万円がピークとなっている。それよりも頂点は低いが、130万円で再び別のピークを形成していることが定量的に明らかにされた。やはり103万円、130万円で就業調整が行なわれているのだ。