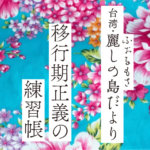雑誌の「雑」は、「純」と対をなして、「まじる、まじわる、あつまる、ともに、みな」といった意味を持っている。「誌」は書き記すといった意味なので、「雑誌」ということばは「様々なものを書き残したもの」といったあたりになる。そこには、交わること自体に意味を持つ、いわば「共通の場」(フォーラム)という面と、同じ目的をもって「集まる」同志的な(ということは、志が異なる人を寄せつけない)面とが緊張感を持ちつつ同居しているとも言える。
現在、政府の設定した課題に対し、その前提を批判的に検討せず、最初から同じ土俵に乗って議論をしようとする「対案主義」や、そもそも政府の主張を垂れ流すような言論が支配的になっている。本稿では、敗戦前までの日本において、その時代状況の中で可能な限り批判的であろうとしたいくつかの雑誌のあり方を検討することで、今日の「あるべき言論」を考えるためのヒントを探ってみたい。
『青鞜』の衝撃
日本初の女性弁護士となった三淵嘉子をモデルとしたNHKの朝ドラ『寅と翼』が話題となっている。大日本帝国憲法下で、女性は参政権がないことをはじめ公的領域での権限を担えず、民法上も家長の下に服従し法律上「無能力」とされ、家庭という私的領域においても低い地位におかれた。そして「天下国家を動かすのは男」「女性は家庭を守る」といった通俗的な価値観がその制度を支えた。
大逆事件(1910年)の翌年9月、日本ではじめて女性のみによって作られた文芸誌『青鞜』が世に出された(1916年廃刊)。発起人は平塚明(らいてう)、保持研子、中野初子、物集和子、木内錠子の5名。第2号の巻末に掲載された青鞜社概則(社則)の第一条には、「本社は女流文学の発達を計り各自天賦の特性を発揮せしめ他日女流の天才を生まむ事を目的とす」とある。第六条には、雑誌の発刊のほかに研究会や大会の開催、旅行の実施が書かれている。単に発表の場としてだけでなく、交流し、学びあい成長する機会を作ることを目指す同志的結社と言えよう。
文芸誌でありつつも、当初から評論・批評も積極的に掲載した。後世から見た時、『青鞜』は「女流文芸誌」と「女性解放運動の機関誌」の両面を持つ雑誌となった。らいてうを研究してきた米田佐代子は、らいてうに発刊を勧めた作家の生田長江に言及しつつ、「大逆事件」の死刑執行(1911年1月)から間もない「『冬の時代』に政治を語ることの危険性は誰の目にも明らかである。『政治的ではない』文学の世界で、しかも『女流』に限定することで『危険』を回避できるという判断が長江に働いたとしても不思議はないだろう」註1と書いている。
『青鞜』以前から、女性が雑誌に書き手として小説や論考を発表する機会自体は存在していた。しかしそこでは、男性の作る雑誌や新聞の家父長制的な秩序内で許容できる範囲の表現しかできない。その世の中に一石を投じるには、まさに「同志」が集まって女性のみで雑誌を刊行し、既存の雑誌とは異なる言論を提示する必要があった。