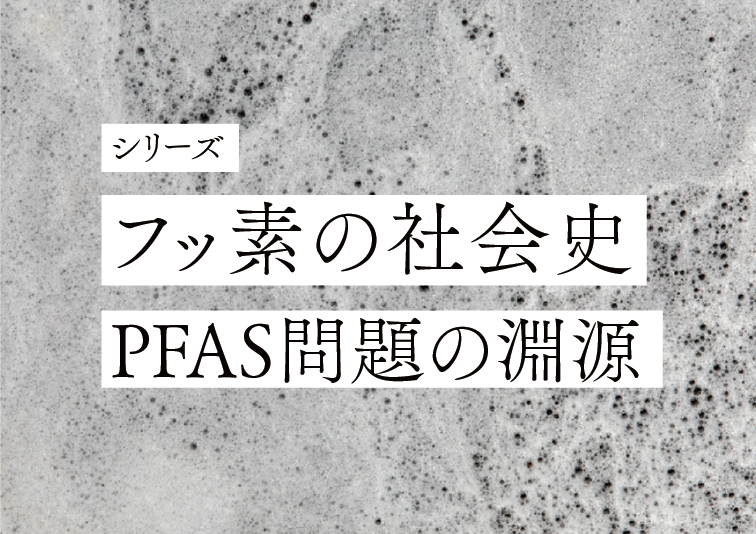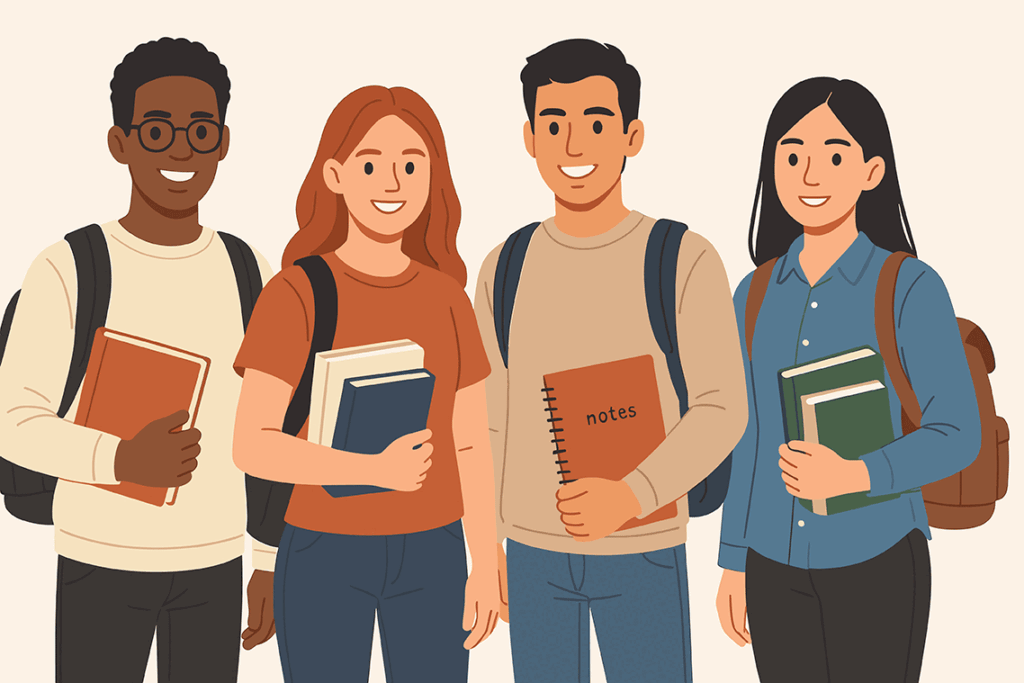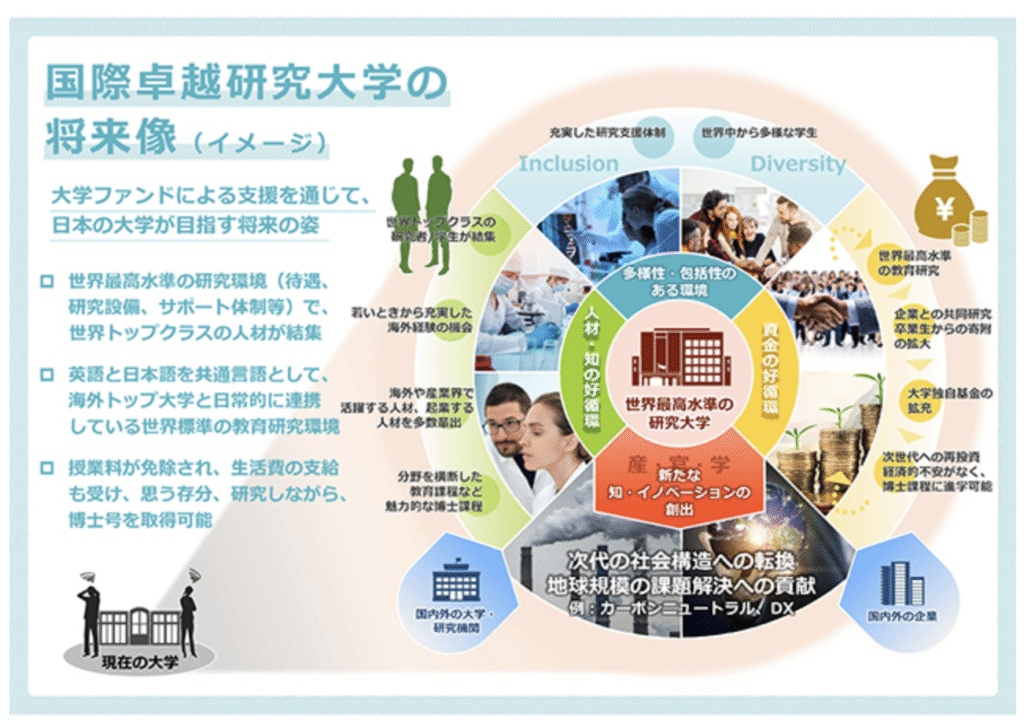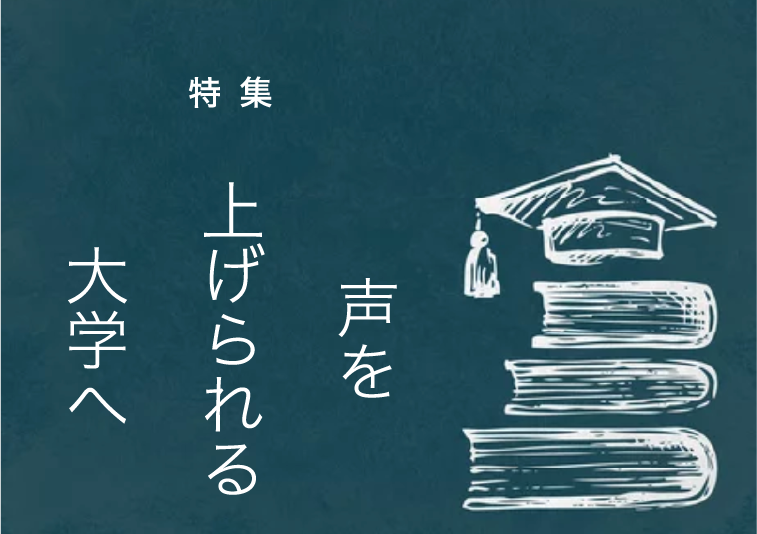2022年2月のロシアによるウクライナ侵略が契機となって、日本では「軍事的抑止力論」が急速に強まった。敵国からの侵略の意図を、軍事力を増強することによって抑止して国を守るとの論で、多くの国民の支持を得ている。それに勢いを得て岸田首相は、同年12月に安保関連三文書を閣議決定し、軍拡路線がすっかり定着してしまった。5年先には軍事予算をGDPの2%(1年で約10兆円)を目標に、5年間の軍事費を43兆円とする計画が着々と進んでいる。その結果として、防衛省はあれもこれもと装備品を買い漁るとともに、アメリカから提示される数年先までの武器を言い値で買い込んでいる。
私はこの状態を「軍拡バブル」と言っている。防衛省は政府の軍事予算の大盤振る舞いで、出費は気にせず、買い込んだ兵器が使いこなせるかも頓着せず、内外の軍需産業のお勧め品を多量に買い付けているからだ。「敵基地攻撃能力」を獲得するということは、敵側からも同様の攻撃を受けることを想定しなければならないから、攻撃用ミサイルを装備すれば、同時に迎撃用ミサイルをもセットとして購入するという次第である。だから、どんどん重装備になっていくのだが、もうこれで十分という限界はなく、軍事力を増強すればするほど、より強力な装備が必要、という蟻地獄に落ち込んでいく。こうして「バブル」はどんどん膨らみ続けるのだが、それが弾けるのは敗戦を喫するときあろう。「新しい戦前」といわれているが、まさしく日本は来るべき大敗北を迎える戦争前夜にあると言えよう。
この「軍拡バブル」に乗じて、防衛省は2023年6月に、安保三文書で示された防衛技術基盤の強化にかかわる方針を具体化して「防衛技術指針2023」としてまとめている。そのキャッチフレーズは「将来にわたり、技術で我が国を守り抜く」というもので、軍事技術の開発の強化を目指したものだ。二つの柱として、①将来の戦い方に直結する機能・装備を迅速に創製し、5年又は10年以内の早期の装備化と、②10年以上先を見通して、官民連携の下で技術的優越を確保し、他国に先駆け先進的な能力を実現、と掲げている。短期目標と長期目標というわけだが、それに応じて、防衛装備庁は「技術的優越」を実現するために、新機軸の武器を調達しようと躍起である。
本稿では、「軍拡バブル」に便乗して進められようとしている軍事研究への、主として大学の研究者動員の状況について報告する。現時点では、歴史的経緯もあって、まだ軍事研究への組織的な大動員が行なわれているわけではない。しかし、文科省は国立大学の自治権を剥奪し、予算の厳しい締め付けを通して政府に抵抗しない大学とする方策を講じている。他方、教員の多くは研究費不足に悩み、研究資金が出る(軍事的、経済的)「安全保障」という名の付く募集に靡いていきかねない状況にある。軍事研究への協力が当然という雰囲気が強まり、学問の軍事化が急速に進展する恐れがあるのだ。そうなってしまうともはや引き返すことができず、大学は死屍累々の状態になるであろう。