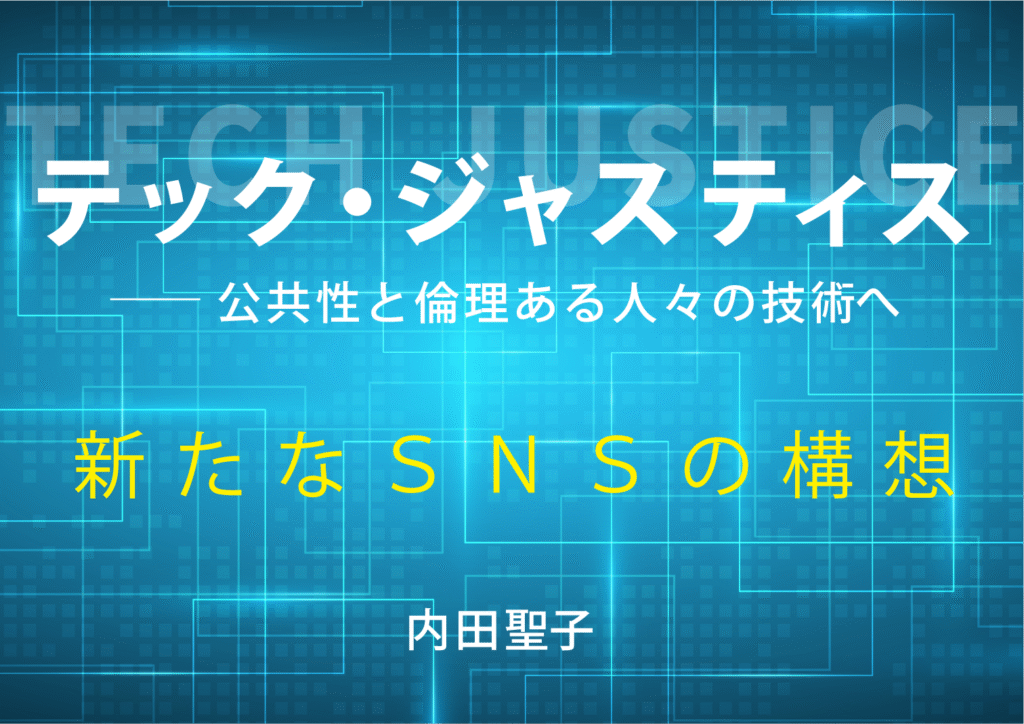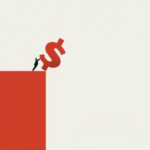昨年7月の東京都知事選挙、現職・小池百合子氏の三選の一方で、石丸伸二氏が2位、蓮舫氏が3位という結果が大きな波紋を呼んだ。
とりわけ注目されたのは、世代別の投票傾向である。10~20代では石丸氏が40%超の支持を集め、小池氏の得票を大きく上回った。30代では石丸氏と小池氏が拮抗し、40代でも石丸氏は小池氏に迫る勢いを見せた。50代以上になると小池氏の支持が優位となり、特に70代以上では小池氏50%、蓮舫氏30%と、若年層との違いが顕著だった。
今後、現在の高齢者層の投票数は減っていかざるをえない。これは、戦後日本の政治に存在しつづけた「平和・平等・人権」といった理念が、次の時代に継承されるとは限らない現実を示す。蓮舫氏の支持層が今後ますます縮小していく予兆に、不安を感じる人もいたのではないだろうか。
都知事選の結果だけでなく、近年、若年層がいわゆる「ネオリベ的」な候補者や政党に支持を寄せる現象が散見される。たとえば、昨年の衆議院選挙において国民民主党が若者からの一定の支持を集めたことは、その一例としてしばしば取り上げられている。このような支持の背景を、メディアリテラシーの有無やSNS戦略の巧拙といった点に求めようとする言説が数多く提示されてきた。
たしかに、現代の若年層には独特のメディア消費傾向や価値志向が認められる。たとえば、映像作品を倍速で視聴することや、ネタバレを回避できないまま映画館に赴くことへのためらい、いわゆる「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する姿勢、あるいは失敗を極度に恐れる傾向などは、世代的な特性として看取される。加えて、SNSを通じて常に他者と接続される環境において、現実と仮想の境界が曖昧化し、「叩かれたくない」との恐れから、無関心を装うという振る舞いも見られる。さらに、自己責任を問う言説の流布もあいまって、「自分のことは自分でなんとかするしかない」との意識を強く抱く若者にとって、平等や包摂を謳うリベラルの言説は、現実離れした「きれいごと」として映りがちという指摘もあるだろう。
しかしながら、私はこうした現象を若者の気質や性向に還元しようとする見方に、一定の懐疑を抱いている。問題の本質は、単なる「伝え方」や「戦略」の巧拙にあるのではない。むしろそこには、より深層的な社会構造の歪みが横たわっていると考えるべきではないだろうか。
現在、新自由主義的な言説をまとった政党や候補者が若年層の共感を得る一方で、マイノリティに対する差別や排外主義が不満の受け皿として煽られ、支持を集める状況が続いている。また、「若者・現役世代」対「高齢者世代」という単純な対立構造が社会に広がるなかで、リベラルが長らく掲げてきた理念や語彙は、かつての説得力を失いつつあるように見える。
このような状況下において、私たちはいかなる言葉を紡ぎうるのか。誰に、何を、どのように語るべきか。今、問い直されるべきは、単にリベラルの「メッセージの発信力」ではなく、その言葉が根差す現実認識の土台そのものである。本稿では、こうした問題意識のもと、筆者が目にしてきた風景を手がかりに、届かぬ言葉の所在をともに考えるための素材を提示したい。