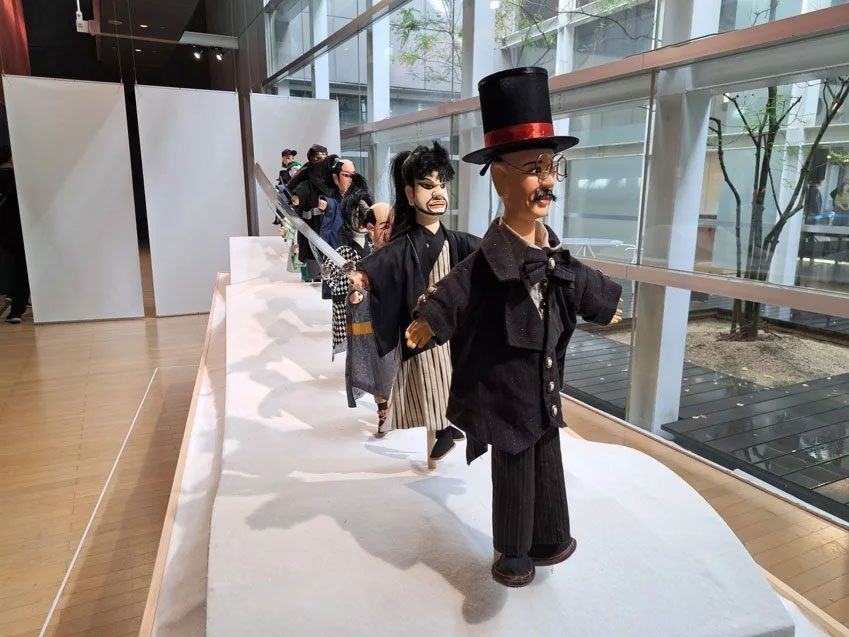――われわれは生まれながらの善良な公民でもなければ、高貴な王者の一族でもない。窮地に迫られて、美徳と技術を学んだ。窮地に追い込まれたことは、われわれをして世界に立ち向かわせた――呉叡人『台湾、あるいは孤立無援の島の思想』(駒込武 訳)
* * *
花蓮の震災と台湾のアップデート社会
2024年4月3日の朝、台湾東部にて花蓮沖を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生した。台湾各地の復旧は早く、現在では花蓮のごく一部を除いてまったく通常運転で世界中の観光客を受け入れている。震源に近い花蓮では、特に被害の大きかった国家自然公園の太魯閣(クロコ)渓谷エリアについて無期限閉鎖が発表された。日本統治期より台湾のメイン観光資源のひとつで、ここに頼って商売をしている地元の方も多いため残念ではあるけれど、毎年のように落石で命を落とす観光客があとを絶たないリスクの高い観光地でもあった。大自然の神々への畏敬や神聖さをも感じられる土地だが、地球内部のダイナミクスがあがり世界各国で自然災害が巻き起こる近年、今しばらくは神々に返すということなのかもしれない。花蓮にはほかにも素晴らしい場所が多くあり、そうした地域の整備や認知度を上げていく良い機会ともいえる。
今回の花蓮の震災について日本の報道では特に避難所の様子に注目が集まっていたが、台湾に長く暮らす立場から少し掘り下げて考えてみたい。まず、このたび被災地となった花蓮を拠点とする「慈濟(ツージー)」のほか、東日本大震災発生時にいち早く大量の避難用テントを日本に送った「佛光山(フォーグワン)」など、台湾では、新宗教系の仏教団体を母体とした民間の慈善組織が災害時に活躍をみせるのが常だ。こうした団体は中国にも支部を持つため、中台問題にまつわる距離感が取り沙汰されることもあるが、基本的には義損金をはじめテントの提供から炊き出しまで長年の経験と機動力を活かし、裕福な台湾人の現世利益的な功徳観とうまく連動もして、政府が目配りできない部分をカバーする。葬式があればボランティアで読経をして回るなど、社会貢献度とその存在感は日本における新宗教/新興宗教団体への印象と異なり、台湾の人々の信頼を得て暮らしに密着している。そんなわけで、行政が非常時において担う役割は台湾と日本でかなり違うため、単純に「台湾政府・行政はスゴイ!」とは思わない。しかし、行政というよりも「台湾社会」の凄みを感じたことがある。それは、前回の花蓮地震(2018)の際の避難所は日本と同じような雑魚寝状態だったのに、今回の避難所では当時の反省をさまざまな形で生かして快適な避難所が実現されたことだ。