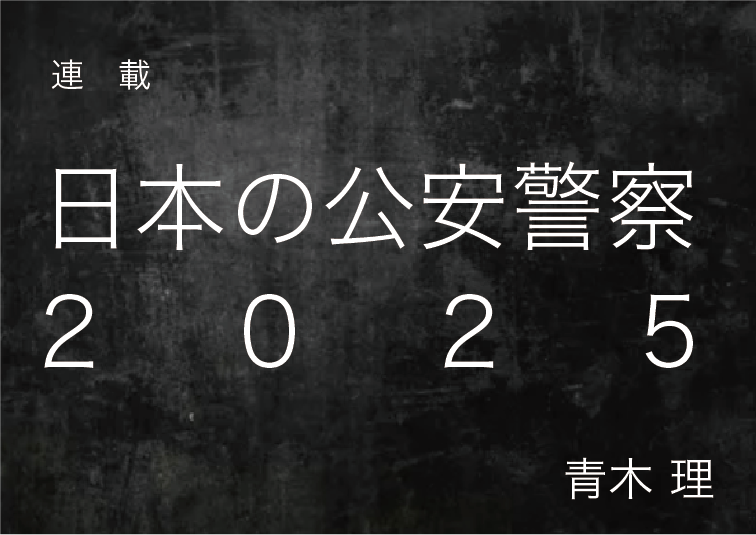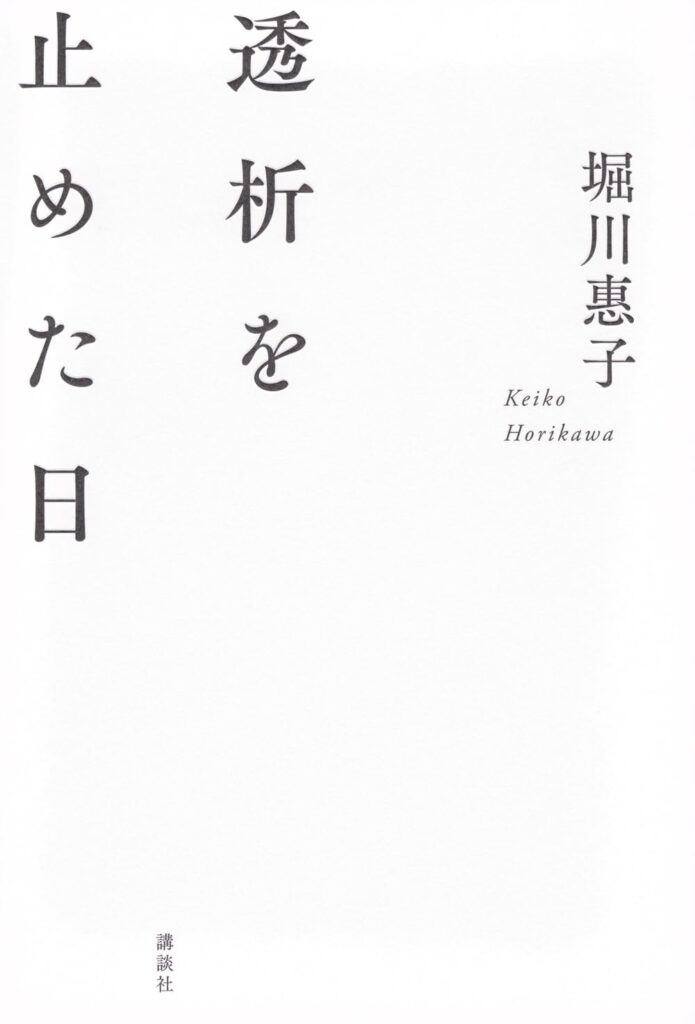【これまでの記事】
実力行使の民主主義――高知パルプ生コン事件(1)
実力行使の民主主義――高知パルプ生コン事件(2)
貴重な証言者との出会い
1971年6月9日早朝、高知市江ノ口川に廃液を流していた高知パルプ工業の排水管に、市民ら4人が生コンと土嚢を投入した事件が「高知パルプ生コン事件」。工場は操業を停止し、翌年閉鎖された。
この事件には、実行者である山崎圭次たちに「廃液による被害者である地域住民」が立ち会うことが必要だとして現場に来ることを依頼された女性が2人いる。そのうちの一人、江ノ口川の川沿い、廿代橋の北東、「橋のもと」に位置した佐渡旅館の女将であった秋山武子さんへのインタビューを実施することができた。
最初にお会いしたのは2024年末。旅館はすでに閉め、娘さんがカフェ・レストランを経営し、お孫さんが給仕として働くそのお店で話を聞いたが、90代とは思えない矍鑠(かくしゃく)とした御様子で、口跡も鮮やかな若々しい方であった。
NHKのドキュメンタリー『明日への記録 廃液』では、川の汚染の被害者としてインタビューを受けている40歳過ぎ頃の秋山さんの姿を見ることができるが、事件に「立ち会った」事実は知られていなかった。裁判になる可能性のある案件であり、彼女が当時者として巻き込まれることを避け、関係を意図的に隠したと考えられる。だから秋山さんが「事件に立ち会った人」として取材されるのは、事件後53年を経て、私が初めてということだった。事件関係者でも立会人の存在を知らなかった人が多い。彼女の同年代の夫は、妻が事件に立ち会ったことを知らないまま亡くなったという。
彼女の話じたいは、裁判記録にも残る「地域の被害者」としての証言と重なる内容も多かった。硫化水素を垂れ流された川は「泡がボコボコ」「臭くってそれが一番困った」という。宿泊客の苦情は多く、団体客が夕食後、においが耐えられないから旅館を変わると引き揚げた事件など、川の汚染を理由にしたキャンセルもダメージだった。そして、彼女が気に入っていた真面目な女中さんが川のにおいと頭痛に耐えかねて辞めたことがショックだった。事件後、公害がなくなってからその女中さんに「帰ってきてくれんかね」と言ったが、すでに結婚して戻れなくなっていた。彼女の目線はパルプ工場の人たちにも向けられ「気の毒やなあ、紙工場の人たちもかわいそう。仕事やめなあかん」と言った。もっともその後に「今やったらそんなふうに思いません」と付け加えることも忘れなかった。
秋山さんが子どもに買い与えたキューピー人形も硫化水素の影響で真っ黒になった。ポケットに入れた10円玉も色が変わった。冷蔵庫もすぐ壊れ「しょっちゅう買わないといけなかった」というから、江ノ口川近隣の被害の苛烈さは深刻なものであったとわかる。「川のあの茶色い臭いのをなんとかしたかった」という思いは誰もが持っていた。
秋山さんは、生コンを入れる計画があることは人づてに知っていた。「山崎さんにはそうしょちゅう会いませんでしたが、尊敬しとったから。物腰は柔らかかった。その優しい方がそんなすごいことを」と思ったという。
生コンを入れる姿は「おぼろに憶えている」という。「必死な顔しとったから声もかけず見ていた。みんな真っ赤な顔で、緊張していた。顔の色が変わった」という。冷静で計画的な作戦遂行ではあったが、当人たちの緊迫を伝える証言は貴重である。
彼女は身辺の出来事を日記に書き留めていた。60冊ほどになるという。この事件のことも記しているはずだった。それを全部処分してしまったというのは残念だった。「浦戸湾を守る会」のアクティヴなメンバーではなかったが、会合に出席することもあった。会は組織だった色は持たず、平等で束縛のないものだった。山崎会長の性格を反映していたのだろう。「昔は川で泳げたのに」とか、暮らしの中の声を皆が共有していた。多いときは30人が集まった。会が終わったら必ず唱歌「ふるさと」を歌ったという。