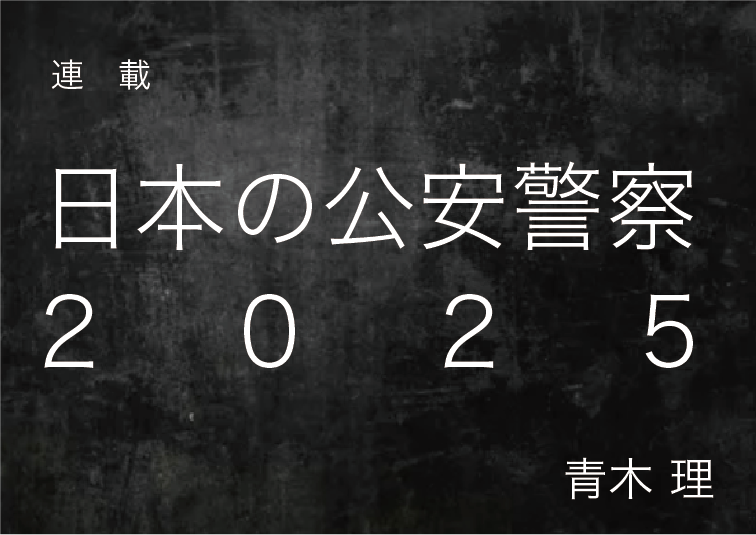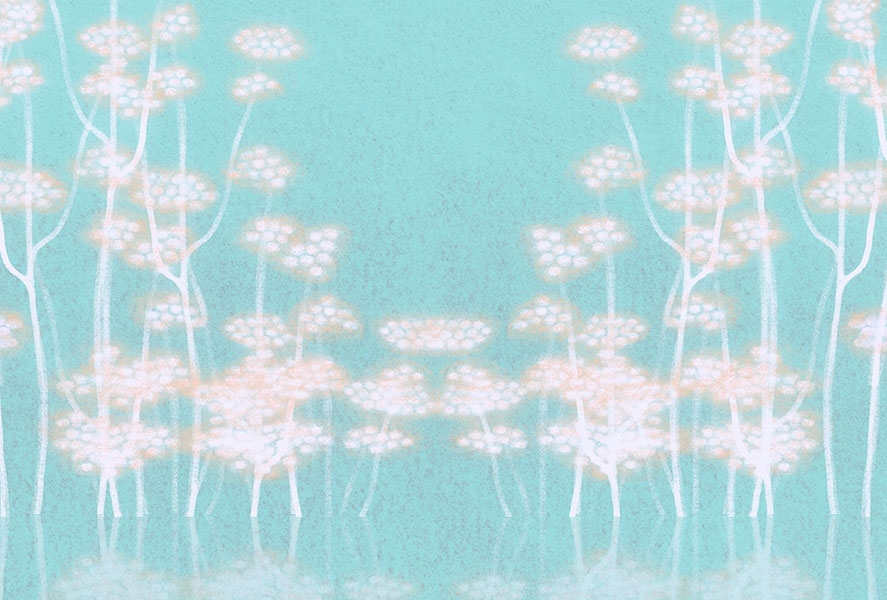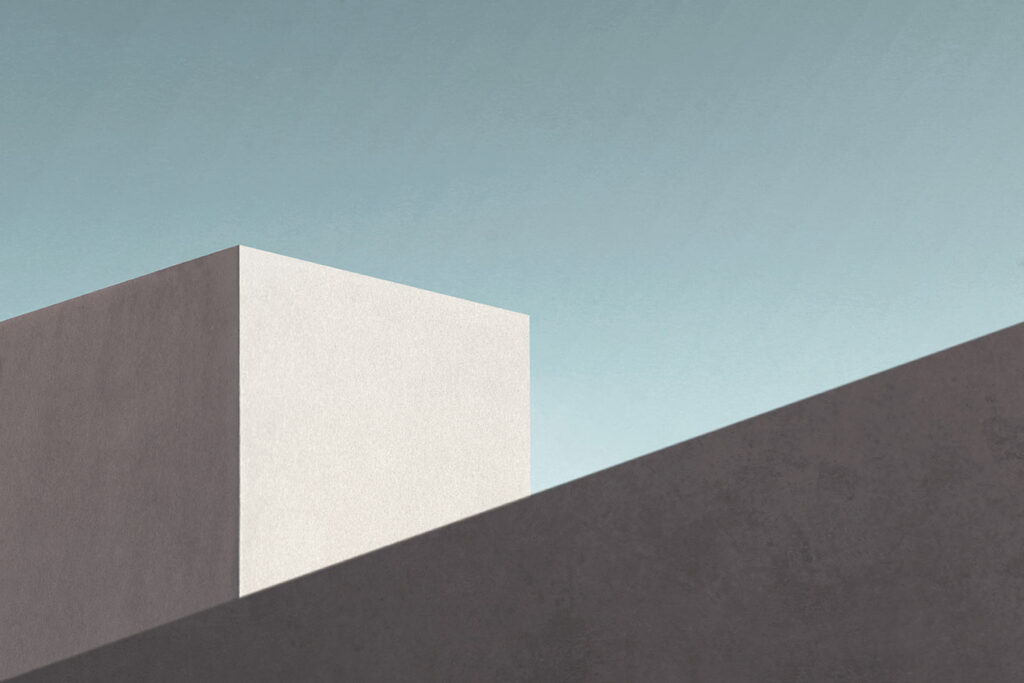契機
1971年6月9日、廃液を垂れ流していたパルプ工場の排水管に4名の高知市民が生コンクリートを投入し、操業を中止させた「高知パルプ生コン事件」。私はこれを、「直接行動による民主主義」の実践だと考えている。
その行動の決定的な契機となったのは、「浦戸湾を守る会」との交渉を一方的に拒否するという、「高知パルプ」側の通告である。県の公害課長が発言した「国が1972年に決めようとしている工場排出基準は600ppmになりそうですよ」という発言。水質排出基準のBOD(生物化学的酸素要求量)をめぐり、その時の高知パルプの廃液の数値がおよそ800から1000ppm。改訂前の150ppmだとその差は誤魔化しようがないが、基準が600ppmとなれば、少しの努力と「誤差」の考え方で、なんとかごまかせるという胸算用だったのだ。
もちろん「浦戸湾を守る会」の坂本九郎事務局長は「県独自の基準で150ppmに戻せませんか」と迫ったが、県が国の方針に逆らえるはずもない。では法に訴えるとしても、当時の民事訴訟では廃液の排出差し止めの展望がなく、行政も十分な対応をとらないことは自明だった。万策尽き、やむを得ず実力行使におよんだという側面がある。
私がインタビュー取材することができた「実行犯」の1人である吉村弘氏の話では、この事件への参加について、彼の勤務先に山崎圭次会長から電話があったという。直々に電話をくれるのは初めてだった。「遊びに来るかい?」とオープンな物言いだったが、吉村はすぐに「大事な話だ」と感じたという。
当時23歳の吉村は、高知市弘化台の会社で働いていた。浦戸湾は目の前。異様なにおいが鼻をつき、おかしな形のボラを目にしていた。市場では、浦戸湾で揚がったというだけで、どんな魚にも値がつかなくなっていたという。
彼は常連の喫茶店で山崎会長らの存在を知った。「地球の将来が心配や」と真顔で言う人に初めて会った、という。さらに「大丈夫やろか」「大丈夫やろか」と繰り返し言う。冗談でも何でもなく、本気で心配している。吉村も恐ろしくなったという。
呼び出された吉村は、彼が「完璧なコンビ」と呼ぶ山崎・坂本両氏と、3人で会った。2人は「当然のこと」「やる」という態度。もちろん「排水管封鎖」のことである。どのくらいインパクトがあるのかはわからない。工場で働く人にも生活があるから、自分たちのやることは決して正義の味方ではない、という自覚を共有し、リスクは承知だったという。吉村は実行メンバーに加わることを約束。実家の親のことが一瞬よぎったが、「それでもやらないかん」と決意した。下宿先には「遊びに出る。しばらく帰ってこないかも」と告げ、決行の地に馳せ参じたという。
決意
面白いのは、吉村ら若者たちと山崎、坂本両氏が、前年の1970年暮れ、11月25日に市ヶ谷の自衛隊東部方面総監部で割腹自決した三島由紀夫について議論したという話だ。山崎から「三島は事件を起こした。我々はどうする」と問われた吉村は、何をやるかはわからなかったが、この人がやるんやったらやりましょう、そう思ったという。その経緯がすでにあることから、実行に向けた連絡があったときも皮膚感覚で「やる気だ」と思った。だが、彼らの考えたことは、三島とは違って、犯罪だとしても、自己であれ他者であれ、人を傷つけはしない。決して血は流されない。実行者たちの間では丁寧な確認がなされたのだ。