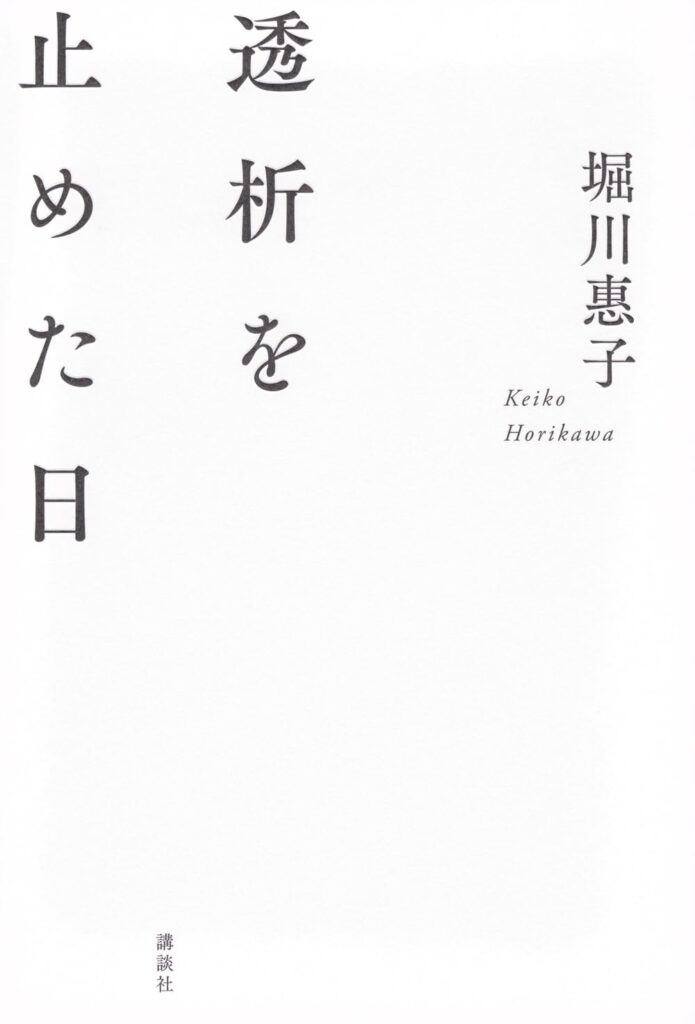【関連】アルバネーゼ報告を読む
・「占領経済からジェノサイド経済へ――パレスチナ地域における人権状況に関する国連特別報告者報告書〔抄訳〕」フランチェスカ・アルバネーゼ
・「世界はこの報告書を受け止められるか――アルバネーゼ報告の射程と意義」早尾貴紀(東京経済大学教授)
・「国際人権法へのあからさまな攻撃を前に沈黙という選択肢はない――トランプ政権による国連特別報告者に対する制裁」小坂田裕子(中央大学大学院法務研究科教授)
正義は、被告人が訴追され、弁護され、裁かれることを要求する。同時に、より重要に思える他の問いも存在する。――「どのように起こりえたのか」「なぜ起きたのか」「なぜユダヤ人だったのか」「なぜドイツ人だったのか」「他国の役割は何だったのか」「連合国の側にどのような共‐責任があったのか」。
ハンナ・アーレント
2025年10月26日、市民社会が組織した民衆法廷「ガザ法廷」は、イスタンブールで開催された最終会合において、イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への攻撃に関する判決を下した。筆者はその瞬間を現地で見届け、公式の裁判所によらない「良心の陪審」が、新たな国際法を切り拓く瞬間を垣間見た。「法が権力によって沈黙させられるとき、良心こそが最後の法廷でなければならない」という理念のもとで展開された民衆法廷に、我々はどのような意義を見出しうるか。
「良心の陪審」
そもそも「民衆法廷」は、国家や国際機関による正義の不在に対し、市民社会が自律的に設けてきたフォーラムである。その起源は1967年に開催された「ラッセル法廷」にある。哲学者バートランド・ラッセルとジャン=ポール・サルトルらは、ベトナム戦争における米国とその同盟国の違法行為に対し、「沈黙という犯罪」を防ぐために、民衆法廷の必要性を訴えた。既存の裁判所がその事態を取り扱えないなかで、証拠に基づく公聴を行ない、実定国際法の違反のみならず、帝国主義的拡張への批判というナラティヴの中に位置づけようとした。
この系譜に属する民衆法廷は、実定国際法からこぼれ落ちてきた法規範(先住民法、人民の権利など)に照らし、市民社会主導で審理を進める。そこでは、法律家に限定されない陪審が、資料や証言に基づき認定と勧告を提示する。法的拘束力は持たないが、それゆえ制度的制約に縛られずに、傾聴の手続と正統性の形式を重んじ、被害を受けた人々の声を記録し、説明責任を促す機能を果たす。国際司法裁判所(ICJ)や国際刑事裁判所(ICC)など公式の裁判所の制度がはらむ正義の空白を市民的熟議が埋める点にこそ、民衆法廷の意義がある。
2024年11月に設立されたガザ法廷は、この民衆法廷の系譜に連なる最新の試みである。その審理は、ジェノサイド条約・ローマ(ICC)規程・国際人権条約といった実定国際法に加え、「自然正義の道義的命令」という観点から行なわれ、最終的に「道徳的判決」を導くことを目的とする。ICJやICCといった公式機関もすでにガザ事態に着手しているが、判決が出るまでには長い歳月を要する。そのような正義の遅れに対して、ガザ法廷はサラエヴォ(2025年5月)とイスタンブール(同年10月)での公聴を重ね、喫緊の要請に即応する判断を生み出した。
イスタンブール最終会合
10月23日からイスタンブールで開催された最終セッションでは、4日間にわたりガザでの多面的犯罪、国際的共犯構造、市民の連帯と抵抗が集中的に検証された。第1・2日目では、ガザで進行するジェノサイドの具体的構造が詳細に証言された。専門家や被害者証人らが共通して描いたのは、単一の手段による殺害ではなく、住環境、生態系、医療、教育、情報など複数の領域を同時に破壊する「複合的ジェノサイド」の様相である。
たとえば、「意図的な飢餓」として、食料・水・医薬品・燃料の搬入が意図的に遮断され、国連やNGOの援助配布所さえも攻撃対象とされていることが報告された。家屋やインフラを無差別に破壊する「住居体系破壊(ドミサイド)」や、農地・樹木・漁場への攻撃、不発弾や有毒廃棄物による「生態系破壊(エコサイド)」も系統的に指摘された。とりわけ病院や医療従事者の標的化、産科医療への攻撃、不妊治療施設の破壊などは、「医療体系破壊(メディコサイド)」や「生殖体系破壊(リプロサイド)」と呼ばれた。また、学校・大学・図書館の破壊や教員・学生の殺害・排除によって、「知的・情報的インフラ」が根こそぎ破壊されている状況から、「学知体系破壊(スコラスティサイド)」という概念も提示された。さらには、パレスチナ人記者の標的化によって、「ジェノサイドの記録化」が妨害される経緯も危険視された。政治・文化の指導者・代表・活動家の標的殺害・拉致などは、政治体系破壊(ポリティサイド)と名付けられた。
第3日目には、こうした暴力を可能にしている国際的な共犯構造に焦点が当てられた。米国や欧州諸国による軍事援助、拒否権の行使、ICCの弱体化など国家の関与に加え、Amazon・Googleなどのテック企業が監視・標的化システムを提供していること、メディア・大学・研究機関の連携がジェノサイド的構造を支えていることが指摘された。また、ガザ内部の文化的・社会的抵抗の姿勢に加え、それに連なるBDS(ボイコット、投資撤収、制裁)運動や市民法曹ネットワーク、ガザ包囲の突破を目指す「不屈の世界船団(グローバル・スムード・フロッティラ)」、ガザ法廷自体の対抗運動も評価され、ジェノサイドに対抗するグローバルな連帯と記録の重要性が強調された。
良心の陪審による道徳的判決
第4日目に公表された「道徳的判決」は、イスラエルによる行為を「進行中のジェノサイド」と明確に認定し、その根底に「優越主義的・植民地主義的なシオニズム・イデオロギー」があると断じた。特筆すべきは、個別の殺傷や破壊行為を超え、パレスチナ集団の抹消を目的とする全体的な意図と政策的体系性を構造的暴力として摘示した点である。また、陪審は「リアルタイムで高度に可視化された」ジェノサイドであると強調し、可視性のもとでも暴力が、なおも止まらないという歴史的に前例のない状況に対する国際社会の不作為を指弾した。
これらの認定に基づき、法廷は各方面への勧告を提示した。まず「不処罰の終焉」を掲げ、関与主体への将来的な責任追及、イスラエルの国際機関からの資格停止、国連総会「平和のための結集」(377A)に基づく禁輸・制裁・保護措置を要請した。さらに、ジェノサイド体制を可能にする政治・軍事・学術・経済・文化的基盤への多層的な対峙を呼びかけ、市民社会に対しては「スムード(非暴力的な抵抗)」の支援と、抑圧体制に対する全方位の包囲網の構築を求めた。最後に法廷は、「沈黙は中立ではない。沈黙は共犯であり、中立は悪への降伏である」と結語し、道徳的判断を超えた責任倫理としての応答を訴えた。
我々を突き動かすもの
ガザにおける人道危機に対しては、すでにICJやICCで取り扱われ、国や個人の法的責任が問われ始めている。だが、アーレントが喝破したように、正義とは単に加害者を訴追し裁くことにとどまらず、その事態が「なぜ」「どのように」起きたのかという問いを引き受ける営為でもある。まさにガザ民衆法廷が照射したのは、違法行為の表層だけではなく、それを深層で支えてきた国際秩序の沈黙、国家間の共犯構造、そしてメディアや経済ネットワークの加担性といった構造的暴力の全体であった。
こうした状況の中で、市民が自発的に行動に踏み出すことは、もはや単なる倫理的関心を超えている。収容所の内側で不可視化されたホロコーストと異なり、ガザでの暴力は全世界にストリーミング配信され、もはや「知らなかった」と背を向けることができない時代にある。いま多くの人びとが持ち始めているのは、ジェノサイド的暴力を生み出す世界に、自分自身も住みつき、何らかの形で巻き込まれている以上、「応答可能性(レスポンス・アビリティ)」を持つのだという切迫した感覚であろう。特にジェノサイド禁止という国際法の強行規範が破られている事態の中で、黙認や無関心そのものが、構造の維持と再生産に関わる意識が市民の行動を突き動かしている。
このような「応答可能性」としての「責任」は、世界人権宣言の最終3条にもその規範的根拠を見出すことができる。28条は人権が完全に実現される「秩序への権利」を保障し、29条は人格の自由かつ完全な発展が可能となる「共同体への責務」を明記する。さらに30条は、他者の権利を破壊する手段としての「権利濫用禁止」という制限原理を掲げている。ガザの文脈に照らすならば、ジェノサイドを許さない秩序を求め(28条)、自らの共同体が加担する暴力への倫理的責任を引き受け(29条)、他者の存在を否定しない姿勢そのものが(30条)、応答可能性としての責任を支える条件となる。ガザ民衆法廷は、こうした応答の回路を可視化し、個々人の倫理的関与と構造的暴力への抵抗を国際法の理念と結びつける実践として、その意義を明確に示したのである。それは同時に、「国際法以後」(最上敏樹)に到来するであろう新しい国際法の在り方――裁判長リチャード・フォークはそれを「良心の国際法」と呼ぶ――も描き出している。