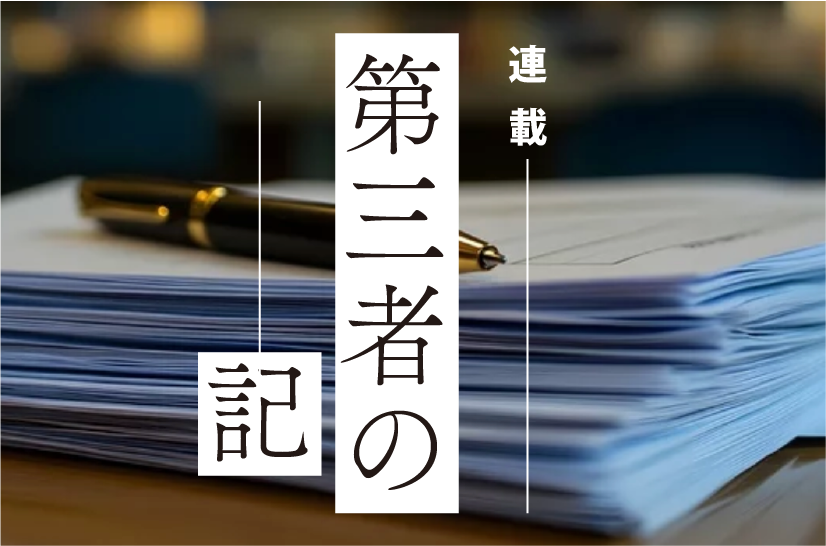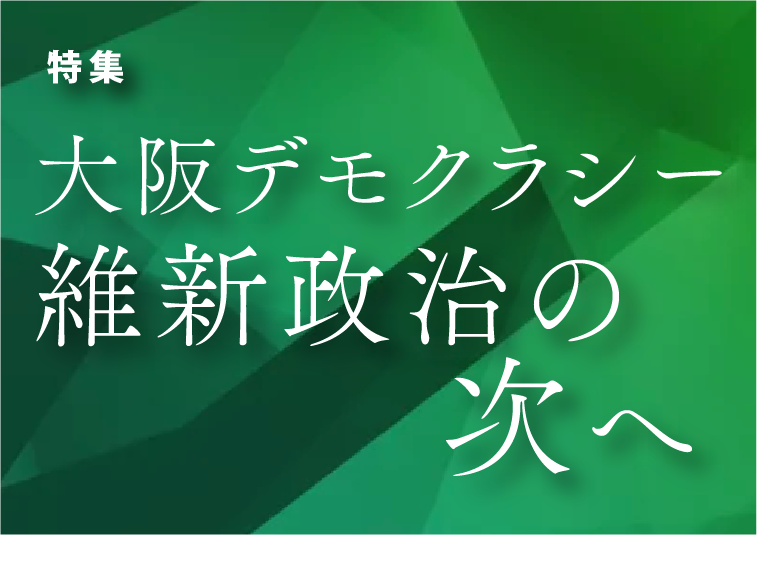いまの日本で、「ジャーナリズム」という言葉に、どれだけの人が反応するだろうか。
おそらく多くの人は、この単語は知っているし、具体的なかたちとして、これまでであれば新聞・雑誌や放送の取材・報道活動を何となくイメージするものの、その意味や意義を明確に答えられる人は少ないのではないか。むしろ、その存在感は日本国内において決して高くないともいえよう。社会一般の見方として、「上から目線で偉そう」、「押し付けがましい」といったマイナス評価も少なくないし、一方では「横並びで深堀りがない」、「必要性を感じない」という層も多いという実感がある。
その結果、伝統的メディアといわれジャーナリズム活動を担ってきた言論報道機関は、社会的影響力を相対的に軒並み失ってきている。メディア接触状況をみても、各種調査の数字は、一般市民の新聞離れ、テレビ離れを明確に示している。さらにいえば、小中高校に子どもが通う世帯はもちろん、教師や大学教員の側でも、もはや新聞を定期購読する人は少数派と思われるし、家にテレビがない者も珍しくない。企業経営者や政治家、官僚といったいわゆる社会のリーダー層においてすら、たとえば首相が国会で新聞を読まないことを推奨したり、SNSがニュースの情報源であると公言したりする状況にある。
本稿はこうした実相を前に、このままジャーナリズムの消滅を待つのではなく、むしろ積極的に社会の認識を変え、まっとうなジャーナリズム活動を日本社会に根付かせ、民主主義社会の維持・発展に寄与するために何ができるかを問うものだ。そのための挑戦を紹介しつつ、その前提の現状をいくつかの事例を通して情報共有することにしたい。
表現の自由の後退
現在のジャーナリズム弱体化の要因の一番には、活動の基盤となる法制度、すなわち表現の自由が揺らいでいることが挙げられる。
いうまでもなく、取材や報道の拠って立つところは憲法でも保障されている「表現の自由」であって、情報の収集過程にあたる取材行為、そして発表過程における報道行為が、とりわけ公権力からの束縛を受けることなく自由に行なえることが求められる。あるいは読者・視聴者の「知る権利」の代行者として、必要な情報を入手し報じるということが、一定程度、法社会的に保障されていることが、十全なジャーナリズム活動を支える必要条件だ。
しかし残念ながらここ四半世紀、2000年代に入ってからの雲行きは相当に怪しい。なぜなら、取材や報道をいつでも制限できるような新たな法の仕組みが矢継ぎ早にできあがってきているからだ。この具体的な法律のありようは別稿註1で詳述しているのでここでは割愛するが、こうした法改正と並行して進む運用実態の変化をここでは指摘しておきたい。
最初に3枚の写真を見ていただきたい。これらは偶然、2019年から2020年にかけてのわずか1年間に撮影したものだ。
1枚目は2020年3月、東日本大震災にともなう東京電力福島第一原子力発電所の爆発によって立ち入りが制限されている福島の状況だ。常磐線・夜ノ森駅改札を抜けると目の前の住宅街の入口が封鎖されていた(現在は撤去済み。ただし大熊町・浪江町など、まだ立ち入りが制限されている地域は少なくない)。
メルトダウン(炉心溶融)の発生で発出された緊急事態宣言は、2011年から14年が経過しようとしている今も継続中であって、宣言の根拠法は、現在全部で10存在する緊急事態法制の一つである原子力特措法である。さらにこれと連動する別法などによって、居住、移動の自由といった憲法で保障された基本的人権としての住民の権利が、完全に剥奪されている。明確で直接的な法にもとづく権利制限ということになる。もちろん、移動の自由が制限されている関係で(立ち入りが法で禁止されているため)、自由な取材も全面的に制限を受けることになる。