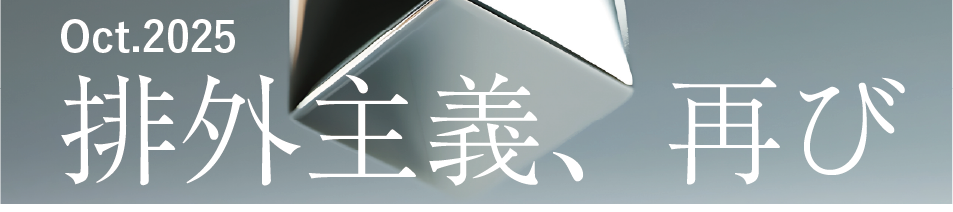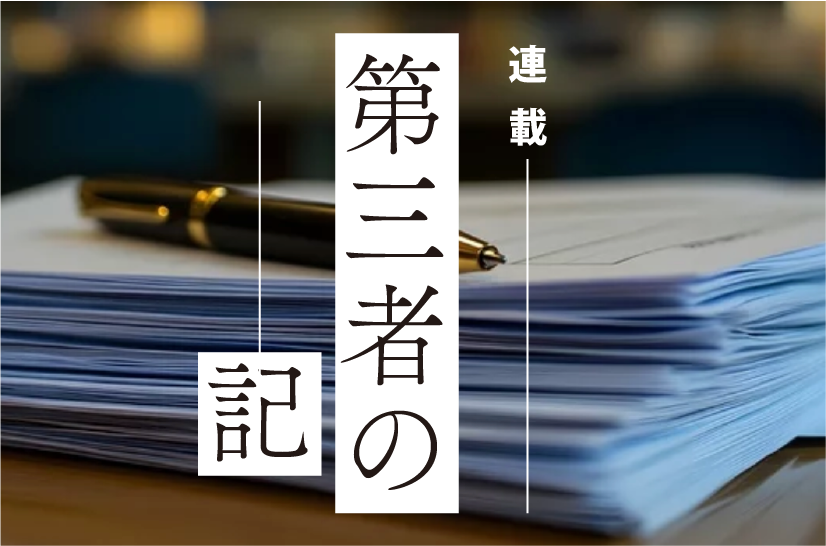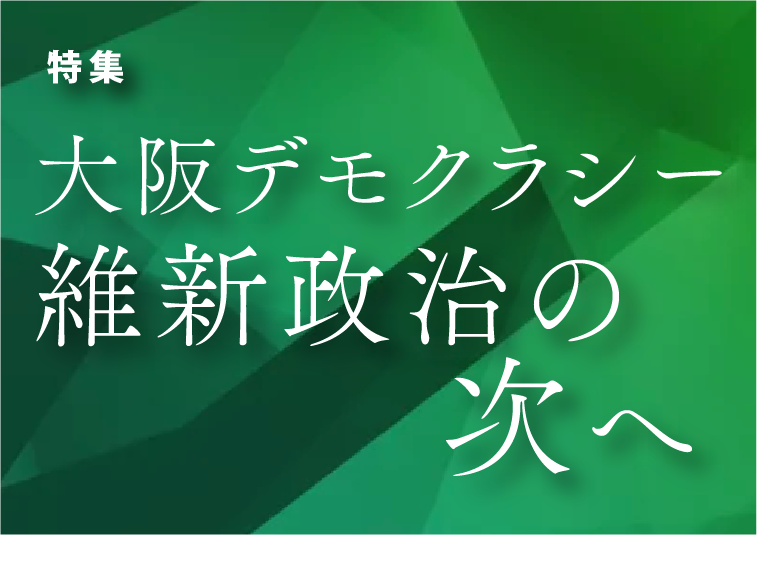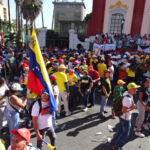森鷗外に、「鼠坂」という短篇がある。
「戦争の時満州で金を儲けた人」が新築した屋敷で酒宴が開かれる。主人と女房、満州時代の知人が二人。こちらも民間人だ。主人が客の一人小川という男の「凄い話」を話題にする。
日露戦争で日本軍が侵攻した後の寒村でのこと。小川はある夜、隠れ潜んでいた女性を強姦し、殺害した。その一部始終を、酒のさかなに、主人が露悪的に語る。苦い顔で聞く小川。その晩、小川は被害者の死体、顔を、幻影で見る。そして朝、冷たくなっていた。
鷗外こと森林太郎は、陸軍軍医として日清、日露戦争に出征した。
「鼠坂」は、実話ではない。しかし軍内部にあって鷗外が見聞きした戦時性暴力の、現実の一端をもとに書いたことは間違いないだろう。鷗外は『うた日記』でも、兵に強姦された少女の悲惨を歌う「罌粟(けし)、人糞(ひとくそ)」を書いている。
戦争で非道を働くのは、兵だけではない。帯同した民間人にも、戦時性暴力の加害者がいた。鷗外はそれを、「鼠坂」で不気味に描き出した。ちなみに小川の職業は、新聞記者だ。
従軍慰安婦について「強制はなかった」「売春婦の商行為だ」などといった発言が繰り返される。
慰安婦を強制連行したとする吉田清治氏(故人)の証言が虚偽だったと、朝日新聞が過去の記事を取り消したことは、結果として火に油を注ぐような状況をつくった。「従軍慰安婦などいなかった」。そう言わんばかりの主張さえ、勢いを増している。
うそは楽だ。うそは事実に向き合わない。だから、どんなことでも簡単に、明快に言い切れてしまう。一度うそを信じる空気が生まれると、根拠を問われることなく、広がっていく。「うそも百回つくと本当になる」とは、このメカニズムのことだ。
私は、慰安婦問題を追ってきた記者ではない。
だが、91年に元慰安婦の金学順さん(故人)らが、東京地裁に提訴したとき司法記者として取材し、事実を少し知った。日本が植民地朝鮮で何をしたか。半島出身のBC級戦犯の人たちを、断続的だが20年以上取材して、多少は学んだつもりでもある。
「鼠坂」は、日本人による戦時性暴力が、日露戦争時代から数々あったことを推測させる。日清戦争でも、蛮行は行なわれていたかもしれない。
しかし、すべては歴史の闇の中にある。個別の検証は、もはや不可能。それは、日中戦争から太平洋戦争下でも同様だ。
「原住民の女を襲うもの(中略)も出てきた。私は苦心して、慰安所をつくってやった」
中曽根康弘元首相『終わりなき海軍』の一節だ。日本軍が「女を襲う」軍隊だったことの一証言。民間人にも、軍の威勢をかって性暴力に及んだ男がいただろう。新聞記者にも?
想像しきれない数の犠牲者。その人たちは、黙して語らない。強姦被害を、女性として、どう語れよう。まして、たとえば南京でなぶり殺しにされた女性。殺された人は、語れない。
従軍慰安婦の問題は、日本人が日本の外の土地に乗り込んで犯した、性暴力の一局面。なぜそれが、クローズアップされるのか。
金学順さんが名乗り出て、後に続く人も現れたからだ。被害者が語り、資料でも裏付けられるからだ。
慰安婦問題に誠実に向き合わないことは、語るすべをもたない、日本人による戦時性暴力の、おそらくは膨大な被害者一人一人への冒瀆でもある。
慰安婦問題の報道制限
10年余り前に書いたこの文章は、2014年11月9日の北海道新聞2面に掲載されるはずだった。私は当時、東京支社報道センター所属の編集委員として、毎週日曜日掲載の「異聞風聞」というコラムを4週に1度の分担で書いていた。札幌の窓口編集委員への出稿は木曜日。この原稿もその昼過ぎに送信した。しかし翌日夕方になってもゲラが送られてこない。窓口委員に問い合わせたところ「(これから)出稿する」。しかし30分後に同委員から私の携帯に「編集局長、編集局次長判断で掲載しない」と通告があった。判断したという二人からは何の連絡もなかった。
本誌昨年10月号掲載の下地由実子氏による「ルポ やめ記者」に、興味深い事案が紹介されていた。2021年6月22日、国立旭川医科大学への取材過程で北海道新聞社の新人記者が建造物侵入容疑で逮捕される事件があり、北海道新聞は実名で報道した。その判断を批判する土江富雄編集委員の記事が北海道新聞に掲載されたという。
確認してみると、同年9月19日朝刊「守ろうとしているものは何か」という見出しのコラムで、実名報道に疑問を示し「記者を守るのは、表現の自由や取材の自由、国民の知る権利を守るためだ。その基本に踏みとどまっている確信さえあれば、どんな状況でも頑張れる。逆にそれなしでは戦えない」と書いている。下地氏のルポによると、ゲラを読んだ編集局長から土江氏に「取り下げてほしい」と執拗に要請があった。土江氏は「取り下げることになったら会社を辞める」と抵抗し、原稿は掲載された。