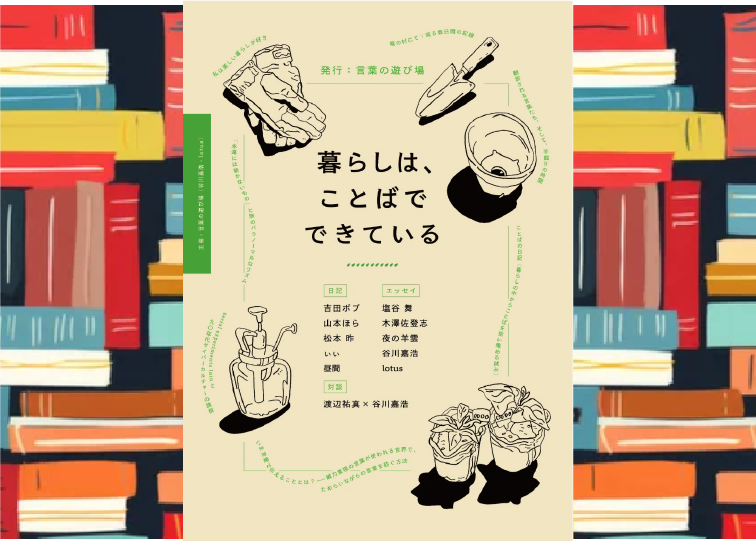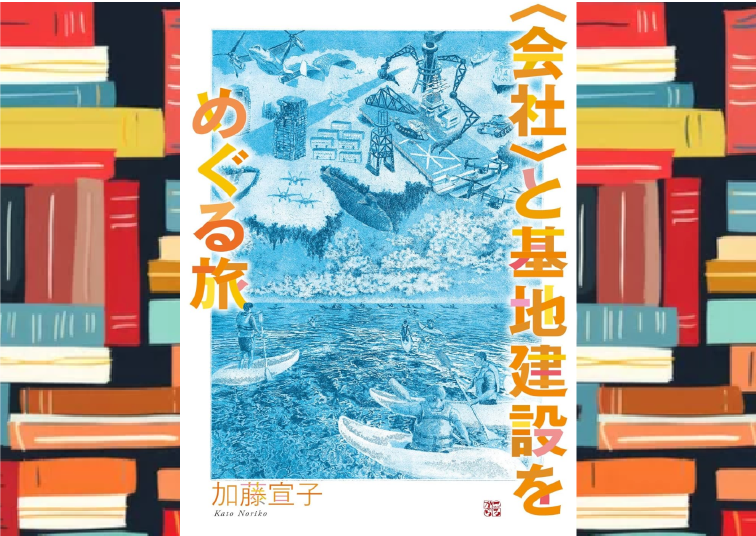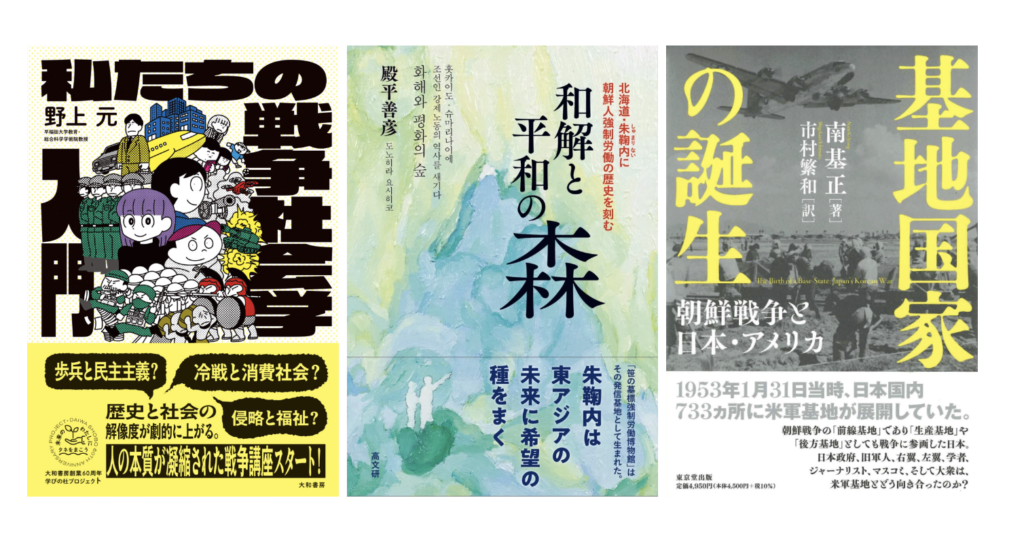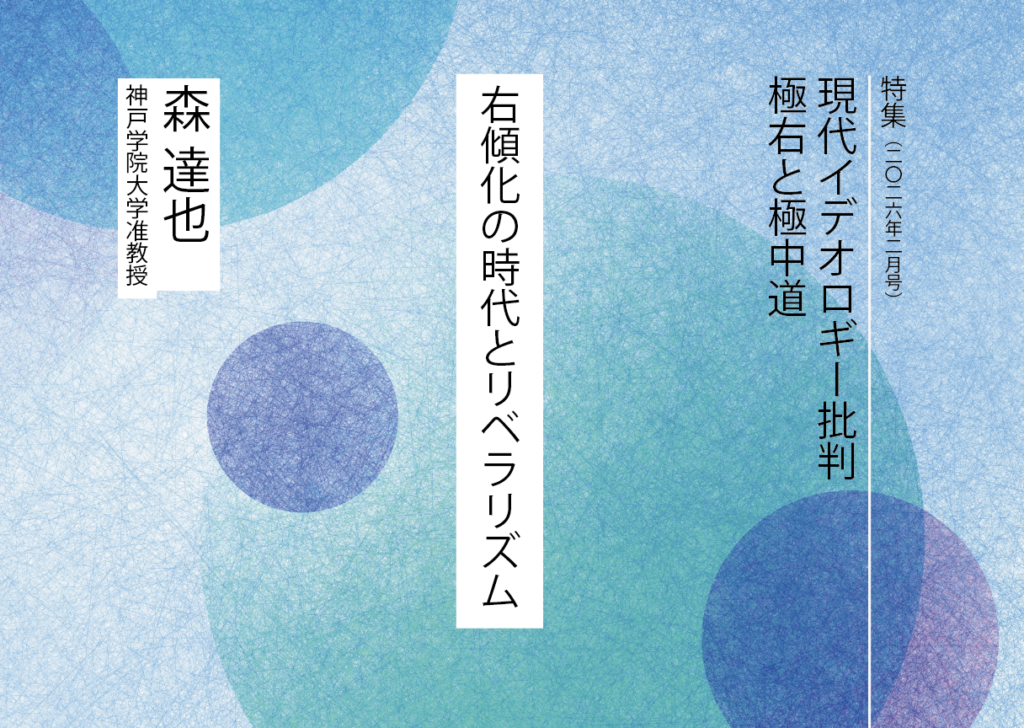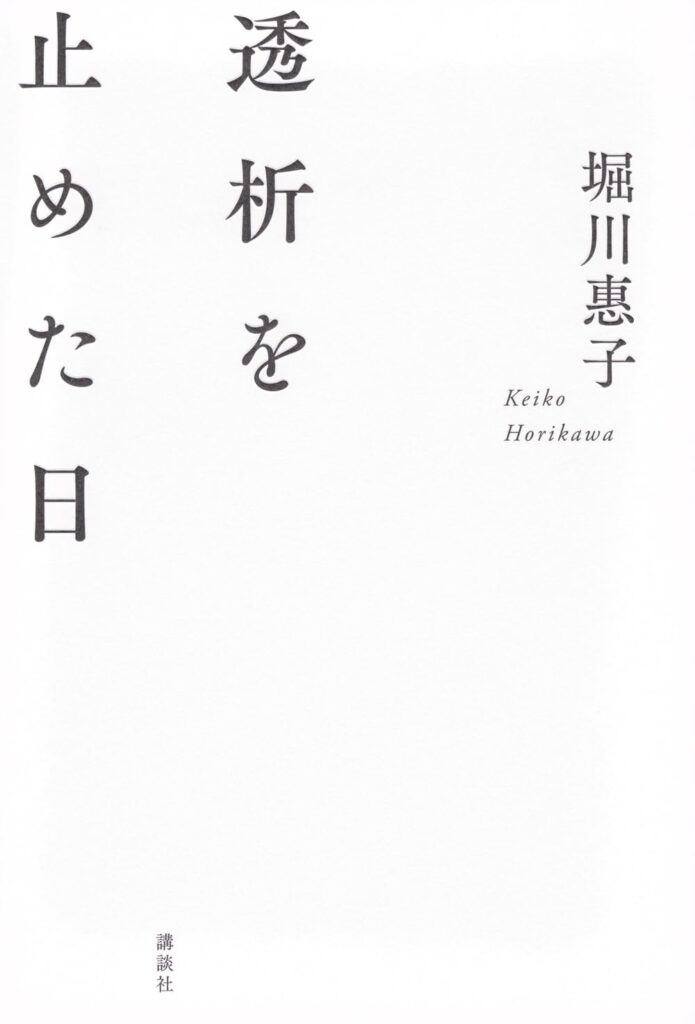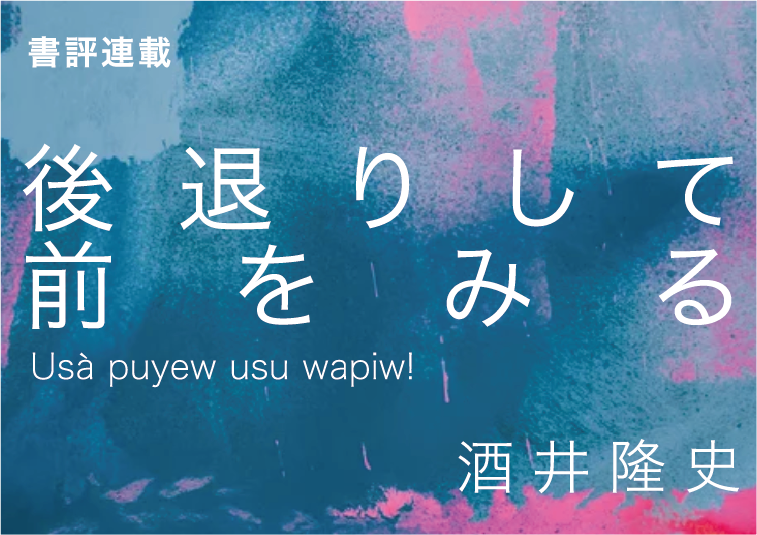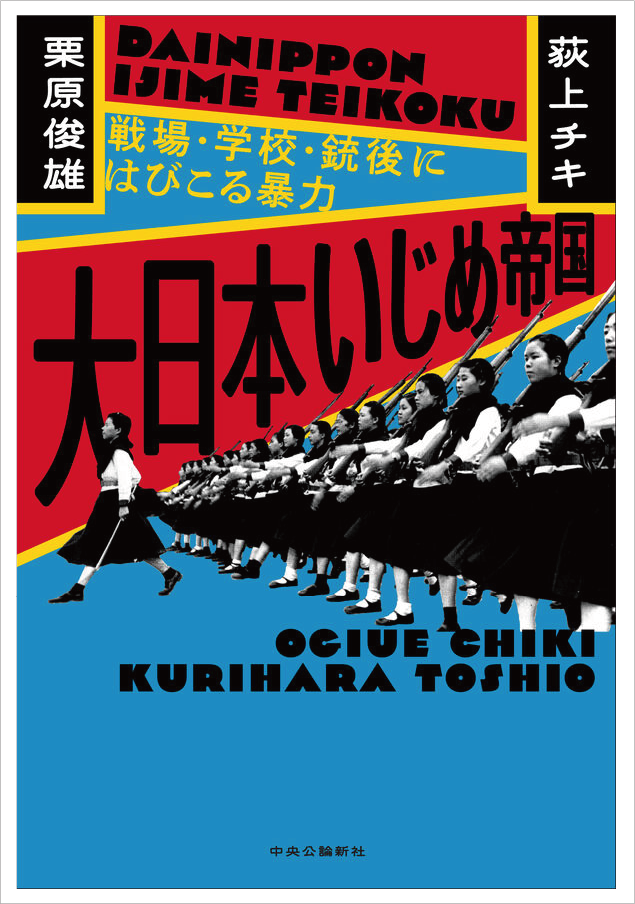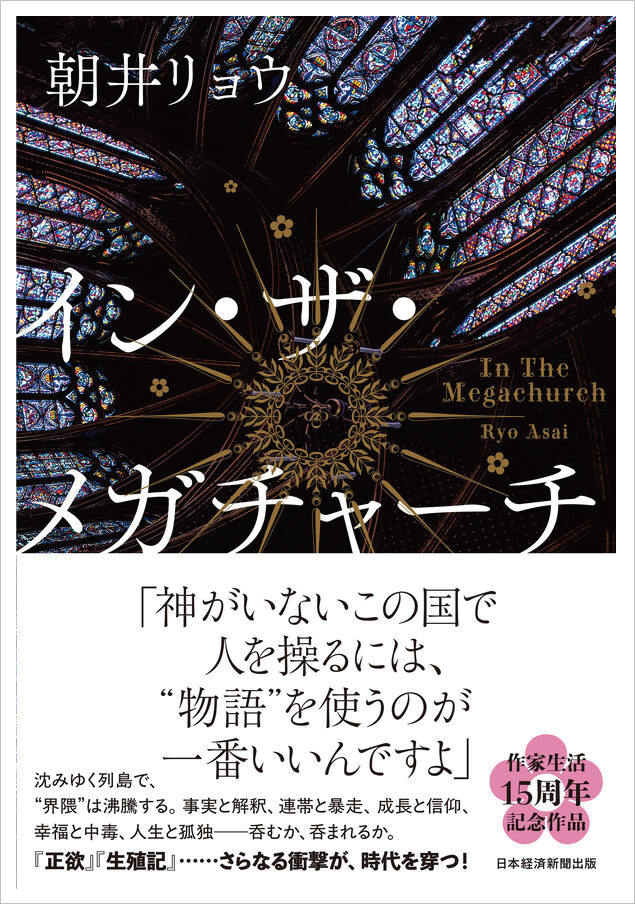20代半ばの二人組が店内でこんな会話をしていた。
「SNS疲れるよな。Instagramも最近見てへんわ」「ガラケーがちょうどええよな」
やっぱりそうかと思う。仕事でSNSを利用するが、長時間タイムラインを追っているとどっと疲れがくる。次々と流れこんでくる刺激の強い言葉に頭が限界を迎える。
本書の発行人の一人である哲学者の谷川嘉浩は、そうしたネット上に溢れる「まばゆく、騒がしく、前向きで、誇張されている」言葉を「昼の言葉」と表現する。そして、「昼の言葉」から距離を取り、自分たちの言葉をゆっくりと育てていくことができる場として、ZINEという紙のメディアを挙げる。その一つの実践が本書だ。
暮らしは、ことばでできている。この当たり前の事実がどこか現実離れしたものに思えてしまう。「昼の言葉」の氾濫は、暮らすなかで生じる他愛のない言葉を覆いつくそうとする。匿名の誰かの反論を気にして、好きなものを好きということも憚られるような状況が実際にある。こうした現実に対して寄稿者の一人、文筆家の塩谷舞は「今の時代は『好き』というシンプルなことを伝えるだけでも、そうした面倒くささが付き纏う」と述べるが、その通りであろう。
一方で、近年の文学フリマの隆盛に見られるように、表現したいことを表現する人たちは増えてきている。それは谷川が指摘した通り、「昼の言葉」からリトリートする場所として、ZINEという媒体が選択をされるようになっているということである。「SNSは疲れる」と本屋に足を運ぶ二人組も同じ文脈のなかにいる。
表現する手段はなんであれ、その人が表現したいことを表現している現場にであうと素直に感動してしまう。なんだみんな言葉をもっているではないか、と嬉しくなる。本書のなかで引用されている「ことばを、誰もが探しているのだ ことばが、読みたいのだ」という長田弘の詩に心が鎮まっていく。
谷川は自身の論考のなかで、kashmir『ぱらのま』を補助線に「おわり」の感覚について考察する。人間は終わりのあるものにかれてしまうと指摘し、「うーん、わかってもらえるかわかんないけど、無性に終着駅に行きたくなるんだよね」という主人公の台詞を紹介している。この台詞にみられる日常の暮らしのなかで非日常的な旅を求めたくなる衝動は、SNSと本の関係においても当てはまるだろう。SNSのタイムラインの終わりのなさに対して、綴じられた本は「おわり」を求める気持ちに沿う。
また、この「おわり」の感覚は、日記を書くという行為にも通じる。区切りをつけることで一日一日が「その日」として残ることに私たちは安心する。誰の評価を気にすることなく、自分のペースでゆっくりと言葉を探し求めることができる日記は、「夜の言葉」のメディアだ。本書にも会社員をはじめ五名の日記が収められているが、読者にも自分の言葉を育てる場所として日記を書くことを促しているように思える。
暮らしは、ことばでできている。この当たり前に立ち返りたい。言葉は一つ一つ手探りで育てなければならない。ときに傷つけ、傷つけられもする。しかし、「わかってもらえるかわかんないけど」という不安な気持ちを取り払ってくれうるのも言葉だ。
「この人の文章好きなんよな」「わかるー」
二人組は、1時間以上棚を見て6冊買って帰った。
〈今回紹介したZINE〉
『暮らしは、ことばでできている』
発行:言葉の遊び場(谷川嘉浩/lotus)2000円+税