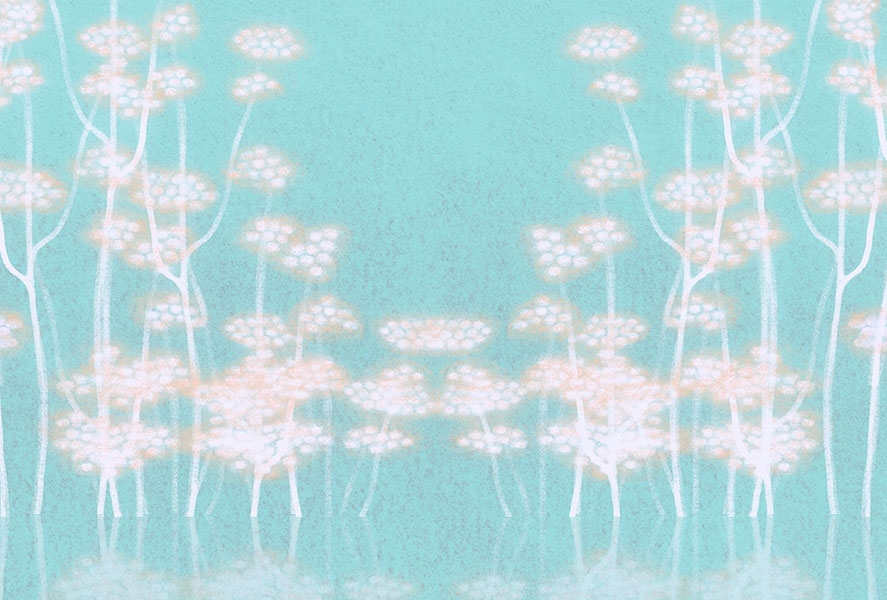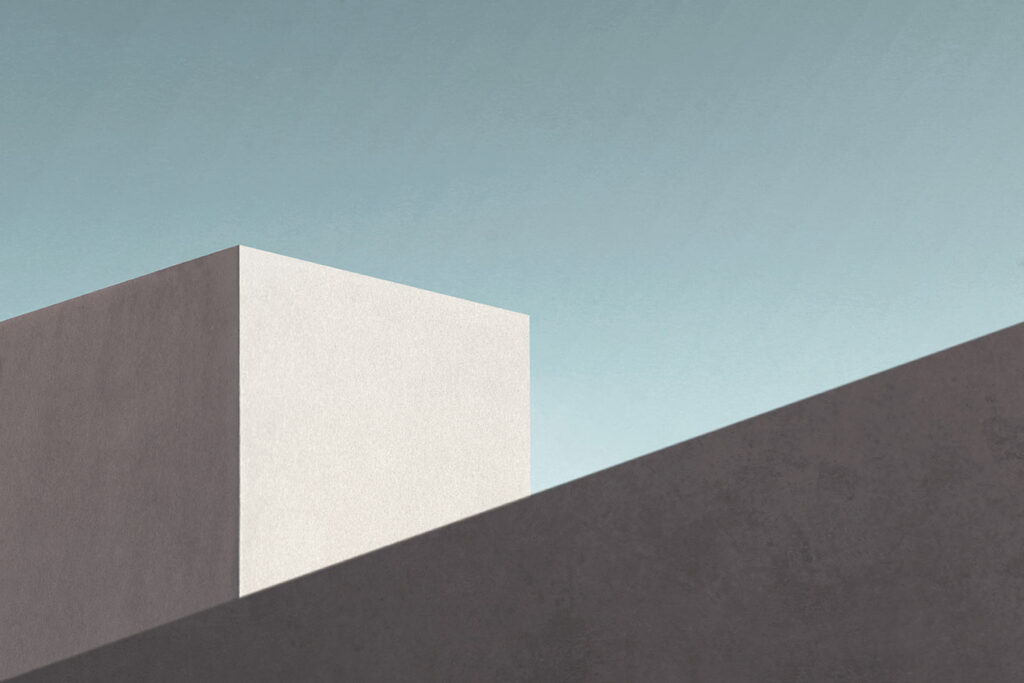2023年10月にイスラエルによるガザ地区への攻撃が始まってから2年、本稿を執筆している最中に停戦合意と人質解放のニュースが飛び込んできた。その数日後にはイスラエルによる攻撃再開も報じられ、停戦合意の今後の先行きは見通せないが、これまでガザへの執拗な攻撃と徹底的な破壊を続けてきたイスラエルが戦闘停止に合意した背景として、この間の国際世論の変化とイスラエルの孤立の深まりを指摘することができるだろう。
ロシアによるウクライナ侵攻を非難する一方で、ガザでの戦闘開始当初はイスラエル批判を避けるダブル・スタンダードの対応をとってきた西側諸国のあいだでも、今年に入ってからパレスチナを国家承認する動きが相次ぐなど、イスラエルへの外交的圧力が強まっている。
イスラエルによるガザ攻撃に対していち早く明確な非難の声をあげたのは、グローバル・サウスの国々であった。そのなかでも南アフリカは、民主化以前のアパルトヘイト政策と、イスラエルによるパレスチナ人およびパレスチナ被占領地に対する政策のあいだに多くの共通点をもつがゆえに、パレスチナ/イスラエル問題に関して、並々ならぬ関心を示してきた。アパルトヘイトは、もともとは南アフリカの歴史上の固有のことがらを指す用語であるが、近年、イスラエルのパレスチナ支配は国際法上の犯罪としてのアパルトヘイトにあたる、という理解が広がってきている。そして南アフリカは、よく知られているように、「ジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約」(以下、ジェノサイド条約)にもとづき国際司法裁判所(ICJ)にイスラエルを提訴し、イスラエルの法的責任の追及強化をめざす国家の連合体である「ハーグ・グループ」においても中心的な役割を果たしてきた。南アフリカは、イスラエルによるアパルトヘイトとジェノサイドというふたつの国際法上の犯罪の責任追及において独特な立ち位置にあるといえる。
以下、本稿ではまず、南アフリカの歴史を参照しつつ、イスラエルのパレスチナでの実践がアパルトヘイトと呼ばれることの意味を検討する。次いで、ICJへの提訴をはじめとする南アフリカによるイスラエルの国際法違反の責任追及の動きについてみていく1。
1 本稿の内容の1部は、2025年2月に開催された第4回「イスラーム信頼学」国際会議で筆者がおこなった口頭報告にもとづいている。
南アフリカとイスラエルのアパルトヘイト
アパルトヘイトとはアフリカーンス語で隔離または分離を意味する言葉で、南アフリカで1948年に成立した国民党政権の政策の中心概念であった。南アフリカにおける入植植民地主義の歴史は17世紀にまで遡り、国民党政権が白人至上主義を初めて導入したわけではなかったが、国民党政権は、既存の隔離メカニズムの再編成と体系化を行なって、「白人の南アフリカ」を確立し、防衛することを目的とするアパルトヘイト政策を推進した。
アパルトヘイト政策のもとで南アフリカの人口は法律によって4つの人種(「人口集団」)に分類され、人種ごとに居住地域が指定され、大規模な土地の収奪と強制移住が行なわれた。多数派であるアフリカ系黒人は、形ばかりの独立や自治権を与えられた民族ごとの「ホームランド」(あるいは「バンツースタン」)に帰属させられることを通じて、南アフリカの市民権をはく奪された。アパルトヘイトは議会によって制定された法律にもとづき行なわれた政策であったが、それに抵抗する者は、容赦なく超法規的なものを含む暴力によって弾圧された。1960年のシャープビル虐殺と1976年のソウェト蜂起は、非暴力のプロテストを国家が暴力的に押しつぶした出来事として最もよく知られた事件である。暗殺や獄中での拷問によって殺害された反アパルトヘイト活動家も数多い。アパルトヘイト体制は、1994年の初めての民主的選挙でアフリカ民族会議(ANC)が勝利し、ネルソン・マンデラ大統領が率いる国民統合政府が成立するまで、約半世紀にわたって継続した。