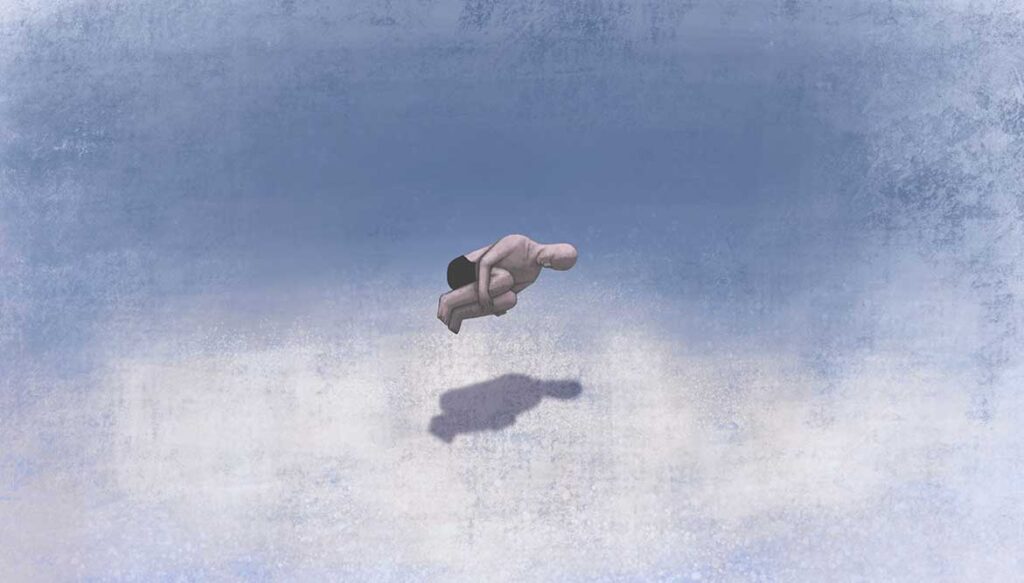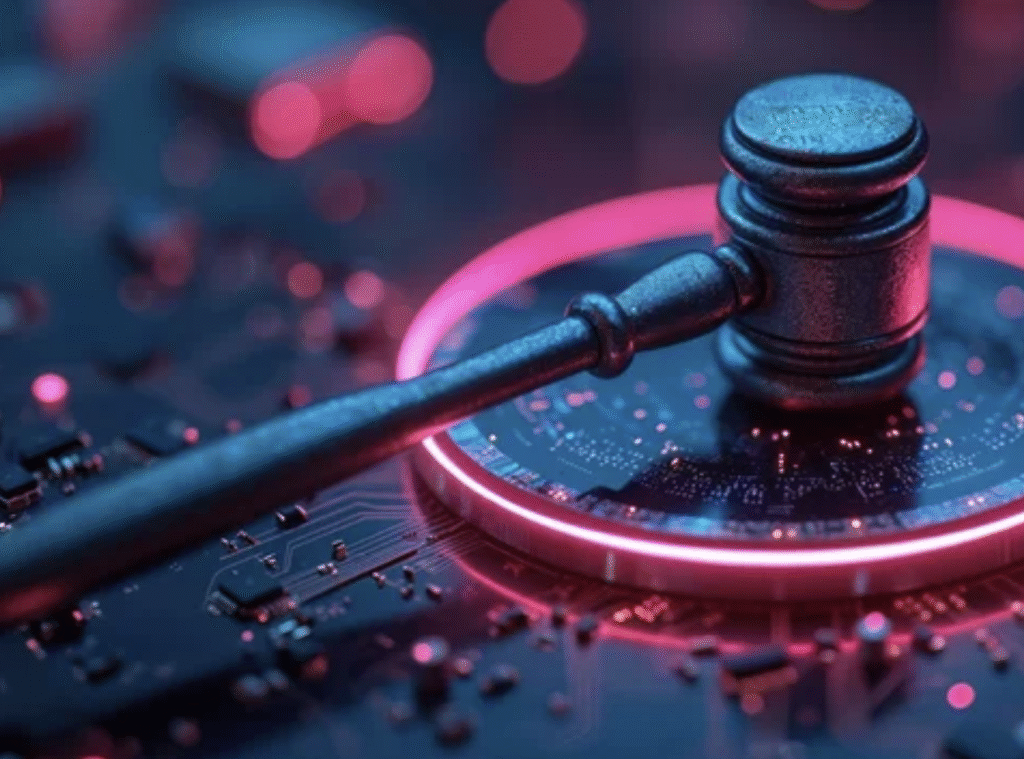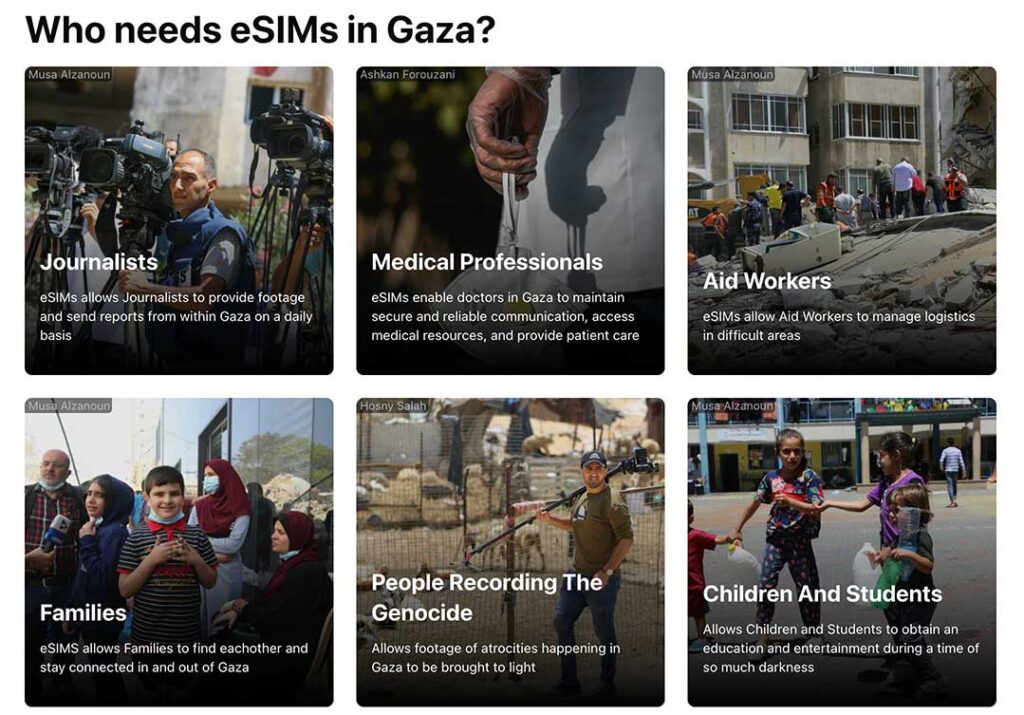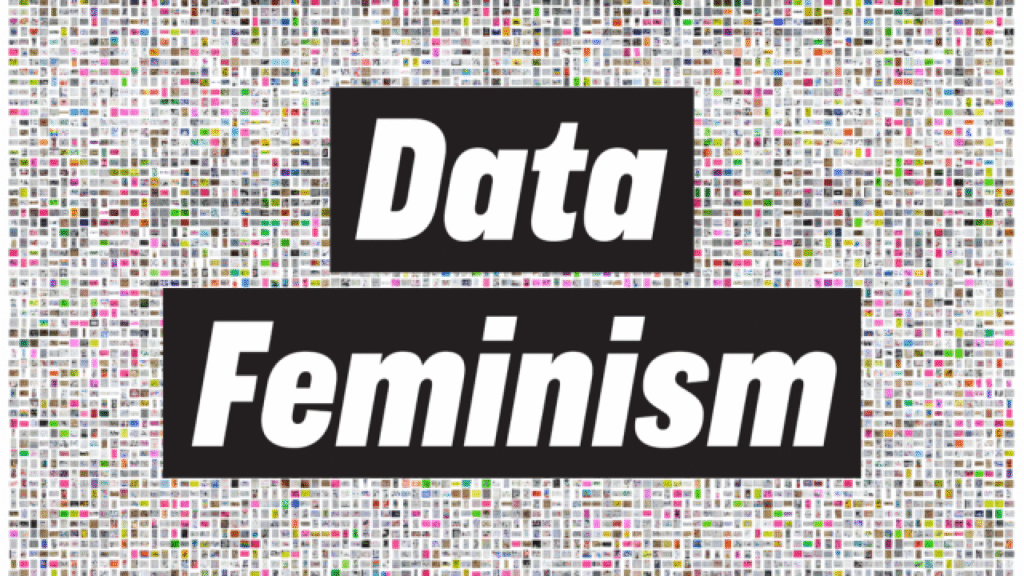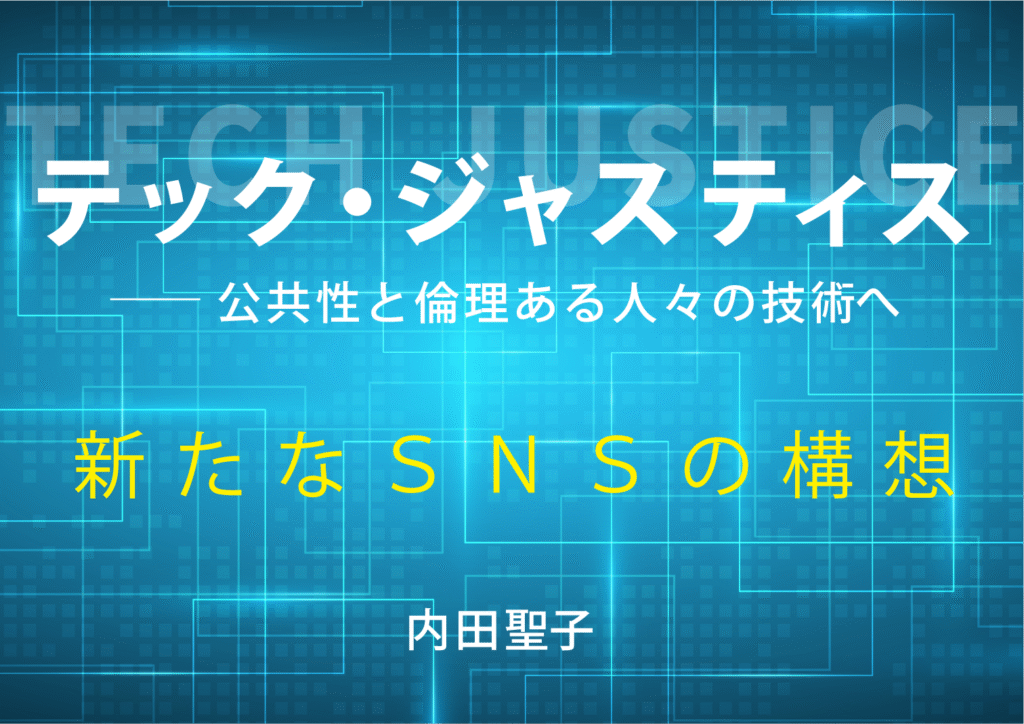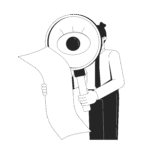(その他の記事)
・ネット空間の検閲を望んでいるのは誰か(上)──政府主導の誤情報対策の罠
・ネット空間の検閲を望んでいるのは誰か(下)──過剰な脅威に潜る官製ファクトチェック
日本ファクトチェックセンターへの懸念
「河野太郎デジタル大臣 @konotarogomame が日本ファクトチェックセンター(JFC)@fact_check_jpの記事を立て続けにRTしてくれたおかげで、JFCのフォロワーが一気に千人増えた。ありがとうございます。認知が高まれば、行政取材がしやすくなるし、ファクトチェックが届く範囲も広がります」
これは日本ファクトチェックセンター(JFC)編集長の古田大輔氏が旧Twitter(現X)で投稿したものだ(2022年11月8日)。
この直前、河野太郎デジタル大臣(当時)は、JFCのファクトチェック記事を少なくとも3本、たてつづけにシェアしていた。河野氏自身は「ほお」「これも」と一言つぶやくだけだったが、内容は新型コロナワクチンに関する誤情報を検証したもので、記事を拡散させたい意図は明白だった。河野氏はワクチン接種推進担当大臣として、SNSやブログなどを通じて「ワクチンデマ」を否定する情報発信を積極的に行なってきた。政治家としてダントツトップの250万超のフォロワー数をもつ「SNSインフルエンサー」による拡散の効果は大きかっただろう(なお、2位は猪瀬直樹参議院議員の100万超)。
JFCは、主にSNS投稿の真偽を検証する「ファクトチェック記事」を、日本で最も多く発表しつづけている組織だ。編集部の中心は朝日新聞社やNHKの出身者で、一見すると、ジャーナリズムに根差した独立系メディアのようにみえる。だとすると、現職大臣が特定のメディアの記事を拡散し、それによる認知拡大の恩恵を認めて礼を伝える姿は異様だ。権力者との関係に敏感であるべきジャーナリズムの精神とは相容れないからだ。
ファクトチェックは本来、河野氏のような極めて多大な影響力をもつ公人や公的機関の言説を検証する。しかし、JFCは匿名のSNS投稿のチェックに集中していた。メディアの報道も検証から外す方針にネット上で厳しい批判を浴びていたが、あまり意に介していない。
「何かがおかしい……」。そう感じながらも――。
当時、筆者はファクトチェックの担い手を増やし、普及を目指すNPO団体、ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)事務局長。同じくFIJ理事を務めていた古田氏が率いるJFCのスタートアップを支援する立場にあった。ネット上の批判に対しJFCを擁護する記事を書くなど、できるだけ協力しようと努めた。だが、その年の暮れ、FIJから退くことを決めた。政府がファクトチェック業界に接近し、「ネット警察」に変質していくのではないかと、先行きに不安を覚えたからである。
ここで、JFC設立の経緯を振り返る。JFCは2022年10月、一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が設立した「偽情報・誤情報対策を行うファクトチェック機関」だ。SIAは、ヤフー株式会社(現LINEヤフー)など事業者4社で構成され、警察など行政機関と連携してインターネット上の違法有害情報の対策や取り締まりを進めてきた団体。JFC設立の約2年前の2020年、総務省の有識者会議「プラットフォームサービスに関する研究会」(以下「総務省研究会」。詳細は『地平』2024年12月号記事を参照)の提言を受け、「Disinformationディスインフォメーション対策フォーラム」という協議体を設置していた。有識者、グーグルなどのプラットフォーム事業者に加え、総務省もオブザーバーに加わった、いわば“官民協議体”だった。
キーパーソンは憲法学者の宍戸常寿・東京大学教授だ。総務省研究会でもSIAの協議体でも座長を務め、「協議体をSIAでやるよう総務省に提案したのは私だ。その流れで座長も引き受けた」と筆者に明かした。ちなみに、筆者は弁護士になる前の法科大学院時代に宍戸教授の講義を受けたことがあり、大変尊敬する憲法学者である。
SIAの協議体は非公開で議論を重ね、2022年3月の最終報告書で新たなファクトチェック団体の必要性を提言。SIAがグーグル合同会社から150万ドル(当時のレートで約2億円)の支援を得て、偽・誤情報対策の一環としてJFC設立を発表したのはその半年後である。筆者を含めFIJ関係者は全くタッチしておらず、寝耳に水だった。