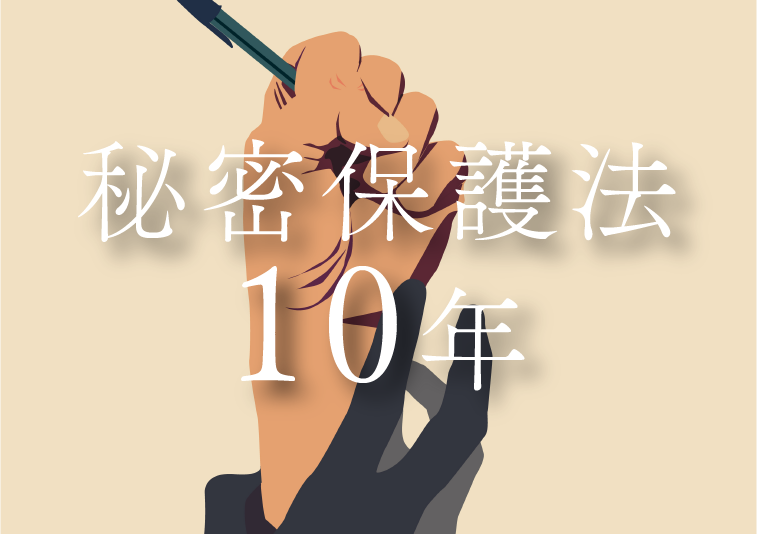急拡大する学校給食無償化
学校給食費の無償化が広がっている。
全部無償と一部無償を合わせると、すでに半数以上の市区町村が実施している。少し前までは考えられなかったことである。強い追い風が吹いている。その背景と理由を明らかにするとともに、すべての市区町村で実現するだけでなく、給食費以外も無償にする道を拓きたい。この風を逃してはならない。
文科省はこれまで、学校給食のあり方について、義務教育無償の原則から逸脱し、食材費等の保護者負担に依存してきた。また、学校内に調理場を置く自校給食から、効率化を狙って給食センターへの転換を進めてきた。学校給食事業の大規模共同実施の推進と民間事業者への転換許容がはかられてきた。それは子育て世代の負担増をもたらし、また温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに食べることを難しくさせた。
無償で安全安心の学校給食を子どもたちが笑顔で食べられる、その方策を考えたい。そのために実現していくべきことは、学校給食無償化と自校給食、すなわち再公営化である。さらには地元農産物、特に有機食材の積極的な利用である。本稿では、全国的に拡がる学校給食費無償について展望する。まず現状を概観し、拡大してきた経過を振り返り、そして今後の課題について言及する。
日本の給食は学校教育の一環として実施されるという特徴をもっている。その観点から見れば学校給食は教材であり、その負担を授業を受ける本人(保護者)に強いてきたことになる。これは「教育後進国」の姿である。敗戦後、地域からの取り組みによって、主たる教材である教科書の無償化などは実現してきた。だが、学校給食に関しては学校給食法で食材費等の保護者負担が明記されてしまっている。だが、食料品など生活必需品の高騰は保護者家庭を直撃し、市区町村の財政も悪化させ、学校給食費の値上げも起きていた。この事態に保護者が危機感をもって学校給食費無償の声を発し、そして公立学校の設置者である市区町村がそれを受け止め、都県の力を借りて、給食費の無償化は2024年度、以下のように拡大した。
給食無償化は、財政に余裕のある東京都が先行してきたが、先に、和歌山県が100%無償自治体になった。全国的にみても過半数の市区町村が無償・一部無償にしている中で、財源不足を言いわけにしてきた地方自治体も決断を迫られている。
ただし、せっかく無償化を実施したにもかかわらず、給食の内容が粗末だという問題のある自治体もある。「おかずが少なすぎる! 大阪市の小学校給食が「あまりにショボすぎる背景」とは?」(FRIDAY、2024年5月24日)では、唐揚げ1個、豆もおかずは2粒、チーズ1個という状況が紹介されている。大阪万博にかける予算を回せないのだろうか。
公立の義務制小中学校は、国や県ではなく、市区町村が設置者である。地域住民が、地域の子どもたちを「わたしたちの子ども」としてともに育てること、それが市町村が設置し運営している理由である。学校給食もその中で行なわれている。つまり、義務教育は地方自治として実施されている。したがって主体は地域住民であり、住民自治であり、地域住民による団体自治である。その自治が円滑に実施できるように補完するのが政府の役割である。地域の子どもの成長を願っての学校給食費無償であり、「わたしたちの学校」のためである。
その無償化を全国どこでも可能にするためには、学校給食法の改正・運用規則等の改善(任意実施条項の廃止、公会計、無償、自校給食促進・再公営化、地場物の有機食材の積極的な利用)と地方自治を伸ばす財源確保が重要となる。