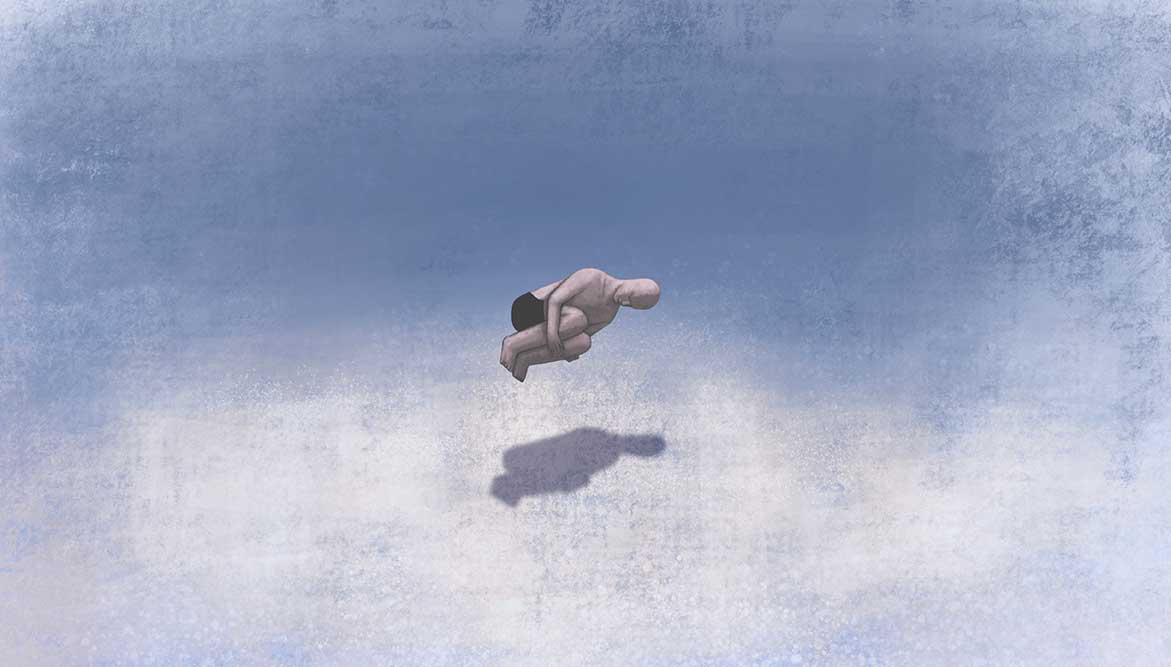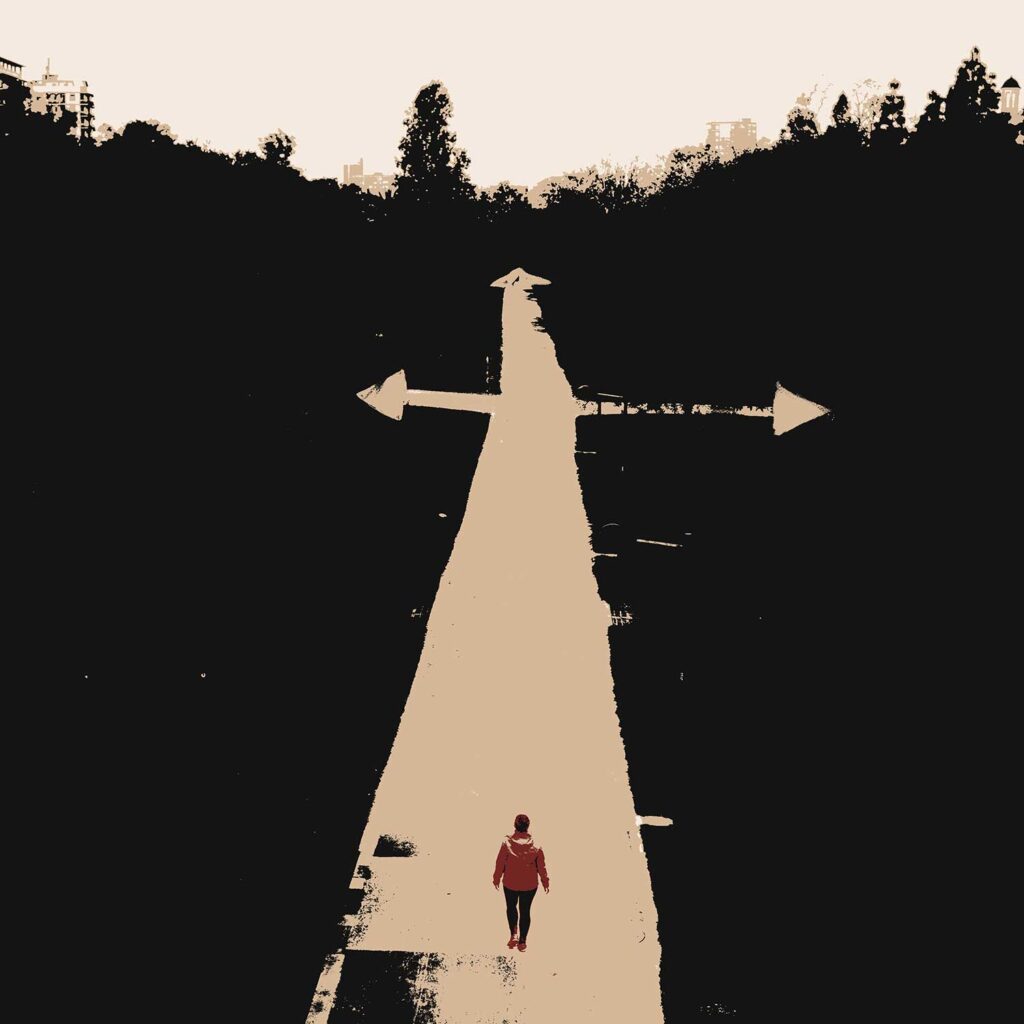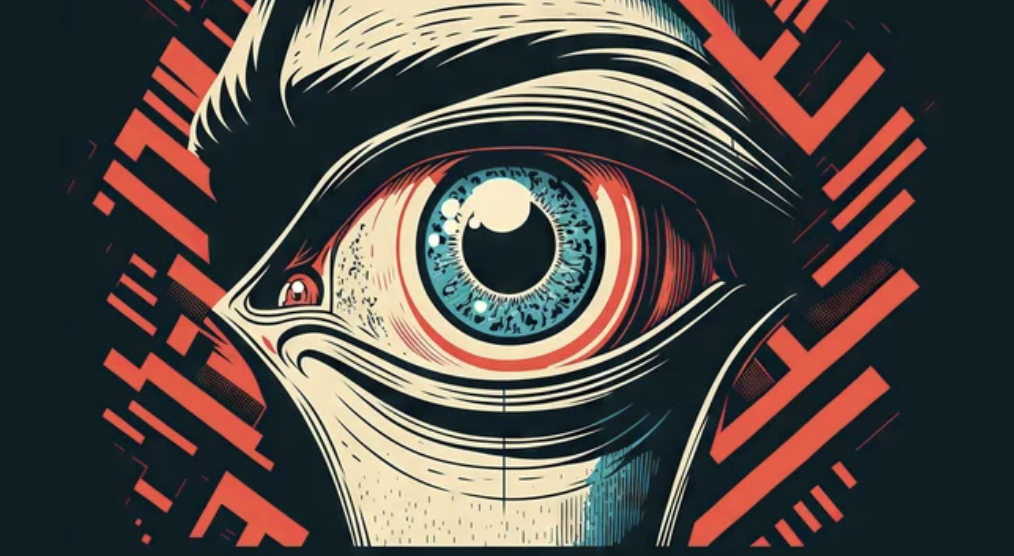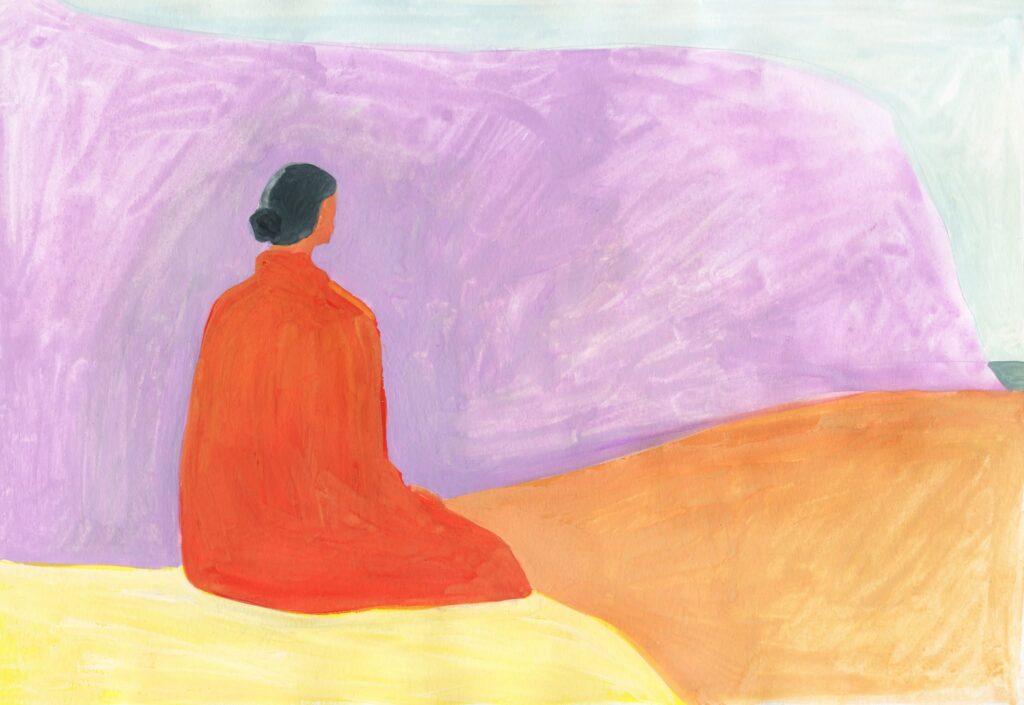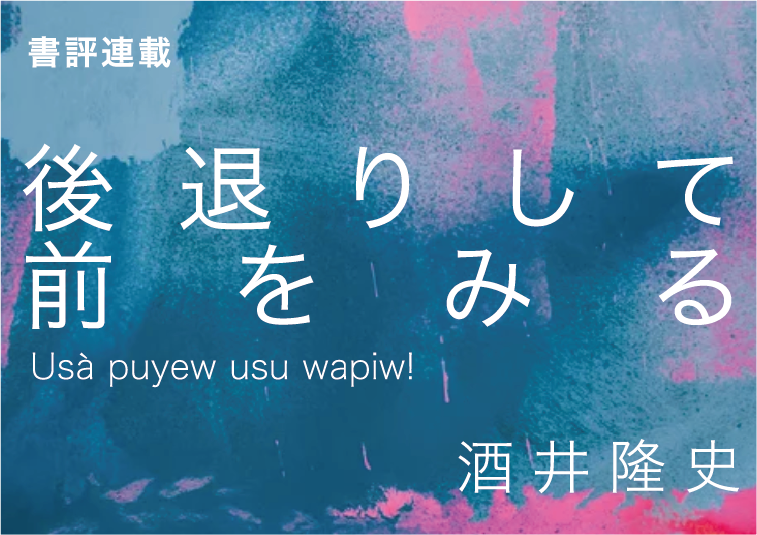関連:「特集 排外主義、再び」(2025年10月号特集)

【座談会登壇者】
金澤 伶(かなざわ・れい)
東京大学四年生。国際関係論専攻。EmPATHy代表。難民の保護や、教育を受ける権利のために活動。
崎浜空音(さきはま・そらね)
慶應義塾大学法学部法律学科四年生。基地と性暴力の問題に取り組む。
岩本菜々(いわもと・なな)
一橋大学大学院社会学研究科修士課程在籍。NPO法人POSSE代表。
安田浩一(やすだ・こういち)
ジャーナリスト。『ルポ 差別と貧困の外国人労働者』(光文社)『地震と虐殺 1923-2024』(中央公論新社)など。
――先日の参院選では、参政党を中心に、排外主義的言説がさかんに喧伝されました。差別の現場でたたかう四人に論議していただきます。
金澤 東京大学の学部四年生で国際関係論を専攻している、金澤伶です。いまは、東京都や愛知県で、日系ブラジル人の方を生活から雇用までサポートする会社で正社員として働いてもいます。学生時代を通じて、難民、移民という背景を持った友人たちと団体を運営し、そうした人たちがどのような人生を送っているのかを知ってもらう啓発活動などをずっと続けてきました。難民フェス、写真展、シンポジウム、アイデアコンペティションなど多岐にわたります。
クルド人やアフリカのルーツなどの、仮放免の状況にある高校生の奨学金プロジェクトにも関わり、メンタル、受験、進路などの相談や、教育機関、文科省や入管庁との交渉などもやっています。国籍や在留資格を問わず、「教育を受ける権利」を守るために日々、活動しています。
崎浜 慶應義塾大学法学部法律学科四年生で、憲法を勉強している、崎浜空音です。
私は沖縄出身です。琉球人という先住民としての権利があるなかで日本に植民地化され、皇民化政策によって日本人にさせられた。その先住民の地にある米軍基地、日米地位協定から発生する問題、性暴力などについて、私はずっと問題提起をしてきました。私が米兵や米軍について何かを言うと、「じゃあ移民はどうなんだ」「移民の人たちが治安を悪くしてるじゃないか」という反応が絶対に返ってきます。琉球人のアイデンティティを持つ者として、自分は日本人と言われるのも何か違う。だから、移民は排除しろ、という言葉を耳にすると、複雑な感覚になるんです。
私が米兵の性暴力を問題にするとき、その人を人種で判断して攻撃していると捉えられているのでしょうね。まったく違う問題なのに。私のなかでも、人種や属性で勝手に区別されていく問題は、伝え合うのも、理解し合うのも難しいことだと感じています。
岩本 一橋大学大学院修士課程で貧困問題について研究し、NPO法人POSSEの代表もしている岩本菜々です。
POSSEは、移民などの国籍に関係なく、貧困や労働の問題に陥っている人の支援や、そのなかでの調査、実態告発をしている団体です。もともとは、ブラック企業や非正規雇用が蔓延するなかで「使い捨て」にされる若者の労働・若者の貧困問題に取り組み、さまざまな調査や支援をしてきた団体でした。そこから20年のあいだに、外国人労働者や、家計から自立して働く女性が増え、若者を中心とした問題が全般化していったので、私たちの支援の範囲も広がっていきました。
コロナ禍初期は日本国籍の人でも職や家を失った人が一気に増え、私はひたすら生活保護の申請同行をしていたんです。そのなかで、支援団体の仲間から、川口市ではクルド難民の人たちがいよいよ生活の基盤を失って困窮していると聞いて。かれらは生活保護を受けられず、支援も薄い。放置しちゃいけない問題だと、支援活動に加わることに。生活保護の適用を求めて行政へ申し入れ、食料の配布、若者の学習支援などを週に一回ほど、開催しました。
安田 ジャーナリストの安田浩一です。2005年からは、外国人労働者、とりわけ技能実習生を中心とする非正規労働者を取材しています。いわゆる送り出し国、受け入れ国双方の「人間キャッチボール」のような事態に驚愕し、この問題に深くコミットするようになりました。
私が週刊誌の記者だった時代は、雇用の流動化を社会がものすごく熱狂的に受け入れ、その裏で非正規雇用の増加が進んでいた。それに伴って、今度は外国人が安価な労働力として使われていく現状を目の当たりにしたんです。
この問題は技能実習生だけではありません。日系ブラジル人などの取材で静岡県や愛知県、岐阜県といったところに行くことも多かった。そうした現場でもやはり、技能実習生と同じ構造、つまり完全労働者ではなく安価な労働力として外国人を見ていくという、企業の立ち位置がありました。だから、必ず経営者を取材するんです。
技能実習生はなぜ、時給300円で、休みなく働かされているのか。なぜ、パワハラやセクハラに耐えなくてはならないのか。そういうことをきくと経営者の多くからは、「外人だから」という答えが返ってきた。
外国人は賃金が低くて当たり前だし、日本人より下に見て当たり前、酷使してもかまわない。そんな言葉のシャワーを浴びた。これは個々の経営者の属人的な問題ではなくて、社会の構造の問題なんだ、これは雇用の問題ではなくて、差別の問題なんだと強く意識するようになりました。
いまの参政党と同じくらい露骨な人種差別団体は、今世紀はじめくらいから可視化されてきた。その差別の現場では、外国人だけではなく、国内の特定の地域や先住民族、障害者などへの差別も誘発されています。崎浜さんがおっしゃった沖縄に対する差別もそう。だから、沖縄、琉球に向けられたいわゆる「本土の視線」も取材しはじめた。
岩本さんがおっしゃったクルド人については、クルド人に問題があるわけではなく、「クルド人問題」を作りあげている側の問題として、いま非常に気にかけています。ほぼ毎日、埼玉に通うだけでなく、実際にトルコまで行って、クルド人がなぜ日本に来るのかといったことも含めて取材をしているところです。
私はあくまで取材者という上っ面のかたちではありますが、今日集まった金澤さん、崎浜さん、岩本さんのそれぞれが深く関わっておられることに、関心をもって触れつづけてきました。みなさんが見ている風景を想像することくらいはできるかなと思っています。
SNSという差別の現場
金澤 私も、埼玉周辺に住んでいる、難民や移民の背景をもつ子どもや家族に会いに行くことが多いんですね。支援というよりは、年の近い信頼できる友人の一人として接するということを大切にしています。
あるクルド人の姉妹は、SNSにアップした写真を盗用され、2万人もフォロワーがいるようなアカウントに、デマとともに拡散されてしまった。こういう差別の言説がSNSを中心に流布されるのは、差別の収益化と、差別者のやったもん勝ちの構造ができてしまっているから。差別もヘイトスピーチも、デマの拡散も、罰せられることはほぼない。罰してもらうには、お金をかけて弁護士を雇い、民事などに訴えるような体力が必要だし、当事者ばかりにその負担を負わせてはいけません。
多くの人が、フォロワーが言っている、それを新聞やテレビが取り上げた、というようにデマが権威化し、あたかも真実であるかのように扱われていく。非対称的に当事者は声を上げられないから、正しい情報はあまり拡散されない。私がいくら反論しても、「それはお前がクルド人の味方をしているからだ」「むしろテロリストを支援している側だ」と陰謀論みたいなことを言われてしまう。陰謀論に染まって、私の関係先に迷惑電話をかけてくる人もいました。
仮放免で在留資格のない状態で長く暮らしてきたクルド人の方は、20年ほど付き合いのあった人から突然、参政党支持を表明され、「あなたは噓つきだ」と非難されたそうです。仲がよかったはずの友人から、いきなり「早く日本を出ていけ」と言われるなんて、もう泣くしかありません。ネットの言説の影響は現実を大きく侵食し、その逆もありますし、ネットと現実は分けて語れなくなっています。
崎浜 私もSNSでは嫌な言葉ばかり言われます。弁護士を目指しているのですが、「お前みたいな土人は弁護士に絶対なるなよ」みたいに、何回も「土人」という言葉を使って誹謗中傷する人がいて、めちゃくちゃしんどかった。その人は、「土人」という言葉が私たちにとってどういう言葉なのかもわからないし、意識もしていないと思うんです。でも私は、この言葉がこれまでに何度も問題になっていることを知っているから、何が問題なのかを論証し、私の言い分が正しいことを裁判官に認めてもらうために、本人訴訟で開示請求をして、損害賠償請求に動いています。
開示請求に対してX(旧Twitter)の代理人弁護士は、「土人という言葉は誹謗中傷にあたらない」といった反応を返した。職務的な対応であることはわかっていても、差別を肯定する言葉を弁護士からされたのは、本当にキツかった。
安田 いまは、クルド人に対しても、ネット上で「土人」という表現をする人が少なくありません。
沖縄について、1903年に大阪で行なわれた内国勧業博覧会の人類館をふと思い出しました。人類館のパンフレットには「七種の土人を用意しました」といった意味のキャッチフレーズが書いてあり、その一種として琉球人が生きたまま展示された。120年以上前から、差別と偏見の眼差しが沖縄に向けられてきたということです。
これはけっして昔話ではない。それがはっきりしたのは2016年の高江です。大阪府から派遣された警察官が、ヘリパッド建設工事に反対する沖縄県民に対して、「土人」「シナ人」などと叫んだ。
つまり、ありとあらゆる差別がパッケージにされているんです。沖縄の人もクルド人も、差別者からすると全部同じ仕掛けで、同列に結ばれている。そうやって誰かを差別し、叩くことが、120年以上前から日本社会でしっかりと定着してしまっている。