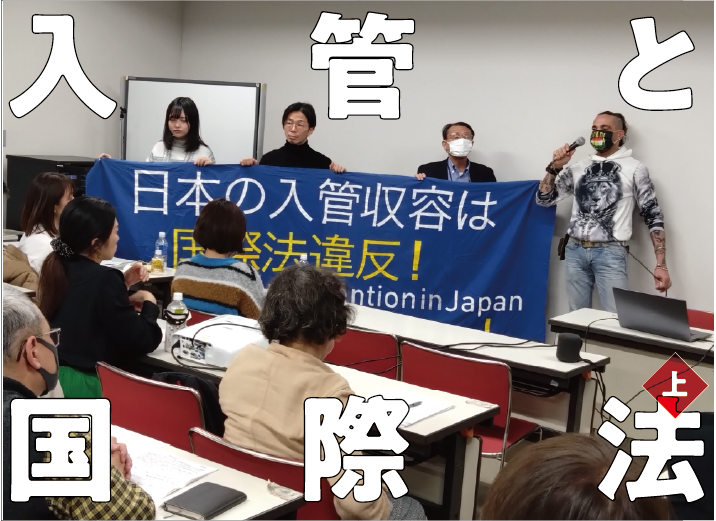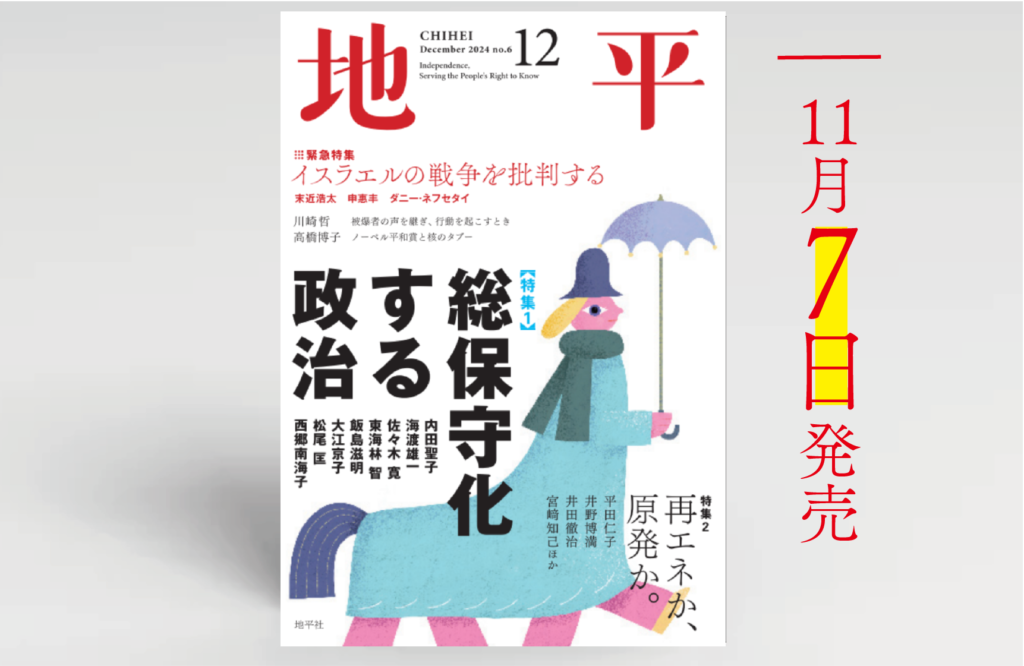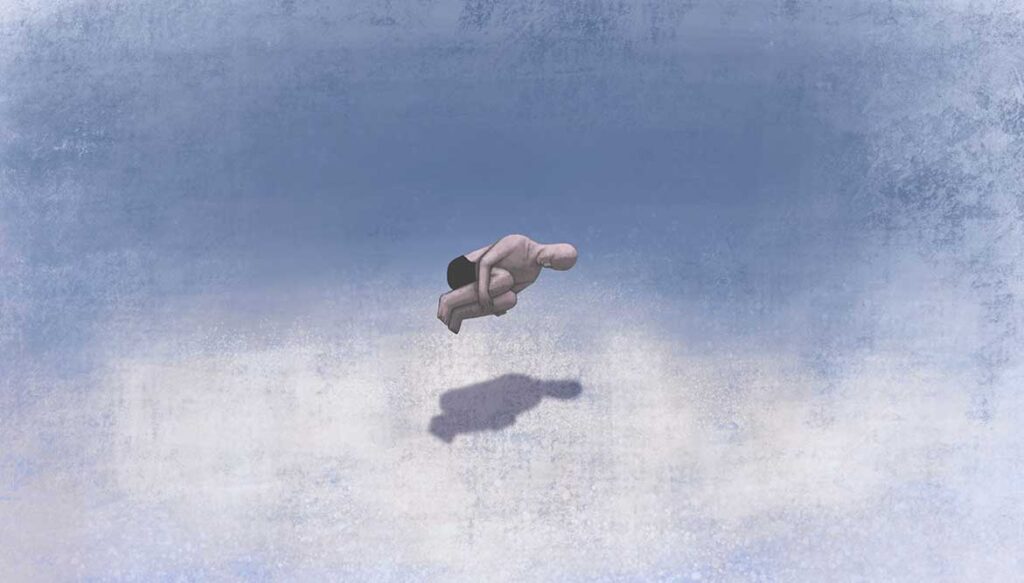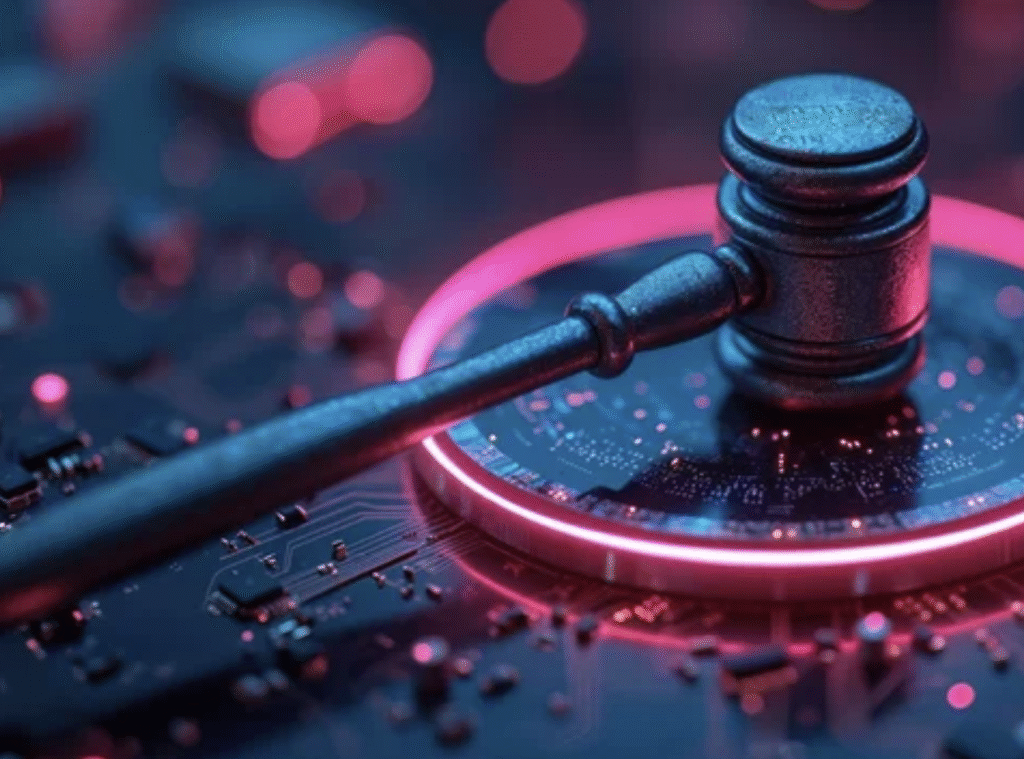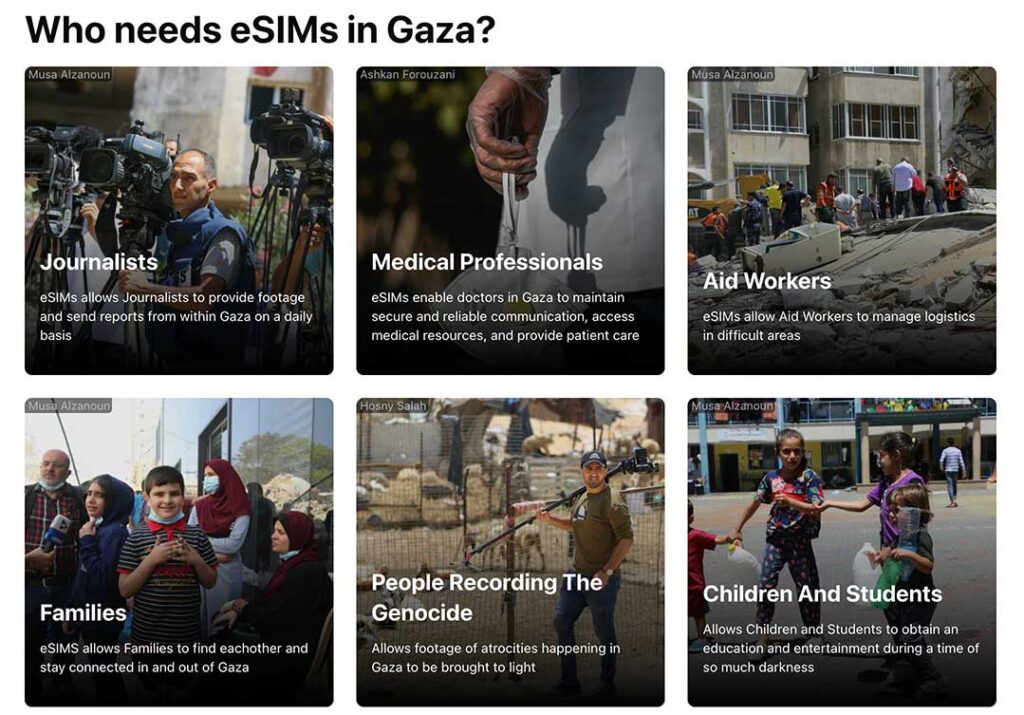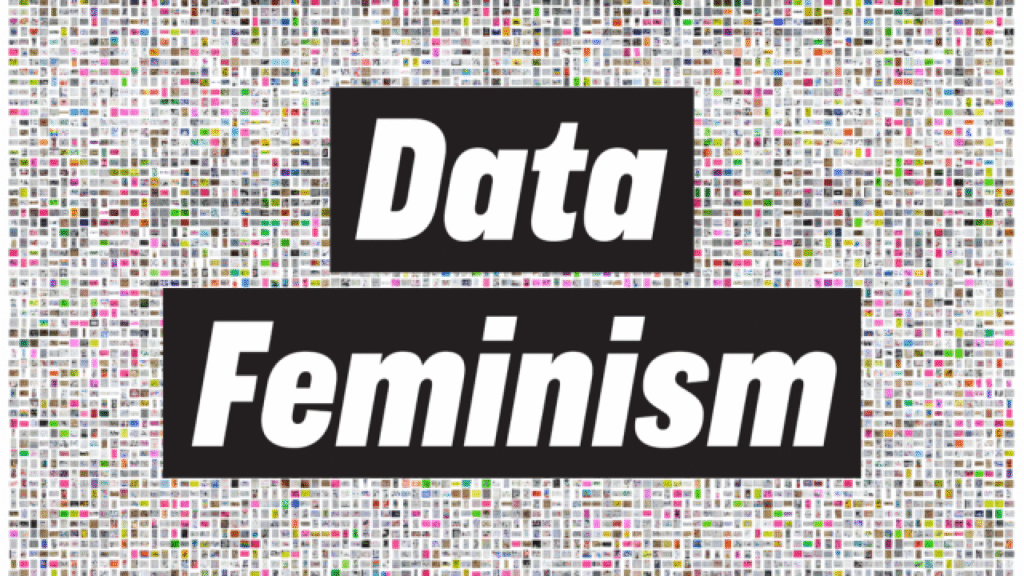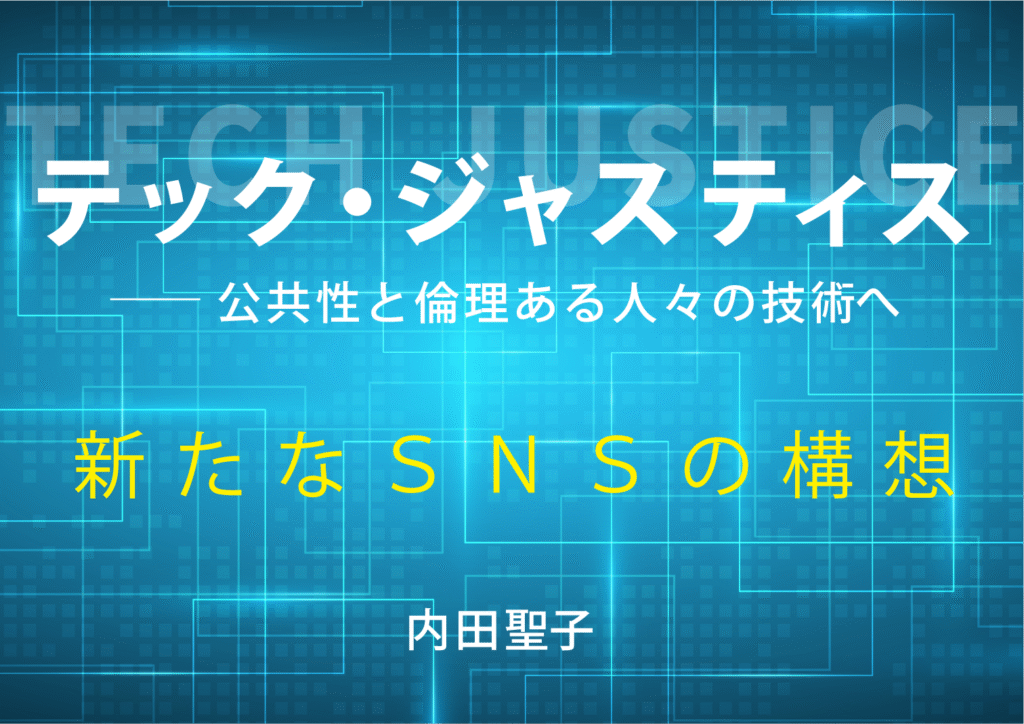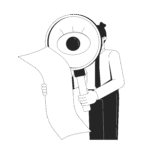・ネット空間の検閲を望んでいるのは誰か(中)──独立した団体を装うメディア
・ネット空間の検閲を望んでいるのは誰か(下)──過剰な脅威に潜る官製ファクトチェック
表現規制を求める世論を誇張した朝日新聞
2024年の憲法記念日の朝日新聞朝刊1面トップ記事がどのようなものだったか、ご記憶の方はいるだろうか。恒例の憲法に関する世論調査について、次のような大見出しで報じていた。
「SNS規制『必要』85% 本社世論調査 選挙に偽情報影響『心配』82%」
筆者は、この記事に大きな衝撃を受けた。
世論調査の結果に対して、ではない。従来リベラルメディアの筆頭とみられ、憲法上の人権保障の価値を強調してきたはずの朝日新聞が、あたかも多くの国民がSNS上の偽情報等に対処するため表現規制を求めているかのような「社会の空気」を作り出そうとする紙面展開を行なったことに対して、である。
まず、この見出しを含めた報じ方である。ファクトチェックの手法によって検証すれば、「ミスリード」と判定されても致し方ないようなものだった。
1面記事の冒頭は次のように書き出していた。
ソーシャルメディアで交わされる情報について、朝日新聞社が実施した全国世論調査(郵送)で規制が必要かどうか尋ねたところ、「必要だ」という回答が85%に達した。
その後、選挙の際に偽情報で影響を受けることや誹謗中傷に懸念を示した人がいずれも8割を超えたことに言及した上で、次のように報じていた。
規制の必要性については、憲法が「表現の自由」を保障していると前置きして質問した。それでも規制が「必要だ」が85%に上り、「必要ではない」が11%と少ない。
ここまで読めば、「偽情報や誹謗中傷に対処するため、法規制を求めている人が85%もいる」という印象をもつ人が多いのではないだろうか。
だが、これは誤解だ。別の紙面に掲載された質問と回答の詳細を確認すると、こうであった。
◆憲法は『表現の自由』を保障しています。ソーシャルメディアで交わされる情報について、健全さを確保するには、一定の規制が必要だと思いますか。
必要だ85 必要ではない11
◇(「必要だ」と答えた人に)では、そうした規制をかけるには、次の二つでは、どちらで対応するのがよいと思いますか。
ソーシャルメディアの事業者などが自主的に対応する30〈25〉▽法律で対応する67〈57〉
〈 〉内の数字が全体に対する比率だ。つまり、「事業者などの自主的な対応」も含めて「SNS規制『必要』85%」という見出しで報じていたが、「法律」による規制が必要だと答えた人は全体の「57%」だったのだ。
85%という圧倒的多数が法規制を求めているとなれば、表現規制の口実になりかねないことには、考えが及ばなかったのだろうか。
虚偽の救助要請の本質を見誤る政府とメディア
こうした報道の背景には、偽・誤情報問題に対する関心の高まりがある。たとえば、2024年元旦に能登半島地震が発生した際には、SNS上の虚偽の救助要請などの偽情報の拡散が注目された。発災翌日、岸田文雄首相が記者会見でじきじきに「悪質な虚偽情報の流布は、決して許されるものではない。こうした行為は厳に慎んでほしい」と述べた。SNS上で偽の救助要請が救助の妨げになっている、と多くのメディアで報じられもした。新聞の社説は「ネットの虚偽情報 救助活動阻む投稿一掃を」(産経新聞1月6日)、「SNSと偽情報 社会守る取り組みが急務」(毎日新聞1月14日)、「能登地震のデマ 悪質投稿 許さぬために」(朝日新聞1月27日)など、相次いで対策の必要性を訴えた。
だが、政府の呼びかけ方や一連のメディアの取り上げ方をみていると、問題の本質を見誤っているのではないかと思えてならない。
第一に、SNSの偽情報が現実に与えた悪影響、救助活動の支障となるような実害がどれほどのものだったのか、検証されていない点だ。
救助要請は119番通報が原則だ。消防も警察もSNS投稿をチェックして出動するかどうか判断しているわけではない。投稿を見た第三者からの通報で、無駄な出動を余儀なくされるケースはあり得るが、実際にはそれほど多くなかったとみられる。共同通信によれば、消防が出動したケースが2件、警察が出動したケースも複数件あったという。偽の投稿をした埼玉県在住の20代の男が偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された事例も一件あった。「旦那が足を挟まれて出られません」というXの投稿を見た人が、知人に頼んで市役所に通報。県警機動隊による捜索が行なわれたという。しかし、本当に助けを求めているなら、市役所に通報するだろうか。このアカウントの主は過去の投稿から男性の可能性が高いという指摘も出ていた。発災から半年以上経ってからの逮捕で、テレビでも実名で大きく報道されたが、数日後に釈放された。見せしめ目的の逮捕だった可能性がある。
SNSを契機とした虚偽通報で救助活動が妨害された事例がどれほどあったのか、総務省消防庁に情報公開請求したが、そうした事例を確認した文書はないとのことだった。もちろん、災害時に意図的にデマを流すこと自体が不謹慎で、許されないのはいうまでもない。それとは別に、現実への影響は冷静に分析する必要があるのではないか。
第二に、本来は本人か関係者が通報すべきもので、SNSでの救助要請にはらむ問題が指摘されていない点だ。