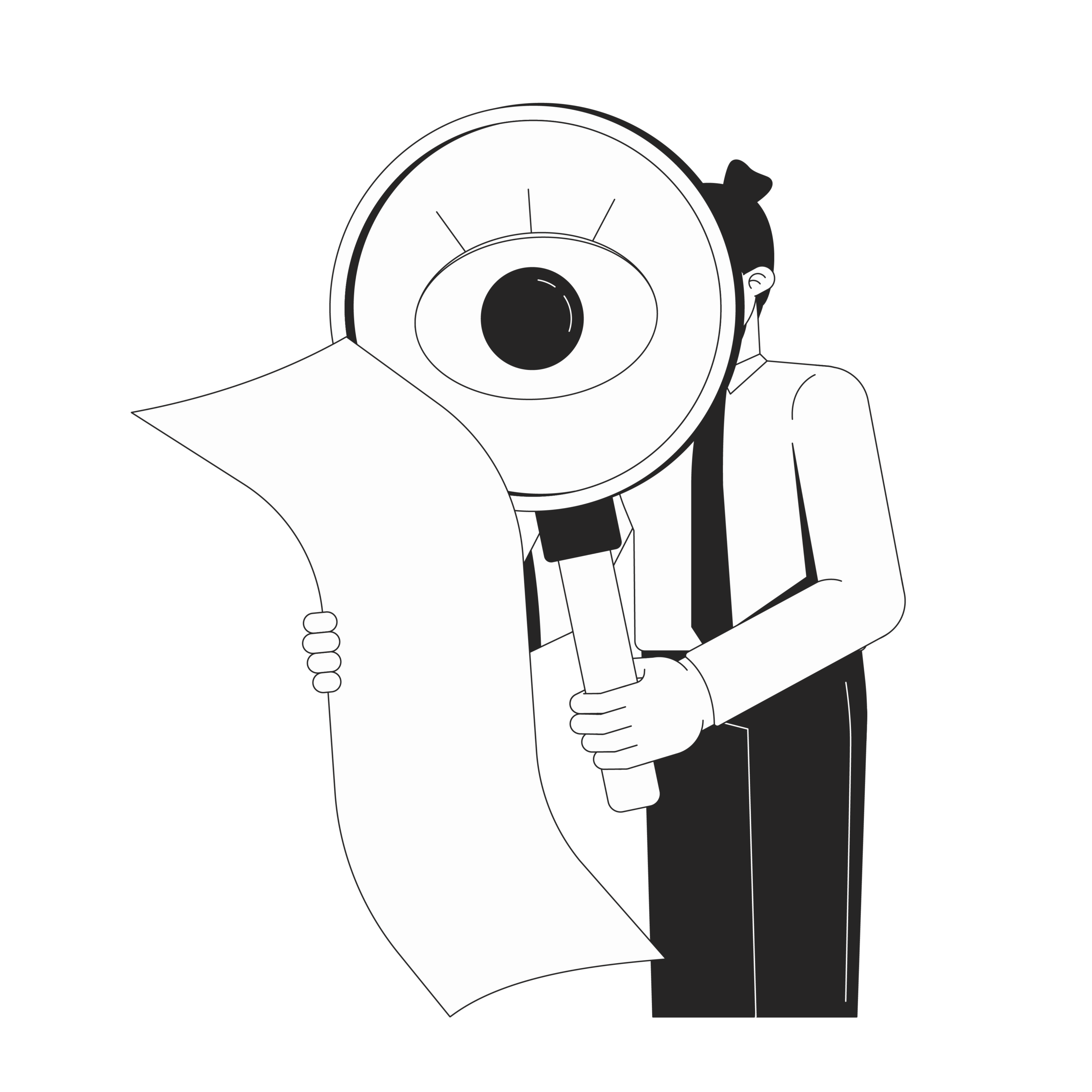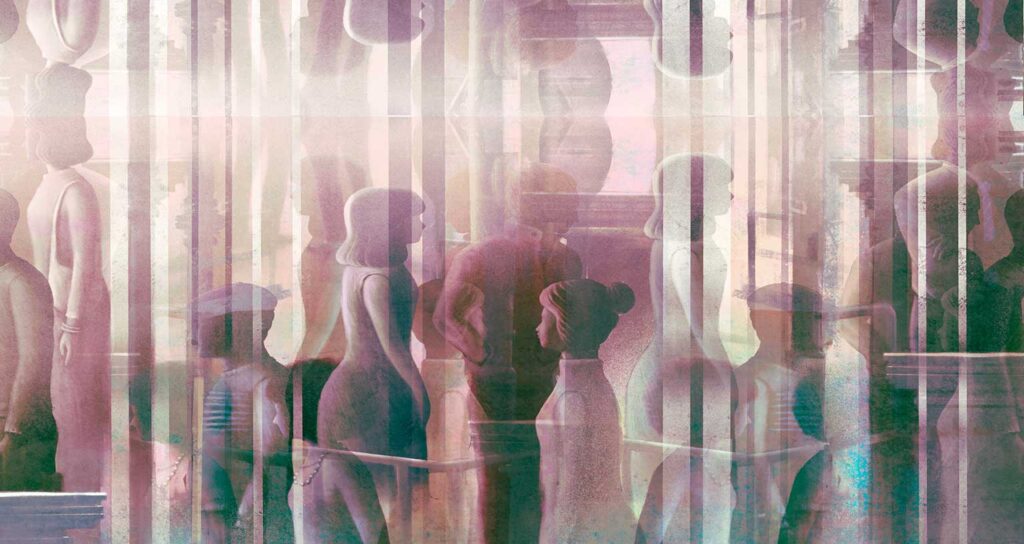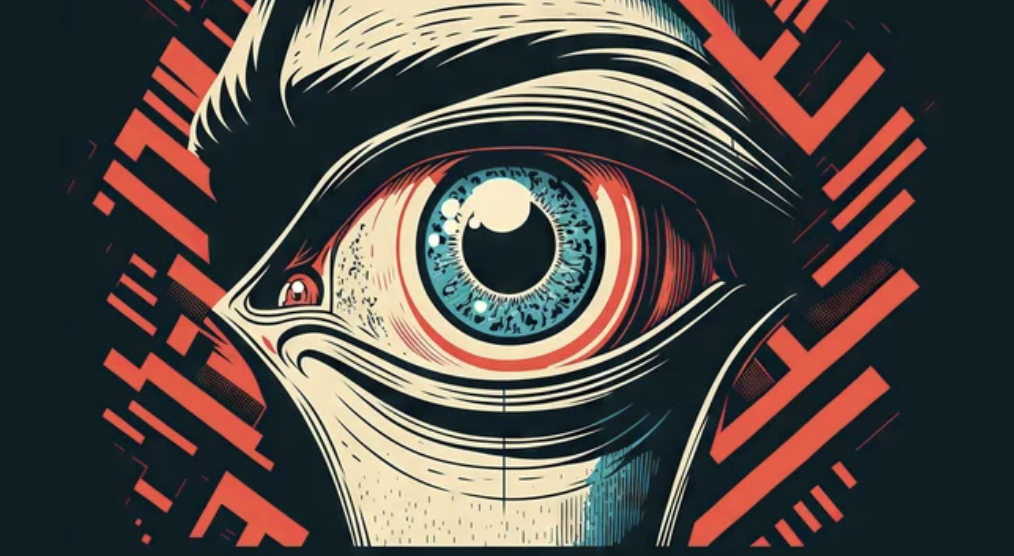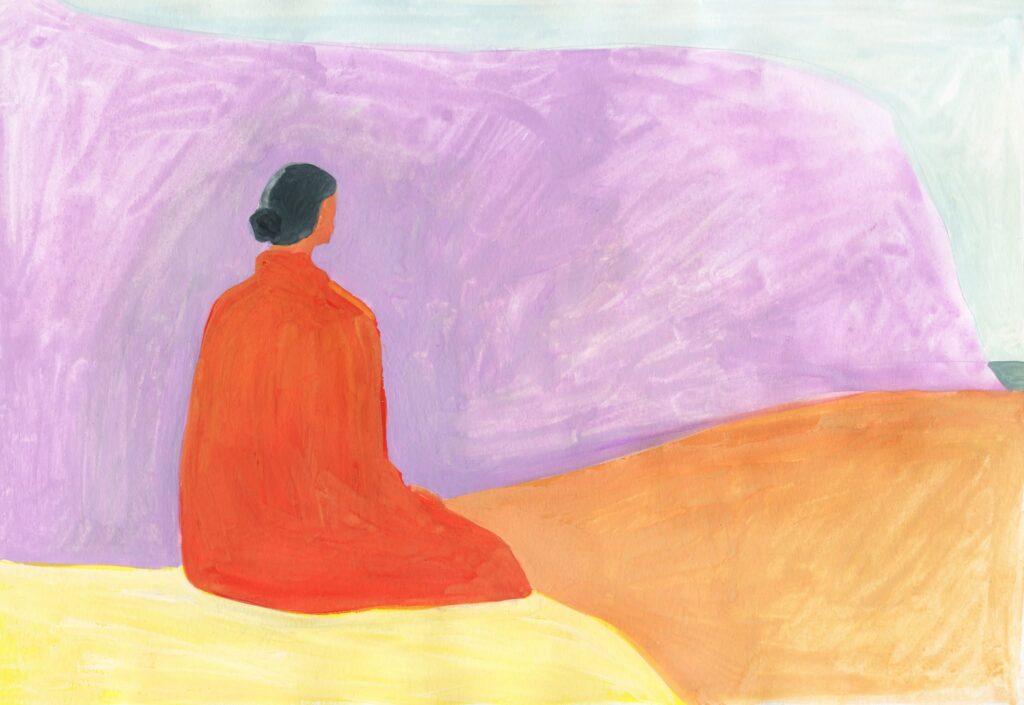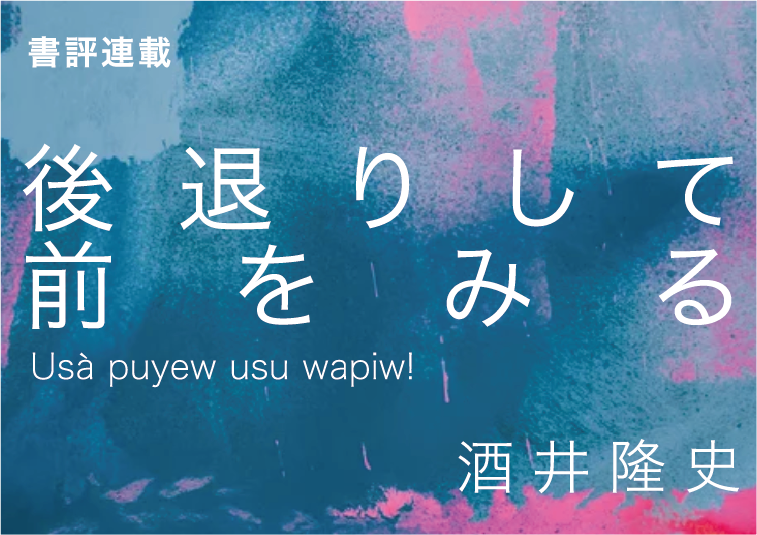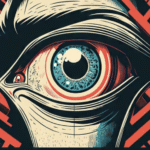読売が投じた一石
今年、メディア業界でファクトチェックの議論に一石を投じたのが、これまで消極的だった読売新聞だ。
日本新聞協会で選挙報道の在り方を議論している「選挙報道研究会」で、協会としてファクトチェックに取り組むことを提案したからだ。全国の新聞社・通信社・放送局が加盟する協会として、各社の社論の違いを超えた取り組みの構想は画期的だった。複数の社が賛同したが、「訴訟や抗議があった時に協会として対応できるのか」「各社で立ち位置が異なる中、共通してファクトチェックできる言説がどれほどあるのか」などの異論も出て、研究会では合意に至らなかった。
そこで、読売は「有志社によるファクトチェック」を協会加盟社に呼びかけた。ファクトチェックに必要な経費の大半を読売が負担し、ファクトチェック専門のネットメディア「日本ファクトチェックセンター」(JFC)から助言を受けながら進めるという内容だった。最終的に日本テレビ、時事通信、佐賀新聞の3社が賛同し、「6月13日告示の東京都議選から、選挙に関してインターネット上に流れている情報を対象に共同でファクトチェックを実施する」と6月4日に発表した。
新聞協会も6月12日、「インターネットと選挙報道をめぐる声明」を出した。加盟社が「選挙報道の在り方を足元から見直し、国際的なファクトチェックの手法なども参照しながら、有権者の判断に資する確かな情報を提供する報道を積極的に展開していく」と宣言するものだ。読売の提案を一部受け入れる形で、加盟社が行なったファクトチェックの記事を集めて公開するX(旧ツイッター)のアカウント「選挙情報の真偽検証 新聞協会」の運用も始めることになった。
「読売新聞社など有志四社が共同でファクトチェックに乗り出すことに、与野党からは歓迎の声が出ている」(6月5日読売)――。鳴り物入りで始まったが、6月13日からの2カ月間で出たファクトチェックの記事は次の3本だ。
○都議選の投票で鉛筆を使うと書き換えられる?→誤り(6月20日)
○選挙の開票前なのに午後8時に当確が出るのはおかしい?→誤り(6月26日)
○外国人に事実上の「生活保護」は憲法違反?→不正確(7月15日)
富山県のニュースを集めたページに掲載された「『小麦は食べるな』『ロシアと仲良し』…真偽不明の情報を政党や候補者に聞いて検証してみた」(7月7日)、「富山選挙区 候補者の主張するデータに注目 税金や防衛費などファクトチェック」(7月15日)という読売独自の記事を含めても、参院選の期間中に「読売新聞オンライン」に掲載されたファクトチェックの記事は3本にとどまった。
参院選後の7月23日には「石破茂首相は退陣する意向を固めた。米国との関税交渉が妥結し、最大の懸案に解決の道筋が付いたことを受けて決断した。月内にも退陣を表明する方向で調整する」と号外を発行する。石破首相本人が「そのような発言をしたことはない」と否定し、逆に読売報道がファクトチェックの検証対象になってしまった。しかし、「月内」の期限が過ぎ去って石破首相が退陣の意向を示さなくとも、読者への説明はなく、ファクトチェック報道も止まっている(8月25日時点)。