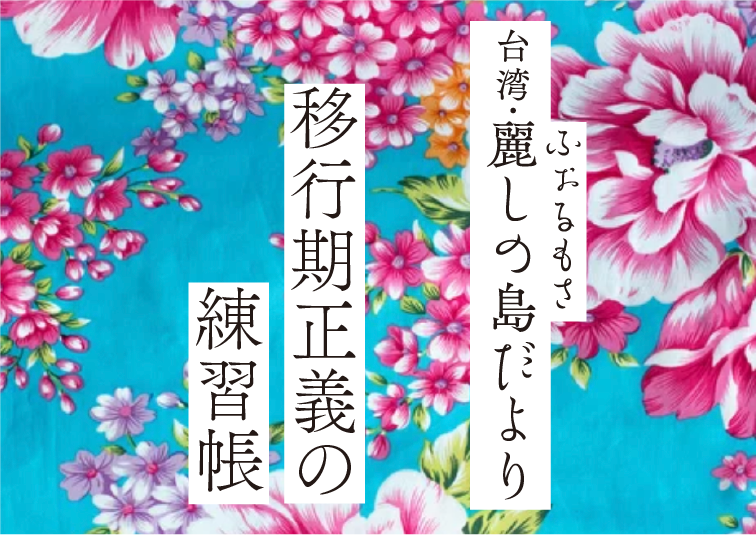〈移行期正義(Transitional Justice)〉
過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、真実を追求して責任の所在を明確にすると共に、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスのこと。
これまでの記事はこちら(連載:台湾・麗しの島〈ふぉるもさ〉だより)
現代アートの展覧会――歴史的事件の交差点
台湾の現代アートでも「移行期正義」は大事なテーマだが、ここ数年でとりわけ心に深く残っているのが《浪のしたにも都のさぶらふぞ》という展覧会である。
このタイトルは、『平家物語』に登場する壇ノ浦の有名なシーンから来ている。平氏が源氏に敗れ、幼い安徳天皇が祖母の二位殿に「わたしをどこへ連れていくのか」と問うと、祖母は「海の底にも都がございます」と答えて天皇とともに壇ノ浦に入水する。下関市にある赤間神宮はこの安徳天皇を祀っており、竜宮城のような赤間神宮の社殿から鳥居を見ると、その向こうに一行が身を投げたとされる現場が見える。神宮の奥の院には平家一門の墓もある。
壇ノ浦とは、瀬戸内海と日本海の潮がぶつかる関門海峡にあり、重要な歴史の舞台となってきた。壇ノ浦の戦い、宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の決闘、長州藩と英・仏・蘭・米が戦った馬関戦争……。「台湾と源平合戦、なんの関係が?」と不思議に思われるかもしれないが、日清戦争のさいに、清国から日本へと台湾「割譲」を取り決められた日清講和条約は、赤間神宮に隣接する料亭「春帆楼」にて調印された。下関の海を挟んだ向かい側は、福岡県北九州市の門司である。関門トンネルが開通するまえ、門司港は九州鉄道の始発点であり、日本の玄関口でもあった。台湾と門司港を内台航路が結び、台湾から運ばれたバナナのうち黒ずんだ荷は門司港で卸され、露店商が「バナナのたたき売り」をした。これは今も伝統芸として残り、歌詞には台湾が日本の植民地であった記憶を留める。そして、台湾における日本植民地時代の主要産業として発展した「砂糖」が台湾から門司へ運ばれたことで、台湾の製糖拠点のひとつであった雲林県の虎尾(フーウェイ)と門司は結ばれていた。
製糖工場と、ある祖母との記憶
そうした製糖業を横糸に、目の回るような発展を現代まで続ける科学や映像技術を縦糸にして、植民者/被植民者、支配/被支配という関係の複雑さを織り上げ、台湾と日本にまつわる近代化の記憶を見つめたのが本作である。
虎尾では、日本統治期に「大日本製糖」(現・DM三井製糖ホールディングス)がサトウキビ農園と製糖工場を築き、工場を中心とした近代的な街が発展した。ここで生産された粗糖は船で福岡県門司へと運ばれ、門司大里の工場(現・関門製糖)で精製糖となり全国へ出荷されていた。
第1部では、ポテヒの伝統音楽を奏でる音楽隊や、製糖工場で戦前に使われた機械や廃材と工場空間に張られた鉄線を用い、工場そのものを楽器として響かせる現代音楽家の姿がスクリーンに映し出される。「歴史を奏でる」のは誰なのか。工場全体から生みだされる不協和音が、虎尾の過去と現在を交差させる。








.jpg)