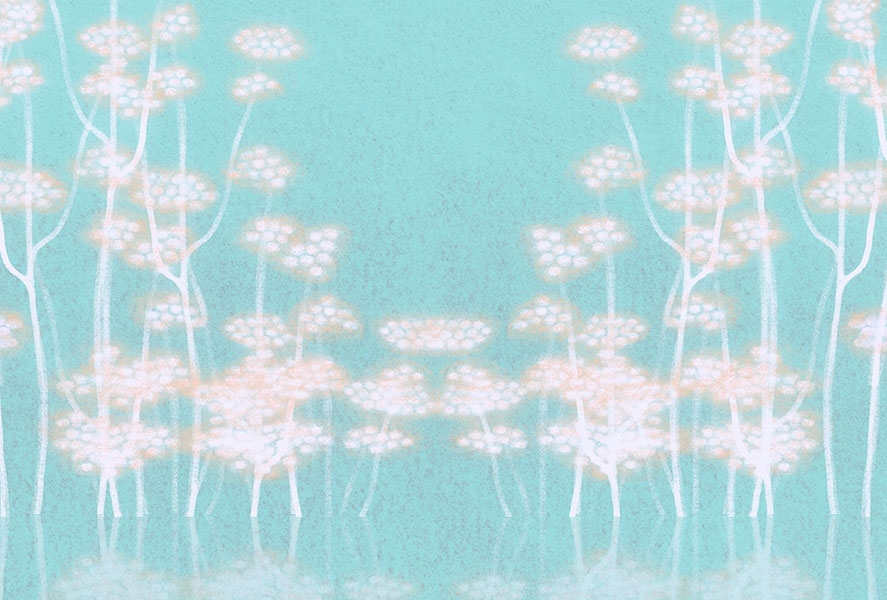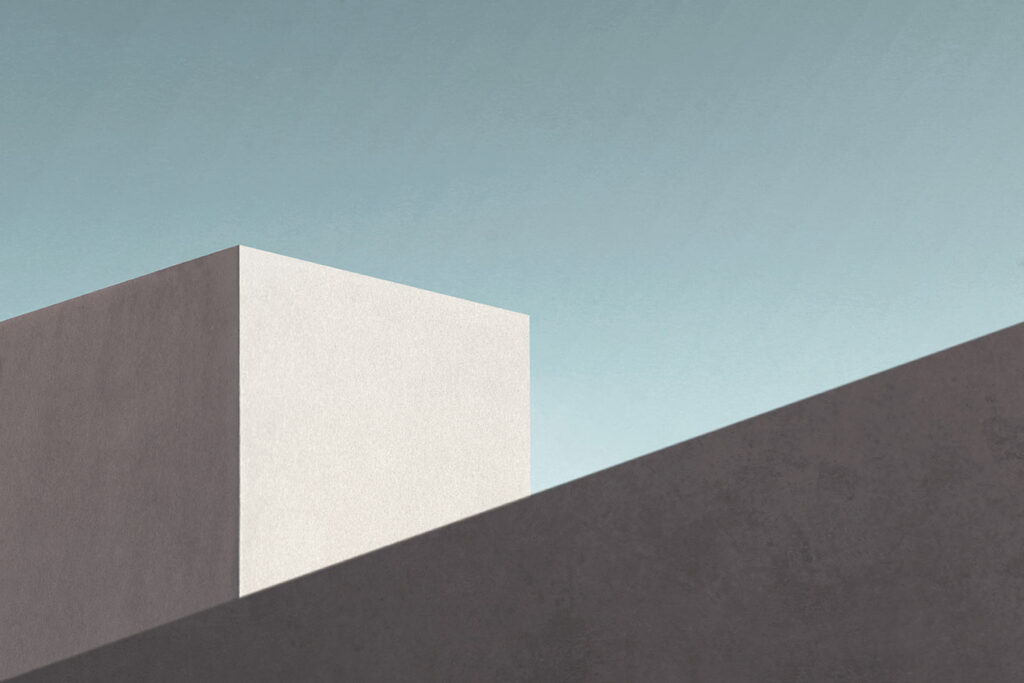【関連】「特集:加害と和解ーー東アジアの不再戦のために2」(2025年12月号)
アウシュビッツ収容所の生存者にお会いしたことがある。5歳に満たない頃、ワルシャワ蜂起に加わったとして家族ごと拘束され、親と引き離されて収容されたポーランドの方だ。子ども専用バラックにはそんな子どもたちがひしめいていた。親たちは別の区画に収容され、あるいは殺された。
その老婦人は部屋に入るにもしばらく躊躇し、ようやく語り始めても、話はたびたびのため息と涙で中断された。
私は会場となった施設を管理するカトリックの尼僧に尋ねた。
「あの方は、忘れたい過去を見ず知らずの東洋人たちに語らされて、おつらいのではないでしょうか」
「いいえ、語ることは治療なのです。今夜あの方はぐっすり眠れると思います」
そう答えた尼僧は、他の証言者の例も教えてくれた。その老人は、付き添いの息子にきつい口調で何度も促されながら、声を絞り出すように語るのだという。
「息子さんは、お父さまの心のリハビリのために証言活動を勧め、サポートしているのです。今日は遠路、証言を聞きに来てくださってありがとうございました」
『夜と霧』の著者ヴィクトール・E・フランクルは、初版の訳者霜山徳爾氏によると、濃いブラックコーヒーを立て続けに飲むこととチェーンスモーキングでかろうじて心の平衡を保っているようだったという。フランクルは強制収容所で人間が見せた崇高な姿を透徹した観察眼で記録し、世界に読者を持ち、精神医学の分野でも一家をなした。戦後2人目の伴侶を得て、相互の信頼のうちに満ち足りた私生活を送った。そんなフランクルにとってさえ、2年8カ月に及ぶ収容所体験のPTSD、心的外傷後ストレス障害は克服できる何かではなかった。それは、脳の機能を一部不可逆的に変質させてしまう、文字通りの外傷性後遺障害だった。
人間としてありうべからざる仕打ちを受けた人の心の傷は一生癒えることがないのだ。
「花岡は第二のふるさと」
花岡事件の生存者もそうだ。10年以上前には、毎年の慰霊式に生存者たちが参列した。彼らは戦争末期、日本国内の労働力不足を補うために捕虜収容所から、あるいは畑仕事の最中に日本軍によって連行された3万8935人の中国人のうち、秋田の花岡鉱山に連れてこられた986人の中の生き残りだった。彼らは極寒の中、1日12時間の河川工事を強いられた。乏しい食事と粗末な衣服、非衛生な宿舎、皆無の医療、そして監督者たちのすさまじい暴力のために、ばたばたと死んでいった。
1945年6月30日の集団脱走は、人間の最後の尊厳を守るための企てだったろう。たんに生き延びるためなら、足手まといになる弱者は度外視して、逃げる力のある者だけで決行するのが理にかなっている。しかし彼らは、歩くのがやっとの衰弱し切った者も含めて一人の仲間も見捨てず、全員で行動した。これが、脱走が彼らの尊厳をかけた戦いだったことの証だ。ちなみに、ナチスのソビボル収容所やアウシュビッツ第五クレマトリウムの蜂起も、全員の脱出を企図していた。