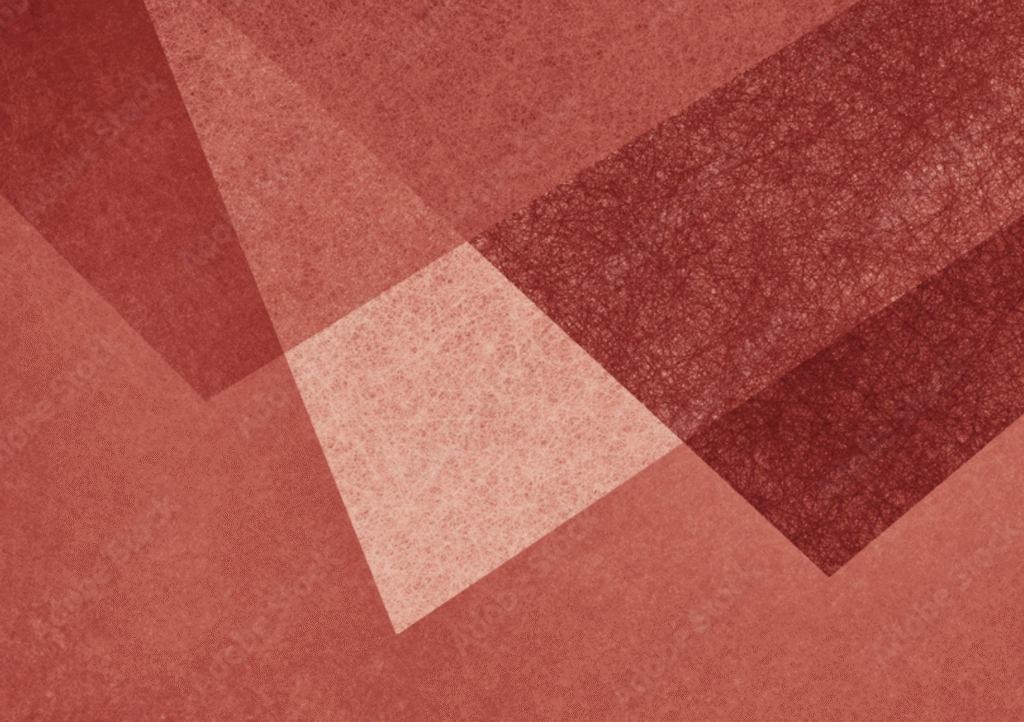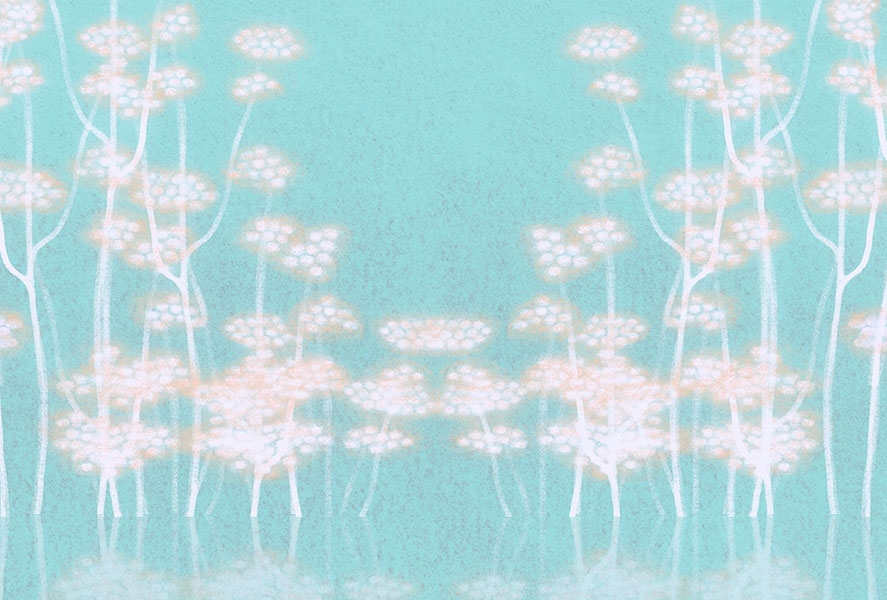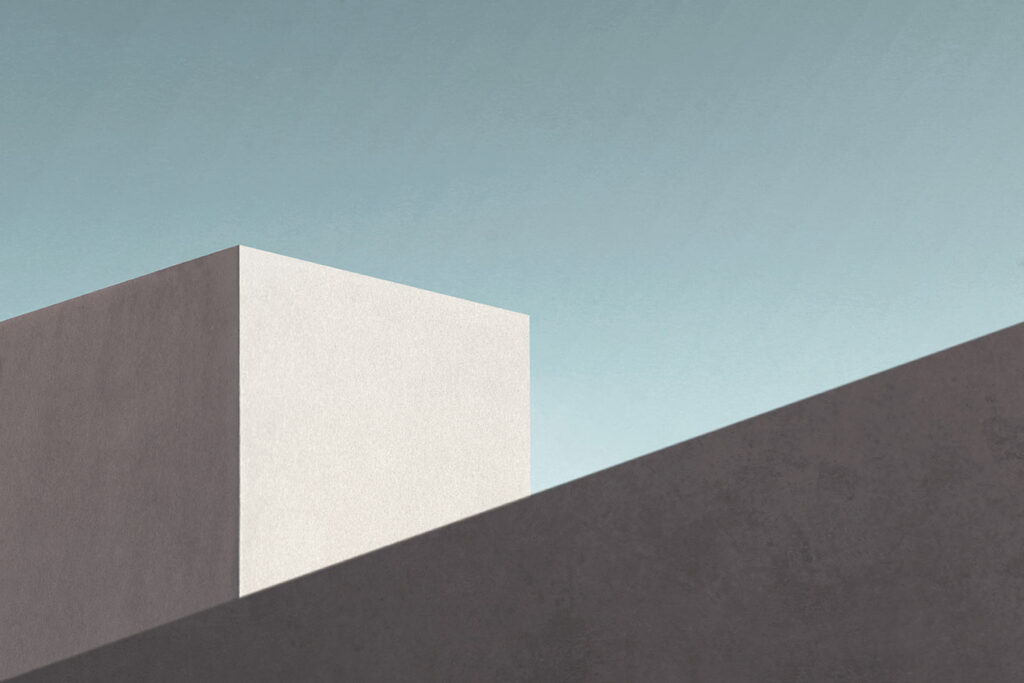【関連】「特集:加害と和解ーー東アジアの不再戦のために2」(2025年12月号)
【関連】【長生炭鉱】「犠牲者に会いにいく――暗い坑道の先へ」安田浩一(ノンフィクションライター)
【関連】「ルポ 長生炭鉱――海底に眠る朝鮮人遺骨」安田浩一(ノンフィクションライター)
今年8月、山口県宇部市の長生炭鉱をめぐるニュースがメディアで盛んに報道された。戦時中の事故で183人が犠牲になった後、坑道は閉鎖された。事故後80年以上海底に放置されていた遺骨を、地元の市民団体が独力で探し出し、収容したのだ。戦没者の遺骨収容史はもとより、戦後補償史全体においても画期となる出来事だった。本稿では市民団体の活動の経緯とこれまでの成果、日本政府の責任や今後の課題について触れていきたい(敬称略、年齢取材時)。
ため息と、怒声が混じる集会となった。2023年12月8日、国会内で開かれた市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」(刻む会)と、厚生労働省など政府側との意見交換会だ。「現時点での調査は困難」。厚労省の担当者はそう繰り返した。「まず、どんな調査ができるのか考えるべきではないか」「水中ドローンを使ったらどうか」。会場からそうした声が上がった。厚労省の担当者は、遺骨が地上の本坑口から1㎞程度先の海中との見通しを示した上で、「ドローンが届くのは200m程度で難しい」などと否定的だった。
会場からは「それならばまず、200mから調査をすればいい」「日本人の遺骨も含まれている」などの強い声が上がった。
参加した約100人の中には、韓国遺族会会長、楊玄(ヤンヒョン)(76)がいた。20歳だったおじの楊壬守(ヤンイムス)を亡くした。
「日本政府には心からの謝罪と、犠牲者の遺骨を発掘して故国への奉安を強く望んできましたが、何の返事もありません。良心と人権と人道主義という言葉が通じない政府でしょうか。悔しく、もどかしく、怒りを感じます。1日も早く過去の汚点に謝罪して遺骨を発掘し故郷で永遠に眠りにつけるよう再度お願いします」などと話した。
だが厚労省は、「調査は困難」との説明を繰り返した。「政府に長生炭鉱の遺骨調査をする気はない」。傍聴していた私は、そう感じた。
戦時下の事故で183人が犠牲に
1942年2月3日朝。山口県・宇部、瀬戸内海の海底に延びていた長生炭鉱では海岸からおよそ1㎞沖で坑道が崩落し、労働者183人が犠牲となった。うち136人は朝鮮人労働者だった。事故後、坑口は塞がれ遺体も遺骨も海底で眠るままとなった。
米英などを相手とした「太平洋戦争」が始まってから2カ月。石炭は、戦争まみれの大日本帝国にとって欠かせない戦略物資であり、国策として増産を目指していた。民営の長生炭鉱では、安全性より採掘拡大を重視した無理な採掘が行なわれた。過酷な現場には当時日本に植民地支配されていた朝鮮人の労働者が多かったことから、「朝鮮炭鉱」とも呼ばれていた。敗戦後は自然消滅した(登記簿上は1974年に抹消登録された)。
事故から約半世紀が過ぎた1991年、地元の有志が「刻む会」を結成した。「水非常」とは、炭鉱用語で水没事故のことを指す。刻む会は地元でも忘れられつつあった事故を後世に伝えるべく、関連資料の発掘や生存者と遺族らへの聴き取りを進めた。同年秋には韓国の遺族との交流も始まり、「韓国遺族会」も結成された。
2013年には、事故現場の海岸近くに二基からなる追悼碑を建立。一基に「日本人犠牲者」、もう一基に「強制連行 韓国・朝鮮人犠牲者」と記された。費用の1600万円は市民からの募金だった。
刻む会には、達成感があった。活動としては「一区切り」のはずだった。しかし、遺族の気持ちは違った。追悼碑の除幕式で韓国人遺族が、刻む会のメンバーに言った。
「これで終わりじゃないですよね。私たちは遺骨を故郷に持って帰りたい」
その言葉を聞き、同会の共同代表を務める井上洋子(75)は思った。「遺骨を探し出して、それぞれの故郷に帰っていただく。そこまでが私たちの責任なのだ」。追悼碑建立はゴールではなく、新しいスタートとなった。
海底の坑道には多数の遺体や遺骨が残っていると考え、ダイバーを雇って海中調査を行なったものの、坑道の内部に入ることはできなかった。土に埋もれた坑道も探し出すべく、専門業者に頼んで地中レーダー探査も行なった。1993年からは毎年2月3日もしくは近い日、韓国からの遺族を招いて追悼式も開いてきた。
慰霊行事を続けていたが、海底の遺体や遺骨を収容するまでの道は遠く、入り口すら見えない状態だった。
刻む会は日本政府との交渉を進め、政府による調査・収容を依頼した。しかし、政府は動かなかった。その一端が、冒頭に見た政府との交渉だ。厚労省の担当者は「遺骨の具体的な場所が明らかでないことなどから、現時点での調査は困難」との主張を繰り返すばかりだった。
遺骨調査を始めた市民団体
筆者はこの2023年の政府交渉を取材していた。刻む会の許可をもらった上で、厚労省にこう質問した。「硫黄島では滑走路の下を、遺骨があるかどうか分からない状況でも地中レーダーを使って調査した。長生炭鉱は遺骨がある可能性が極めて高いのに、調査さえしない。推進法に鑑みて整合性はどうなのか」。メディアの取材者として、本来は当事者同士のやりとりを聴く立場だが、厚労省の言い分があまりに理不尽で、その理不尽さを会場にいる多くの人に知ってもらいたいと思ったからだ。
東京都小笠原村の硫黄島は、太平洋戦争末期の1945年2月から3月にかけて日米両軍が激突。日本軍守備隊およそ2万人が戦死した。後述する、戦没者遺骨収集推進法成立にともない、政府は硫黄島での遺骨収容を進めるためプロジェクトチームを作り、遺骨が埋まっているかどうか分からない場所でも調査を行なっていた。なぜ長生炭鉱では調査を行なわないのか。法律上の整合性がとれていないのではないか。筆者はそう問うたのだ。