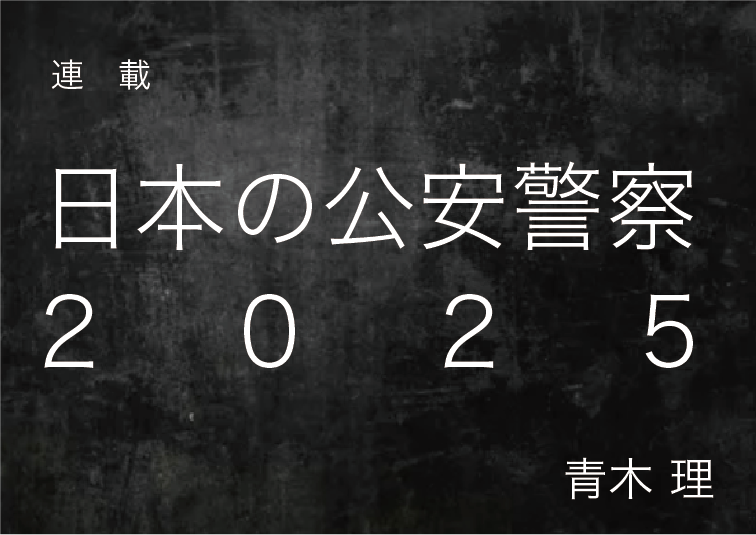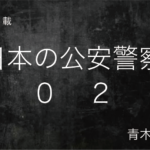日本の公安警察──四半世紀後の更新にあたって
私が『日本の公安警察』(講談社現代新書)を上梓したのは2000年の1月だった。筆名を使わずに書いた初めての単著ではあったが、そこそこのベストセラーとなって評判を呼んだ。いや、いまから考えれば、この手の書籍としては相当な売れ行きだったというべきかもしれない。
理由はいくつかあったろうが、最大のそれは存外、単純だったように思う。類書がなかったから。警察組織の一翼に位置する強大な治安機関だというのに、難解な学術書や一部好事家向けの少部数本などを除けば、警備・公安警察の全貌を総覧しつつ、組織や活動の内実をそれなりに深く抉った一般書が存在しなかったのである。
当時、フリーライターの永江朗氏が、ある雑誌でこんな書評を書いている。
〈1月20日、『日本の公安警察』が出版された。これはひとつの事件である。なぜか。まず、この本は公安調査庁や内閣情報調査室まで含めて、日本の公安の全貌と実態を描いている。しかも、出版社は天下の講談社。それも講談社現代新書というメジャーなシリーズの一冊である。値段はたった680円。従来、この種の本といえば、零細な左翼系出版社から出て、少部数発行であるから必然的にいくぶん高い値段で売られ、巨大な書店の隅に置かれるのみだった。それが堂々の大量部数発行である。そしてなにより「事件」なのは、この本の著者が反体制運動の活動家でも学者でもなく、現役の新聞記者であることだ。それも、66年生まれの33歳と若い〉
早いものであれからもう25年、つまりは四半世紀もの時が経過し、私も同じ歳月の年を重ねてしまった。一方、『日本の公安警察』もいまだに版を重ね、細々とではあるけれど売れ続け、現時点で26刷に達している。こちらも理由はおそらく簡単、やはり類書がないからである。
もちろん、この四半世紀の間にも、たとえばエンターテインメント小説等々が公安警察を作品の舞台にしたり、ノンフィクション系の作家や記者、ジャーナリストを名乗る者たちがその内実をもっともらしく記したり語ったり、公安警察組織のOBや元警察官僚らが自身の体験を回顧したり、そういった類の書籍は幾冊も世に放たれてきた。だが、そうしたものの大半は公安警察を妙にヒロイックに描いたり、過大視したり過小視したり、あるいは批判的視座が皆無だったり、要はジャーナリスティックに組織の実態や問題点を抉り出す書籍はほぼ皆無に近い。
だから、もはや“古典”の部類に属するかもしれない拙著が版を重ねているのだろうが、しかし、これは決して望ましいことではない。実際、あれから四半世紀もの時が過ぎ、公安警察という組織の本質的な性癖に変わりはなくとも、組織機構には幾度かの改変や再編が加えられ、活動の内容も実態もかなり変貌、または拡充してきている。と同時に、社会の情報環境等も大きく様変わりした。
2000年当時は、せいぜい携帯電話の普及が本格化していた程度で、スマートフォンに象徴される携帯用IT機器等は登場しておらず、インターネットだって現在ほど一般化してはいなかった。畢竟、こうした情報環境の激変に公安警察組織がどう対応しているか、各種情報ツールをどのように利用しているか、または利用していないかについて、当然ながら拙著では一切触れられていない。だが、利用=悪用されていないと考えるほうがどう考えても不自然かつ能天気に過ぎる。では、現在の公安警察組織はそうした情報ツール等々を情報収集や監視活動にどう利用=悪用しているのか。
正直にいえば、若き日の私が書いた稚拙な面もあるルポルタージュを、いずれ後輩記者らがバージョンアップさせて上書きしてくれるのを私自身、ひそかに期待はしていた。だが、現時点でその気配はない。ならば、可能な範囲内でその役目を私が果たしてみようか、そう考えて今号から何度かにわたって本誌に連載リポートを寄せることにした。