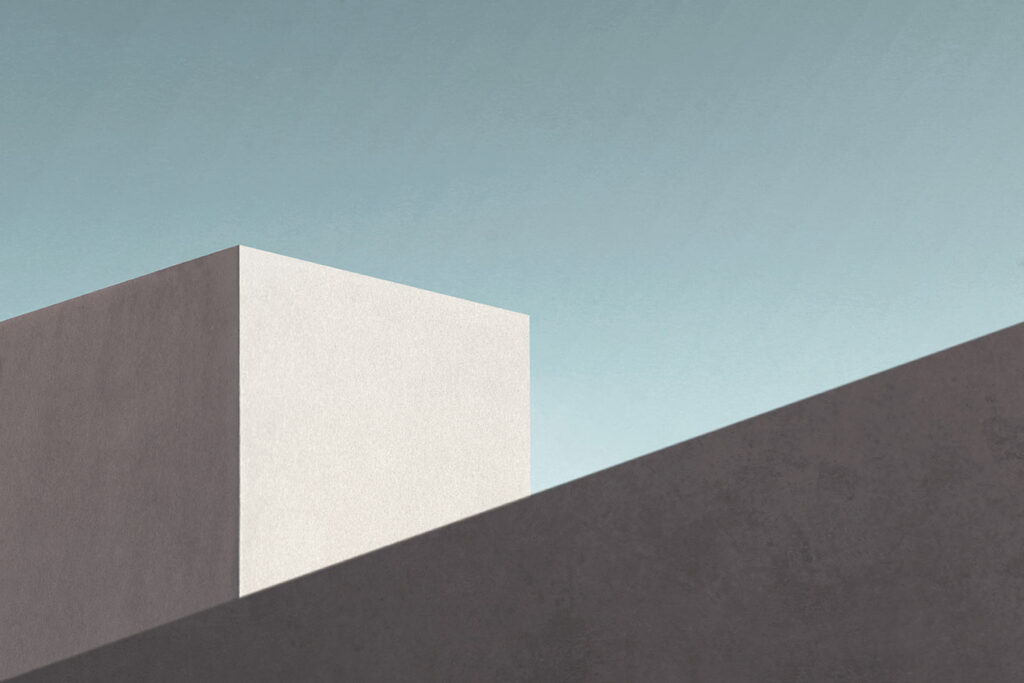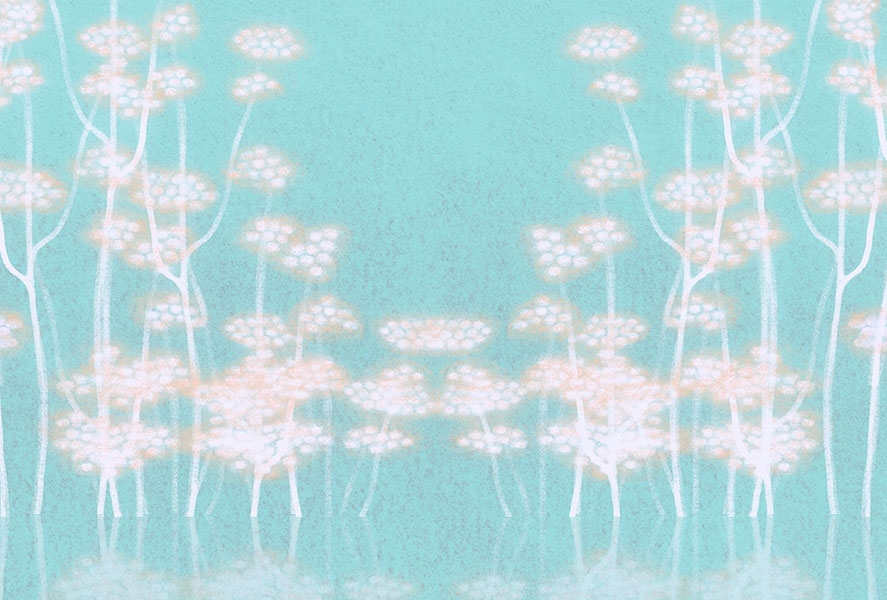【関連】「特集:加害と和解ーー東アジアの不再戦のために2」(2025年12月号)
2025年は、多くの意味で記念すべき節目の年である。それは単なる「戦後80周年」という節目にとどまらず、戦後日本政治史における転換点としても記憶されうる年である。7月に実施された参議院選挙で自公連立政権が多数議席を失い、排外的言動で注目を集めるポピュリズム政党の参政党が大きく議席を伸ばした。石破茂前首相は、全国戦没者追悼の日に内閣総理大臣談話を発表する意向を示したが、党内保守派の強い反発に遭い、最終的には10月10日に個人としての「戦後80年所感」を発表するにとどまった。10月4日に行なわれた自民党総裁選では、極右的立場で知られる高市早苗が当選。その後、公明党の連立離脱や、与野党間の離合集散といった紆余曲折を経て、高市は日本維新の会や他の保守勢力の支持を得て、21日に実施された首相指名選挙で内閣総理大臣に選出された。
一方、中国では、6月24日に国務院新聞弁公室が記者会見を開き、中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事の全体計画を発表した。その中では、抗戦勝利記念閲兵式(9月3日)を含む10項目の主要議程が示され、80周年記念の基調を定めた(1)。同時に、戦後80周年という重要な節目を迎えるにあたり、中国側は日本政府の動向――とりわけ「80周年首相談話」の有無など――にも細心の注意を払ってきた。
(1) 「抗戦勝利八〇周年記念活動十項安排公布」、中国新聞網、2025年6月24日
戦後80周年という節目の年、本来であれば中日両国の学術界、言論界、さらには政府間においても、より多様な形での交流が展開されえたはずである。しかし、右傾化とポピュリズムが政治を巻き込む状況のなかで、日本は戦争の記憶や歴史認識の問題において中国との距離をますます広げており、歴史和解は依然としてはるか彼方にある。
2つの「80周年」
今年は戦後80周年にあたるが、日本国内での関連記念行事はこれまでに比べてはるかに少なかった。国会や政府による例年通りの公式行事(たとえば「全国戦没者追悼式」など)のほか、NHKなどのテレビ局が8月15日に合わせて戦争関連のドキュメンタリーを放送する程度であった。「終戦記念日」は全体として静かに過ぎ去り、今後も毎年8月15日がこのように穏やかに経過することが1つの「新常態」となるのかもしれない。
注目すべきは、石破首相が全国戦没者追悼式での式辞の中で「反省」という言葉を用いたことである。これは民主党政権の野田佳彦首相(2012年)以来、13年ぶりに日本の首相が同式辞の中で「反省」という語を復活させた例となった。ただし、その「反省」の対象はアジア諸国への加害ではなく、日本が戦争に至った過程そのものに向けられたものであり、この点は10月10日に石破本人が発表した「所感」とも通じる部分があった。
一方の中国では、本稿冒頭で触れた各種記念行事が予定通り開催された。南京大虐殺や七三一部隊を題材とする映画が次々と公開され、9月3日には抗日戦争勝利記念の閲兵式が盛大に行なわれ、「静かな日本」との鮮やかな対比をなしている。
中国でのこれらの記念行事をめぐって、日本国内では「反日的だ」との批判も聞かれた。しかし実際にはそうではない。たとえば習近平国家主席の閲兵式での演説は簡潔明瞭であり、「抗日戦争」という固有名詞を除けば、演説の中で特に「日本」に言及することはなく、それを世界反ファシズム戦争という大きな歴史的文脈の中に位置づけていた。仮に批判があるとしても、それは日本の軍国主義者に向けられたものである。もし日本政府が自らを軍国主義者の後継とみなすのであれば、それこそ日本側が自省すべき問題であり、中国を非難したり、各国に圧力をかけて指導者や高官の訪中・記念行事出席を妨げたりする理由にはならない。