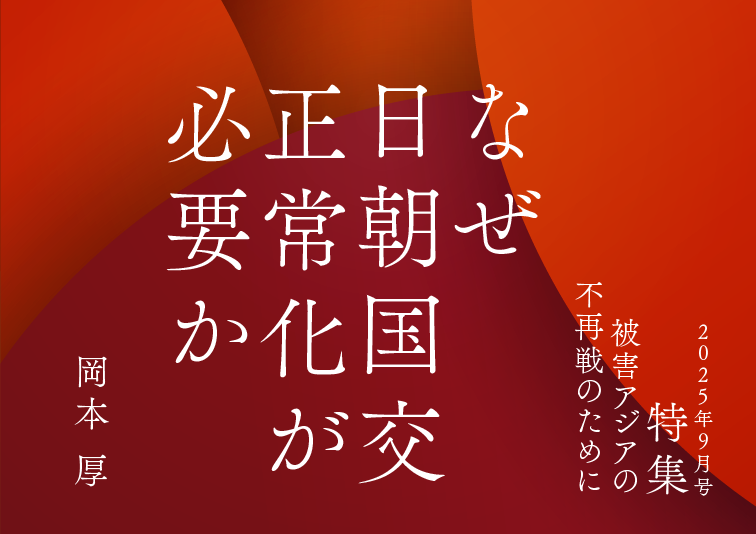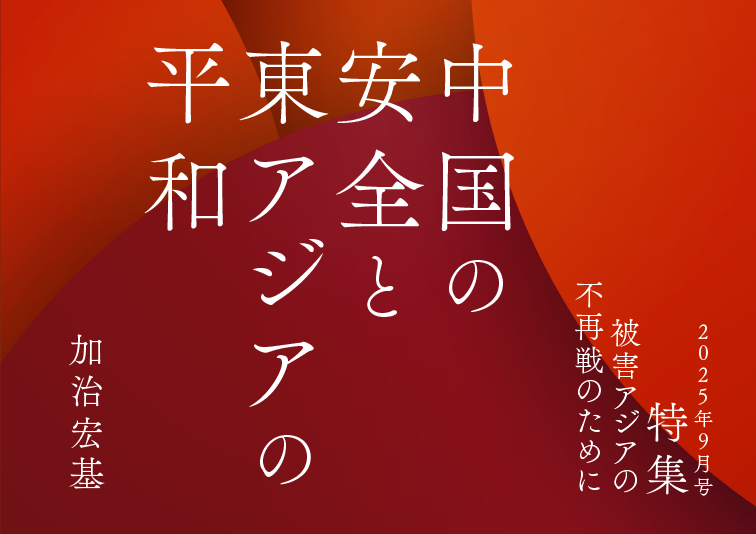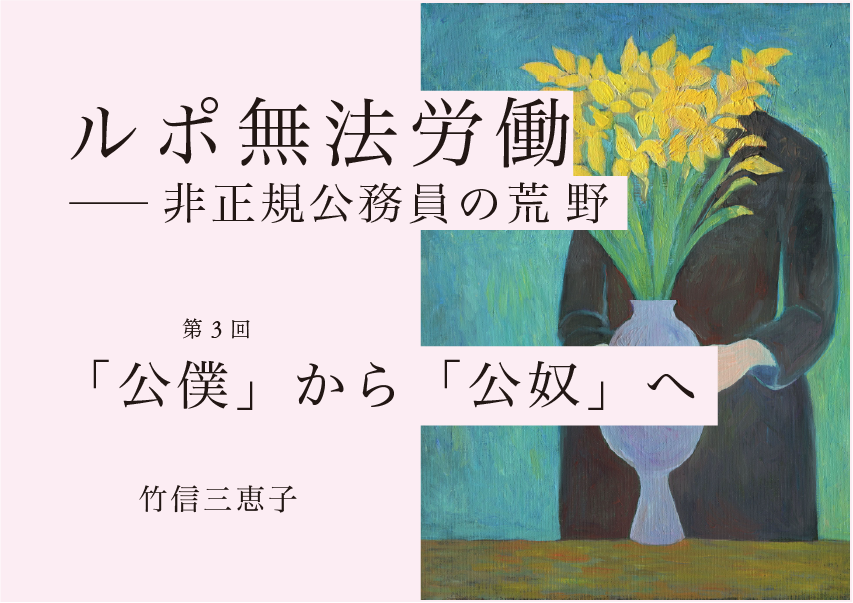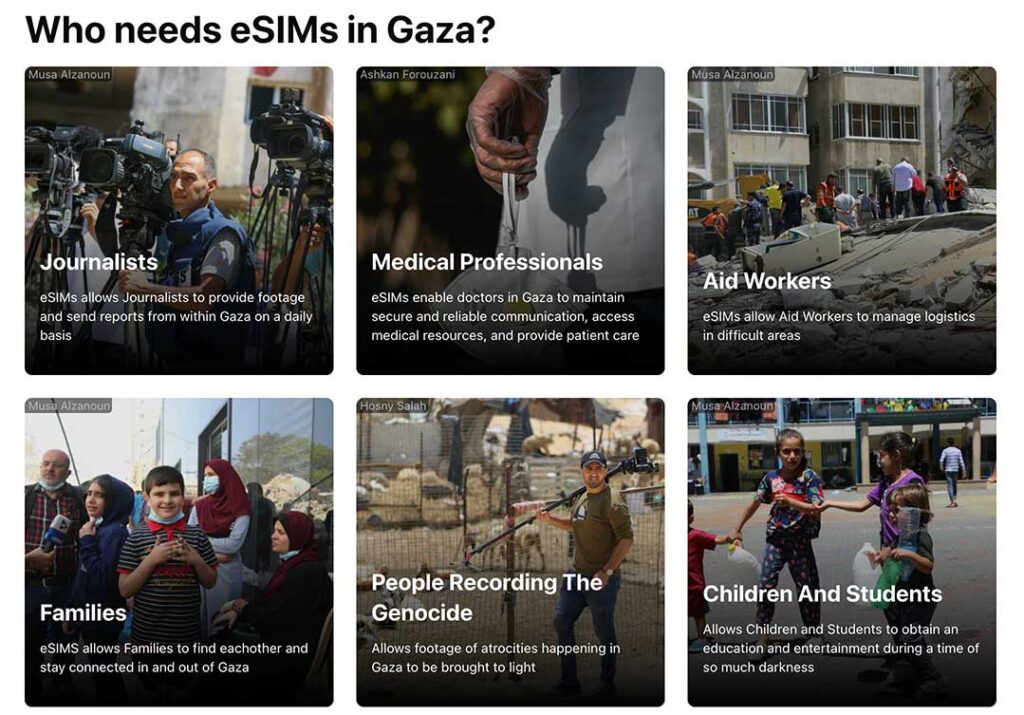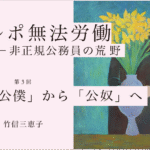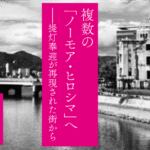特集:東アジアの不再戦のために
今年2025年は、敗戦80年であり、韓国との国交を正常化した日韓条約締結60年に当たる。韓国では、昨年12月の非常戒厳発令以後の政治的混乱が李在明新大統領の就任で収まりつつあり、日韓間で首脳会談も行なわれた。
日韓の間には、60年前の国交正常化のときとは桁違いの経済的、文化的、市民的な交流が活発に行なわれており、とりわけ若い世代においてはこれまでの位相を超えた相互交流が行なわれている。その意味では、当初両国ともに様々な懸念を抱かれた日韓国交正常化は、実り多く、結果的に成功したと言えるかもしれない。
日韓国交正常化が行なわれた1965年は、米ソ冷戦のまっただ中であり、ベトナム戦争などアジアに戦乱が続いていた。日韓条約には冷戦とアジア戦乱の影が色濃く反映していた。日本は1910年、当時の大韓帝国に韓国併合条約を強要し、敗戦の1945年まで36年間、朝鮮を植民地統治した。日本のくびきを脱した朝鮮は独立したが、北部はソ連の影響下に「朝鮮民主主義人民共和国」として、南部は米国の影響下に「大韓民国」として成立することになった(1948年)。本来ならば、日本は植民地として統治した朝鮮全体との和解と新たな関係の構築を目的として、国交正常化を行なわなければならなかったはずである。
しかしこの両国は相手を敵視し、1950年、武力統一を求めて朝鮮戦争を始めた。日本を占領していた米軍が韓国を支援して参戦し、日本も米韓軍に協力した。韓国のみとの国交正常化は、ある意味で当然の成り行きであった。
問題は、独立した朝鮮の新国家と国交を結ぶには、まず日本が植民地支配を反省し、謝罪し、補償することが不可欠であったのに、当時の日本には、植民地支配を「悪いこと」と認識し、反省する気運はまったくなかったことである。それは政府だけでなく、メディアも、市民も含めてである。そして国際社会も、植民地支配を行なっていたかつての列強帝国主義国が、戦後もなお植民地支配を継続しようとし、各地域の民族解放勢力を弾圧し、激しい戦争を戦っていた。
日本側があくまで植民地支配の非を認めず、それに加えて韓国側が親米反日の李承晩政権であったこともあり、1951年に始まった国交正常化交渉は長く実を結ばなかった。1960年の学生革命で李政権が倒れ、翌年軍事クーデタで朴正熙が実権を握ってから、急速に交渉が進み、65年の締結に至った。その背景には米国の冷戦政策があった。日本は植民地支配の反省をしないまま、韓国の軍事政権は植民地支配の補償や賠償ではなく「経済協力」の形を取るという妥協を強いられた。韓国併合条約の「無効」については日韓が別々の解釈をとることになった(日韓基本条約第2条)。一方、朝鮮半島における南北の対立と敵対関係もここに持ち込まれた。韓国の地理的範囲の問題である。当時、韓国は自らを朝鮮半島唯一の合法的な政府と主張し、日本は韓国の統治権はあくまで国連監視下で選挙が実施された南半分に限定されると主張した。ここでも解釈は別々とした(日韓基本条約第3条)。
条約締結後、60年にわたり、冷戦に歪められた日韓条約は改められることはなかった。しかし、いまその歪みを改める機は熟しているのではないか。条約の解釈問題について、私たちは昨年11月にシンポジウムを開き、今年1月に声明を発表して問題提起した(日朝韓三国平和を考える会ウェブサイト参照)。ここでは、日本と朝鮮半島の北部――朝鮮民主主義人民共和国――との国交正常化に焦点を絞って論じることにしたい。