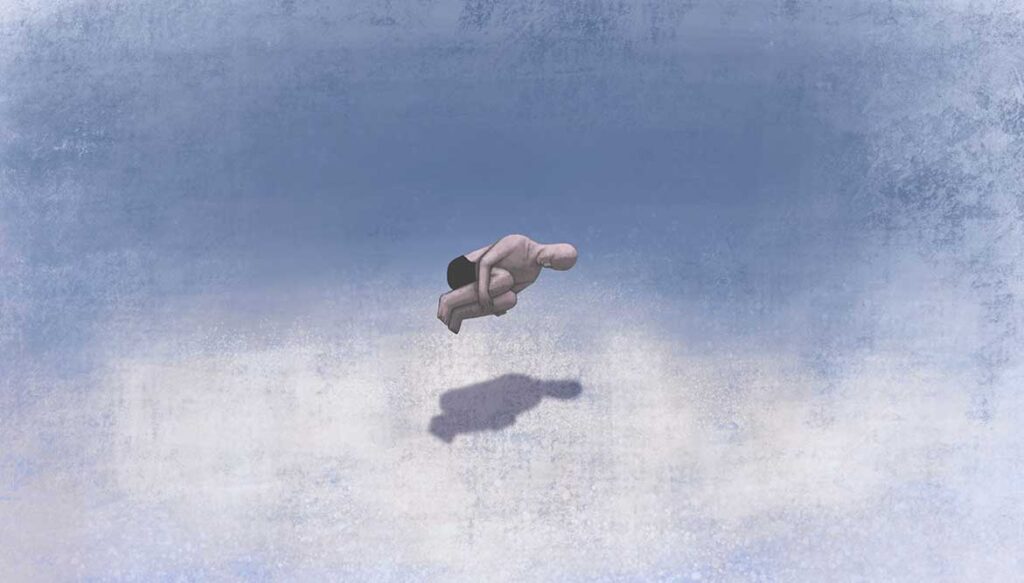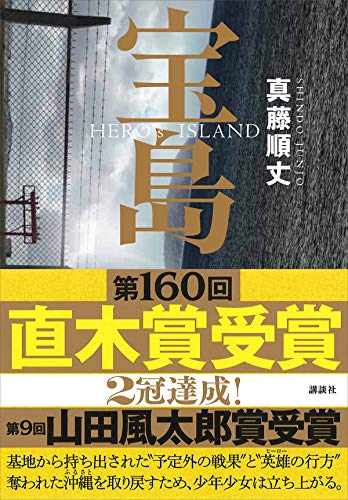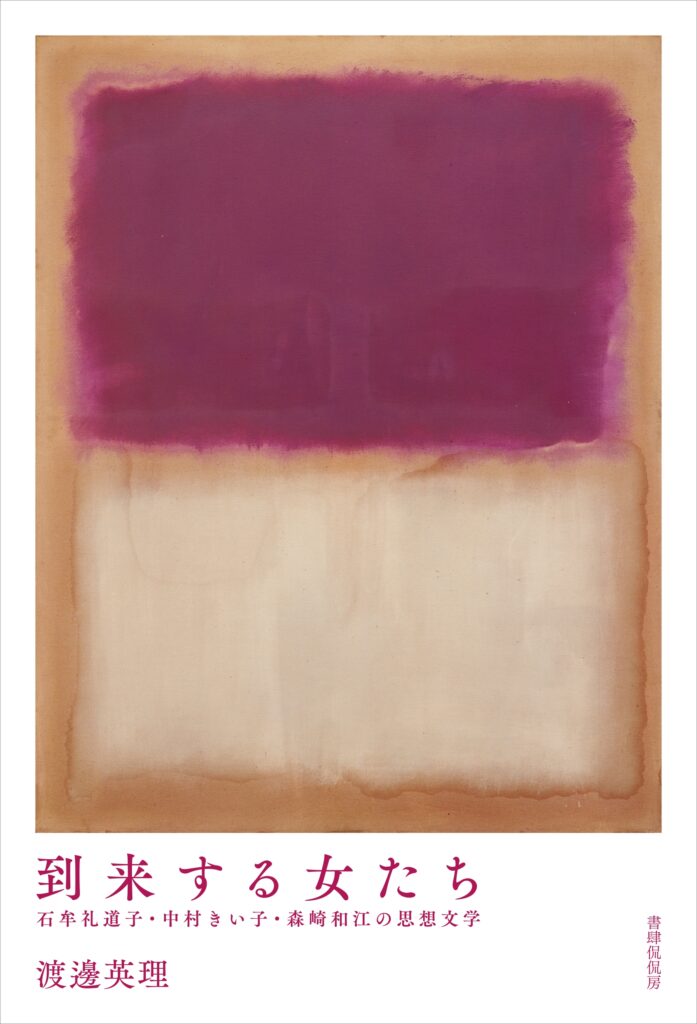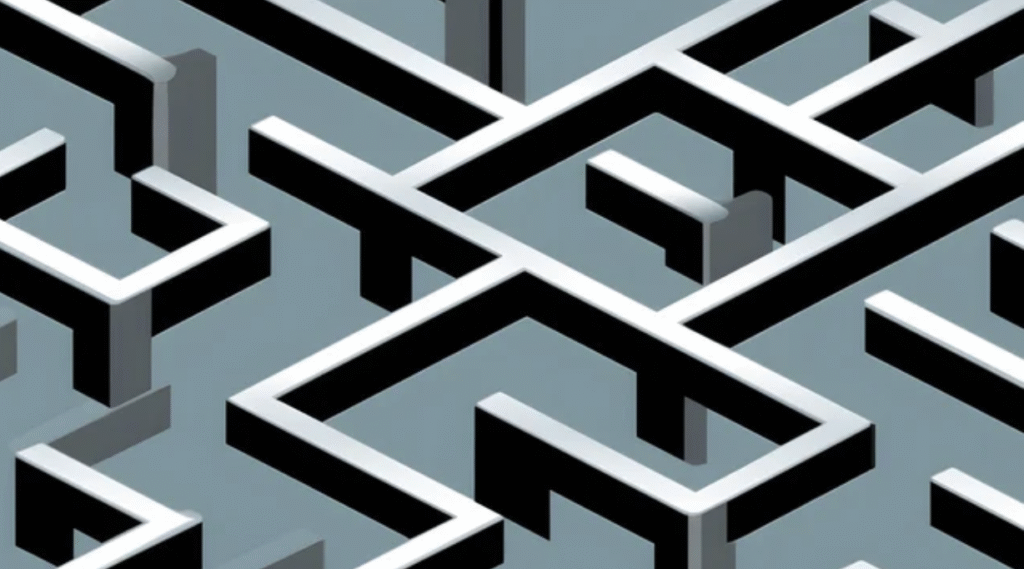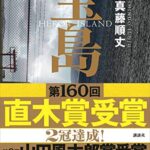【関連】特集:左派は復活できるか(2025年11月号)
【関連】ドイツの行方

2024年7月、フランス総選挙の決選投票で左翼連合「新人民戦線」(NFP)がマクロン大統領の与党陣営と極右陣営を抑えて首位になった。しかし、独断で国会を早期解散したマクロン大統領は強権を行使し、左翼連合政府を拒否しつづけた。昨年9月に組閣された保守とマクロン陣営の連立バルニエ内閣は同年12月、不信任決議で失墜した。マクロンは次に、与党連合のモデム党(中道保守)のバイルーを首相に任命し、再びマクロン陣営と保守の連立内閣が作られた。いずれもマクロンが進めてきたネオリベラル政策(緊縮、公共部門の破壊)を続行するための政府である。
それとは真逆の政策(最低賃金の大幅アップ、富裕層への課税、年金改革の廃止、公共サービスの復元・強化、環境政策の抜本的転換など)を掲げて首位になったNFPのうち、「服従しないフランス」(LFI)は、投票結果の否認は大統領の任務上の重大な過失であるとして、バルニエ首相任命以前の8月中旬からすでに、マクロンの辞任あるいは罷免を求めた。
マクロンに大統領辞任の意思はなく、罷免は手続きが難しい(両院の3分の2以上の賛成が必要)。少数派の政府は強行採択(討論・可決なしに政府が法案を採択できる憲法49条3項の行使)などを濫用して、多くの市民が反対する予算案や法案を通し、政体の機能不全が続いてきた。
右翼を取り込んだバルニエ内閣
左翼政府を拒む富裕層の要請にマクロンは従い、どの陣営も過半数に至らないから「勝者はいない」と主張した(577議席中NFP 192、マクロン陣営164、極右陣営140、保守47、その他34)。保守を取り込むために共和党の熟練政治家バルニエが首相に抜擢された。
バルニエ内閣(2024年9月〜12月)は不信任決議を避けようと、国民連合(RN)におもねった。マクロン政権はすでに極右が唱える移民・難民排斥とイスラモフォビア(イスラム教徒への憎悪)の言説や政策を取り入れて「分離主義防止法」を作った(2023年12月)が、バルニエ内閣が差別発言を頻発するルタイヨー内務大臣(保守)を起用したことにより、保守とマクロン陣営の極右化はさらに進んだ。
それまでの首相と異なり、バルニエのもとでは予算案の国会討議が行なわれたため、NFPは巨大企業と富裕層への課税(超富裕層対象のズュックマン税、フラット・タックス廃止)など、総歳入額を大幅に引き上げる修正案を可決させたが、強行採択で棄却された。一方、富裕税導入、贅沢ヨット・ビジネスジェット課税、富裕層の相続税増加などのNFPの修正案を、極右はマクロン陣営とともに拒否した。RNは伝統保守層と富裕層をつかむために、庶民層向けのポーズをやめて「普通の保守への変身」に勤しんだのだ。つまり彼らはマクロン政権の権力保持の助け舟となり、ブルジョワ陣営と極右陣営が融合してネオリベ政策が続けられた。しかしRNは、社会保険予算案の強行採択に対するNFPの不信任決議に賛成し、バルニエ内閣は失墜した。RNは以前から、非合法滞在外国人に緊急医療を保障する国家医療援助(AME)の廃止を提唱しており、バルニエでは差別政策が不十分だと見たのだろう。
バイルー内閣とスキャンダル勃発
次に組閣されたバイルー内閣(2024年12月〜25年9月)には、2007年以来サルコジ、オランド、マクロン政権下でネオリベ政策を行なった元首相・大臣や、未熟な政治家が集められた。性加害を問われずに内務大臣や法務大臣に任命されたダルマナンや、収賄、利益相反などの不正を指摘された政治家が何人も大臣の地位に居座るマクロン政権の腐敗は、市民の嫌悪感をいっそう強めた。
さらに今年2月、フランス南西部の町ポー近郊のカトリック寄宿学校で数十年存続した暴力、性暴力・レイプの事象が報道され、1990年代の事件当時に教育大臣と現地の県議会議長だったバイルー首相の責任が問われた。この報道をきっかけに、他の学校や施設で起きた児童への暴力・性加害の告発が相次ぎ、多数の被害者団体が作られた。カトリック教会だけでなく国家(教育省)が何十年も学校での児童への性加害と暴力を放置した原因を究明しようと、国会の調査委員会が設けられた。被害者と関係者、歴代教育大臣のヒアリングや現地での調査の過程で、バイルー首相の虚言や隠蔽が露呈したが、マクロン政権、保守、極右と主要メディアは首相に対していたって寛大な姿勢をとり、バイルーは辞任しなかった。
「上から」のイスラモフォビア
不信任決議を避けるために、バイルー政府は極右に倣った差別発言を頻発した。首相は移民・難民の「氾濫を感じる」と言い、同性婚やLGBTの権利を敵視する伝統的カトリック信者のルタイヨー内相は、反移民・イスラモフォビアに加え、アルジェリアを非難する発言を繰り返した。前年の総選挙で、若い層を中心に多くの市民が差別主義の極右に強く反発してNFPを勝利させたにもかかわらず、「第2・第3世代の民族的退行」「(ムスリム女性の)スカーフ打倒!」などと公言する人物が内務大臣となり、極右団体のデモを許容したのだ。図に乗った極右の行動が増大した。