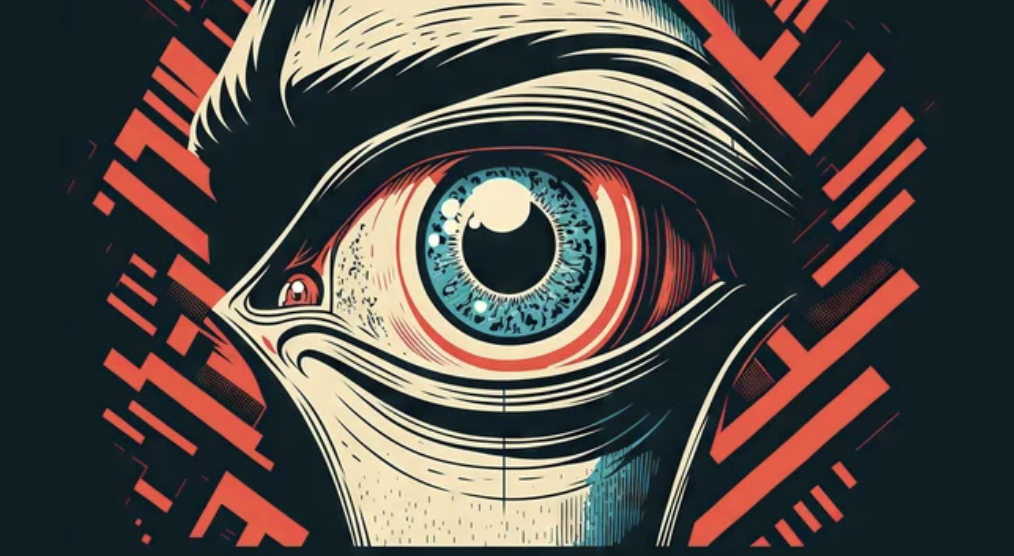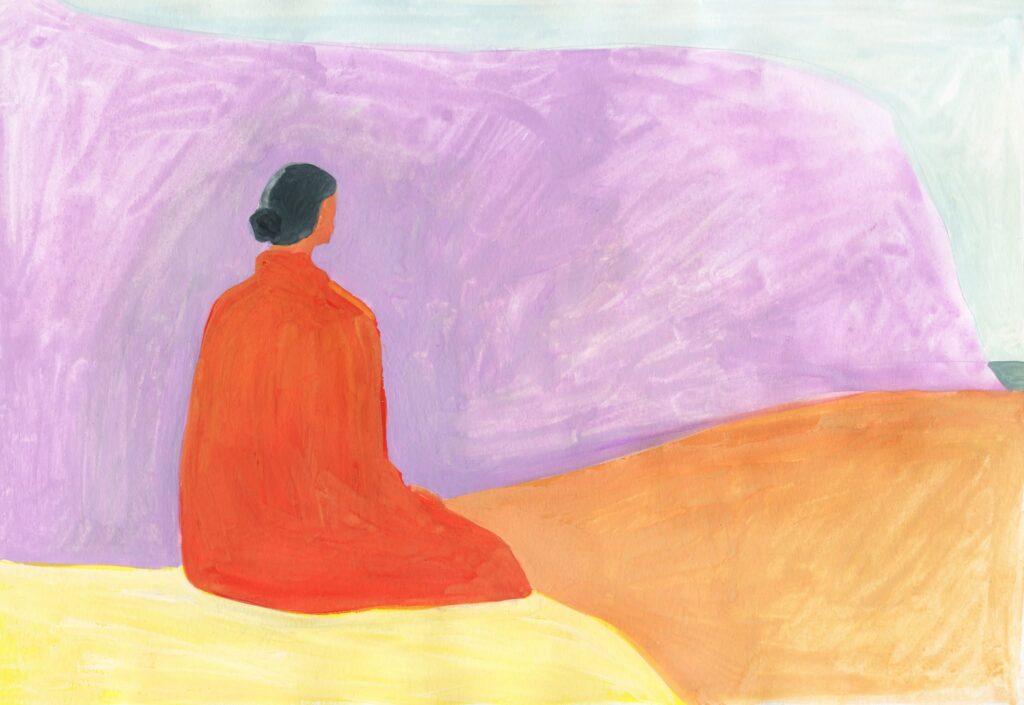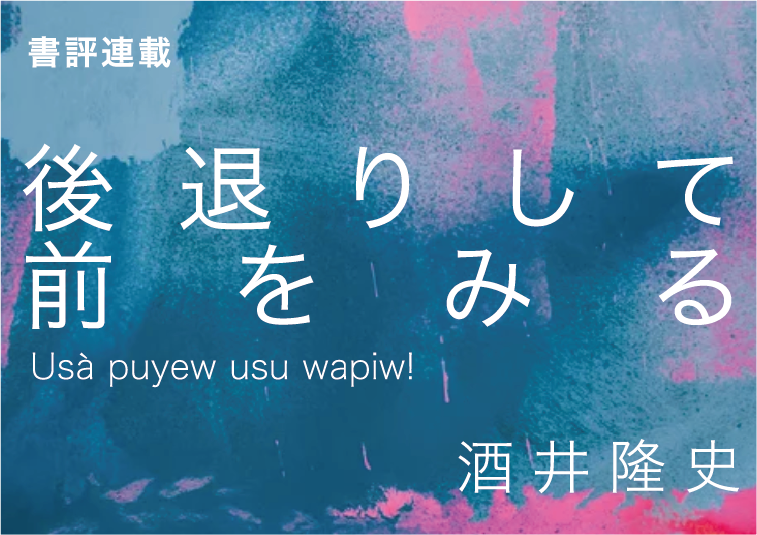関連:「特集 排外主義、再び」(2025年10月号特集)
2025年夏の参議院選挙において、「極右」と呼びうる参政党が比例区では野党第2位となる12.5%の得票率で、選挙区と併せて14議席獲得と躍進した。その得票率は、近年の欧州の極右政党の得票率に近づいており(たとえばドイツの極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」の2024年の国政選挙での得票率は16%程度)、日本政治においても極右政党が、政治の場で一定の存在感を示すようになった。
その参政党躍進の背景には、「日本人ファースト」という標語を前面に打ち出しつつ、外国人に対する様々なデマを前提にしたような選挙運動、またそれと連動した排外主義的言説が広まるネット上の情報空間が存在したことは事実だろう。ただし、日本国籍者の間で生まれた「排外主義の広がり(あるいは高まり)」が原因となって参政党が躍進した、という見立てについては、一定の留保が必要である。
そこで本稿では、まず人びとの排外的な意識について世論調査の結果を確認し、外国人を脅威と見なす人びとは横ばいか、むしろ減少傾向であることを概観する。次に、極端な排外主義者はあくまで少数派であることを確認した上で、そのような排外主義的な人びとの価値意識と、排外主義を広く他者に発信する「動機」について考察する。
続いて、なぜ排外主義的な言説が隆盛しているように見えるのか、まずその背景として社会的な不安を所与とするような時代状況が、その「原因」を求める社会環境として排外主義の底流となっていることを論じる。そして、近年ソーシャルメディア(いわゆるSNS)によって、外国人や移民のような「外集団」を「敵」とみなす排外主義が伸張しやすい情報空間の広がりを説明する。
最後に、それでも移民受け入れが不可避な日本社会の実情を踏まえつつ、排外主義への処方箋を提案してみたい。
「排外主義」は高まっているのか?
先述のように、2025年の参院選における参政党の躍進は、日本社会でも排外主義が政治的変化に結びついた事例として語られはじめている。たしかに、日本に居住する外国籍者の人口は近年急増しており、30年前の3倍程度、人口比で3%の水準にまで達している。その急激な増加を背景に、外国人を脅威とみなす人びとが増えている、と考えるのは自然であろう。
しかし世論調査の結果などをみると、極端な排外主義者はあくまで少数派である。移民が増加している多くの諸国でも、排外主義的意識を持つ人びとが一貫して増えているという傾向は、たとえば欧州について比較政治学者の中井遼がその著作(注1)で端的にまとめているように、基本、確認されていない。そのため世界的にみても、世論の排外主義が高まり、その結果として極右政党が伸張しているという直感的な理解は、あまり正しくないようである。