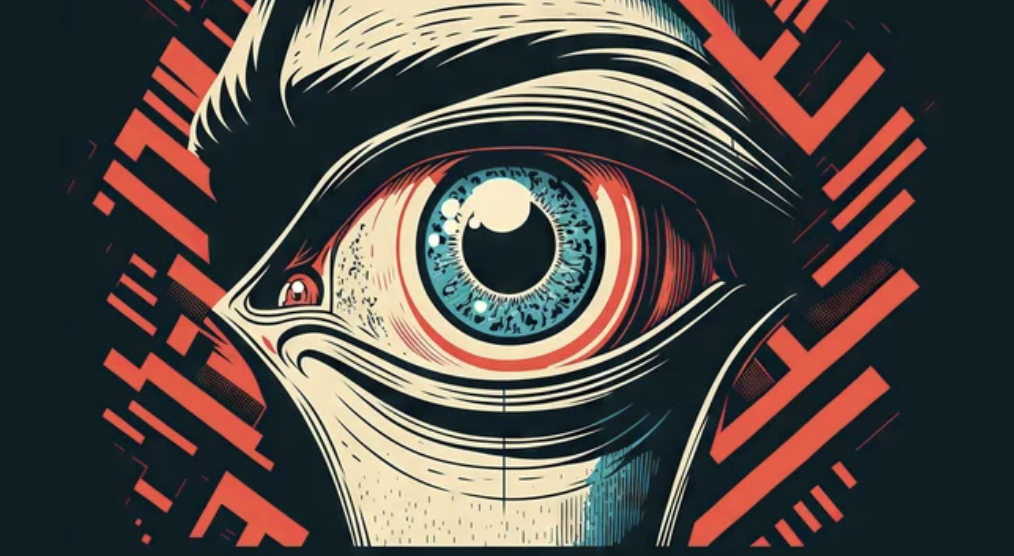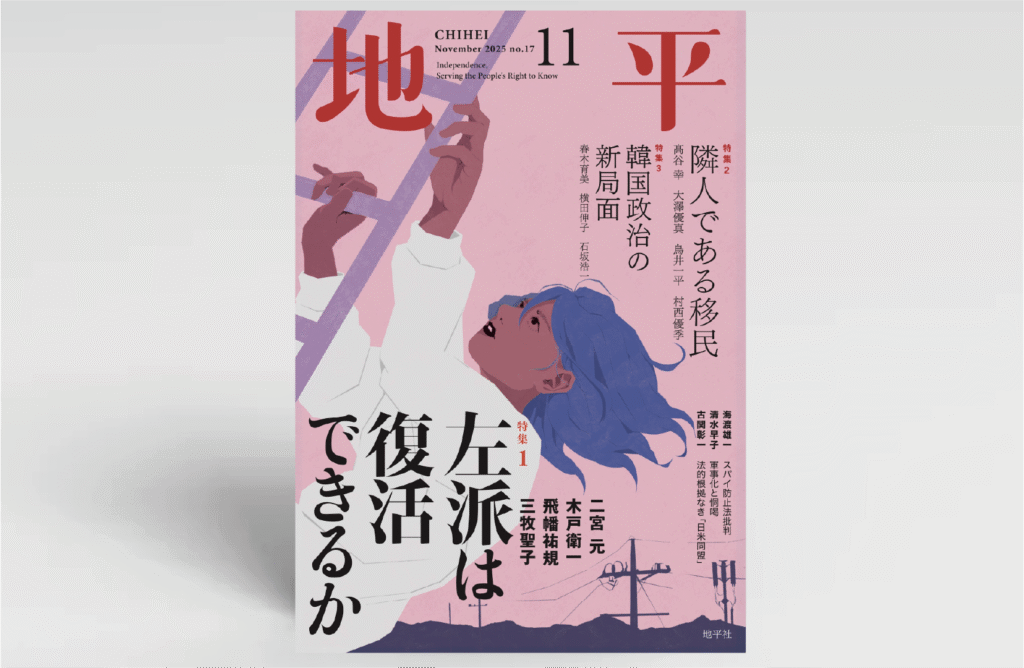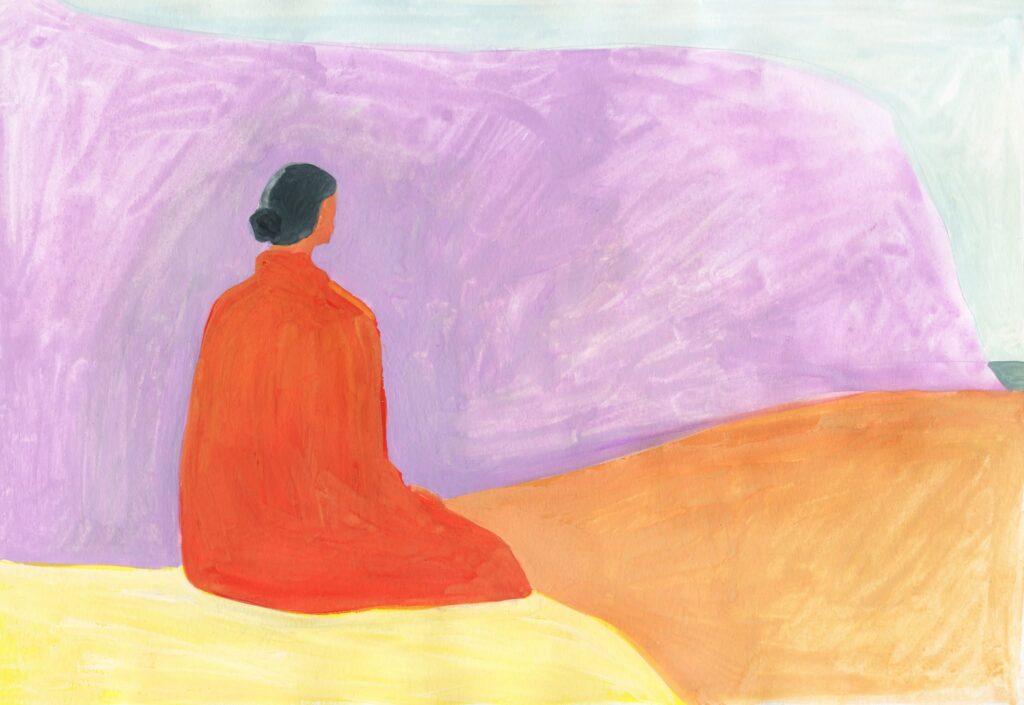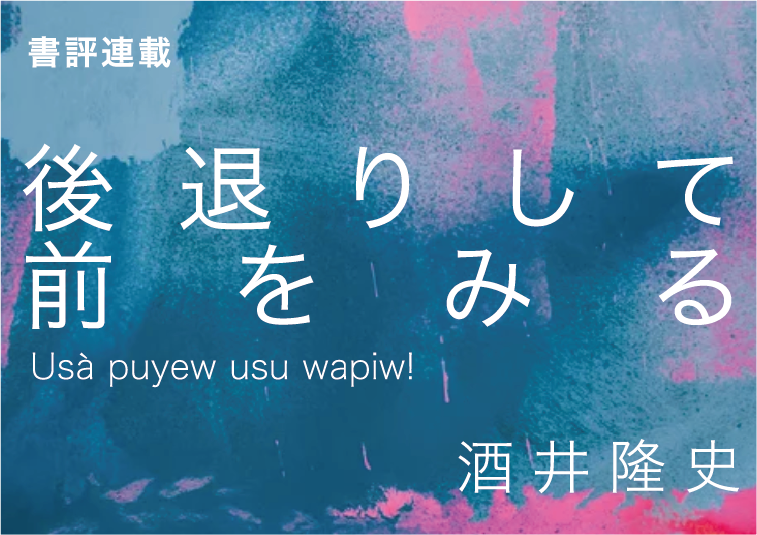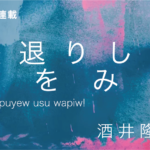自衛隊や警察にインターネット上の個人情報の収集や通信サーバへの侵入を許す「サイバー対処能力強化法案」と「サイバー対処能力強化法整備法案」が5月16日、国会で成立し、1週間後の5月23日に早くも施行された。憲法21条が明記する「通信の秘密」を根源的に脅かすこの2法案は、審議時間わずか23時間に野党が控えめな修正を施しただけで衆議院を通過(注1)。参議院で自民、公明、立憲民主、日本維新の会、国民民主が賛成し、反対したのは共産党、れいわ新選組などだけだった(注2)。メールやチャット、ネット検索をする人なら誰もが通信を収集される可能性があるのに、世論を喚起する間もなかった。
注1 2025年4月8日付朝日新聞デジタル「通信の秘密・分析対象の拡大…能動的サイバー防御法案、残された課題」
注2 2025年5月16日付朝日新聞デジタル「能動的サイバー防御法が成立 政府が情報収集、攻撃サイバー無害化」
政府は「サイバー攻撃のリスクは高まっている」「欧米が先行する取組に追いつかなければならない」と宣伝しているので、個人情報の大量流出や悪用、オンライン詐欺を防ぐための法律だと勘違いしている人も多いかもしれない。
この論考では、こうした誤解を解きながら、この新しい法律がアメリカとその同盟国で近年次々に作られる監視・治安立法の一翼であり、アメリカのスパイ活動の外注化であると同時に、日本がネット空間で戦争に参加することと同義であることを指摘する。
内実を隠す法律名
まず、政府が「サイバー対処能力強化法及び同整備法」と呼ぶ法律を、私は内容を明確にするために、「サイバー攻撃・スパイ法」と呼ぶことにする。「サイバー対処」という日本語自体、何に対処するのかを省略していておかしい。瑣末なことのようだが、法案を書いた公務員たちは、マスコミ受けや世論の反応、国会審議など、法案を波風立てずに通すために、あらゆる思慮を尽くしているはずだ。法案の名称は法案の運命を決めると言っても過言ではない。不自然な日本語を使ってまで政府が隠したかった事実こそ、サイバー攻撃・スパイ活動だと考えていいだろう。
私は新聞記者だった1999年から、盗聴法をはじめとする監視・治安立法の取材をし、社会学者になってからも監視研究を続けているが、政府が基本的人権を含め民主主義の原則を歪める法案を出すときには、経験則的に、たいていその主旨を隠す名前、または真っ向から否定する名称をつけてくる。ジョージ・オーウェルが小説『1984年』で描写した「ニュースピーク」である。例えば、メディアが盗聴法案を報じたときには「通信傍受法」という、不明瞭な名称を押し付けてきた(私たち記者は構わず盗聴法と書いた)。「周辺事態法」という何の事態だか分からない法律は、戦争を放棄したはずの日本が「直接の武力攻撃に至るおそれのある」状況下で、米軍の後方支援、自衛隊の武器使用を可能にする法律だった。アメリカでも9.11後、市民の自由権を大幅に制限する時限立法「愛国者法」がつくられ、内容と正反対の名前を冠した「自由法」に引き継がれた。「戦争の最初の犠牲者は真実」というが、真実を伝えるはずの言葉がまず歪み、倒錯するのだ。
政府は「能動的サイバー防御」を実行するために、今度の法律が必要だという。この用語もニュースピークだ。「能動的」と「防御」は両立しない。実際に何をするかといえば、通信サーバに侵入したり、「無害化」したりするというから、受け身ではなく、攻めなのだ。だが政府はあくまで攻撃と認めたくないようで、広報資料に「サイバー攻撃の脅威は、まるで自然災害」と書き(注3)、自衛隊は災害に対処しているだけと見せかけている。サイバー攻撃はもちろん人為的な行為だ。
注3 政府リーフレット『みんなで備えよう。新・サイバー防御、始まる。』
ニュースピークは政府に都合のよい言い換えによって、人々から批判的思考を奪っていく。サイバー攻撃は自然災害だという比喩は、いったい何を隠しているのだろうか?
憲法を迂回するサイバー攻撃・スパイ活動
国家サイバー統括室はサイバー攻撃・スパイ法の三本柱として、①官民連携の強化、②通信情報の利用、③攻撃サーバの無害化を挙げる。電気、ガス、水道、通信、銀行など重要なインフラを担う事業者がサイバー攻撃を受けた場合に、政府への報告を義務化し、通信事業者から関係する通信情報を取得・分析する。このとき、通信会社であるNTTやKDDI、ソフトバンク、その他インターネット・サービス・プロバイダーなどから個人の通信情報を収集できる。