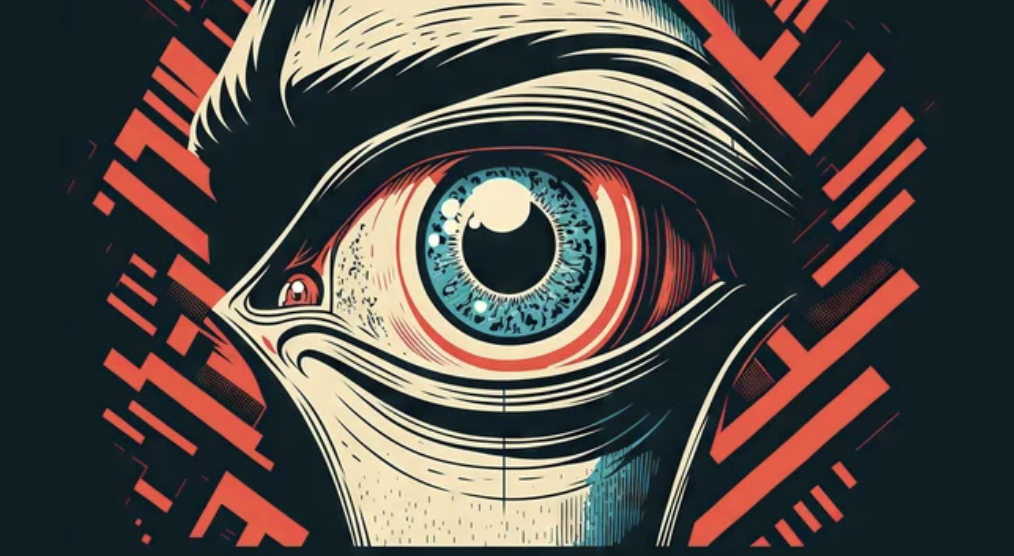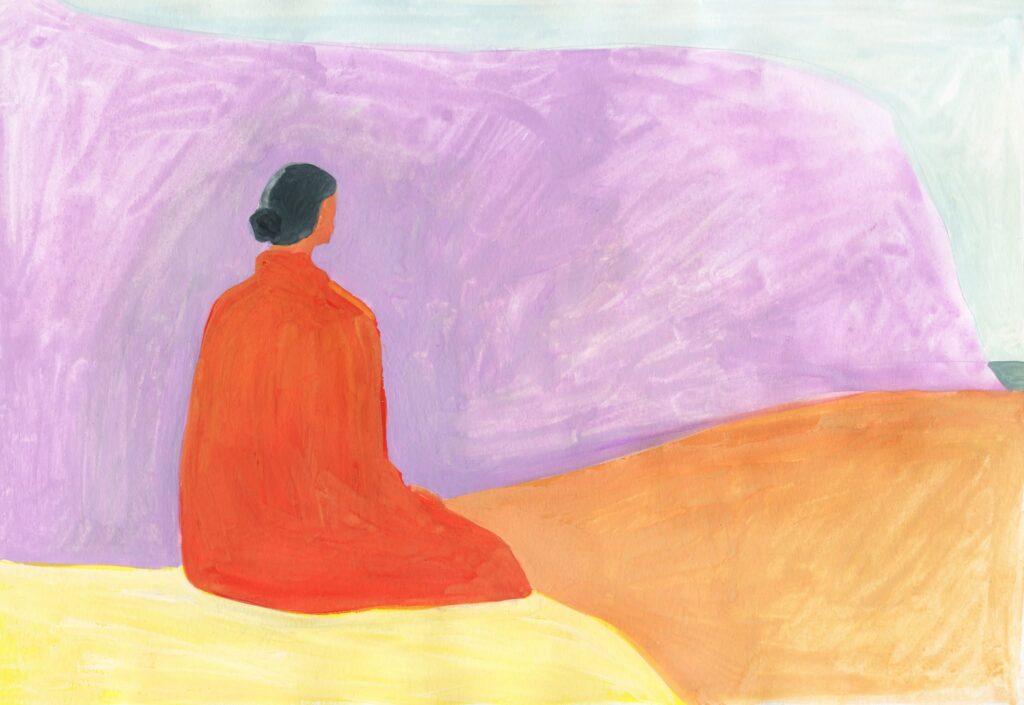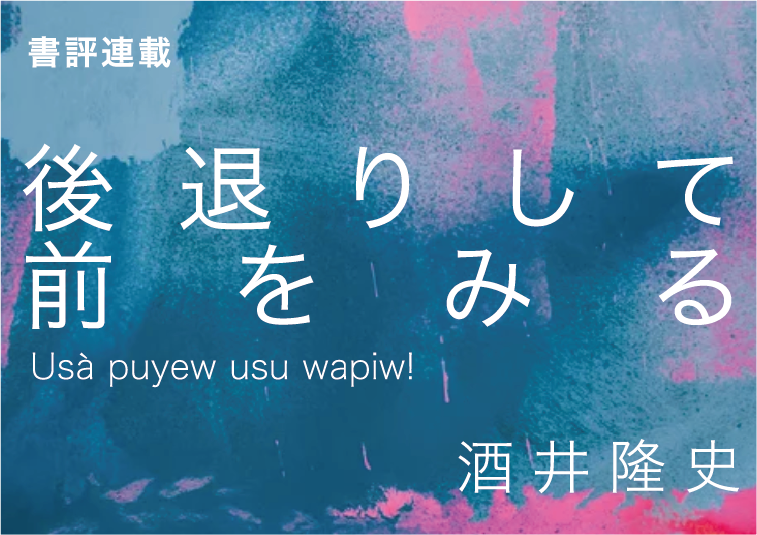座談会参加者
ハニン(コミュニティ・オーガナイザー。ガザ出身日本在住)
滝あさこ(アーティスト、アクティビスト)
杉原浩司(武器取引反対ネットワーク(NAJAT)代表)
ながいまなか(抗議する映画人)
それぞれに、つながって声をあげる
滝あさこ(以下、滝) アーティストでアクティビストの滝です。移民難民の方と一緒に作品やイベントを作ったり、サポートを行なったりという活動をしてきて、2023年10月にガザ地区への虐殺が始まってからは、パレスチナのデモに参加したり、企画をしたりといったことが多くなりました。以前からデモは行なってきましたが、参加しづらい人、既存の活動に違和感がある人、マイノリティの面をもつ方なども参加・活動しやすい運動をどう作れるかということなどを考えながら続けています。
杉原浩司(以下、杉原) 武器取引反対ネットワーク(NAJAT)代表の杉原です。平和運動、特に軍縮の問題に90年代から取り組んできました。2014年に武器輸出禁止三原則が撤廃された翌年、安保法制が成立した年の12月にNAJATを結成し、今に至っています。
パレスチナ問題との関わりでいうと、2010年に無印良品がイスラエルに進出しようとした際、仲間と一緒に反対運動を行なって止めさせました。2018年には川崎で開催されたイスラエル製の監視カメラやサイバーセキュリティ製品などを展示する軍事見本市「ISDEF Japan」に対して反対運動を行ない、結果的に日本企業でもっとも積極的だったソフトバンクが出展と協賛を降り、プレゼンを中止しています。
また、これは『地平』でも報告してきましたが、2023年3月、伊藤忠商事の子会社である伊藤忠アビエーションと、日本エヤークラフトサプライという二つの軍需商社が、千葉の幕張メッセで開かれた武器見本市で、イスラエルの軍需最大手のエルビット・システムズと日本への武器売り込みのための協業に関する覚書を結び、シャンパンをくみ交わしたということがありました。私たちはすぐにこれに反対する運動を始めました。その後、ジェノサイドが激化してからは全国で立ち上がった大勢の人たちとともに声を上げ、また、BDS運動の広がりもあり、2024年2月に覚書を終了させることに成功しました。
※BDS運動:イスラエルの占領を終わらせ、国際法を遵守させるためにパレスチナ人の呼びかけで2005年から始まった国際的なキャンペーン。BDSはBoycott(ボイコット)、Divestment(投資引き揚げ)、Sanctions(制裁)の頭文字をとっている。
ハニン 私はパレスチナ人で、コミュニティ・オーガナイザーとして活動しています。ムスリムです。ガザ出身で、7歳のときに家族とともに日本に来ました。生まれたのはガザ市のアル・アハリ病院です。この病院は2023年10月17日にイスラエル軍に爆撃され、一瞬で500人以上が殺されました。今日はイスラエルによるガザ虐殺の2年間を振り返る座談会ですが、イスラエルによる占領自体はもう100年も続いています。その間、ガザの人々は正義を経験していません。
私は日本で育ちましたが、パレスチナについて積極的に話すようになったのは2023年10月以降です。この虐殺が始まってから最初に参加したデモはこの年の10月13日、新宿駅で行なわれた「パレスチナに平和を! 緊急行動」でした。2009年にも新宿駅でパレスチナの占領に抗議するデモに参加しましたが、その闘いがまだ続いていることを嬉しく思いました。もっと何かしなければいけないと思い、本来私はそういう性格ではないのですが、今こそパレスチナ人が前に出て声を出す時だと思いました。集会に参加するうちに新しい仲間に出会い、「Palestinians of Japan」が結成されました。みんなでアイディアを出し合いながら、ムーヴメントは徐々に大きくなっていったと思います。
以前、UAEに滞在していたことがあるのですが、そこでは自由な表現は難しく、(イスラエルの占領などに)抗議もできませんでした。虐殺が始まって数日後に、家族といるため、そして抗議をするために、日本に戻りました。やっと自分の怒りを表現することができたと感じました。怒りを感じる権利があるんだと。だから、ここで抗議する権利を行使できるということは、私にとってとても大事なことなのです。悲しいことですが、抗議をするというのも特権だということは知られていません。私はこの場所で、今まさにガザにいる人たちの声を伝えることを大切にしています。
ながいまなか(以下、ながい) パレスチナのデモを通して出会った人たちと、沖縄・琉球弧の軍事化などについてのデモを企画しています。今日はハニンの通訳を兼ねて参加しています。パレスチナがこれだけひどい目にあっているのに、このまま何も変わらないのであれば私たちには未来はないと思って活動しています。イスラエルによる前代未聞の虐殺について報道があまりにもなかったため、去年の3月からボランティアでパレスチナの抗議の取材もしています。
運動のはじまりとメディア
滝 路上に出て抗議の声を上げたのは、イスラエルが、占領しているパレスチナを攻撃することがありえないと思ったからですが、メディアがきちんと報道しないからでもありました。運動が始まった当初、参加した誰もが、マスメディアの報道がひどすぎると感じていました。「ジェノサイド」や「虐殺」という言葉を使わず、パレスチナ人の抵抗としてではなく、「ハマースによるテロ」と言うプロパガンダばかり流布し、まるで10月7日がすべての始まりであるかのように描き出す。それまでイスラエルが行なってきた非人道的な行為、国際法に反する行為、パレスチナへの封鎖や入植活動、抑圧などの人権侵害という経過が報じられず、たとえば2023年7月にイスラエル軍がドローンやブルドーザーを使ってパレスチナ・ヨルダン川西岸のジェニン難民キャンプを侵攻していたことなど、まったく触れられない。
杉原 新聞やテレビは今でも、「ジェノサイド」や「虐殺」を使わず、「戦闘」「攻撃」という表現を頻繁に使っていますね。以前、ある新聞からコメントを求められた際、その記者はとても丁寧だったのですが、私が使った「虐殺」という表現に「デスクからチェックが入るかもしれません」と言われたことがあります。結果的にはそのまま通りましたが、おかしなことです。
もう2年近く、パレスチナでは少なくとも6万人もの人たちがイスラエル軍によって、爆撃などだけではなく、強制的な飢餓でも殺されつづけています。地獄としか言いようのない状況になっているのに、本質を軽く見せ、隠蔽する表現で報じるのは、まさしく虐殺への共犯行為です。多くの人が指摘することで修正されたりするケースもありますが、そのような例はまだまだ少ない。武器輸出についても、マスメディアはこれを「防衛装備品移転」と報道します。これでは伝わりません。血のにおいを消すために政府がひねり出す表現をそのままメディアが使っています。
ハニン お話を聞きながら思い出していたのですが、デモに参加して、この問題をなるべく多くの人に届けられるようにと、積極的にメディアの取材を受けるようにしていました。でも、すぐに、あれ、これは違うなと感じました。家族や友人を何人亡くしたか、そういう私のトラウマを掘り出す質問ばかりで、一度も、血を流させた側についてのコメントは求められない。すべての犯罪の加害者であるイスラエルについては質問されないのに、それでいてパレスチナ人のトラウマポルノを過剰に求めるということには不快感を覚えます。
日本でボイコットをどう進めるか
杉原 伊藤忠商事の問題は、「10・7」以降特に、その重大さが多くの人に受け止められたと思います。現在進行中の虐殺に関与しているイスラエル企業の武器が、私たちの税金を使って購入される。憲法9条を持ち、「平和国家」として認められてきた日本の大企業であり、就職先としても人気の高い伊藤忠商事が、イスラエルとの武器取引に手を染めていくことの重みが、広く共有されました。
伊藤忠は昨年2月に覚書の終了を決めましたが、それまでには、ネット署名や伊藤忠本社前でのアクション、そして伊藤忠が出資する系列企業へのボイコットの呼びかけなどが、BDS Japan Bulletinなどを中心に進められました。ファミリーマートやプリマハムなど一般消費者に身近な企業が多かったことも、ボイコットの効果を高めました。決定打は、マレーシアでファミリーマートへのボイコット運動が動き出したことだと思います。
現時点では、日本でのボイコットはまだ企業の業績を大きく下げることにまでは至っていませんが、イスラム教徒が多く、パレスチナへの関心と共感が強いマレーシアでは、マクドナルドやスターバックスが閑古鳥状態となり、店舗が閉鎖されることも起きています。マレーシアで出店拡大計画を持っていたファミリーマートにとって、ボイコット運動は避けたかったでしょう。
もちろん伊藤忠はそんなことは言いません。国際司法裁判所が昨年1月、イスラエルに対してジェノサイドを防止するためのあらゆる措置を取るよう命じる暫定措置命令を出し、日本政府もそれを支持しました。伊藤忠はそれを口実にしたわけです。とはいえ、伊藤忠がこの声明を出したことはとても意義がありました。国際的な反響も大きかった。ただ、日本エヤークラフトサプライは現在も取引を続けています。
ハニン これらの企業が行なっているイスラエルとの取引は本当に恥知らずです。ですから、グローバルに運動が展開され、国際的にプレッシャーを与えられたことの意味は大きかったですね。国内でも、伊藤忠商事がいるところに、常に私たちもいました。本社前で横断幕を掲げて抗議したり、東京ビッグサイトで開かれた就活生向けのイベントでは、会場の外での抗議だけでなく、伊藤忠のブース内で就活生として質問をぶつけたりしました。
杉原 日本でも武器見本市が開かれるようになってしまっていますが、イスラエル企業は常連で、三大軍需企業のエルビット・システムズ、IAI(イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ)、ラファエルは必ず出展しています。フランスなどでイスラエルの軍需企業の出展を制限する動きもありますが、日本は、今年5月の「DSEI Japan」でもイスラエルから二つの政府機関と22社の企業が参加し、エルビット・システムズのブースでは、ガザの虐殺に使われているスカイストライカーという自爆型ドローンが堂々と展示されました(本誌7月号参照)。そこに石破首相と中谷防衛大臣が視察に訪れ、中谷大臣は国会答弁でも「何の問題もない」と言い切っています。この時は初日に350人で抗議行動を行ないました。
また、昨年10月に東京ビッグサイトで開催された「国際航空宇宙展」には、国連特別報告者から名指しで批判されているアメリカのロッキード・マーチンやRTX(旧レイセオン)、ボーイングなどの虐殺加担企業も出展しました。私たちは主催者への申し入れやネット署名などさまざまな行動をして、初日と最終日には、会場入口付近で100人以上集まって抗議しました。私は3日目の夕方、エルビット・システムズのブース前で仲間とプラカードを掲げて抗議を行ない、追い出されましたが、その直後、同社のブースは紙テープでぐるぐる巻きにされ、「撮影禁止」の貼り紙がされる形で、一時的ではありますが閉鎖状態になりました。最終日には在日パレスチナ人や若い人たちが十数人で会場に入り、ロッキード・マーチンなど虐殺加担企業のブースの前でアピールしました。

年金積立金が軍需企業に投資されている
滝 伊藤忠については「イスラエルのジェノサイドに燃料を送るBTC石油パイプラインから今すぐ撤退せよ!」というキャンペーンも気候危機などに取り組む「船と風」ジャーナルによって行なわれました。伊藤忠などの日本企業、石油開発企業のINPEX、イギリスのBP社の日本支社も対象に、イスラエルが使う原油を供給するBTC石油パイプラインへの投資撤退要求をしています。
杉原 この時は、伊藤忠商事だけでなく、トルコ大使館とアゼルバイジャン大使館の前でも集会をしました。トルコはBTCパイプラインで送られてきた原油をイスラエルに輸送していますし、アゼルバイジャンはBTCパイプラインを通してイスラエルに原油を送っている。こうした個別の事業投資もチェックしていく必要がありますね。
ハニン いま、日本に住んでいる人が納める年金保険料の積立金が、イスラエルの国債や、イスラエルに兵器を供給する軍需企業に投資されています。つまり、パレスチナ人を含む人々が一生懸命働いて稼いだお金や納めた年金が虐殺加担企業に投資されて、世界の向こう側で人々がその資金によって殺されているのですが、そのことはあまり知られていません。ですから私たちは、パンフレットなども作成して、投資撤退を呼びかけています。
※年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は2024年3月末現在、イスラエルの国債を2270億円、同国に兵器を供給する軍需企業の株式を11社・合計6398億円保有していることが今年4月に明らかになった。
投資を引き揚げることが簡単でないことは理解しますが、不可能ではありません。人を殺す企業に投資するのではなく、本当の意味で人の幸せや社会にとって意味のある投資をしてほしいと思います。経済的利益をただ追い求めるのではなく、いま国際的にも唱えられているようなESG投資を徹底するべきです。
※ESG投資:環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)といった要素を考慮して行なう投資。
杉原 参考になるのは核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)の取り組みです。核兵器関連企業からの投資撤退の取り組みを集中的に進め、実際に日本の銀行でも投資をしない方針を打ち出すところも出ています。ICANは核兵器にフォーカスしていますが、ガザでは通常兵器によって大量虐殺、大量破壊が行なわれています。通常兵器によるジェノサイドに私たちの年金積立金が投資されている。これはすぐに撤退すべきだし、撤退できるはずです。
滝 街頭などで、「私たちが払っている年金のお金がイスラエルの軍需企業に投資されている」と言うと、耳を傾けてくれる人がいます。しかし、それすらも気にしない人もいる。参議院選挙でも思い知らされましたが、自分の生活と暴力的社会構造の関わりを考えるきっかけや余裕みたいなものをつくるにはどうしたらいいか悩んでいます。
杉原 最近、国連のパレスチナ問題特別報告者のアルバネーゼさんが出した「占領経済からジェノサイド経済へ」という報告書(今号掲載)で述べられているように、ジェノサイドに加担しているのは軍需企業だけではありません。西岸地区でパレスチナ人の家屋を破壊している重機を製造しているキャタピラーやヒュンダイ、ボルボなど、多くの企業が加担しています。報告書のリストに日本企業として唯一あげられているのが産業ロボット大手のファナック社です。富士山の麓の忍野村に広大な施設を構えていて、国内外のあらゆる分野に産業ロボットを供給しています。このファナックの産業ロボットがイスラエルなどの軍需企業で使われ、ガザの人たちを殺す爆弾などの武器の製造に使われています。
ファナックは、意図したものではないにせよ、自分たちの製品がジェノサイドに使われていると指摘されているわけですから、徹底的に調査して、事実関係がはっきりした時には機械を戻させるといった決断をしてほしい。それが企業としての責任だと思います。
滝 すぐに私たちができるボイコットとしては、BDS運動やアルバネーゼ氏の報告に出てくる企業の製品を使わず、他社のものを使う、イスラエル産と書かれた果物やワインなどは購入しない、ということがあります。最近、イスラエル産であることを表示しない製品も増えています。問い合わせて、初めてイスラエル産だったことが分かったというものも複数あります。最近発覚したものでは、「温州みかん」と書いてあるなら日本や中国産だろうと思っていたら、問い合わせたらイスラエル産だとわかって、ショックでした。
パレスチナの国家承認をめぐって
滝 日本は第二次大戦後かなり早くから、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じた支援・援助を続けています。それなのに、パレスチナの国家承認は保留にしたままです。日本もパレスチナの権利を迫害していると思います。
ハニン 日本は長年、「二国家解決」を主張してきましたが、そう言いながら、そのうちの一つを国家として承認していないのは皮肉なことです。いま、G7に名を連ねる欧米諸国が承認するかどうかが話題の中心になっていますが、それは偽りの希望だと感じますし、私たちはそれらの国がパレスチナの存在をやっと発見するのを待っているわけではありません。すでに世界の多数の国々がパレスチナを国家として承認しています(国連加盟193カ国中147カ国が承認)。これに対して、G7の国々はパレスチナが武装解除すれば国家承認するなどとさまざまな条件をつけていますが、そんな条件付きの承認はパレスチナ人に対する侮辱です。想像してみてください、あなたの首に膝を押し当てられて窒息させられている時に、まわりの人は加害者を押しのけて罰する代わりに、あなたが存在するかどうかを話し合っているんです。
現代世界においては国家承認は重要ですが、最優先すべきはイスラエルの虐殺とガザとパレスチナに対する残虐な封鎖を解除し、パレスチナを解放することです。そして、国家承認を話題にするなら、イスラエルという偽の国家の承認を取り下げることが、パレスチナの国家承認と同じくらい大事な話です。文字通りパレスチナ人の血肉の上に作られている「イスラエル」に、存在する権利はありません。
杉原 いま、イギリスやフランスなどが言及しているパレスチナの国家承認は、パレスチナに武装解除を迫るもので、とても危うい側面をもった動きです。もちろんパレスチナを国家承認すべきでないとは思いませんが、前提として、イスラエルに直接的に制裁をかけることが必要です。パレスチナの国家承認が、イスラエルに制裁をしないアリバイにされてはいけない。日本政府は、国家承認と同時に、ジェノサイドや占領を続けるイスラエルに対してただちに制裁をかけるべきです。
25年度に防衛省が初取得する攻撃型ドローンにイスラエル製を選ばせない運動は、市民が政府に実質的なイスラエル制裁をさせるものです。候補機であるIAI製の2機種の輸入代理店を務める海外物産への圧力を強めていきます。
個人と運動、パレスチナをつなげる
滝 イスラエルのジェノサイドを止めさせるための運動は、全国各地で本当に色々な形で行なわれており、言及し尽くすことはできません。名古屋には虐殺に加担する企業の支部が多く、愛知県はイスラエルスタートアップとの協業支援事業まであり、抗議や連帯運動も盛んです。広島でも毎日取り組みがあります。グループではなく一人で活動されている方もたくさんいます。こうした一つひとつの取り組みがうまく連なり、広がっていけば、より大きな変化になっていくと思います。
また、パレスチナの運動は、脱植民地主義や先住民族、マイノリティの権利をめぐる問題と共通する面があることから、さまざまな分野で声を上げている人たちの動きと一緒になることが多いというのも特徴だと思います。
ながい 私自身もパレスチナについての取り組みを通して、脱植民地主義の行動をするようになりました。かつて日本がアジアで行なってきた植民地主義、さらに今も琉球弧の島々で続いている軍事基地の押し付けなどの問題をもっと学ぶようにもなりました。東京は人も多く情報もあるのですが、街が大きすぎて、それぞれでがんばっている人たちとの距離があるような気がします。お互いの顔が見えにくいというのか、それをどうやって近づけられるか、考えていきたいです。
杉原 10・7以降、私が最初に参加したのは、10月11日に呼びかけたイスラエル大使館前での集会でした。60人ぐらい集まっていたと思います。同じころ、本当にたくさんの人たちが各地で呼びかけをして、デモやキャンペーンが一気に広がっていきましたね。今回のジェノサイドに反対する運動は圧倒的に若い世代が多く、職業や背景も多様な人がさまざまに動いていることが大きな特徴だと思います。既存の社会運動のスタイルにこだわらず、自分たちのセンスや方法でクリエイティブに繰り広げられています。それは、参加する敷居をさげ、オープンに誰でも参加しやすい運動の場であることにつながっていると思います。
日本の戦後の平和運動は、憲法9条を守ろうという強い思いに根差したもので、これまでは主にベテラン世代が中心になってきました。これは私たちの世代の課題でもありますが、社会運動の中の風通しが良くなく、ハラスメントがあったり、男性中心的だったりという問題も少なからずありました。でも、今回のパレスチナをめぐる運動は、そういうあり方も乗り越えようとしています。集会の前に差別やハラスメントをしないといったルールを告知するとか、これまでになかった工夫が随所になされています。私たちの側が学ぶべきことがたくさんあります。
ながい いろんな人たちが集まって、ニュースや政治について話す場は日本には多くはありません。お茶を飲みながら気軽にいろんなイシューについて話せるような場所が増え、社会全体がいつかそうなることを願います。
滝 社会運動は、参加している人たちの意識や人間関係も大きく影響しますね。定期的に声をかけたりSNSで活動をシェアしあったり、疲れたら休めるようにお互い調整したり、つらい時に話を聞いたり、より参加しやすいインクルーシブなやり方を考えたり。そういうことをお互い丁寧にすることが大切です。でも、私たちは休めるけど、ガザの人は休めないっていう思いも常にあるのですが……。
ハニン そうですね。日本にいる私たちは疲れたら休めますが、ガザにいる人にはその選択肢がありません。睡眠も食事もとれない。ガザは、もう私たちが想像できないほどひどい状況にあります。ガザから送られてくる動画をいくら見ても、それは現実の断片でしかありません。
もうすぐ700日になります。状況はどんどんひどくなっていて、それなのに国際社会は本気でこの状況を解決しようとしていない。これ以上、パレスチナの人々が何を共有すれば人々が関心を持ってくれるのか、私は分からなくなってきています。壁に張り付いた人の死体や無惨な殺され方をした子どもたちの死体もたくさん伝えられているはずです。これ以上何を見せれば人は行動してくれるのでしょうか。絶望的な気持ちにもなりますが、それでも私たちはあきらめないし、声を上げることをやめない。とにかく闘いつづけるしかありません。個人的には、私には信仰があるので、希望を失わずにいられる神の存在に感謝しています。パレスチナで起きていることは自分には関係ないと思っている人たちも多いと思いますが、自分が何かをしていなくても、年金積立金や日々の消費を通じて知らないあいだに加担しているんです。だからとにかく、人に知らせていかないといけないと思っています。
本当にもっと多くの人が一緒に声を上げてくれることを願っています。そのために、私たちは意識を高めたり、政治的学びを深めたり、お互いに助け合えるような場を作りつづけたいと思っています。さっき滝さんも言っていましたが、助け合う、ケアし合うというのは、すごくシンプルなコンセプトに聞こえるかもしれないけれど、本当に必要なことです。
私は、さまざまなコミュニティと助け合うことができて感謝しています。だからこれからも、パレスチナのためだけではなく、すべての抑圧されている人々のために闘いたいと思っています。 (2025年8月8日地平社にて)