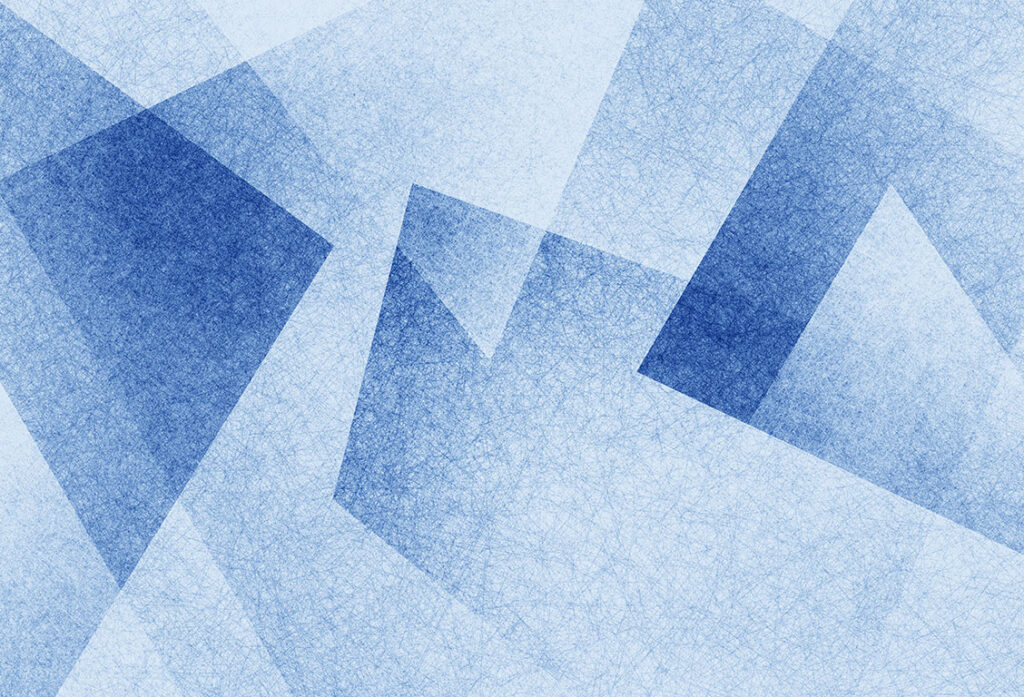●特集「原子力の終活」の他の記事はこちら
原発回帰――「国策」の再稼働
「第七次エネルギー基本計画(案)」が公表された。しかし結論から言えば、その内容は、世界の進歩的趨勢に真っ向から背を向けたものである注1。周回遅れだった日本のエネルギー政策は、今後もさらに歴史を逆行することになる。
この計画では、再生可能エネルギーと原子力とが同じ「脱炭素電源」という概念でラッピングされ、ウクライナ戦争や中東情勢、「DXやGXの進展に伴う電⼒需要増加」を理由に、これまで明記されていた「可能な限り原発依存度を低減」という文言が削除され、代わりに、「原発再稼動の加速」や「既設炉の最大限の活用」、「次世代革新炉の開発」が謳われている。
これまでも原発は、徹頭徹尾「国策」によるものであった。未だ完全な収束をみない3.11福島原発事故は、それを起こした東京電力はもちろんのこと、それ以上に原子力産業自体を育成・推進してきた歴代政府に責任がある。一時は東京も含め、東日本全体が居住不可能になる「最悪シナリオ」が想定され、その意味で、日本の国家安全保障問題としても戦後最大の危機であったが、その経験の総括や政治責任の追及は、未だ果たされていない。そんな中での、“原発回帰”という「国策」の再稼動である。
国家エリートたちが「危機」を危機として認識できないまま、無責任のシステムの中で社会や国家全体の破滅を招く。またそれのみならず、国民も含めてその「破滅」や「失敗」を経験化できずに、また同じ悲劇を繰り返す。筆者が、3.11福島原発事故を、「第二の敗戦」と呼びつづける理由は、ヒロシマとナガサキに原子爆弾が炸裂した「第一の敗戦」と、フクシマ原発の暴走とがあまりにも相似の政治的構図を描いているからである。
世界最大の原発建設と「ライフ・ポリティクス」
「国策(中央)」の誤った政治判断の犠牲となるのは、これまでも常に「地方(周辺)」であった。日本の近現代史は、「富国強兵」という、実際今でも追求されつづけている近代化プロジェクトの延長線上にあるが、その限界と暴力性は、ミナマタ、オキナワなど、いつも「地方(周辺)」の声なき声によって可視化された。
新潟にある世界最大の柏崎刈羽原発は、新潟出身の政治家・田中角栄による、日本の高度成長を背景にした開発政治の産物である。「富国」=「豊かさ」は、地域にお金が回ることであり、国民にとって「楽な生活」ができることに他ならない。原発は、「国策」によって地方が「豊か」になるとの物語の中で、地域にも歓迎された。それは、世界中の途上国で見られた開発型政治の、いわば「日本版」であった。その結果、1978年、かつて原爆投下予定地の最終候補でもあった新潟に、世界最大の原発建設が始まった。
しかし新潟では、1960年代の末には、原発建設に異議申し立てする強固な市民運動も生まれていた注2。彼らは活動を通じて、現代政治に潜む大きな問いを提起した。現在の地点からそれを言い換えるなら、まずは開発によって「豊か」にされるべき「生活=ライフ」には、そもそも「生命」という意味が包含されるべきではないのか。だが原発を受け入れることによって、今日明日のライフ(生活)のために、未来世代も含めたライフ(生命)の安全を脅かすことにはならないのか。さらには、なぜ電力を消費する東京の人びとのライフ(生活)のために、新潟のライフ(生命)がリスクにさらされなければならないのか。いわば、この「ライフ(life)」をめぐる2つの大きな“分断”が問われたのである。角栄は、「政治は生活だ!」と喝破したが、その「生活」のために、地方や未来の「生命」(あるいは未来の「生活」も含めて)が天秤にかけられてもよいのか、という根源的な問いである。